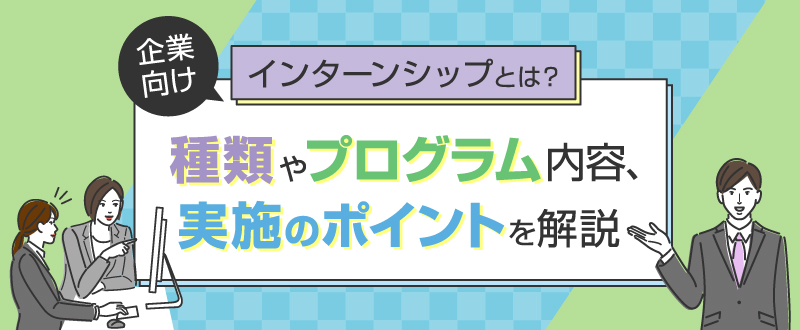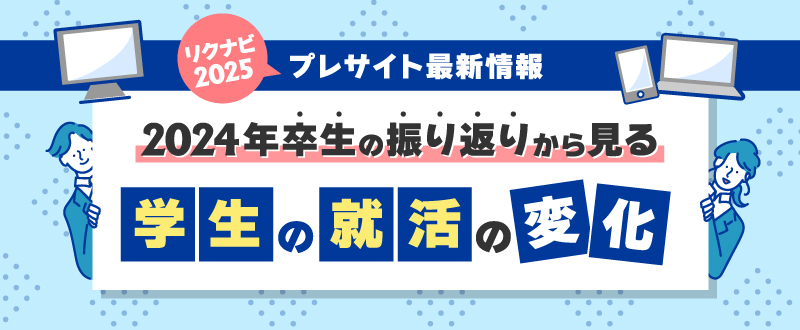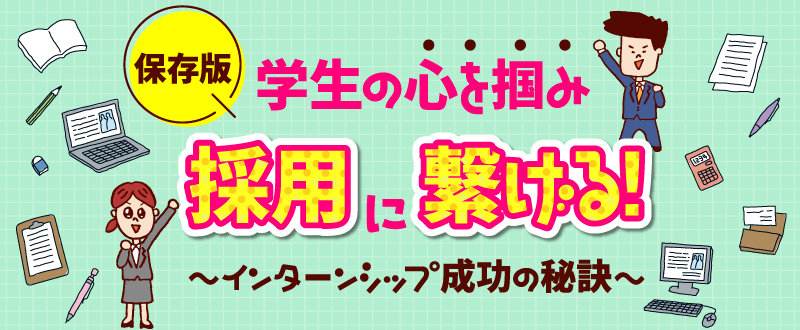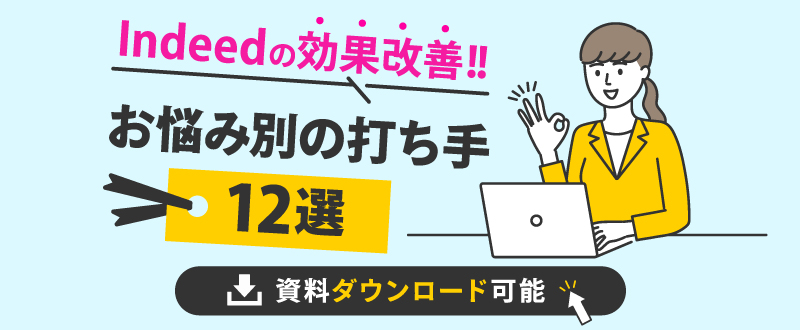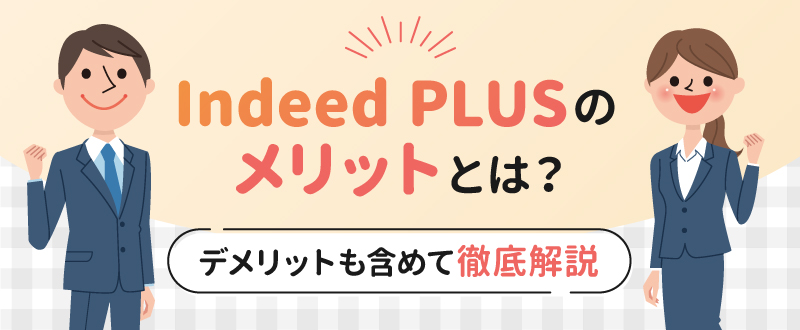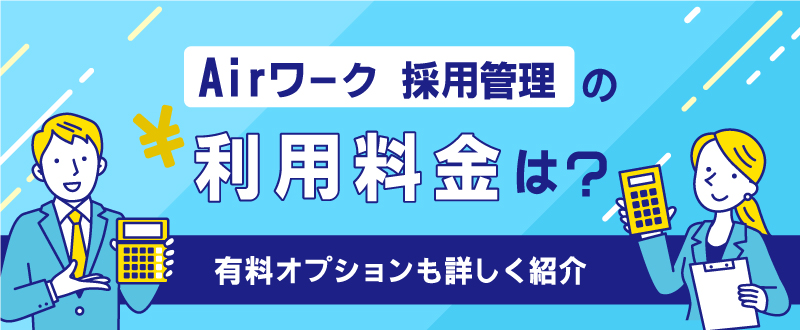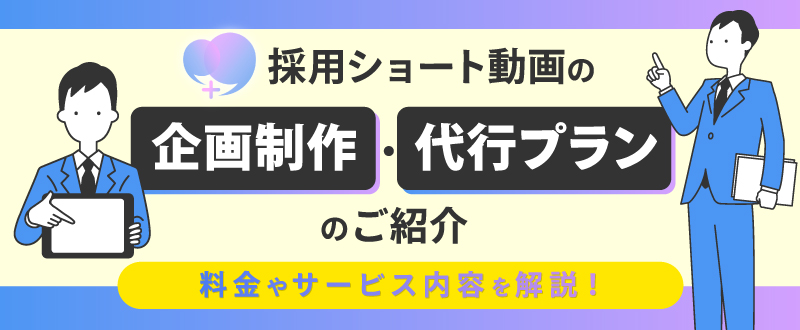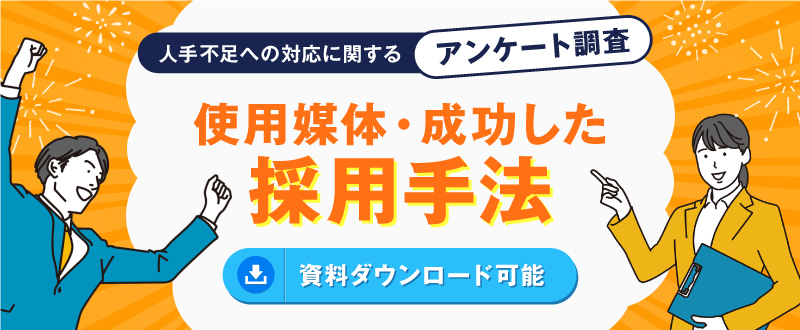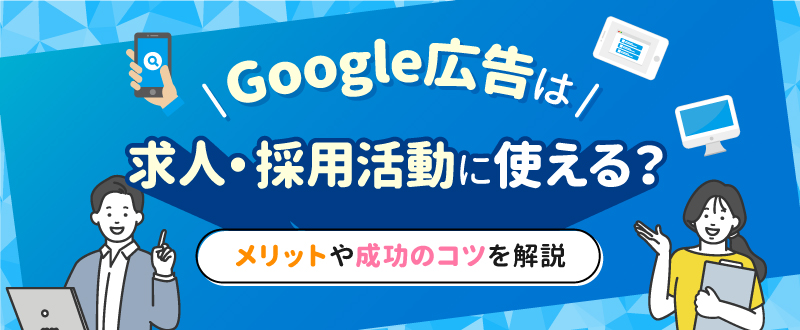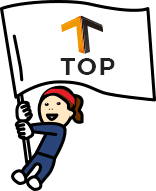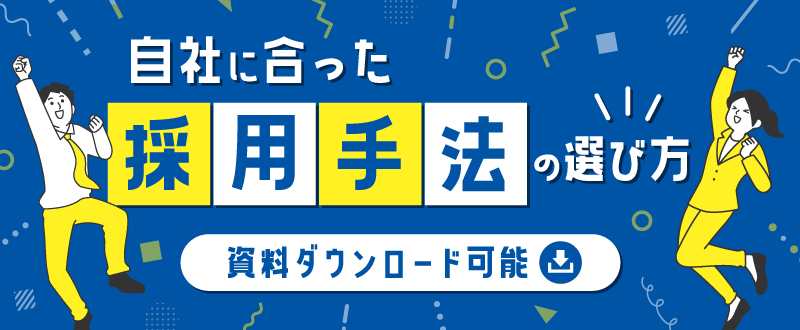
トラコム社員がお届け!
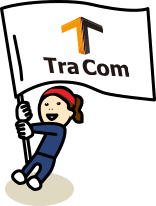
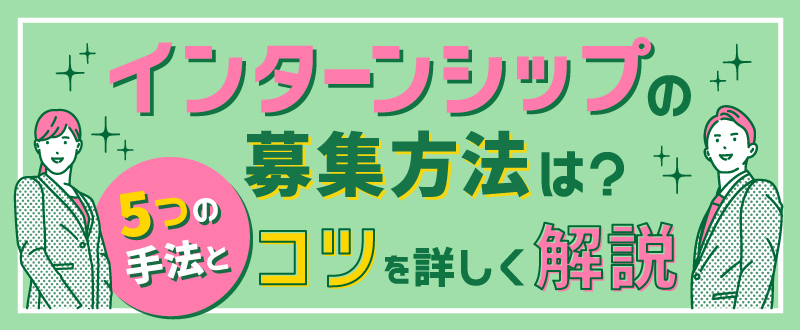
インターンシップは新卒採用におけるアプローチ手法として多くの企業が導入しています。
経団連が2025年卒の就活から「採用に直結するインターンシップ」を認めたことからも、ますます注目を集めています。
インターンシップを導入したいものの、学生をどのように募集するべきか疑問を抱えている担当者の方も多いかもしれません。
そこで本記事では、インターンシップの募集について、5つの手法とコツを詳しく解説します。
インターンシップのメリット・重要性
インターンシップとは、学生が関心を持っている企業で実際に働いてみるプログラムです。
「職場体験」の目的で、学生の勉強の一環として行われることもありますが、企業が自社の求める人材を探す「採用目的」のインターンシップも多く開催されています。
経団連は以前、採用に直結するインターンシップを認めていませんでしたが、25年春入社の採用活動から認める方針に転換。
こうした流れもあり、今後ますます採用目的のインターンシップが盛んになっていくと考えられています。
企業側にとってのインターンシップのメリットは以下の通りです。
- 早期接触
- ミスマッチ防止
- 早期戦力化
インターンシップを開催することで学生と「早期接触」でき、人材獲得競争で遅れを取らないようにできるといったメリットがあります。
さらに体験を通じて業務の理解を深めてもらうことで「ミスマッチ防止」になるだけでなく、業務に必要な最低限の知識を身につけてもらうことができ、新卒人材の「早期戦力化」にもつながります。
インターンシップについて詳しくは、こちらのページもご参照ください。
【企業向け】インターンシップとは?種類やプログラム内容、実施のポイントを解説
インターンシップの募集時期は?いつから可能か
夏のインターンシップは「5〜6月ごろ」に募集を開始するのが一般的です。
6月頭には、求人サイト・ナビサイトの「プレサイト」がオープンし、多くの企業がインターンシップの募集を始めます。
インターンシップを含む新卒採用のスケジュール・時期ごとの進め方について詳しくは下記ページをご参照ください。
【企業向け】2025年卒、新卒採用スケジュールの全体図と企業動向について解説
秋冬に開催するインターンシップの募集時期は、企業によってさまざまですが、「9〜10月ごろ」に募集を始める企業が多いです。
インターンシップには解禁日などの決まりはないため、いつでも募集は可能ですが、基本的に学生の長期休暇と重なるようにスケジュール設定するのがおすすめです。
例えば夏のインターンシップであれば、夏休みの時期に開催すると学生が参加しやすくなります。
インターンシップの募集方法5選
インターンシップの募集方法は、以下の5つです。
・自社のホームページ・SNS
・インターンシップサイト・ナビサイト
・大学のキャリアセンター
・説明会・イベント
・インターンシップ集客サービス
上記の方法について、それぞれ詳しく解説します。
自社のホームページ・SNSで募集する
自社のホームページやSNSアカウントなど、「自社の運用するメディア」にインターンシップの情報を掲載する方法です。
自社が保有しているメディアで募集するため、掲載料金がかからないことがメリットです。
ただし掲載するだけで閲覧されるとは限らないため、「集客」の施策も同時に行う必要があります。
特に自社の知名度が低い場合は、そもそも学生がインターンシップの募集を認知すること自体が難しくなるため、集客方法を工夫しなければ定員まで集まらない可能性もあるでしょう。
次から紹介する他の募集方法も併用して、できるだけ多くの学生に認知してもらうことが重要です。
インターンシップサイト・ナビサイトに掲載する
「インターンシップサイト」と呼ばれる専用サイトや「ナビサイト」への掲載は、インターンシップ募集方法のなかでも代表的なものです。
インターンシップサイトとは、インターンシップを開催したい企業と参加したい学生をマッチングさせるサービスです。
インターンシップを検討している企業の多くがこちらを利用しているため、メインの方法の1つとして検討しておくとよいでしょう。
また一般的なナビサイトもインターンシップの募集に利用できます。
代表的なナビサイトであるリクナビでは、グランドオープンの3月よりも前に「プレサイト」がオープンし、インターンシップの情報を掲載できるようになっています。
詳しくは以下のページをご参照ください。
リクナビ2025プレサイト最新情報|2024年卒生の振り返りから見る学生の就活の変化
大学のキャリアセンターを利用する
大学のキャリアセンターに依頼して、インターンシップに参加してもらう学生を募集することもできます。
キャリアセンターは大学のなかで学生の就職活動支援などを行っている部署です。
学生だけでなく企業とのやり取りもしており、インターンシップの募集も依頼できます。
キャリアセンターには学生のデータがそろっているため、「学部」や「学科」などに絞って募集できることがメリットです。
ただし自社に対する志望度が高くない学生が申し込みをしてくることもあるため、自社に興味を持ってもらうよう、プログラム内容をしっかり計画することが重要です。
説明会・イベントを開催する
説明会・イベントを開催してインターンシップを募集する方法もあります。
例えば合同説明会で、ブースに来てくれた学生に対してインターンシップの募集を呼びかけることができます。
合同説明会では他の企業を目当てにしている学生も含めて一度にたくさんの学生に呼びかけられることがメリットです。
また自社で独自のイベントを開催して、そこで学生と接触する方法もあります。
例えば、少数の学生を集めて開催する「セミナー」などです。
大規模な説明会に比べて接触できる学生の数は少ないものの、その分一人一人と質の高いコミュニケーションがとれます。
自社のターゲットとする学部・学科の学生に絞り込むなど、参加者の質を高めやすいこともメリットです。
インターンシップ集客サービスを利用する
インターンシップ集客サービスを導入する方法もあります。
インターンシップ集客サービスとは、「学生送客サービス」とも呼ばれるもので、企業の代わりに学生を集客してくれるサービス全般を指します。
インターンシップ集客サービスのメリットは、事前に大学や学部・学科などの条件を設定できるため、自社が理想とする母集団形成がしやすいことです。
利用料金は「成果報酬型」で、結果的に学生が集まらなかった場合は費用がかからないのが一般的です。
インターンシップ集客サービスは、採用代行会社などで利用できます。
採用代行について詳しくは下記ページをご参照ください。
採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットやサービスの選び方を解説
インターンシップの準備・募集から当日までの流れ
インターンシップの準備・募集から当日までの流れは、以下の4ステップです。
- 実施する目的や期間を決める
- プログラムの準備
- 募集方法の選定・募集スタート・選考
- インターンシップの実施・開催後のフォロー
下記ボタンより、インターンシップ開催のコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
1.実施する目的や期間を決める
まずはインターンシップの目的・期間を設定します。
期間については、1〜2日ほどの短期の募集にするのか、数週間〜数カ月にわたる長期インターンシップにするのかを決定しましょう。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 短期インターンシップ | ・低コストで多くの学生と接触できる ・自社の魅力を深く知ってもらうことや、学生を深く理解することが難しい |
| 長期インターンシップ | ・学生との相互理解が深まりやすい ・コストや社員の負担が大きい |
時期は、大きく分けて夏と秋冬の2種類です。
それぞれの特徴は以下の通り。
| 夏季インターンシップ | ・学生と早期接触ができ、母集団形成をしやすい ・本選考までつなぎとめておくのが難しい。 ・夏季は多くの企業がインターンシップを開催するため、競争率が高い |
| 冬季インターンシップ | ・選考に直結しやすく、志望度の高い学生に集中できる ・学生とのスケジュール合わせが難しい |
いずれもインターンシップの目的に合わせて決めるのがおすすめです。
インターンシップの開催期間・時期ごとのメリット・デメリットについて詳しくは、下記ページでも解説しています。
【企業向け】インターンシップとは?種類やプログラム内容、実施のポイントを解説
2.プログラムの準備
次に、設定した目的を達成できるようなプログラム内容を準備します。
例えば以下のようなプログラムが代表的です。
- セミナー
- 職場見学
- 業務体験
1回のインターンシップで1つのプログラムを実施する場合もありますが、複数のプログラムを組み合わせることもあります。
例えば長期のインターンシップであれば、募集した学生とじっくり向き合えるため、セミナーをした後に業務体験をしてもらうといったプログラムも組めるでしょう。
プログラムを準備する際は、スムーズに実施できるよう「社内体制」を整えておくことも重要です。
関係者への周知とスケジュール調整などを徹底しておきましょう。
3.募集方法の選定・募集スタート・選考
プログラムが決まったら、募集方法を選ぶ段階です。
「インターンシップの募集方法5選」で紹介した方法を参考に、自社に合ったものを選択しましょう。
応募者が定員より多い場合は、「選考の実施」もしくは「実施日数を増やす」などして対応する必要があります。
選考は書類審査だけで済ませるのか、それとも面接を実施するのかといった詳細も決めておき、スムーズに対応できるようにしておきましょう。
もちろん定員割れを起こしてしまう可能性もあります。
複数のシチュエーションを想定しつつ、どのように対応するかをあらかじめ決めておくことが大切です。
4.インターンシップの実施・開催後のフォロー
無事に募集が完了したら、いよいよインターンシップの開催です。
インターンシップ当日にプログラムをスムーズに進められるよう、事前の準備を徹底しましょう。
インターンシップ開催後のフォローも重要です。
例えば夏にインターンシップを実施した場合は、そこでつながりができた学生を、本選考までつなぎ止めておく必要があります。冬のインターンシップも同様です。
適切なフォローの有無によって、採用につながるかどうかが決まるといっても過言ではありません。
インターンシップ開催後のフォローには、対面でのフォローやオンラインでの接点など、さまざまな方法があります。
詳しいフォロー方法については、次の項目で詳しく解説します。
インターンシップ参加者を選考・採用につなげるためのコツ
インターンシップから選考・採用までスムーズにつなげるためのコツについても確認しておきましょう。
優秀なインターンシップ参加者を選考や採用につなげるためには、募集・実施後に以下のようなフォローをすることが重要です。
- 対面でのフォローを実施する
- オンラインでの接点を保つ
- 選考での優遇も検討する
それぞれ以下に詳しく解説します。
対面でのフォローを実施する
インターンシップ後に「対面」で学生とコミュニケーションをする形のイベントを開催することは、採用につなげるための有効な方法です。
代表的なものとしてよく挙げられるのが「社内イベント」で、自己分析講座や面接対策講座などの各種講座や、就活相談会などの「就活お役立ち系」の内容が定番です。
また自社の魅力を訴求するために、OB・OG訪問やリクルーター面接などを実施する方法もあります。
説明会やイベントでは伝わりにくい、「リアルな情報・雰囲気」を届けられるため、学生に入社後の具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。
対面でのフォローにはさまざまな方法があるため、インターンシップのプログラムなどを考える際に、自社に合ったものを同時進行で決めておくとよいでしょう。
オンラインでの接点を保つ
インターンシップ後は「オンライン」での接点を保つことも大事です。具体的な方法としては、LINEやメールを使ったメッセージがあります。
電話や書面でのやり取りとは異なり、気軽に送付できることがメリットです。
メッセージ内に誘導したいURLを挿入したり、メルマガを配信したりと、メッセージツールには多様な活用方法があります。
ただしあまりにも高頻度でメッセージを送信すると、「しつこい企業だ」と思われてしまう可能性もあるため、さじ加減が大切です。
対面でのフォロー方法として各種講座や相談会をご紹介しましたが、それらはWeb会議ツールなどを使ってオンラインで実施することもできます。
地理的要件を問わないため、遠方の人でも気軽に参加しやすいことが魅力です。
おすすめのWeb会議ツールについては下記ページをご参照ください。
用途別おすすめ!WEB会議システム比較表12選。面接用や無料ツールも紹介
選考での優遇も検討する
インターンシップ参加者に対して「選考での優遇」という特典を用意してもよいでしょう。
例えば、選考フローに複数段階の面接を設定している場合は、「一次面接免除」という形での優遇が可能です。
面接の回数が減ることで、入社へのハードルを下げることになり、インターンシップ参加者を本採用まで誘導しやすくなります。
インターンシップ参加者に「内定パス」を発行する企業もあります。
内定パスとは、一定の期間以内であれば、いつでも入社できる権利です。
期間としては5年以内が一般的で、もし他の企業に新卒で入社してしまったとしても、期間内であれば社会人経験を積んだ状態で自社に入社してもらえる可能性もあります。
インターンシップ募集のご相談はトラコムへ
インターンシップに学生を募集する方法として代表的なものは「インターンシップサイト・ナビサイト」への掲載です。
代表的なナビサイトの1つ「リクナビ」でのインターンシップ募集方法について詳しくは下記ページをご参照ください。
リクナビ2025プレサイト最新情報|2024年卒生の振り返りから見る学生の就活の変化
他にも自社のホームページ・SNSや、大学のキャリアセンター、説明会・イベントなどいくつかの方法があります。
インターンシップ募集にあまり手間をかけられない、どうすればよいか分からないといった場合には、採用サポートサービスの利用がおすすめです。
弊社トラコムでは「新卒採用向けのサポートサービス」をご用意しています。
さらに新卒採用だけでなく、採用全般のコンサルティングや、求人広告の運用代行など、採用にまつわる幅広いサポートをご依頼いただくことが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
インターンシップに関連する記事
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る