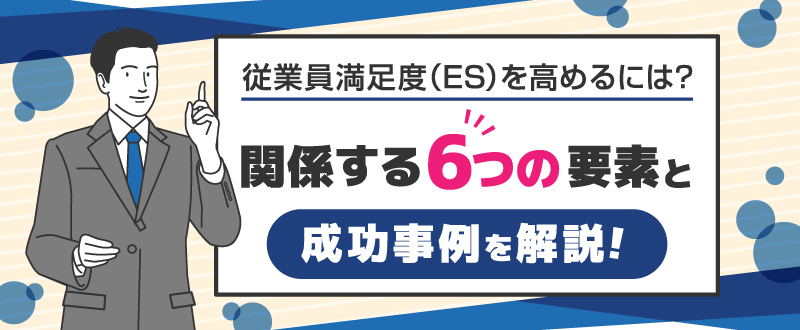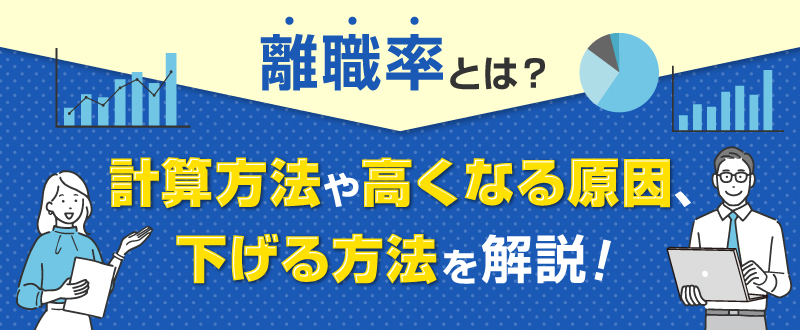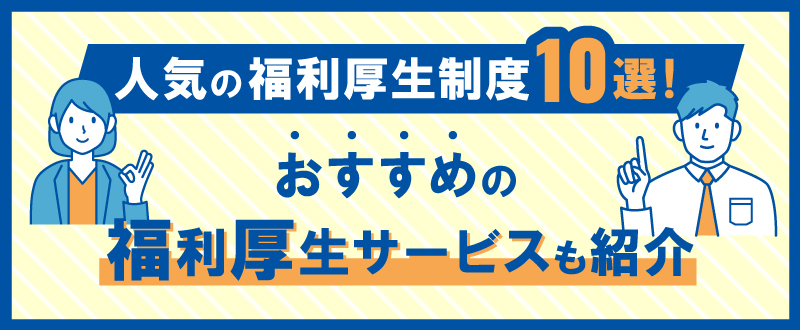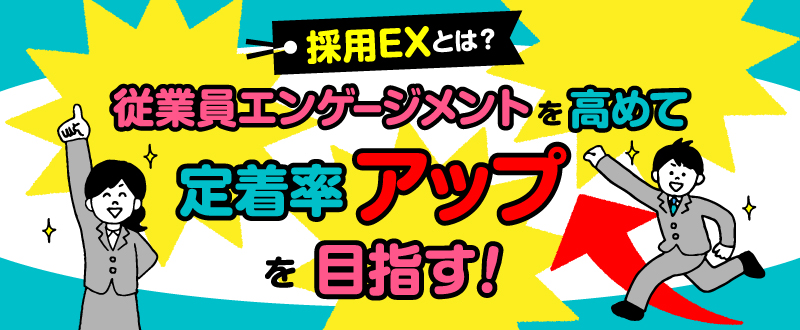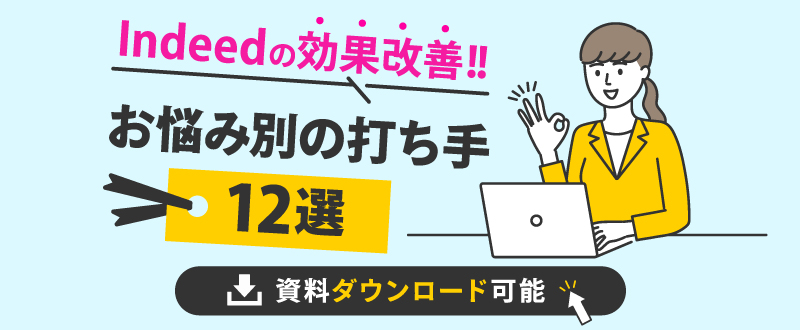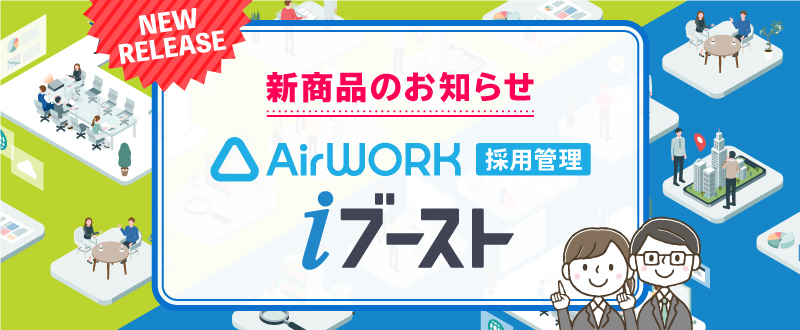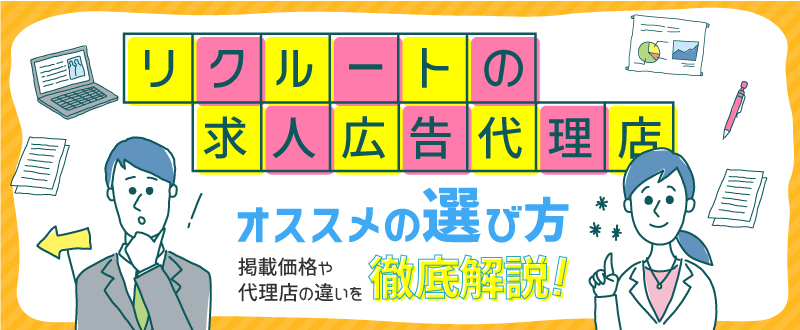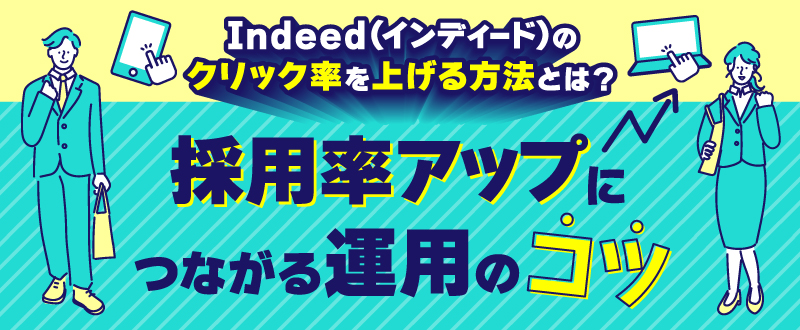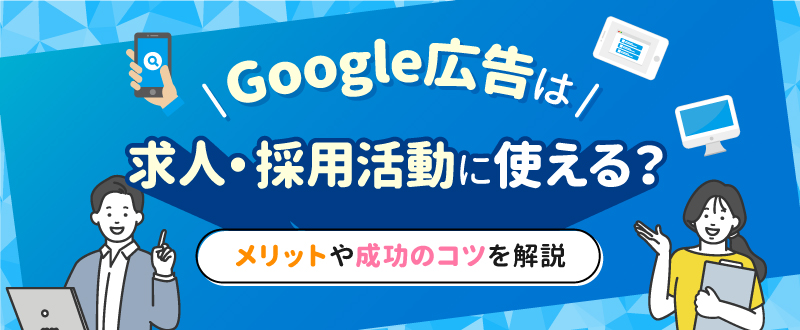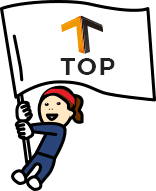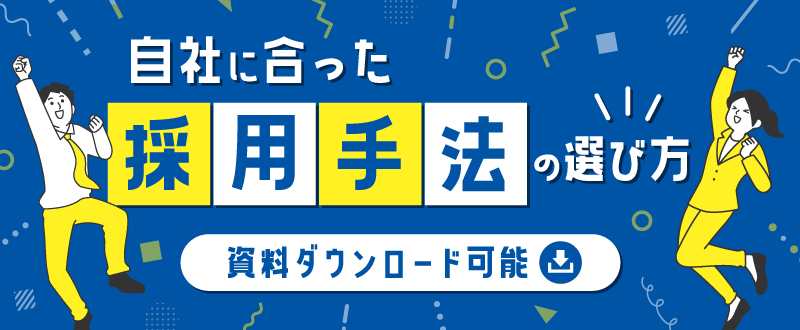
メルマガ登録で最新情報をゲット!
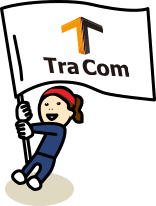
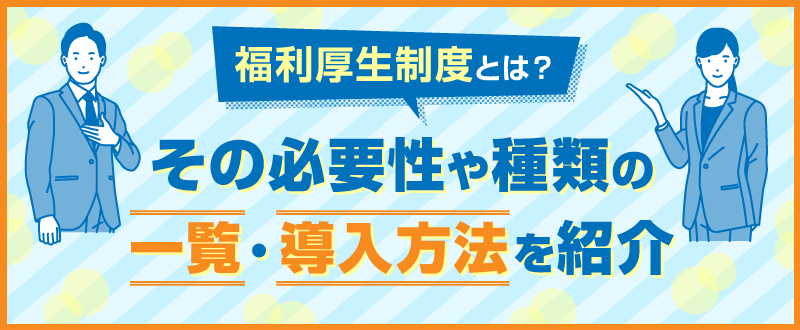
企業の待遇面で重要な要素の一つが「福利厚生」です。昨今では、従業員のニーズを反映した、独自の福利厚生を導入する企業も出てきています。よく聞くワードではありますが、「詳しい意味がよく分かっていない」という方も多いかもしれません。
そこで本記事では、福利厚生制度の概要やメリット、導入方法について解説します。質の高い福利厚生制度を整備するためのポイントについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
福利厚生制度とは何か
福利厚生とは、給料などの基本的労働条件とは別に、企業が従業員やその家族の生活向上のために行う取り組みのことです。主に従業員の健康・安全・幸福などを促進し、職場での満足度と生産性を高めることを目的としています。
福利厚生制度は、求職者が企業選びで重視する要素の1つです。企業にとっても、従業員満足度やロイヤリティを高めたり、優秀な人材を引きつけたりするために重要なものです。
法定福利厚生とは
「法定福利厚生」とは名前の通り、法律で定められた福利厚生のことです。具体的には以下の保険料の全部または一部を企業が負担することが含まれます。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
法定福利厚生に含まれず、企業が独自で設置しているものを「法定外福利厚生」と呼びます。企業活動においては、「法定福利厚生」とともに、「法定外福利厚生」にも力を入れることが重要です。詳しくは、当ページの「どんなものがある?法定外福利厚生の種類一覧」をご参照ください。
なぜ必要?福利厚生制度の意味・メリットとは
福利厚生制度の意味・メリットは、以下の3点です。
- 人材確保がしやすくなる
- 生産性・パフォーマンス向上ができる
- 企業イメージアップ・ブランディングになる
上記のメリットについて詳しく解説します。
人材確保がしやすくなる
福利厚生制度を充実させると、求人募集のしやすさや離職防止につながり、人材確保がしやすくなります。
求職者は仕事を探す際、その会社の福利厚生に注目して選ぶことがあります。リクルートジョブズの「求職者の動向・意識調査2021」によれば、仕事を探す際に「福利厚生」を絶対条件とすると回答した人の割合は22%です。特に正社員は28.6%と高い割合を占めています。
福利厚生を充実させることで「社員を大切にする企業」としてイメージアップにもつながり、求人への応募が集まりやすくなることが期待できます。
生産性・パフォーマンス向上ができる
福利厚生制度を整備すると、生活の充実や健康促進につながり、モチベーション向上・生産性アップが期待できます。
例えばフィットネスプログラム、カウンセリングなどは、従業員の心身の健康維持につながる福利厚生です。福利厚生によって従業員の心身を良好な状態に保つことで、会社全体としての生産性の向上が期待できます。
さらに従業員の離職率を低下させ、人材の採用と育成にかかるコストを削減できるなど、人材確保のパフォーマンス向上にもつながります。
企業イメージアップ・ブランディングになる
福利厚生が充実した会社として知られることで、企業イメージアップやブランディングになるといった効果も期待できます。採用市場での競争が激化するなか、充実した福利厚生制度は、優秀な人材を引きつけるための重要な要素です。
さらに企業が従業員の心身の健康に投資することで、「企業の社会的責任を果たしている」という観点でのブランディングも可能です。ミレニアル世代やZ世代のような若い世代に対しても、企業イメージを向上させる効果が期待できます。
福利厚生の充実によって従業員満足度が高くなるとともにサービスの質も向上し、それによってサービスを受ける消費者からの評価が上がるといった良い循環にもつながります。
どんなものがある?法定外福利厚生の種類一覧
労働政策研究・研修機構の分類によれば、法定外福利厚生は、以下の10種類48例が挙げられています。
| 種類 | 具体例 |
| 財産形成 | 1.財形貯蓄制度 2.社内預金制度 3.従業員持株制度・持株会 4.ストックオプション制度 5.住宅取得のための融資制度 6.金融関係の相談・セミナー 7.教育、結婚等住宅以外の臨時支出に対する貸し付け |
| 食事 | 8.食堂 9.食事手当 10.外部飲食店で利用できる食券等の配布 |
| 健康管理 | 11.診療所、健康管理センター等医療施設 12.メンタルヘルス相談 13.人間ドック受診の補助 14.運動施設の設置 15.運動施設・フィットネスクラブの利用補助 |
| 両立支援 | 16.法定を上回る育児休業・短時間制度 17.企業内保育施設や保育サービス(ベビーシッターなど)、情報の提供 18.法定を上回る介護休業制度 19.介護のための施設やサービス(ヘルパーなど)、情報の提供 20.治療と仕事の両立支援策 |
| 休暇制度 | 21.病気休職制度22.病気休暇制度(有給休暇以外) 23.リフレッシュ休暇制度 24.ボランティア休暇制度 25.慶弔休暇制度 26.有給休暇の日数の上乗せ(GW、夏期特別休暇など) |
| 自己啓発 | 27.社内での自己啓発プログラム 28.社外の自己啓発サービスの提供、経費補助 29.社外の自己啓発に関する情報提供 30.自己啓発のための休暇等の付与 |
| 慶弔災害 | 31.慶弔見舞金制度 32.永年勤続表彰 33.遺族・遺児年金 34.労災補償給付の付加給付 |
| 住宅 | 35.世帯用住宅・寮の整備 36.家賃補助や住宅手当の支給 |
| 余暇活動 | 37.保養施設、レクリエーション施設等の提供、利用補助 38.運動会等のレクリエーション活動の実施 39.社員旅行の実施、補助 |
| 働き方 | 40.短時間勤務制度 41.フレックスタイム制度 42.テレワーク 43.ノー残業デー等の設置 44.時差出勤 |
| 高齢者 | 45.退職前準備教育(セミナーなど) 46.定年退職後の医療保障 47.定年退職後の保養施設、レクリエーション施設の利用 48.OB会等定年退職後の親睦活動 |
出典:調査シリーズNo.203 企業における福利厚生施策の実態に関する調査 ―企業/従業員アンケート調査結果―(図表 2-2-1 法定外福利厚生制度・施策)労働政策研究・研修機構
人気の高いおすすめの法定外福利厚生については、下記ページをご参照ください。
福利厚生制度を導入する方法
福利厚生制度を導入する方法としては「自社で制度を構築する」か「福利厚生サービスを利用する」かの2つがあります。それぞれの概要や、「どのような企業に向いているか」といった点を中心に見ていきましょう。
自社で制度を構築する
1つ目は、自社で制度や設備を用意する方法です。特に「住宅手当」「家賃補助」といった、金銭的な負担をする福利厚生については、自社での導入が向いています。大企業では、企業と従業員によって出された資金を財源とする「共済会」を設立するケースも少なくありません。
自社で制度を構築すると、従業員の特定のニーズや企業文化に合わせてカスタマイズすることが可能です。従業員との直接のコミュニケーションも容易なため、反応やフィードバックを即時に得て、そのまま制度に反映できます。
ただし導入と管理には時間とリソースが必要です。導入する福利厚生の性質にもよりますが、制度設計と実施に関する専門知識が必要なこともあり、特に中小企業では導入のハードルが高い場合があります。
福利厚生サービスを利用する
福利厚生サービスに加入して、外部サービスとして従業員に提供することも可能です。
福利厚生サービスとは、レジャー施設の利用割引や飲食店の割引など、従業員に対して外部サービスとして福利厚生制度を提供できるサービスです。中小企業での導入に適したタイプや、カフェテリアが充実しているタイプなど、さまざまな福利厚生サービスがあります。
福利厚生サービスのメリットは、福利厚生の整備・管理にかかる社内リソースを削減でき、自社のコア業務に集中しやすくなることです。月額会費などを支払えばすぐにでも利用でき、自社で用意する福利厚生と併用することもできます。
質の高い福利厚生制度を整備するためのポイント
質の高い福利厚生制度を整備するためのポイントは、以下の3点です。
- 従業員のニーズを反映させる
- 効果分析・調整を行う
- 従業員満足度の向上とあわせて検討する
それぞれ以下に詳しく解説します。
従業員のニーズを反映させる
まずは従業員のニーズや要望を把握して、それを反映した福利厚生制度を検討しましょう。
企業の組織体系は多種多様であり、そこで求められる福利厚生も大きく異なってきます。他の企業の事例を真似るだけではなく、自社の従業員にマッチするものを選ぶことが大切です。
例えばアンケート調査や従業員との対話を通じて、従業員が望む福利厚生制度を理解するといった方法があります。このプロセスは匿名で行うと、より正確なフィードバックを得やすくなるでしょう。
調査結果を参考にすることで、どの種類の福利厚生が「最も需要が高いのか」「最も効果的であると考えられるのか」を検討できます。その際、従業員の年齢や家族の状況、ライフスタイルなどの要素を考慮に入れることも重要です。
効果分析・調整を行う
福利厚生制度を導入したら、効果分析・調整を行いましょう。福利厚生制度が目指す目標に対して、どれほどの効果があったかを評価することが重要です。
アンケートによるフィードバックや、制度やサービスの利用率のモニタリングなど、さまざまな方法が考えられます。ただし従業員のニーズを調査する際と同様、必要に応じて匿名の調査を入れることで、より質の高いデータが集まりやすくなるでしょう。
効果分析の結果を受けて調整を行うことも重要です。予算の許す範囲で可能な限り従業員の声を取り入れていくことで、満足度の高い福利厚生制度を整備しやすくなります。
従業員満足度の向上とあわせて検討する
福利厚生制度は、「従業員満足度の向上」という全体像を意識しながら整備することが重要です。福利厚生制度の整備は、あくまでも従業員満足度を高める「方法の一つ」に過ぎません。福利厚生の他にも、従業員満足度に影響する要素はたくさんあります。例えば以下の点です。
- 各従業員に合った業務内容を用意する
- 職場のコミュニケーションを活性化させる
- 適正かつ公平な評価システムを構築する
- 企業のビジョン・ミッションを浸透させる
これら他の要素も考慮しつつ、「どのような福利厚生を導入するか」を検討することが重要です。従業員満足度について詳しくは以下をご参照ください。
従業員満足度(ES)を高めるには?関係する6つの要素と成功事例を解説
福利厚生制度についてよくある疑問
パート・アルバイトも福利厚生制度の対象?
結論からいえば、パート・アルバイトも福利厚生制度の対象に含まれます。
一定の条件を満たすパート・アルバイトの従業員は、健康保険や雇用保険などの社会保険に加入することが義務付けられており、正社員と同様の福利厚生を受けることも可能です。
特に2020年4月1日に改正された「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されたことから、パート・アルバイトにも平等に福利厚生制度を適用することが重要です。
「改正パートタイム・有期雇用労働法」では、同一企業内で、正社員と非正規社員の間での「不合理な待遇差」を設けることを禁止しています。正社員との待遇差に対しては、パート・アルバイト従業員が事業者側に説明を求めることが可能です。この法律は2021年4月1日からは、中小企業にも適用されています。
福利厚生と手当の違いは?
福利厚生は従業員全員が対象ですが、手当は条件に当てはまる人が対象となる点が異なります。
手当は、基本給以外の特定の目的や条件に基づいて支払われる追加の給与を指します。例えば「職務手当」は、仕事の難易度や責任の度合いに応じて支払われるものであり、「特定の職務を全うしていること」が条件となります。条件を満たしていない人には、手当は支払われません。
一方の福利厚生は、健康保険・年金制度・食堂・レクリエーション施設の利用など、従業員全員が平等に活用できるものです。
上記からも分かるように、福利厚生はより広範で、従業員の生活全般をサポートするためのものです。一方の手当は、特定の条件に対する「給与の補足」であり、役割が大きく異なっています。
従業員1人あたりどのぐらいの福利厚生費がかかる?
厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査」によれば、従業員1人あたりどのぐらいの福利厚生費は以下の通りです。
- 従業員1人1ヶ月あたりの「法定福利費」は、平均で5万283円
- 従業員1人1ヶ月あたりの「法定外福利費」は、平均で4,882 円
上記調査の法定外福利費の内訳は「住居に関する費用」「医療保険に関する費用」「食事に関する費用」が中心となっており、特に住宅に関する費用が平均で50%以上を占めています。
ただし法定外福利費については、業種や会社の規模によっても目安が異なります。自社の法定外福利厚生費が平均を超えているからといって、従業員が「福利厚生が充実している」と感じているとは限りません。自社の従業員のニーズに合っているかどうかを検討することが重要です。
まとめ
福利厚生の充実度は、今後の採用活動をも左右する重要な要素です。自社にとって効果的な福利厚生制度が何かを十分に検討し、従業員のニーズに合わせて必要なものを見極めることが大切です。
自社で福利厚生の体制をつくるのが難しいという場合、「福利厚生サービス」の活用がおすすめです。弊社では福利厚生サービスのご案内ができますので、お気軽にご相談ください。
関連する記事

この記事を書いた人
R.UEYAMA
この人の記事一覧を見る
2015年に中途入社し、京阪エリアサービスに配属。
枚方市・京阪エリアを中心にアルバイト・社員領域をメインに担当。
2016年、2017年リクルートクラストップ賞受賞
2018年からユニットリーダーに就任。
2020年リクルートFM部門クラスMVP受賞
最新の採用事例やノウハウ、新着ブログ、セミナーなど
採用活動全般にプラスになる情報をお届けします。
ご登録いただく前にプライバシーポリシーをご一読ください
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る