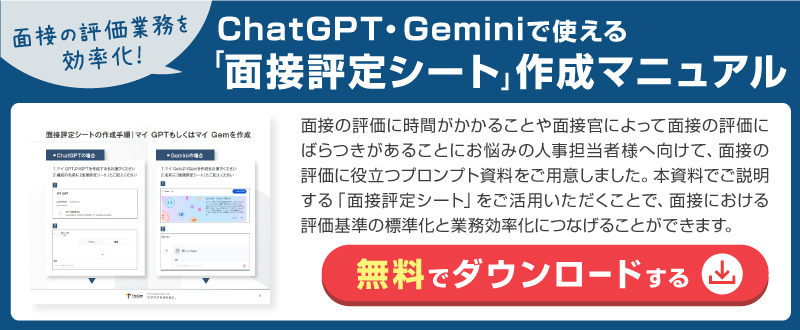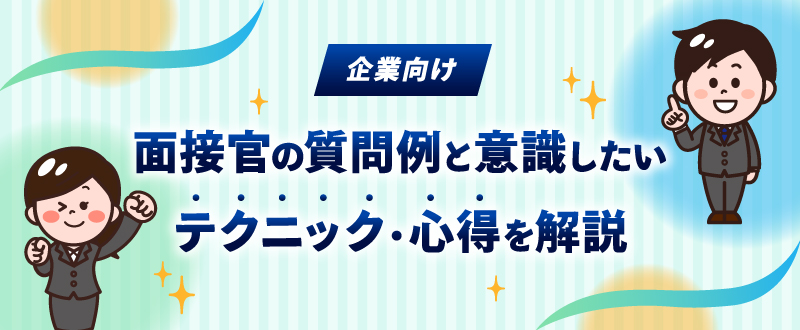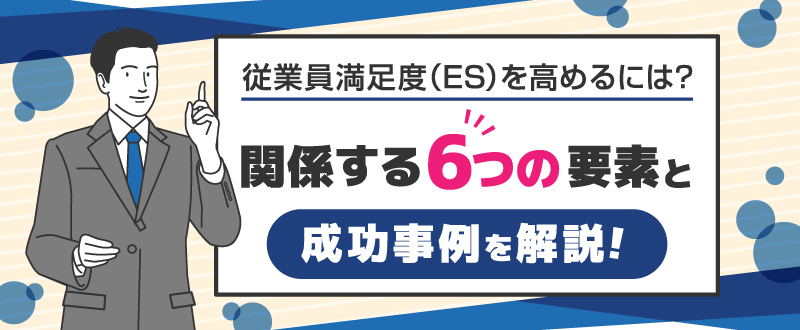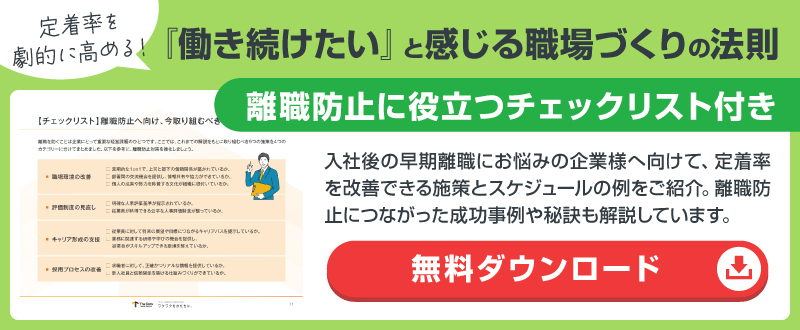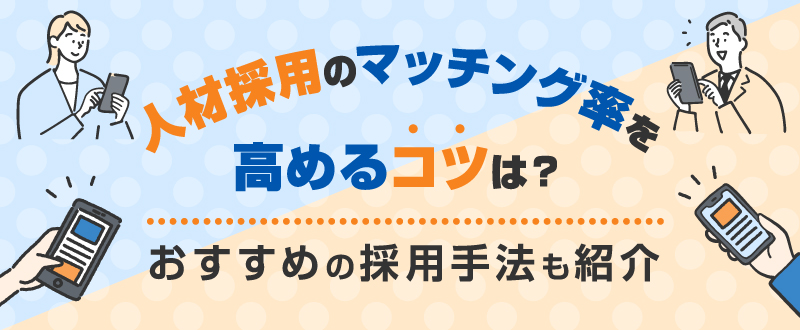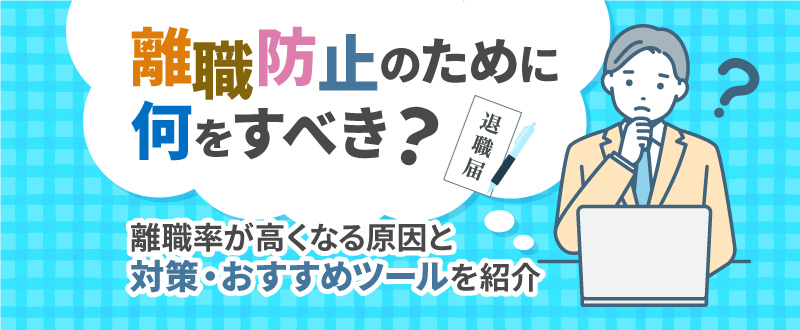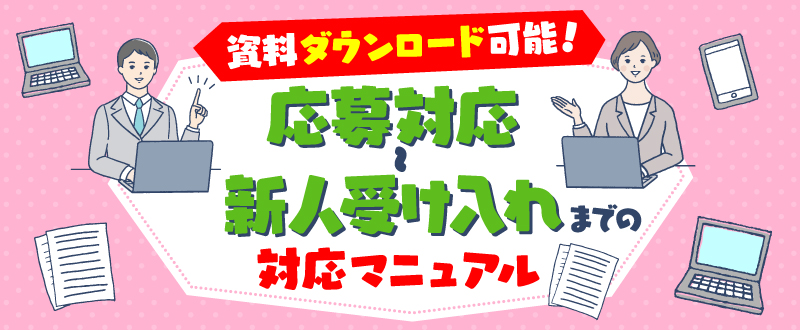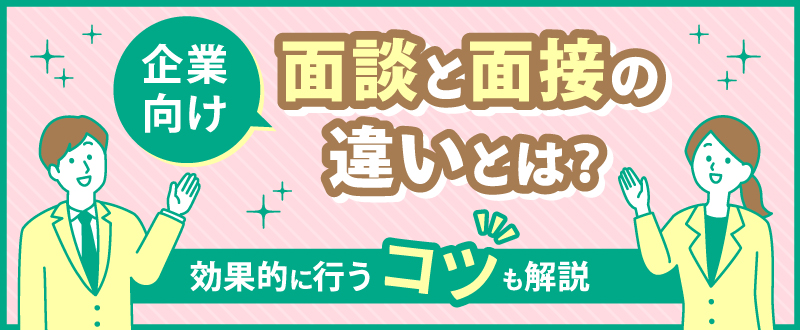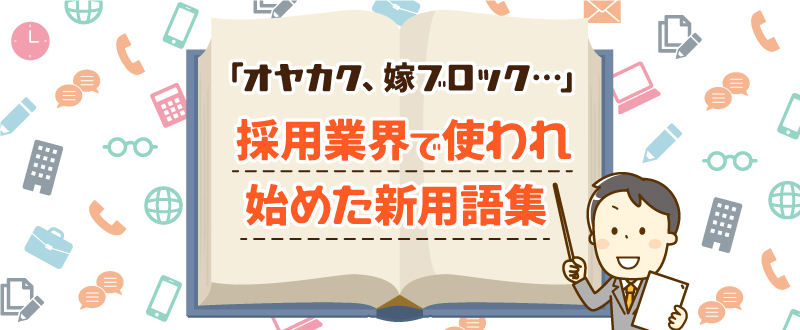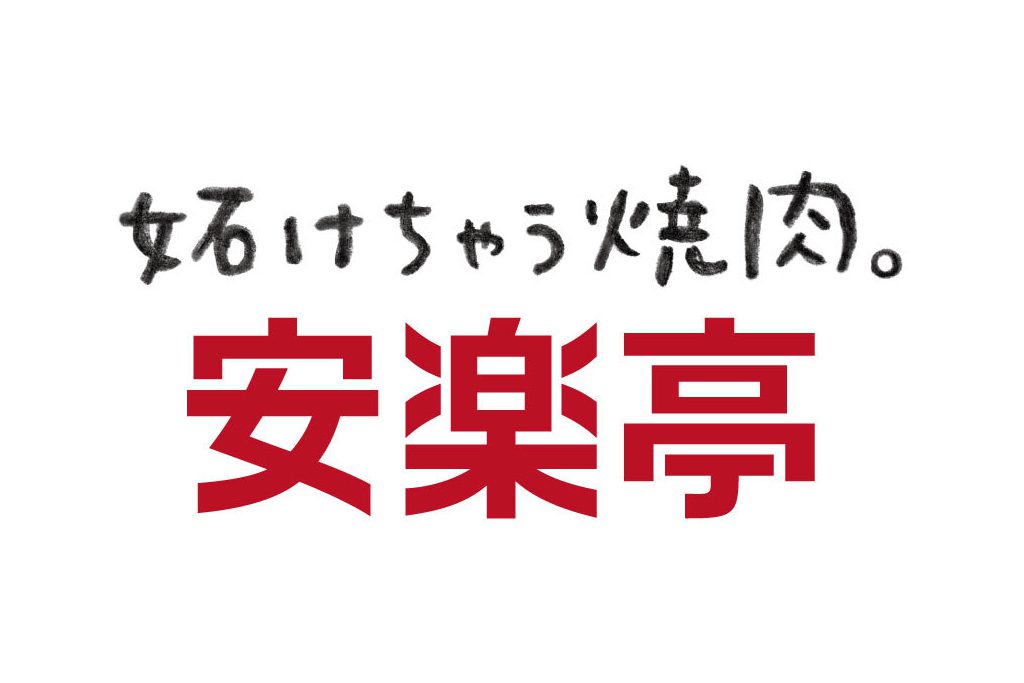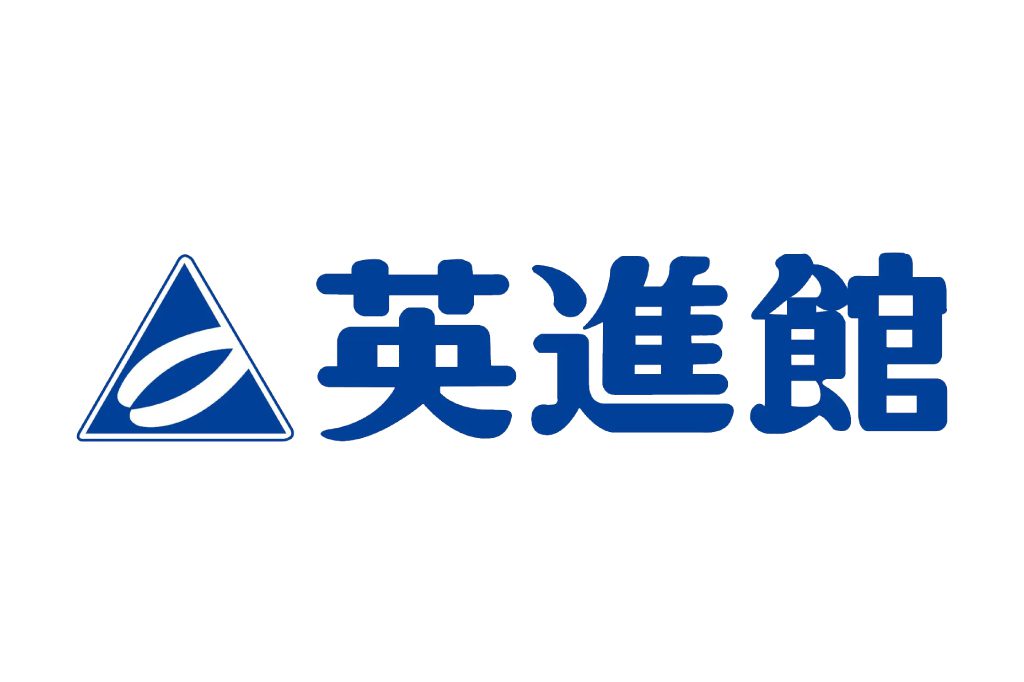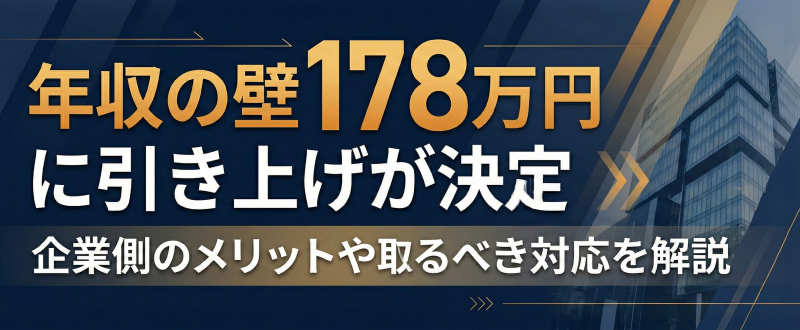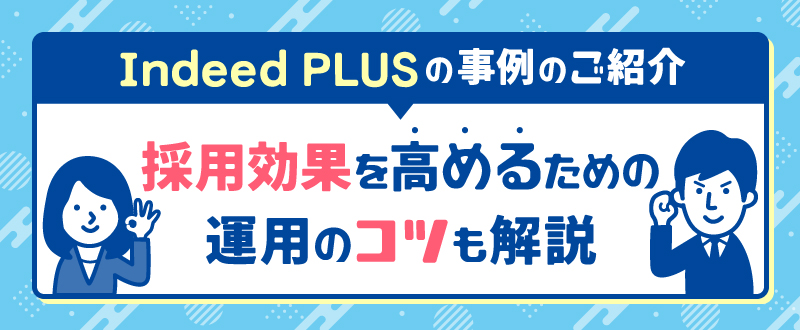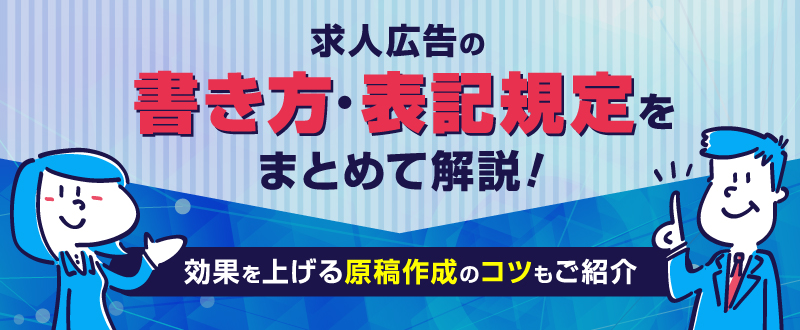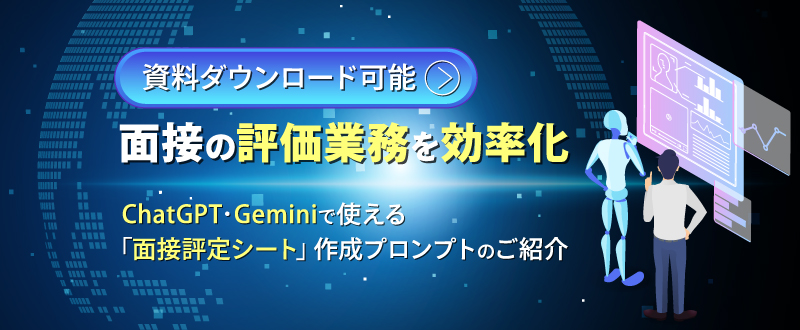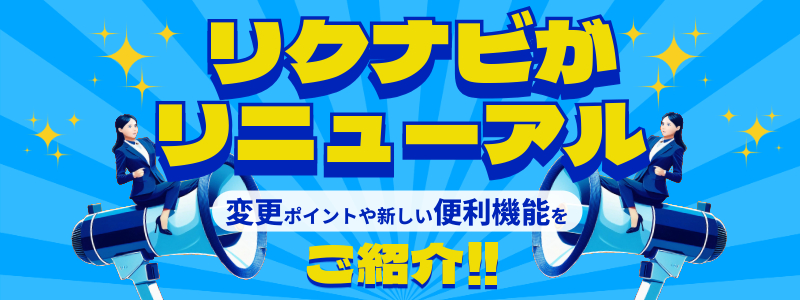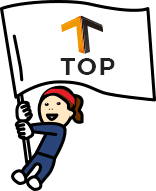トラコム社員がお届け!
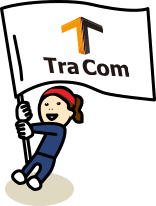

人材採用において特に避けたいことの1つが「採用ミスマッチ」です。いかに採用ミスマッチを避けるかが、人材採用の成功を大きく左右するといえます。採用ミスマッチを避けるために、どのような対策を取ればよいのでしょうか。
当ページでは、採用ミスマッチのよくある事例・原因と、防止に役立つ10の対策を解説します。具体的な成功事例も紹介しているので、ぜひご参照ください。
採用ミスマッチとは
採用ミスマッチとは、採用した人材と企業側で認識のズレが生じることです。人材側は「入社してみたら、思っていたような仕事じゃなかった」、企業側は「自社に合うと思って採用したが、実際にはマッチしなかった」といった、認識と現実にズレが生じることを指します。
採用ミスマッチは「早期退職」といった結果につながることもありますが、そのような分かりやすい結果にならないこともあります。採用ミスマッチが社員の不満の蓄積やパフォーマンス低下といった形で、水面下で悪影響を及ぼすこともあるため、「早期離職が少ない=採用ミスマッチが発生していない」とは限りません。
採用ミスマッチが及ぼす悪影響について詳しくは、次に解説します。
採用ミスマッチが企業に及ぼす影響・デメリット
採用ミスマッチが及ぼす主な影響・デメリットは以下の3つです。
- 採用コストの無駄が発生する
- 社内のパフォーマンスが低下する
- 企業イメージの悪化につながる
採用ミスマッチの増加によって早期離職者が増えると、採用するまでにかかったコストが無駄になってしまいます。
また離職にまでは至らなくても、採用ミスマッチによって不満を抱いた状態では、人材は高いパフォーマンスを発揮できなくなるでしょう。それは他の従業員にも影響することがあり、結果として社内全体のパフォーマンスに影響する可能性もあります。
さらに採用ミスマッチによって離職した人材は、自社についての悪い口コミを広げる可能性があり、企業イメージの悪化につながる恐れもあります。
このように採用ミスマッチは、「早期離職されたらまた募集すればいい」といった対処方法だけでは解決できない、さまざまなデメリットにつながります。
採用ミスマッチが発生する割合
採用の現場において、採用ミスマッチはどのぐらいの頻度で発生するのでしょうか。
株式会社PRIZMAが実施した『求職者と人事採用担当者に関する調査』によると、「採用ミスマッチが要因で、社員が入社後すぐに退職してしまった経験はありますか?」という設問に対し、87%が「はい」と回答しました。
求職者側も「入社後、想定していた会社・業務内容と違うなと思うことはありましたか?」という設問に対し、「かなりあった」「少なからずあった」と回答したのは合計で66.3%にのぼります。
このように多くの企業・求職者が採用ミスマッチを経験しています。企業規模・業種にかかわりなく、全ての企業が採用ミスマッチの防止対策を行うことが求められているといえるでしょう。
採用ミスマッチのよくある事例5選
具体的にどのような点で認識のズレが生じることで、採用ミスマッチが発生するのでしょうか。よくある事例としては以下の5つが挙げられます。
- 待遇・労働環境のミスマッチ
- 人間関係のミスマッチ
- 企業文化・社風のミスマッチ
- スキルのミスマッチ
- 仕事内容・キャリアパスのミスマッチ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
待遇・労働環境のミスマッチ
給与や福利厚生、残業の多さなど「待遇・労働環境」のミスマッチは、よくある事例の1つです。
転職サービスdodaが2024年に実施したアンケート調査によると、転職理由のトップとして挙がっているのは「給与が低い・昇給が見込めない」という、待遇についての不満です。
他にも「労働時間に不満(残業が多い/休日出勤がある)」「働き方に柔軟性がない(派遣常駐型、リモートワーク不可など)」といった、労働環境についての不満を離職理由として挙げている人も多く見られます。
出典:転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査! |転職サービスdoda
待遇・労働環境のミスマッチは多くの場合、事前説明の不足によって発生します。詳しくは後述の「企業からの情報提供が不十分」をご参照ください。
人間関係のミスマッチ
人間関係のミスマッチも、よくある事例の1つです。
前述の転職サービスdodaが実施したアンケート調査でも、離職理由として「人間関係が悪い/うまくいかない」が3位に挙がっています。
人間関係の良し悪しは生産性に大きく影響することがあるため、特に避けたいミスマッチの1つです。
採用する人材が入社後に良い人間関係を築けるかどうかは見極めが難しい点ではありますが、「ミートアップ」「カジュアル面談」など、採用前に社内メンバーと交流できる採用手法を取り入れるなどの方法で対策できます。
企業文化・社風のミスマッチ
人材の性格や考え方と「企業文化・社風が合わない」というミスマッチもあります。
単に「社風」といっても漠然としていますが、具体的に関係するのは「評価形式」「組織体制」「既存社員の性格」などの要素です。
前述の転職サービスdodaが実施したアンケート調査でも、離職理由として「社内の雰囲気が悪い」「昇進・キャリアアップが望めない」「会社の評価方法に不満があった」といった社風に関係する理由が多く挙げられています。
こちらも事前確認が難しい要素ですが、「インターンシップ」など事前に企業文化・社風を知ってもらう機会を増やすことで対策できます。
スキルのミスマッチ
人材のスキルが足りないという理由でのミスマッチもあります。
「スキルを盛っていた」「経歴を偽っていた」など、候補者側に原因があることもありますが、「見極めに失敗した」という企業側に原因があるケースもあります。
例えばポテンシャル採用で、成長の見込みがあると思って採用したものの、実際には成長しなかったというミスマッチです。「充実した経歴」や「面接での印象の良さ」など、第一印象に引っ張られて選考の判断を誤り、実際のスキルを十分に見極められないこともあります。
スキルのミスマッチは基本的に、選考プロセスに問題があることで発生します。詳しくは「選考プロセスに問題がある」をご参照ください。
仕事内容・キャリアパスのミスマッチ
「希望する仕事ではなかった」「想定していたキャリアパスと違う」など、仕事内容への不満によるミスマッチもあります。
候補者がどのような仕事やキャリアパスを希望しているのか、あらかじめ十分に確認できていないことで発生するミスマッチです。詳しくは「候補者についての情報が不十分」で解説しています。
採用ミスマッチが発生する5つの原因
上記のような採用ミスマッチはなぜ発生するのでしょうか。主な原因として以下の5つが挙げられます。
- 母集団形成の方法が自社に合わない
- 企業からの情報提供が不十分
- 候補者についての情報が不十分
- 選考プロセスに問題がある
- フォローの不足
それぞれ以下に詳しく解説していきます。
母集団形成の方法が自社に合わない
母集団形成で使うサイトや、その使い方が原因でミスマッチが発生する場合があります。例えば「自社のターゲット層とユーザー層が異なる求人サイトを使っている」などのケースです。
さまざまな母集団形成の手法があり、それぞれターゲット層やメリット・デメリットが異なるため、自社にマッチするものを選ぶことが大切です。
新たな母集団形成の手法の導入を検討することで、自社にマッチする手法が見つかるかもしれません。詳しくは「母集団形成の方法を見直す」で解説しています。
企業からの情報提供が不十分
候補者に提供する自社についての情報が不十分なことが原因でミスマッチが発生する場合もあります。
例えば「求人原稿の内容が薄い」「面接で十分に説明しない」などのケースです。仕事の魅力を「誇張しすぎる」ことも、誤解につながりミスマッチの原因になることがあります。
企業からの情報提供が不十分であることで発生するミスマッチは、適切に情報開示を行う「RJP」(Realistic Job Preview)の考え方を取り入れることで防止できます。
候補者についての情報が不十分
逆に、候補者側から得る情報の不足が原因になるケースもあります。
例えば面接で、その人の性格・仕事に対する考え方を十分にヒアリングできていない場合などです。応募フォームに入力する項目が少ないなど、応募時に得られる情報が少ないことも考えられます。
このようなミスマッチは、応募フォームにアンケートを追加するなど、応募時に得られる情報をできるだけ増やすことで対策できます。詳しくは「応募フォームの入力項目を見直す」をご参照ください。
選考プロセスに問題がある
面接など選考プロセスがミスマッチの原因になることもあります。
例えば選考基準があいまいで、担当者ごとにばらつきがあるなどです。選考基準は決まっていても、それに沿った選考を面接官が適切に実施できていないケースもあります。
選考プロセスが原因のミスマッチは、「選考基準を明確にする」「面接官トレーニングを行う」といった方法で防止できます。
スキル・経歴に詐称や間違いがないかを確認するために「リファレンスチェック」を導入してもよいでしょう。
フォローの不足
入社に至るまでのフォロー、または入社後フォローの不足が採用ミスマッチにつながることがあります。
例えば入社に至るまでのフォロー不足により不安が高まり、入社前に辞退されてしまうケースです。
また入社後のフォロー不足によって会社になじめず、人間関係をつくれなくなってしまう場合もあります。
このようなミスマッチは「オンボーディング」を実施することで対策することが可能です。
採用ミスマッチ防止のためにできる10の対策
採用ミスマッチが多く発生している場合、以下の10の対策を実施することで改善できます。
- 母集団形成の方法を見直す
- ミートアップを開催する
- インターンシップを導入する
- カジュアル面談を取り入れる
- 選考基準を明確にする
- 応募フォームの入力項目を見直す
- 面接官トレーニングを行う
- RJPを意識する
- リファレンスチェックを行う
- オンボーディングを実施する
各対策の実施方法について、以下に詳しく解説します。
母集団形成の方法を見直す
母集団形成に使うサイトや手法を見直すことで、ミスマッチを防止できることがあります。
主な母集団形成の手法としては、以下に挙げる18種類が知られています。
- 求人サイト(ナビサイト・転職サイト)
- 採用ホームページ
- 採用動画
- 採用ピッチ資料
- SNS採用・SNS広告
- ダイレクトリクルーティングサイト
- 人材紹介エージェント
- 求人検索エンジン
- Web広告
- リファラルリクルーティング
- アルムナイリクルーティング
- ハローワーク
- ミートアップ
- 合同説明会(就活イベント・転職フェア)
- インターンシップ
- ヘッドハンティング
- フリーペーパー
- スキマバイトアプリ
この中から自社に合った手法や、特にマッチ率を高めやすい手法を選ぶことで、採用ミスマッチを防止することが可能です。各手法の特徴について詳しくは、以下のページをご参照ください。
採用の母集団形成とは?母集団を増やす18の方法と難しいときの対処法
ミートアップを開催する
ミートアップとは共通の興味・関心を持つ人たちが集まって交流するイベントのことです。採用活動においても「自社に興味を持つ人」を集めるミートアップが、多くの企業で開催されています。
ミートアップを開催することで、直接会って自社についての理解を深めてもらうことができ、ミスマッチ防止につながります。
ミートアップのメリットは、「少し興味がある程度」といった人でも気軽に参加できることです。次に解説するインターンシップと比べて参加ハードルが低いため、幅広い層からの参加が期待できます。
採用ミートアップについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
採用ミートアップとは?実施時の注意点や運用のポイント【人事お役立ち情報】
インターンシップを導入する
インターンシップとは、就業体験を含むプログラムのことです。主に新卒採用で現役学生向けに開催することが多いですが、「社会人インターンシップ」と呼ばれる中途向けに開催するタイプもあります。
インターンシップを実施することで、応募前に仕事の様子やオフィスの雰囲気などを実際に感じてもらうことができ、ミスマッチ防止に役立ちます。
インターンシップの開催方法について詳しくは、以下のページにある資料をご参照ください。無料でダウンロードいただけます。
学生の心を掴み採用に繋げる!インターンシップ成功の秘訣【資料ダウンロード可能】
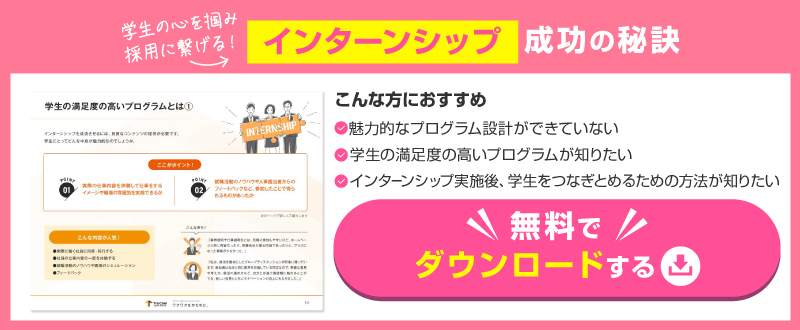
カジュアル面談を取り入れる
カジュアル面談とは、面接よりもリラックスした雰囲気で人材と直接会って話すことです。一般的にオフィスではなくカフェなど緊張せず話せる場所で行われます。
面接よりリラックスして「素に近い状態」で話せるため、候補者の理解が深まりやすいことがカジュアル面談のメリットです。人材と直接会って自社の魅力を伝える機会にもなり、面接前に自社の情報を多く伝えることでミスマッチの防止につながります。
カジュアル面談と面接の違いについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
【企業向け】面談と面接の違いとは?効果的に行うコツも解説
選考基準を明確にする
ミスマッチ防止のためには選考基準を具体的に決めることが大切です。
選考基準を決めるには、前提として「採用ターゲット」を明確にする必要があります。採用ターゲットを基準にすることで、「それをどのように見分けるのか」といった観点で選考基準を決めやすくなります。
選考基準は社内で共有できるように「面接評価シート」など目に見える形にしておくことも重要です。
採用ターゲットの決め方について詳しくは、以下のページをご参照ください。
「採用ターゲット」を決める上で大切な3つのポイント
【資料ダウンロード可能】面接の評価基準の一定化につながる|面接評定シート作成マニュアル
こちらの資料では、ChatGPT・Geminiを用いて面接の評価を効率化できるプロンプトをご紹介しています。本プロンプトをご活用いただくことで、面接の評価業務の効率化だけでなく、面接官ごとに評価基準を一定にすることができます。
面接の評価基準の一律化にお悩みの企業様はぜひお役立てください。
応募フォームの入力項目を見直す
応募者の情報を事前によく知るためのツールとして、応募フォームも有効活用しましょう。
求人サイトを使った募集などでは、応募フォームに必要な情報を入力してもらうことがありますが、サイトによっては入力を求める項目のカスタマイズが可能です。応募フォームの入力項目を見直すことで、採用ミスマッチを防止できることがあります。
例えば生年月日など一般的な項目の他にも「希望職種」「志望動機」「備考(気になることを自由に記載)」などの項目を加えることで、あらかじめ応募者についての理解が深まる情報を得られます。
ただし応募フォームへの入力項目が多すぎると、入力を面倒に感じて離脱するケースが増える恐れがあります。バランスを見て、入力項目を厳選するようにしましょう。
面接官トレーニングを行う
面接官の質を高めることもミスマッチ防止のために重要です。
面接官の質問の仕方が悪いと候補者の本音を引き出せず、面接で得られる情報量が少なくなって採用ミスマッチにつながることがあります。
「面接官トレーニング」を実施して、面接官に候補者の本音を引き出すスキルを身につけてもらうなどして「内容の濃い面接」を行える体制を整えることが大切です。
質問集を作成するなど「マニュアル・ガイドライン」を整備することも面接官の質を高めることにつながります。以下のページで、面接官のガイドラインとして取り入れたいテクニックなどをまとめているので、ぜひご参照ください。
【企業向け】面接官の質問例と意識したいテクニック・心得を解説
RJPを意識する
RJP(Realistic Job Preview)を意識した採用を行うことも、採用ミスマッチ防止のために重要です。
RJPとは、企業が求職者に対して自社についてのマイナス面を含めたリアルな情報を提示することです。自社について悪い面を隠したり、魅力を盛ったりすることなく、正直な情報提供をすることを指します。
求人広告や採用ホームページに掲載するコンテンツ、面接で説明する内容など、採用活動全体にRJPの考え方を取り入れることで、誤解や情報不足による採用ミスマッチを防ぐことができます。
リファレンスチェックを行う
候補者についての情報不足による採用ミスマッチを防止するために「リファレンスチェック」を実施してもよいでしょう。
リファレンスチェックとは、候補者の人物像やスキルレベルなどについて、前職の企業などに問い合わせて情報を得ることです。候補者について第三者に質問することで、本人と話すだけでは分からないような情報を得られることが期待でき、経歴詐称などを回避することにもなります。
ただしリファレンスチェックを実施する際には、必ず応募者の同意を得るようにしましょう。
オンボーディングを実施する
フォローの不足によるミスマッチを防止するには、オンボーディングを実施することが大切です。
オンボーディングとは、新入社員を定着させるための取り組みのことです。入社後フォローや、新入社員の教育・育成プログラム、社内交流イベントなど、さまざまな施策が含まれます。
オンボーディングを行うことで、新入社員が会社に馴染み、人間関係を構築できるよう助けることができ、人間関係や社風のミスマッチを防止できます。
オンボーディングについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
オンボーディングとは?概要から実施の目的、事例までを解説
以下の記事では、採用ミスマッチを防ぐための効果的なオンボーディング施策や、採用段階での工夫などを解説しています。
参考:離職率高すぎ?定着率の向上のための具体的な取り組みのネタを網羅!|あるバイ
採用ミスマッチ防止に成功した企業事例
実際の企業で、採用ミスマッチをどのように防止しているのか見ていきましょう。以下3社の事例をご紹介します。
- 株式会社 猿人様
- トランコム株式会社様
- 株式会社西松屋チェーン様
株式会社 猿人様
BtoBマーケティングの支援を行っている株式会社猿人様では、自社にフィットする母集団が少ないという課題を抱えていました。特に「企業カルチャーとのフィット」といった企業文化・社風にまつわるミスマッチの発生が課題でした。
そこでマッチ度の高い採用を実現するために、求人サイトやWeb広告での募集だけでなく「ブログ・SNS」での発信や「採用ピッチ資料」(スライド)など、さまざまな施策を展開。例えばブログでは、社員インタビューや対談企画など、リアルな企業カルチャーが伝わるようなコンテンツを発信しました。
その結果として、求職者の質を向上させ、マッチングの精度を高めることに成功しています。
参照:カルチャーにフィットする人材を見つけたい。多様なアプローチから企業の成長に貢献【株式会社 猿人様】
トランコム株式会社様
全国に物流拠点を構え、幅広い物流・倉庫事業を展開するトランコム株式会社様では、「求める人材からの応募が少ない」といった応募者のミスマッチが課題でした。特に経験や資格の有無といったスキル面ではなく、「コミュニケーション力」など人柄の面でのミスマッチを防止する必要がありました。
そこで求人原稿を一新し、コミュニケーション力を活かせる仕事であることをアピールするような内容に修正するといった対策を実施。求人原稿には、「人と接する仕事をしていた方へ」といったメッセージと共に、従業員同士やお客様とのコミュニケーションを大事にしていることを記載しました。
その結果、販売サービス経験者でマッチ度の高い人材の採用に成功。応募から採用に至らないケースの削減にもつながっています。
参照:本社と現場をつなぐ架け橋に。市場の変化に基づくターゲット設定で新たな人材獲得に成功!【トランコム株式会社様】
株式会社西松屋チェーン様
幼児や子供の日用品専門店として事業を展開されている西松屋チェーン様では、SNSでのリアルな情報の発信を実施することで、マッチ度の高い採用を実現しています。
西松屋で働いているスタッフには10代、20代の若年層も多いことから、若年層にアプローチしやすいInstagramを利用して、自社の魅力を発信する施策を実施。その結果、自社採用ホームページへの流入数増加に成功し、採用率が良くマッチ度の高い応募者の獲得につながっています。
参照:自社の採用ホームページへの流入を増やす、新たなチャレンジへの伴走。【株式会社西松屋チェーン様】
こちらもおすすめ|求人ボックス運用事例集【無料ダウンロード可能】
求人ボックスには採用のマッチング率を上げるための機能が豊富に実装されています。本資料では、求人ボックスを活用して採用ミスマッチを改善できた事例をご紹介。採用課題と課題解決に向けた提案・効改善結果をご確認いただける資料となっているので、資料ダウンロードのうえ、ぜひ参考にしてください。
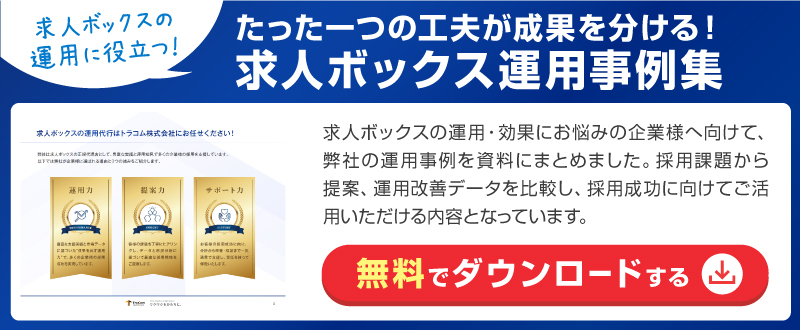
採用ミスマッチ防止の他に検討したい定着率アップの施策
離職につながる理由はミスマッチだけではありません。採用ミスマッチを防ぐ目的である「定着率アップ」を実現するためには、ミスマッチ防止以外の施策を実施することも大切です。
特に重要な施策として、以下の2つが挙げられます。
- 従業員満足度の向上
- リテンションの実施
それぞれ以下より詳しく見ていきましょう。
従業員満足度の向上
定着率を高めるには、定着しそうな人材を探すだけでなく、従業員満足度を高めて「自社の魅力」を高めることも必要です。
どんなに募集方法や選考プロセスを工夫しても、自社のアピール材料が弱ければ、ターゲット層が自社を選んでくれる可能性が低くなってしまいます。採用ミスマッチを避けるには、自社についての悪いところも伝えるRJPが大切ですが、伝えるべき悪いところが多すぎると、それだけ採用に至る見込みが下がってしまうでしょう。
待遇・福利厚生を見直すなどして、従業員満足度を高めることで定着率の向上につながり、採用ミスマッチの防止も期待できます。
従業員満足度を高める方法について詳しくは、以下のページをご参照ください。
従業員満足度(ES)を高めるには?関係する6つの要素と成功事例を解説
リテンションの実施
人事採用における「リテンション」とは、人材の流出を防止し、定着を促す対策を行うことです。
採用時点ではミスマッチが発生しなくても、少しずつ不満がたまるなどして離職につながるケースもあります。リテンションの取り組みを行い、退職につながる理由をできるだけ減らしていくことが大切です。
例えば退職理由のヒアリングを行い、従業員が不満を感じやすい部分を調査して改善の参考にするなどの方法で、リテンションの取り組みを進めることができます。
リテンションの実施方法について詳しくは、以下のページをご参照ください。
的外れな離職防止に終止符!明日から実践したいリテンション施策事例
こちらの資料がおすすめ|定着率を劇的に高める! 『働き続けたい』と感じる職場づくりの法則【資料ダウンロード可能】
本資料では、「働き続けたい職場」をつくる際に押さえるべき3 つのポイントや定着率アップへ向けた具体策などをまとめました。離職防止のために取り組むべきチェック項目や成功事例もご紹介しているので、ぜひご活用ください。
まとめ
採用ミスマッチとは、「待遇」「人間関係」「社風」「スキル」「仕事内容」など、さまざまな理由で認識のズレが生じることです。
その原因としては、母集団形成の方法や選考プロセスなどに問題があることが考えられます。
採用ミスマッチの防止に課題を感じる場合には、当ページでご紹介した「10の対策」を参考に、未対応の部分があれば実施を検討してみましょう。
採用ミスマッチ対策のご相談はトラコムへ
「採用ミスマッチが多くて困っている」「選考プロセスを改善したい」などのお悩み・課題がございましたら、弊社トラコムにご相談ください。
トラコムでは、母集団形成方法のアドバイス、選考プロセス改善のご提案など、採用にまつわる幅広いコンサルティングをご提供いたします。「応募受付代行」「面接官トレーニング代行」などの各種代行サービスもご依頼可能です。まずは以下のフォームより、お気軽にお問い合わせください。
関連する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る