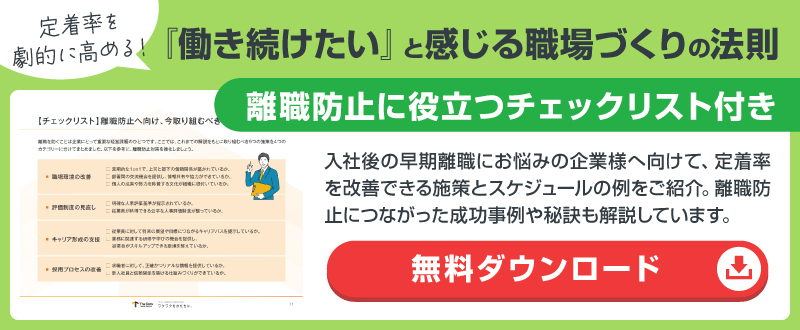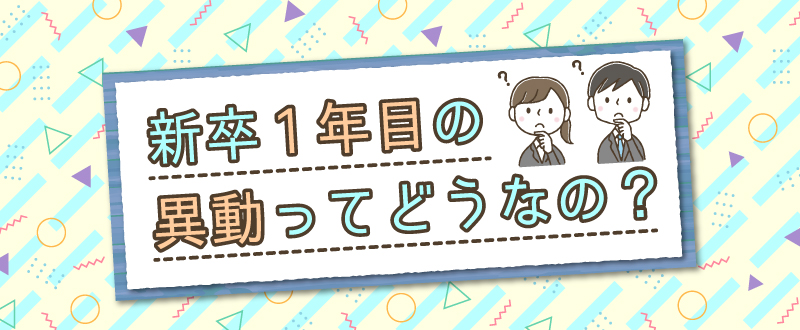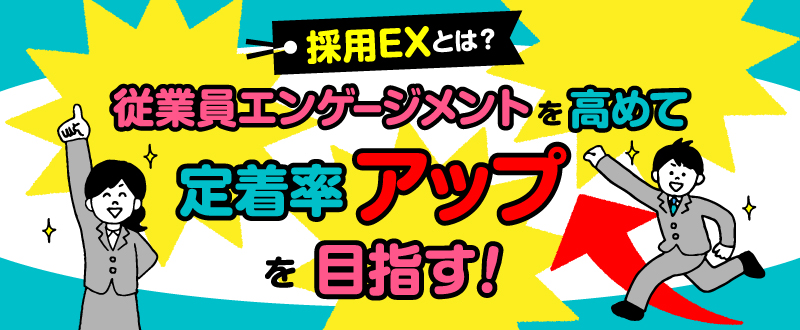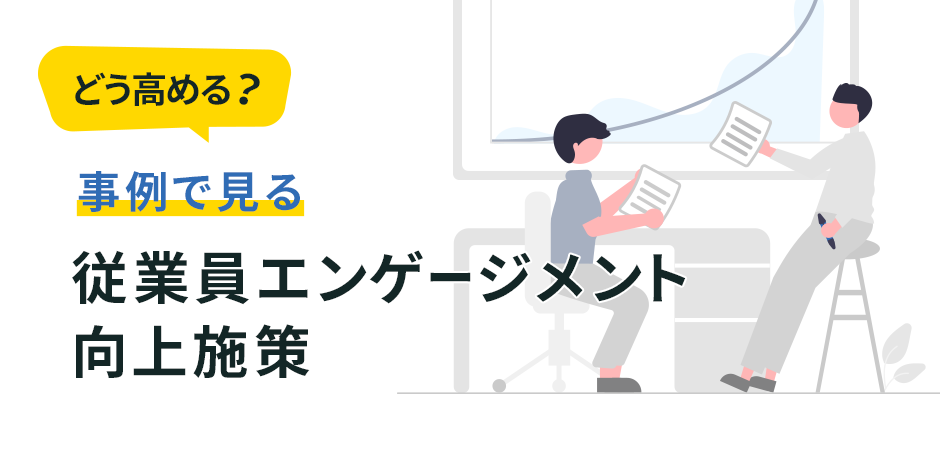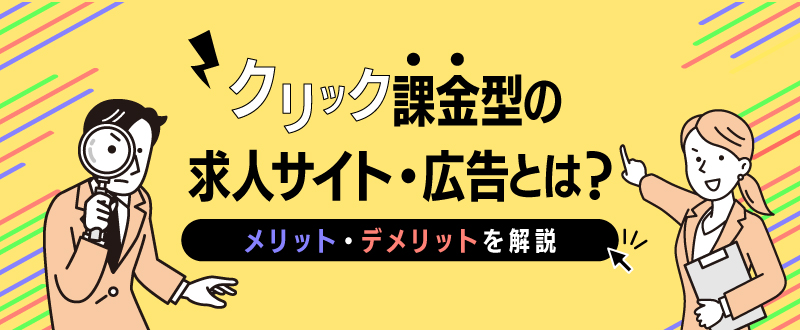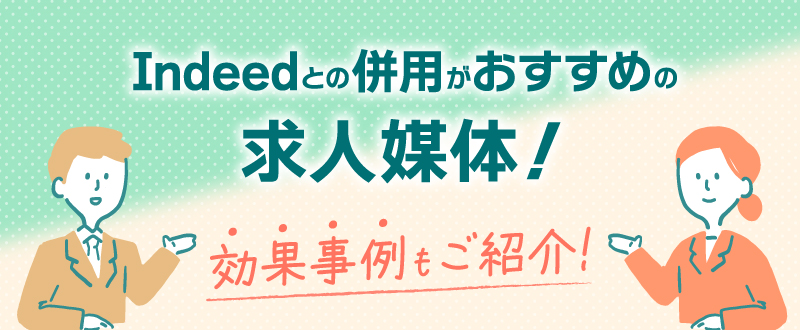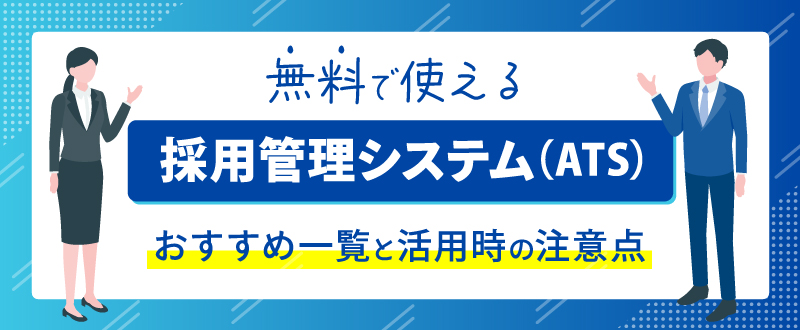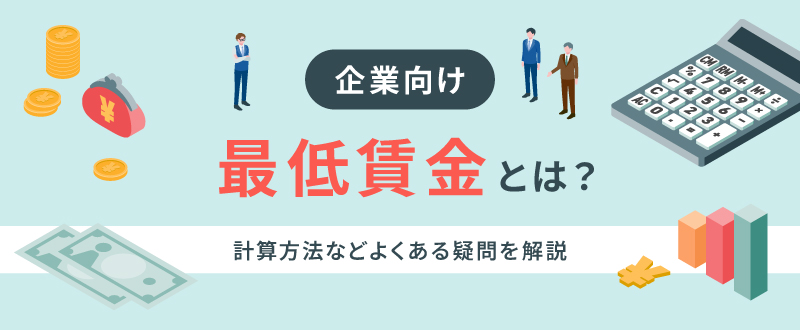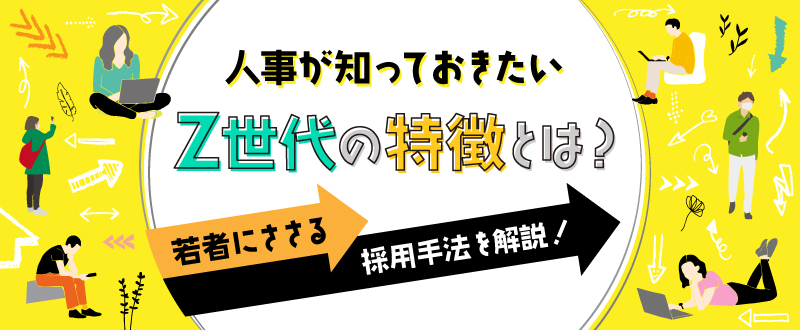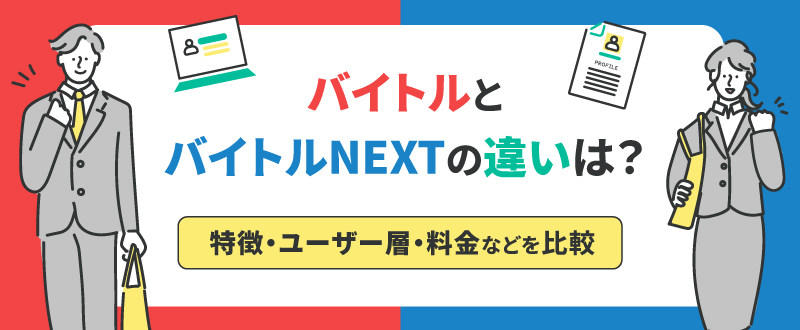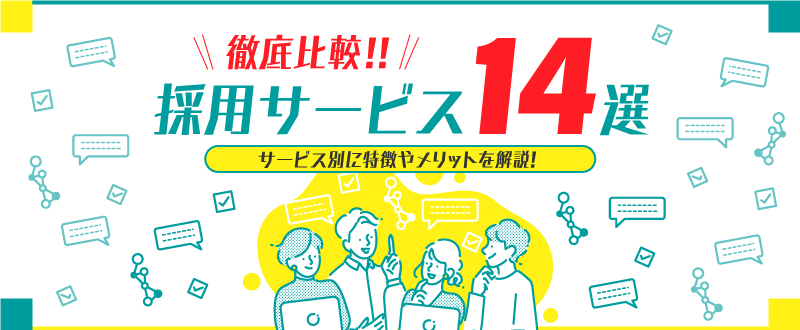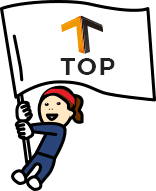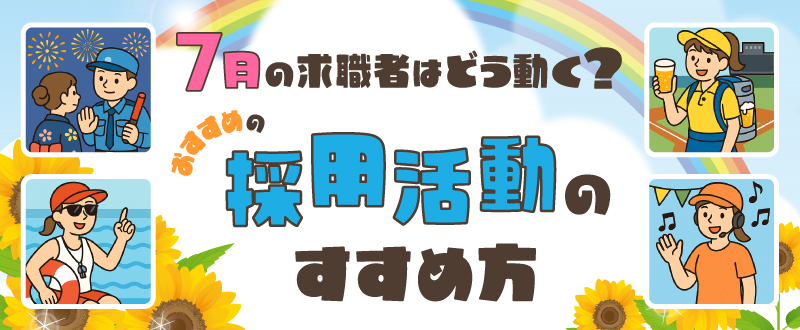
トラコム社員がお届け!
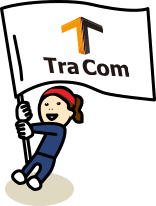
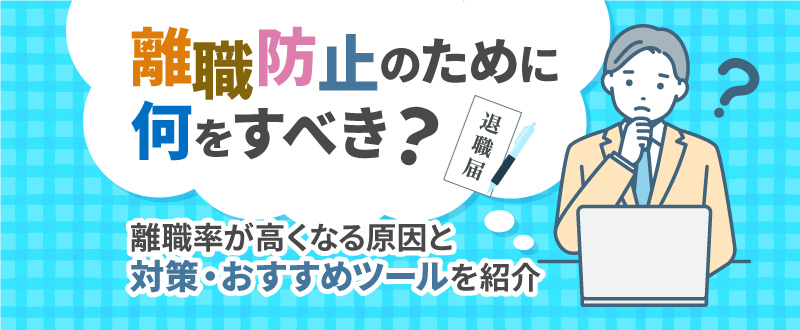
少子高齢化などによる人材不足が加速する昨今、ますます離職防止の重要性が高まっています。
人材の定着率を高めるため、多くの企業が離職防止に取り組んでいますが、どのような施策を実施すれば効果があるのでしょうか。
この記事では、離職率が高くなる原因や定着率を高める8つの対策、おすすめの離職防止ツールなどを紹介します。
離職防止が重視される背景
入社3年以内の離職率はほぼ横ばいで推移しており、過去30年のデータを見ても大きな変動はありません。
厚生労働省が新卒就職者を対象に行なった調査によれば、令和3年度の新卒就職後3年以内の離職率は、大卒で34.9%、短大卒で44.6%、高卒で38.4%、中卒で50.5%となっています。
「3年で3割」といわれる通り、大卒者でもおよそ3人に1人が3年以内に離職してしまう状況です。
少しでも人材の定着率を高めるため、多くの企業が離職防止施策に力を入れています。
企業が離職防止の施策をする必要性
「離職防止施策を打たなくても、採用に力を入れれば十分では?」と考える方もいるかもしれません。
なぜ多くの企業が人材の定着率を高めようとしているのか、離職防止の必要性を解説します。
人材確保のコスト増加を防ぐため
新たに採用した人材を育成して独り立ちさせるまでには、多額の採用コストや教育コストがかかります。
就職みらい研究所の「就職白書2020」では、新卒採用の平均採用コストは1人あたり93.6万円、中途採用で103.3万円です。
また、産労総合研究所の「2023年度 教育研究費用の実態調査」によれば、企業が教育研修にかけた費用の従業員1人あたりの平均額は34,606円でした。
離職が発生すると、それまでに費やした採用・教育コストが無駄になるばかりか、新たに人材を採用するために追加でコストをかけなければならず、コスト増加につながります。
採用市場におけるイメージダウンを避けるため
離職が多いことは、求職者にとってネガティブな情報です。
「何か問題がありそう」「ブラック企業かもしれない」というイメージを持たれて求職者から敬遠されてしまい、採用活動の停滞を招きかねません。
特に、現代ではSNSや口コミサイトが普及しており、会社に関するネガティブな情報が求職者に伝わりやすくなっています。
そのため離職防止に努めることは会社のイメージダウン回避に繋がり、ひいては採用活動の成果にも影響を及ぼします。
離職率が高くなる原因は?
厚生労働省が行なった「令和3年雇用動向調査」では、転職入職者が前職を辞めた理由として、回答の多かった項目とその回答率は次の通りとなりました。
- 職場の人間関係が好ましくなかった(男性8.1%、女性9.6%)
- 労働時間、休日等の労働条件が悪かった(男性8.0%、10.1%)
- 給与等収入が少なかった(男性7.7%、女性7.1%)
- 会社の将来が不安だった(男性6.3%、女性4.5%)
この4つの項目について、なぜ離職の原因となるのか詳しく解説します。
職場の人間関係
職場における人間関係は、女性の離職原因で最も多い回答率を得ています。
セクハラやパワハラといった大きな問題が発生していなくても、部署内のささいなやり取り、上司・同僚・部下との関係性がストレスになっている場合もあります。
また、昨今は「カスハラ(=カスタマー・ハラスメント)」という言葉も登場しており、お客様とのトラブルに悩まされているケースも考えられます。
労働時間、休日等の労働条件
残業が多く長時間労働が慢性化している、サービス残業や休日出勤を強要される、有給が取れないといった労働環境の良し悪しも、離職につながりやすい観点です。
特に、働き方改革が推進されるようになった昨今では、ワークライフバランスの取れた働き方を希望する人が増えています。
劣悪な労働環境は肉体的にも精神的にも負担が大きいため、離職を考えるきっかけとなりやすいのです。
給与等の収入面
仕事の負担や責任に対して十分な報酬が得られないことは、従業員エンゲージメントに直結する問題です。
業務量が多く、責任が重い仕事を担っているにもかかわらず、その負担が給与に反映されていないと、社員は会社に対して強い不満を抱きますし、意欲の低下も招きます。
それだけでなく、給与の低さは生活水準にも影響を与えるため、日々の生活や将来への不安にもつながってしまうのです。
同じ業務量・仕事内容でも、より給与待遇の良い企業へ転職を考えるきっかけとなってしまいます。
会社の将来に対する不安
会社の業績不振が続いている、取り扱いサービスに将来性がない、自身の年収アップが見込めないなど、将来性に対する不安も離職の原因になります。
特に、管理者層や優秀なメンバーの離職原因となりやすいので要注意です。
会社の中でも上位職種についているほど、自社の業績や経営・機密情報に触れる機会が多いため、危機感を抱きやすいのです。
他にも「この仕事を続けてもキャリアアップが見込めない」「自分の成長につながらない」という理由で離職を選ぶ人もいます。
社員自身のビジョンと会社の方向性が一致していないことも、離職の原因となるでしょう。
社員の定着率を高めるには?離職防止の施策8選
離職を防止するために行われる施策は「リテンション施策」とも呼ばれ、企業の人事における重要な分野です。
具体的な8つの離職防止施策を紹介します。
離職防止の施策1:労働環境の改善
社員が安心して働ける労働環境が整っているかどうかは、離職防止において最も重要な観点といえるでしょう。
長時間労働や残業が続くと、肉体的にも精神的にも負担が大きくなります。
残業や休日出勤が常態化している場合は、抜本的な組織改革が必要かもしれません。
時間外労働が発生する原因はどこにあるのか、まずは状況の整理から始めて、業務フロー全体の見直しを図りましょう。
離職防止の施策2:働き方の多様化
多様な働き方を実現できるようにすることも有効です。
国をあげて働き方改革が推進されている背景もあり、前述のとおりワークライフバランスの取れた働き方を希望する人が多くなっています。
特に、女性は育児や介護を理由とした離職が多いため、ライフイベントに合わせた働き方を選択制度・環境を整えることで、離職防止に高い効果が期待できます。
具体的には、リモートワークやフレックス制度、時短勤務制度など、就業場所・時間の融通が利きやすい働き方を整備するとよいでしょう。
また働き方の選択肢が広がると、求職者からの企業イメージアップも期待できます。
離職防止の施策3:待遇・福利厚生の充実
給与などの待遇面はモチベーションに直結する問題です。
とはいえ、単に給与額を増やしたり、ボーナスを支給したりすればよいわけではありませんし、簡単に実施できるものでもありません。
人事評価制度などと連動した、納得感のある給与体系が構築されていることが重要です。
また、社員の要望を加味した福利厚生が充実していると、自社に対する社員の愛着心が高まりやすくなります。
福利厚生とは、住宅補助や家族手当といった給与以外の報酬です。
自社ならではの福利厚生制度があると、他社との差別化にもつながります。
福利厚生を充実化させる具体的な方法については、以下のページもご参照ください。
・こんなのあるんだ!福利厚生についてご紹介|種類や導入メリット
・GOOD待遇!これがあれば嬉しい!そんな福利厚生一覧
・アフターコロナで注目される新福利厚生
離職防止の施策4:スキルアップの支援
社員のスキルアップを支援する制度が充実していると、社員エンゲージメントの向上が期待できます。
業務に関係する資格取得の支援や書籍購入の費用負担制度などがあると、社員のキャリアに対する不安も軽減されるでしょう。
また、スキルアップやリーダー育成を目的に研修を実施する際は、外部から講師を招いたり、e-ラーニングシステムを使ったりするのも一手です。
社内人材では教えられない知識や技能を取り入れられ、受講する社員の満足度アップが見込めます。
離職防止の施策5:人事評価制度の整備
社員の努力が適正に評価される人事評価制度が整備されていると、仕事にやりがいやモチベーションが高まります。
「頑張った分だけきちんと評価してもらえる」と会社への信頼感が強まり、組織の生産性向上といった効果も期待できるでしょう。
人事評価制度は、上司の主観に依存せず、評価基準が明確であることが大切です。
結果だけでなく、どうしてその評価になったのか、評価を上げるためにはどのような努力が必要なのかといった評価の理由を共有できると、納得感のある制度になるでしょう。
離職防止の施策6:定期的なフォロー面談の実施
上司や人事担当者による定期的な面談を設定すると、社員が抱える不満や悩みをいち早くキャップアップできます。
特に人間関係の悩みについて、周りが早急に気がついてフォローをしてあげることが離職防止に効果的です。
また定期的な面談は、会社が社員をどう評価しているか、今後はどのような成長を期待しているかを共有する場にもなります。
社員にとっても、自分の目指すべきキャリアパスが明確になり、将来への不安を解消できる良い機会になるはずです。
離職防止の施策7:採用時のマッチ度向上
「想像していた仕事内容じゃなかった」「期待していたキャリアを積めていない」など、そもそも採用の時点でミスマッチがあると、早期離職の原因になります。
ミスマッチを防ぐには、インターンシップの導入や求人内容の改善など、採用フロー全体の見直しを行って、採用の精度を高めることが大切です。
特に、採用活動で企業の良い面ばかりを伝えすぎていないかを見直してみましょう。
母集団を増やそうとすると、どうしても良い面ばかりを訴求してしまいますが、それだけではミスマッチが起こりやすくなります。
自社の抱える課題や仕事の大変な面も正直に伝えることで、マッチ度の高い採用が実現できるでしょう。
おすすめ資料のご紹介|定着率を劇的に高める! 『働き続けたい』と感じる職場づくりの法則【資料ダウンロード可能】
本資料では、「働き続けたい職場」をつくる際に押さえるべき3 つのポイントや定着率アップへ向けた具体策などをまとめました。早期離職へとつながる”採用ミスマッチ”を防ぐための参考資料として、ぜひご活用ください。
離職防止の施策8:離職防止ツールの導入
離職防止ツールとは、社員エンゲージメントの見える化や社員満足度の調査、ストレスチェックといった離職防止施策の管理や効率化ができるツールです。
人材マネジメントシステムの一機能として利用できるものもありますが、昨今では離職防止専用のツールも多数登場しています。
ツールの具体例については、以下で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
定着率の向上に役立つ離職防止ツール5選
離職防止ツールを導入すると、エンゲージメント調査やストレスチェックの結果などを一元管理し、より効果的な離職防止策を実行できます。
ここでは、おすすめの離職防止ツール・サービスを5つご紹介します。
いっと
いっとは、既存社員や退職予定者へのアンケート・インタビューによって、社員の本音を引き出すサービスです。
得られた結果を分析し、離職の傾向や原因を把握することで、在籍者の中から離職の可能性が高い人物を早期に発見・対処することも可能になります。
離職防止対策のコンサルティングや効果検証、改善提案までサポートしてくれる点が特徴です。
Visual(ビジュアル)
Visualは、社員のエンゲージメントを可視化するツールです。
エンゲージメント診断アンケートを実施し、回答結果から社員一人ひとりのエンゲージメントを可視化できる機能があります。
さらに、エンゲージメントの状況に合わせて具体的な改善施策の提案もしてくれます。
150パターンの改善アクションが用意されており、施策実行までをワンストップでカバーできる点が魅力です。
EX Intelligence(EXインテリジェンス)
EX Intelligenceは、組織と個人両方の課題を可視化できるクラウドツールです。
人材のデータ管理・分析に役立つさまざまなクラウドサービスを展開する「HRBrain」が提供しているツールで、組織診断のためのさまざまな機能があります。
独自のアルゴリズムをもとに、さまざまな方向から組織の状態を分析し、改善方法の提案を表示することが可能です。
優先的にフォローすべき従業員を可視化するなど、離職防止の機能もあります。
Geppo(ゲッポウ)
Geppoは、毎月3問のアンケートを実施する個人向け調査と、半期/四半期に1回の組織全体のエンゲージメント調査を行えるツールです。
個人が抱える細かな悩みや不安から、部署やチーム単位の組織課題まで把握でき、自社の課題やボトルネックを洗い出すことができます。
また、分析結果を直感的に把握できるよう工夫されたレポートフォーマットも特徴です。
「重要度」「緊急度」「相関レベル」「実行可能性」の4つの項目から実施すべき施策を検討でき、効果的な実施プランを組み立てることができます。
タレントパレット
タレントパレットは、人材データを一元管理・分析するタレントマネジメントシステムで、離職防止の機能も備えています。
離職者の傾向分析や離職予兆の検知、モチベーション・エンゲージメントの見える化が可能です。
AIを用いた予測システムによって、離職リスクの高い社員を割り出すことができます。
手遅れになる前にリスクの高い社員を早期発見し、的確なタイミングでフォローする体制を構築できるツールです。
離職防止のご相談ならトラコムへ!
弊社トラコムでは、人材確保にまつわる全般的なコンサルティングを行っています。今回取り上げた離職防止ツール/離職防止施策についてのご相談はもちろんのこと、離職防止に関して漠然とでもお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
例えば、「そもそも採用のミスマッチから減らしたい」というお客様には、経験豊富な専任プランナーがマッチ度を高める採用手法をご提案。
ミスマッチ減少による定着率の向上をサポートします。
また、採用した人材の入社後のサポートについてのご相談も大歓迎です。
人材の定着率向上につながる福利厚生サービスや、経験の浅い社員を対象とした研修サービスなど、新入社員のエンゲージメントを高めるさまざまな施策をご提案します。
離職防止の具体策にお悩みの方は、ぜひ一度トラコムへご相談ください。
まとめ
採用売り手市場が続き、優秀な人材の獲得がますます難しくなる昨今、離職防止は企業にとって重要な課題です。
離職率を改善するには、心身ともに健康的に働ける労働環境を整え、さまざまな面から社員のストレスを取り除く姿勢が大切です。
エンゲージメント調査などを実施して離職の原因を把握し、自社に適した離職防止策を組み立てましょう。
トラコムでは、人材の定着率を高める施策についてもサポートを行っています。
全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
関連する記事

この記事を書いた人
K.SHINKAWA
この人の記事一覧を見る
2007年に新卒で入社し、京阪エリアを9年、東大阪エリアで3年、地域のお客様の採用のお手伝いを担当。
2016年にリーダーへ昇格。
2021年10月より京都営業所へ異動。
2024年4月より大阪支社へ異動。
10余年に及ぶ営業経験を活かし、大手クライアントと派遣業界を主に担当している。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る