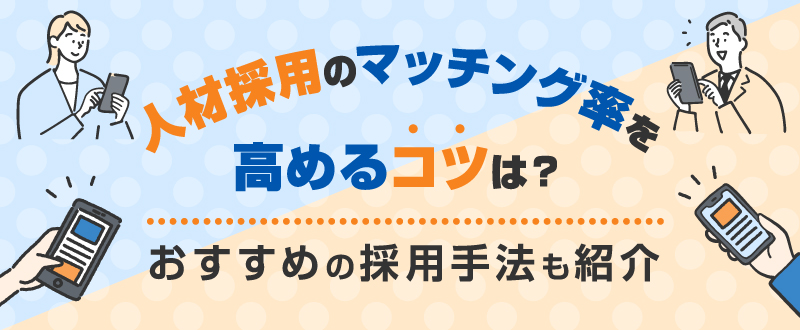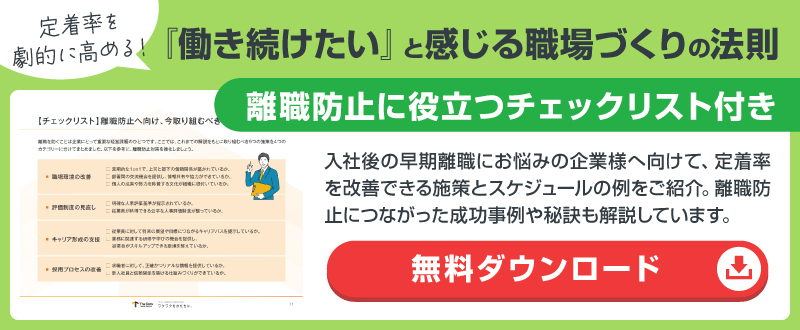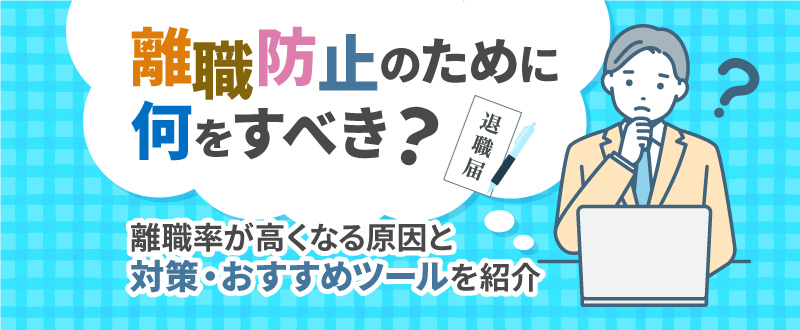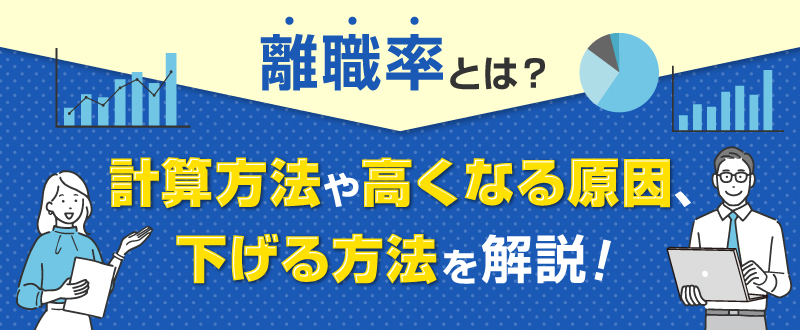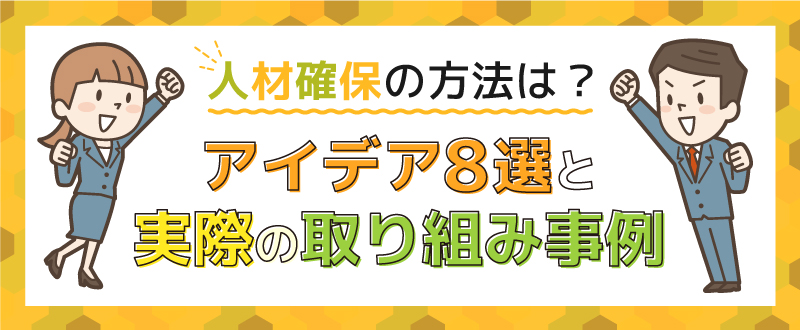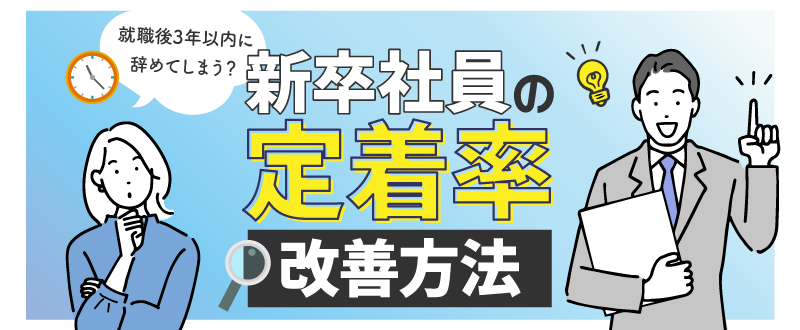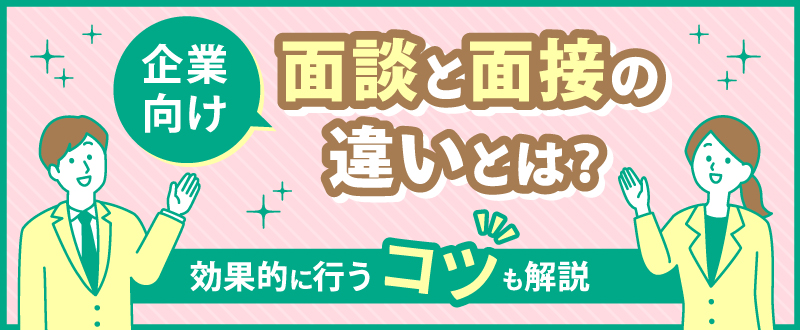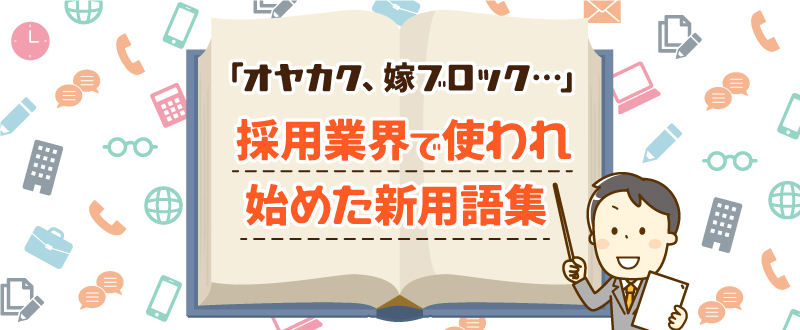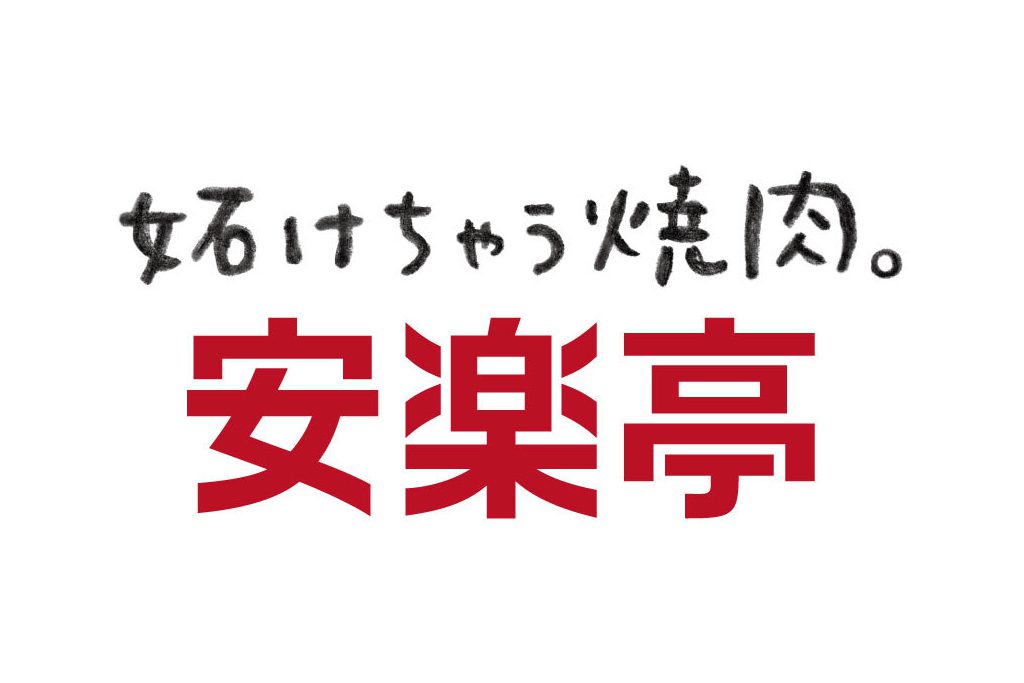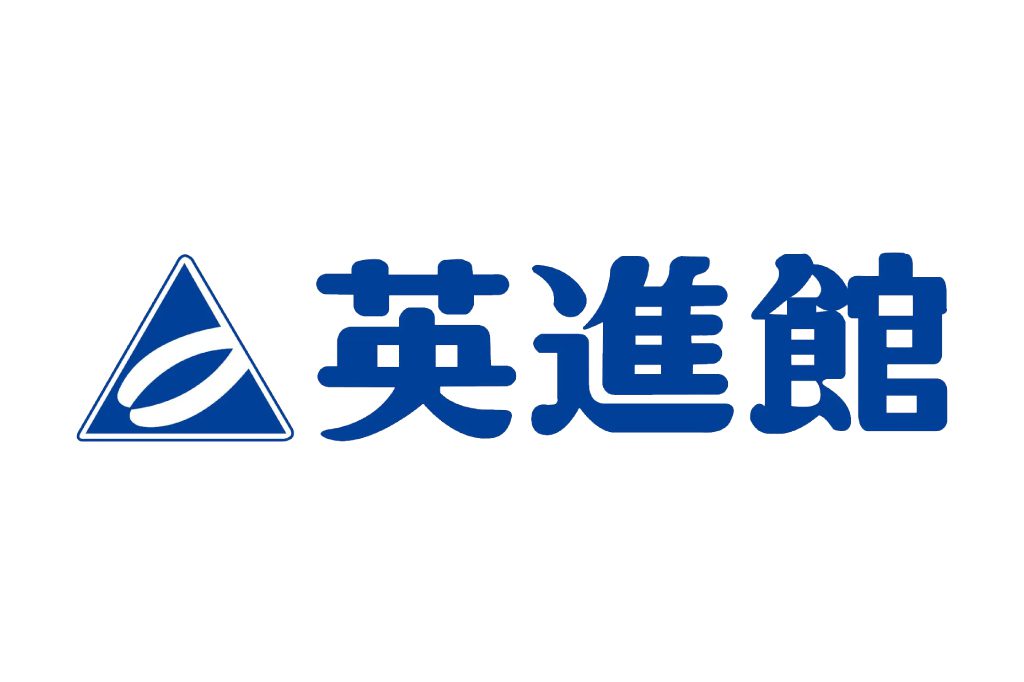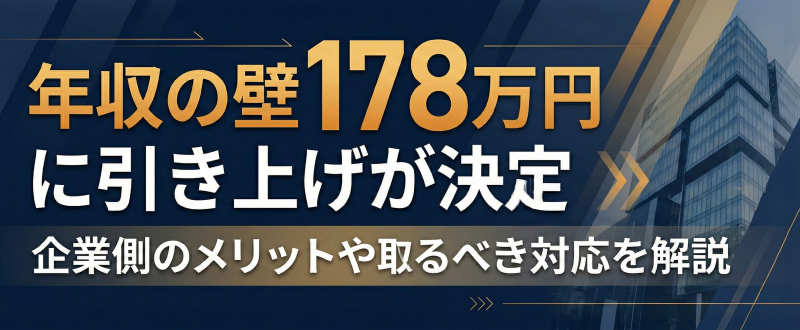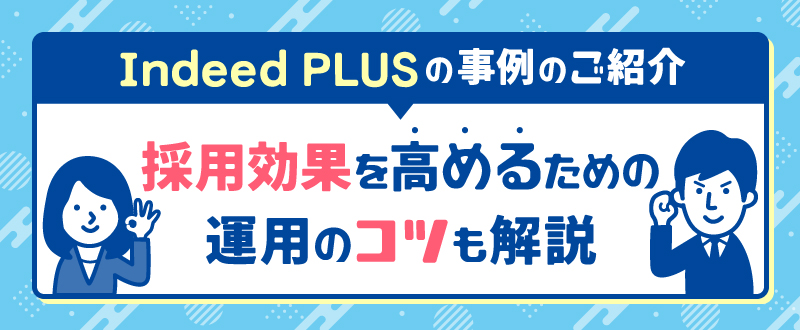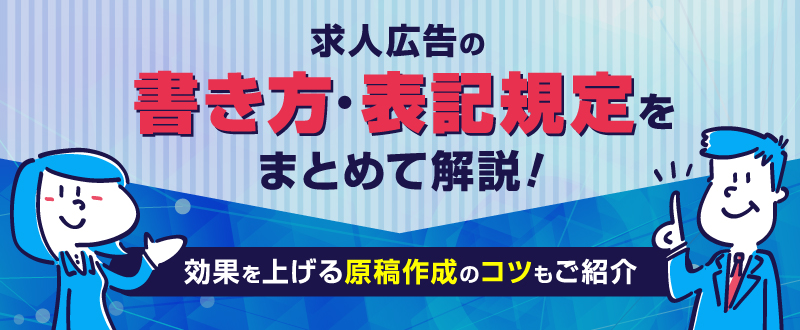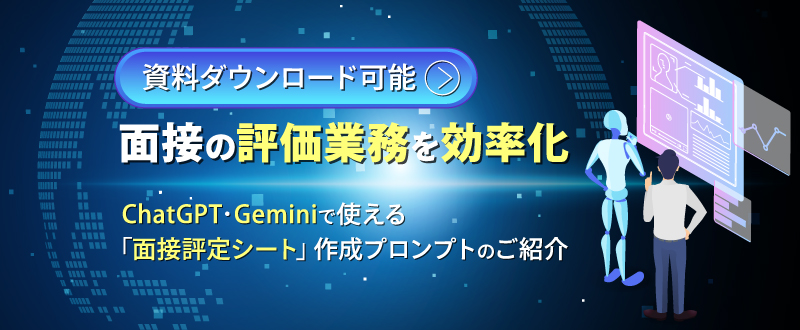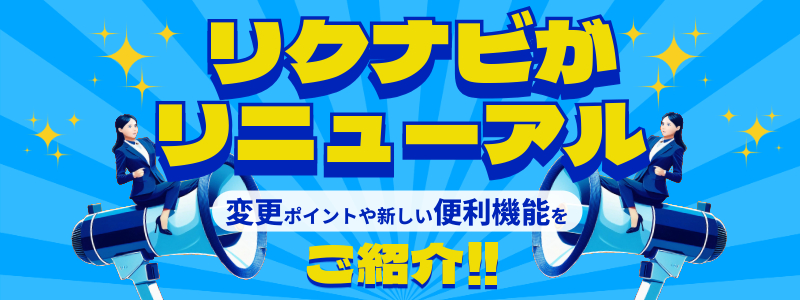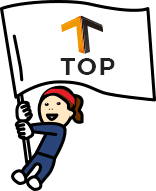トラコム社員がお届け!
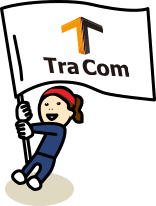
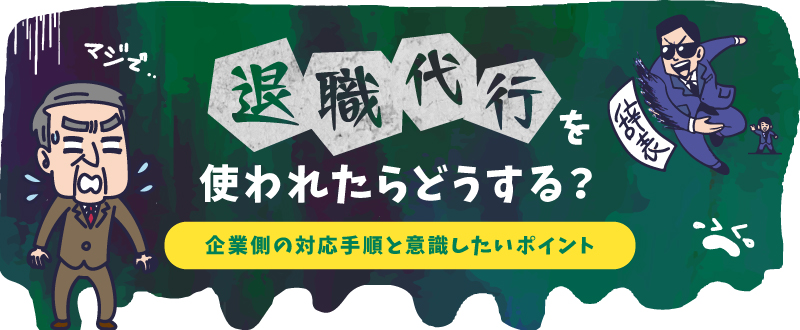
従業員が会社を辞める際に「退職代行サービス」を利用するケースがあります。退職代行サービスからの連絡が来ると、企業側はどのように対応すべきか悩むかもしれません。実際に退職代行サービスを使われた場合、企業側はどのように対応・対処すればよいのでしょうか。
当ページでは、従業員が退職代行サービスを利用した際の企業側の対応手順や、うまく対処するために意識したいポイントなどについて、詳しく解説しています。そもそも退職代行サービスを使われないためにできる対策についても触れているので、ぜひご参照ください。
退職代行サービスとは
退職代行サービスとは、従業員本人に代わって退職の意思を会社に申し入れるサービスです。
「上司に退職を言い出しにくい」など、本人が自分で退職の交渉・手続きをすることに抵抗を感じる場合に利用されるケースが多いようです。
対応できるサービスの範囲は業者によってさまざまで、単に本人に代わって退職届を提出するだけのサービスもあれば、退職に必要な交渉・手続き全般を代行するサービスもあります。
退職代行サービス業者には、大きく分けて以下の3種類があります。それぞれの概要とサービスの範囲は以下の通りです。
| 概要・サービス範囲 | |
| 弁護士 | 弁護士の資格がある個人もしくは有資格者が所属する業者。代理人として退職に必要な交渉・手続き全般を代行できる。 |
| 退職代行ユニオン | 労働組合がない企業が利用する外部の労働組合。会社との団体交渉権が認められているため、退職に必要な交渉・手続きを代行できる。 |
| その他の民間企業 | 上記以外の民間企業。退職に必要な交渉・手続きを代行する正式な資格はない。本人と会社の間に立って、お互いの意向を伝えることしかできない。 |
退職代行サービスを使われるとどうなる?
従業員が退職代行サービスに依頼をすると、退職代行サービス業者から企業に対して、当該従業員に退職の意思がある旨の連絡が来ます。
その後は以下の図のように、退職代行サービス業者が間に入って退職に向けた手続きを進めていきます。
退職代行サービスでは多くの場合、職場の同僚や上司と顔を合わせたくない依頼者のために、「企業との直接連絡は一切不要」を謳っています。そのため企業の労務担当者は、従業員本人ではなく退職代行業者と交渉しながら手続きを進めることになります。
退職代行サービスを使われた際の企業側の対応手順
従業員に退職代行サービスを使われた際、企業側は次の手順に従って対応するのが基本です。
- 退職代行サービス業者の身元確認をする
- 本当に本人から依頼があったか確認する
- 本人の雇用契約の内容を確認する
- 退職の手続きを進める
- 貸与品の返却を依頼する
以下、順に解説します。
退職代行サービス業者の身元確認をする
まずは、連絡してきた退職代行サービス業者の身元確認を行いましょう。退職代行サービス業者は、一般的に電話を使って連絡してきますが、顔が見えず素性も分からない段階では詐欺や嫌がらせである恐れが拭えないため、慎重な対応が必要です。
その場で詳細なやり取りを進めるようなことはせず、先方の連絡先を聞いた上で、改めてこちらから連絡する旨を伝えましょう。その後、Webサイトなどを確認して会社情報を調べ、信頼できる業者かどうかを確認します。
本当に本人から依頼があったか確認する
連絡してきた退職代行サービス業者の身元が確認できたら、次に本当に従業員本人から依頼があったかを確認します。基本的には本人へ直接確認するのではなく、退職代行サービス業者に対して依頼の証明となる委任状や契約書などの提示を求め、間接的に確認ができる仕組みです。
とはいえ「絶対に本人と連絡を取ってはいけない」という法的効力があるわけではないので、後々のトラブルを避けるために、念のため本人に直接確認してもよいでしょう。
本人の雇用契約の内容を確認する
本当に本人から依頼があったことが分かったら、次に雇用契約の内容を確認します。契約内容によって、「いつ退職できるか」が異なってくるからです。
雇用期間の定めのない正社員の場合、雇用契約の終了は退職を申し出た日から2週間後と民法627条に規定されているため、基本的にはそれ以前の退職を認めなくてもよいといえます。また、雇用期間が定められている契約社員などの場合は、業務期間満了までは必ずしも退職に応じる義務はないとされています。
ただし、賃金の未払いやパワハラなどのやむを得ない事由があるケースでは、その限りではないので注意が必要です。
退職の手続きを進める
雇用契約の内容を確認の上、退職日が決定したら、いよいよ退職に向けた実際の手続きです。退職届を始めとする書類の提出依頼など、退職に必要なやり取りを行います。
労務担当者のやり取りは従業員本人ではなく退職代行サービス業者と行うのが一般的です。有給休暇の取得・消化などを含め、不備や抜け漏れのないよう慎重に進めましょう。
なお、本人への連絡は必須ではありませんが、トラブルを防ぐために、一連の手続きが完了したらその旨を伝えるなどしてもよいでしょう。その際は、メールであれば適切な証拠が残るうえ、本人の心理的負担も下がると考えられます。
貸与品の返却を依頼する
退職の手続きが完了したら、最後に貸与品の返却を依頼します。仕事で使用していたパソコンやスマートフォン、記憶装置など、機密情報の漏えいにつながる恐れがあるものは特に慎重な確認が必要です。そのほか、制服、健康保険証なども忘れずに返却してもらうようにしましょう。
これらは、従業員本人が直接持参する必要はありません。宅配便などによる返送で問題ありませんが、その際は破損や紛失のリスクに対しての注意点を十分に理解してもらうことが大切です。
退職代行サービスを使われた際にうまく対処するために意識したいポイント
退職代行サービスを使われた際に企業側がうまく対処するために、次の3つのポイントを意識しましょう。
- 基本的に引き留めはしない
- 本人との直接連絡は慎重に行う
- 予防策を考える
以下、順に解説します。
基本的に引き留めはしない
退職代行サービスを利用する時点で、すでに会社と良好なコミュニケーションを図ろうとする意思は期待できないため、基本的に引き留めはしないのが賢明です。引き留めに成功する見込みは薄いばかりか、仮に成功しても、前向きなモチベーションで高いパフォーマンスを発揮してくれる可能性は低いでしょう。
そのため、退職代行サービス業者の身元確認や本人確認などで問題がなければ、できる限り好印象を持って退職してもらえるよう、粛々と手続きを進めることをおすすめします。
本人との直接連絡は慎重に行う
退職代行サービスを利用した従業員は、基本的に「会社と直接連絡を取ることは拒否したい」と考えている可能性が高いため、本人との直接連絡は慎重に行いましょう。
ただし前述の通り本人との直接連絡を禁止する法的効力はなく、絶対にNGというわけではありません。必要以上に直接連絡することは避けながらも、最低限の確認・連絡はできる範囲で行うことができます。
予防策を考える
従業員の退職にはさまざまな理由があり、それ自体をゼロにするのは難しいといえます。ただ、少なくとも退職代行サービスを使われるような事態が発生しないよう、予防策を考えることは重要です。
退職代行サービスを使われたということは、「職場の雰囲気が良くない」「上司とコミュニケーションを取りたくない」など、背景に何らかのハラスメントや問題が潜んでいる恐れがあります。それらを分析して対策を講じることが、結果的に従業員の定着率を高め、退職自体を減らすことにもつながるでしょう。
退職代行サービスを使われないためにできる具体的な予防策については、以下に詳しく解説します。
退職代行サービスを使われないためにできる対策
退職代行サービスを使われないためにできる企業側の主な対策は、次の通りです。
- 常にコミュニケーションできる関係を築く
- 採用ミスマッチを防ぐ
- 従業員満足度を高める施策を行う
- 離職防止ツールを導入する
それぞれ以下に解説します。
常にコミュニケーションできる関係を築く
常にコミュニケーションできる関係を築いておくことは、退職代行サービスを使われないためにできる対策の第一歩です。
従業員が退職代行サービスを使う大きな理由の1つは、良好なコミュニケーションが取れず不満を言い出しにくいような職場環境であることが考えられます。そのため、普段から従業員とのコミュニケーションを密接に行って、退職について考え始めたときにも率直に相談できるような関係を築いておくことが重要です。
特にリモートワークの場合、普段のコミュニケーションが希薄になりがちで、相談されやすい環境づくりのために一層の工夫が求められます。詳しくは、以下のページをご参照ください。
マネジメントに役立つ!リモートワークでも相談されやすい環境づくり
採用ミスマッチを防ぐ
そもそもの退職を防ぐためには、採用ミスマッチが発生しないようにすることも大切です。
採用ミスマッチとは、企業側が求める条件やニーズに合わない人材を採用してしまうこと。採用ミスマッチが発生すると、従業員は不満やストレスを募らせることになり、高いパフォーマンスが発揮できないばかりか、早期に退職してしまうことも珍しくありません。
採用ミスマッチを防ぐための採用手法などについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
人材採用のマッチング率を高めるコツは?おすすめの採用手法も紹介
また、採用手法を見直す際には、ペルソナの設定も重要です。以下のページで詳しく解説しているので、こちらも参考にご覧ください。
採用ペルソナとは?失敗しない作り方やテンプレートを紹介
こちらの資料もおすすめ|定着率を劇的に高める! 『働き続けたい』と感じる職場づくりの法則【資料ダウンロード可能】
本資料では、「働き続けたい職場」をつくる際に押さえるべき3 つのポイントや定着率アップへ向けた具体策などをまとめました。早期離職へとつながる”採用ミスマッチ”を防ぐための参考資料として、ぜひご活用ください。
従業員満足度を高める施策を行う
従業員満足度(ES=Employee Satisfaction)を高めることも、そもそもの離職を防止するために重要な対策です。
せっかく自社にマッチする人材を採用できたとしても、職場環境で不満に感じる点が多いなど従業員満足度が低ければ、ゆくゆくは離職につながってしまいます。
従業員満足度を高めるには、「適材適所の人材配置を行う」「公平な評価システムを構築する」「十分な給与や福利厚生を提供する」などの施策があります。詳しくは、以下のページをご参照ください。
従業員満足度(ES)を高めるには?関係する6つの要素と成功事例を解説
離職防止ツールを導入する
離職防止ツールの導入も、おすすめできる対策の1つです。例として、従業員と組織の課題を見える化できる「Geppo(ゲッポウ)」があります。
Geppoは、あらかじめ用意された簡単な設問に定期的に答えてもらうことで、個々の従業員の悩みや不安、部署・チームの課題やボトルネックなどを洗い出すことができるツールです。回答内容を分析することで、離職防止のために実施すべき対策を検討していくことができます。
離職防止のための対策やおすすめツールについて詳しくは、以下のページをご参照ください。
離職防止のために何をすべき?離職率が高くなる原因と対策・おすすめツールを紹介
まとめ
退職代行サービス業者から連絡があった場合、業者の身元を調査し、本当に従業員本人から依頼があったことが確認できたら、引き留めなどはせず退職の手続きを進めていきましょう。
引き留めることよりも、退職代行サービスを使われるケースが増えないよう、従業員との関係性構築や職場環境の改善について検討していくことが重要です。
退職代行サービスを使われないためにできる対策についてサポートをご希望の際は、ぜひ弊社トラコムへご相談ください。トラコムでは、採用ミスマッチを防ぐための手法の提案など、人事・採用にまつわる総合的なコンサルティングをご提供しています。まずは以下のフォームより、お気軽にお問い合わせください。
退職代行に関連する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る