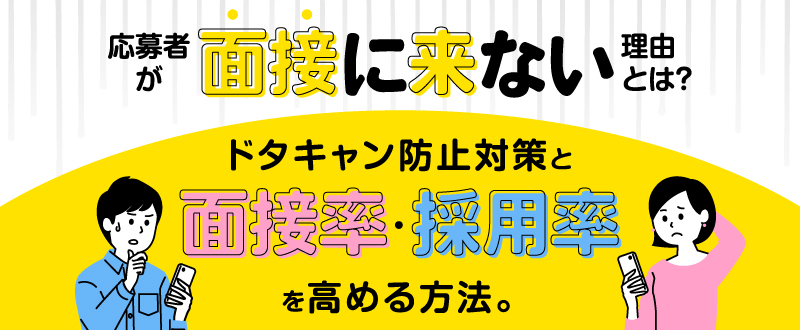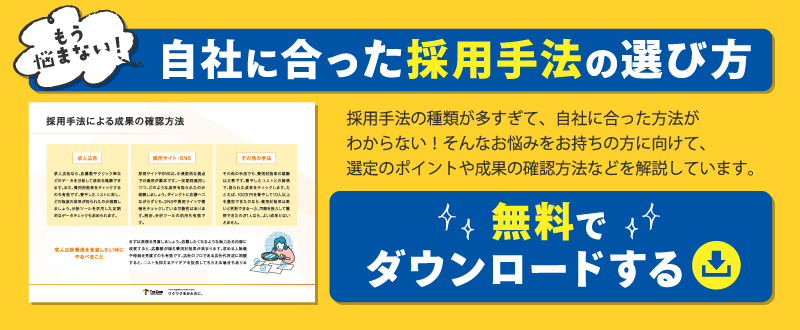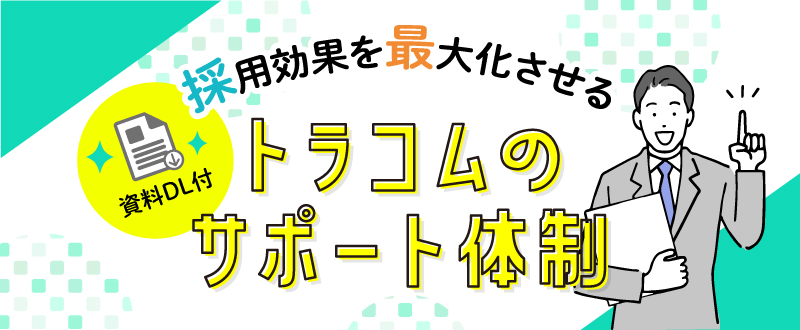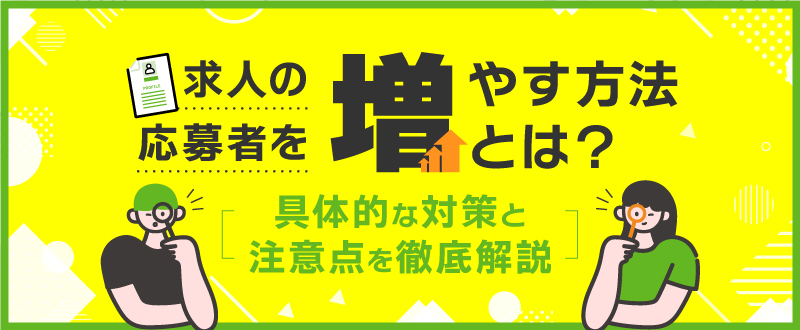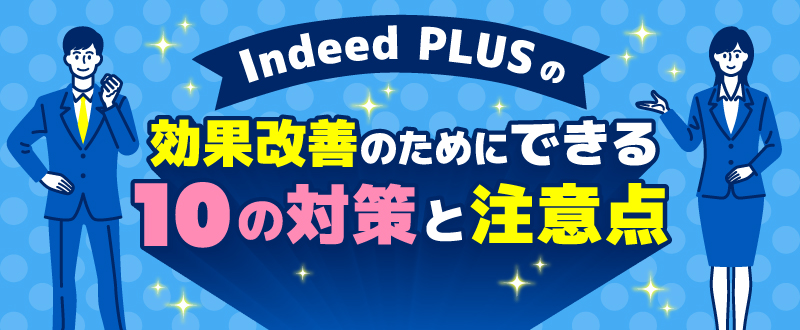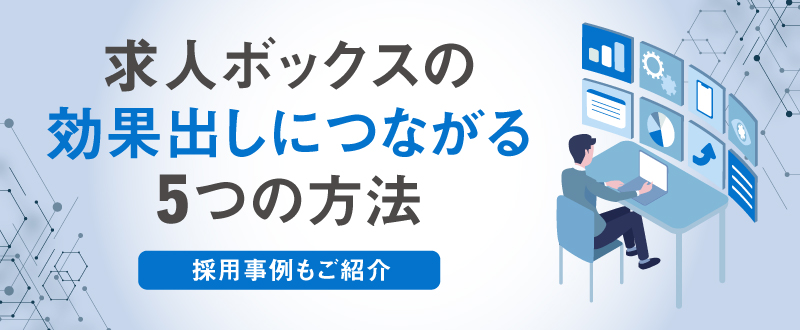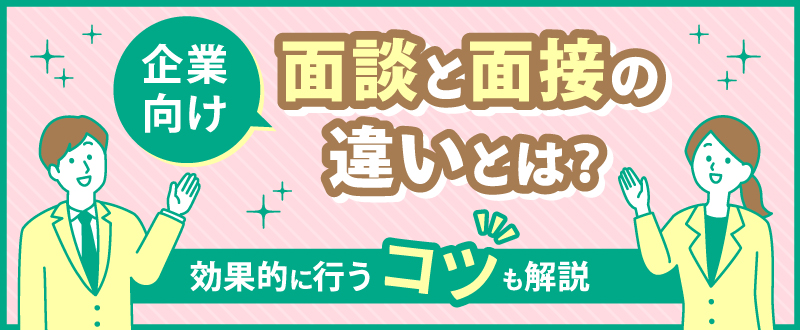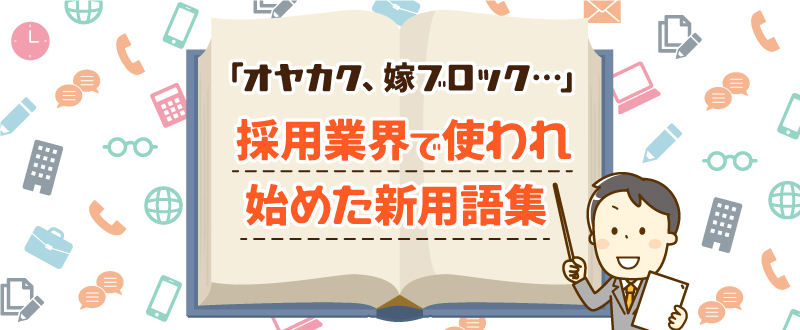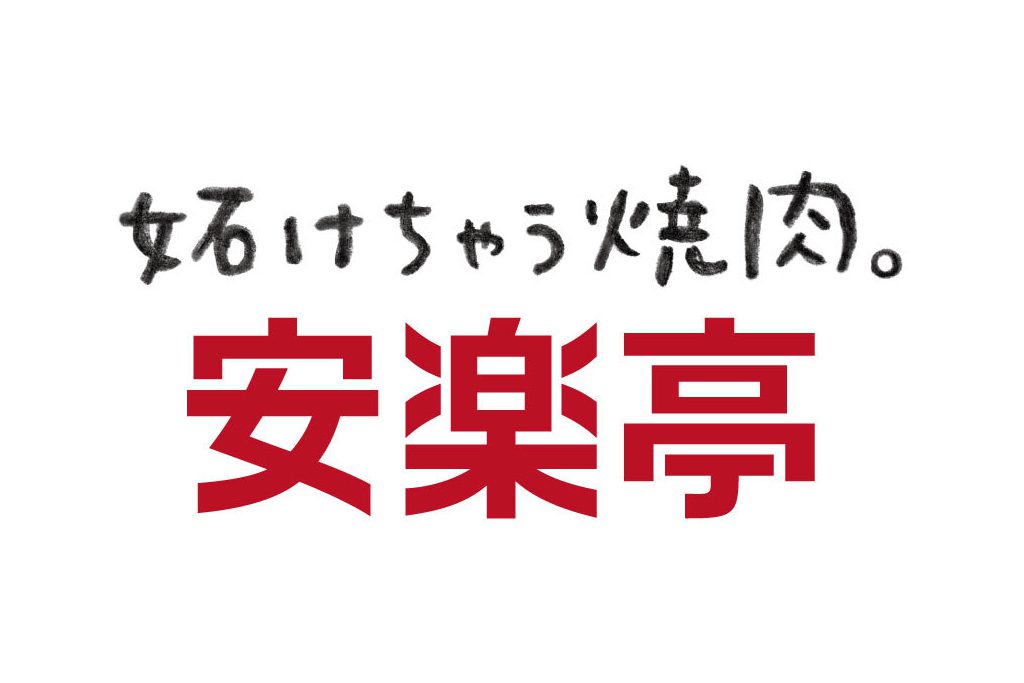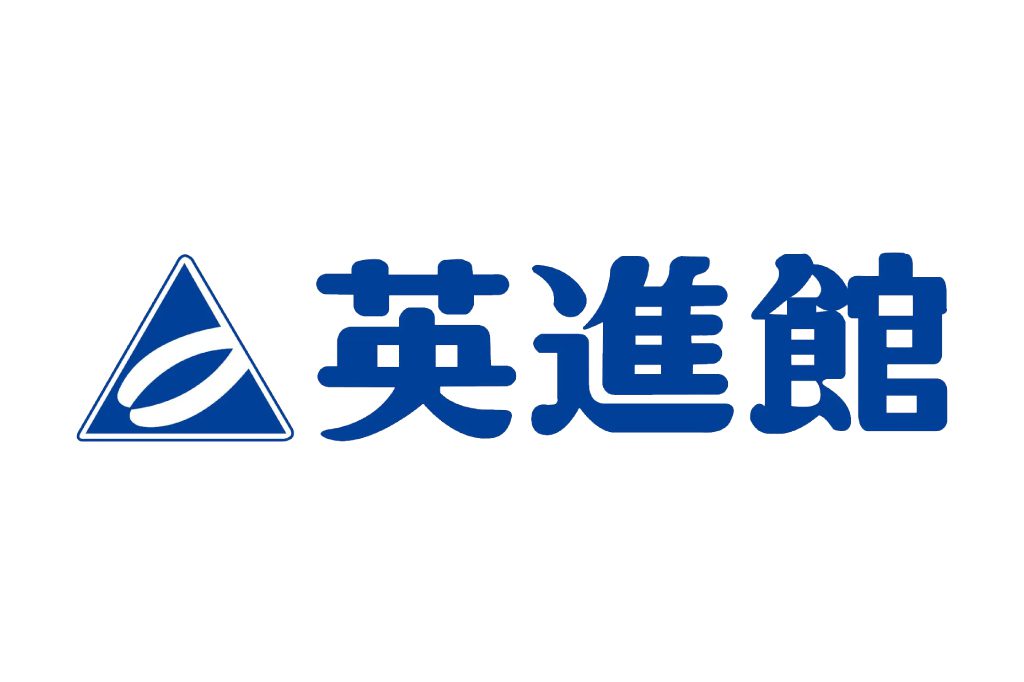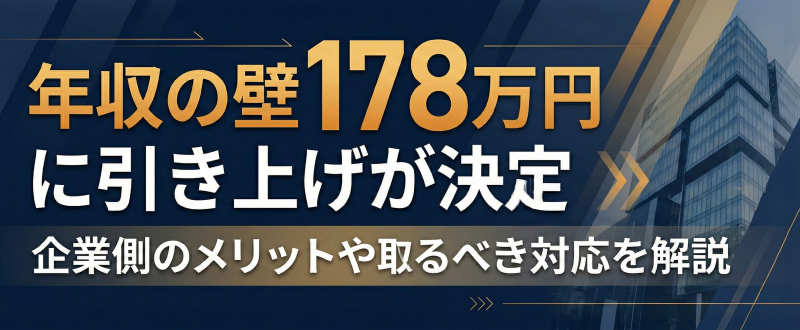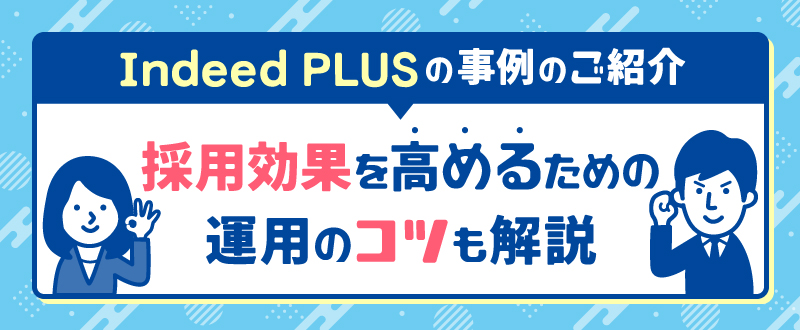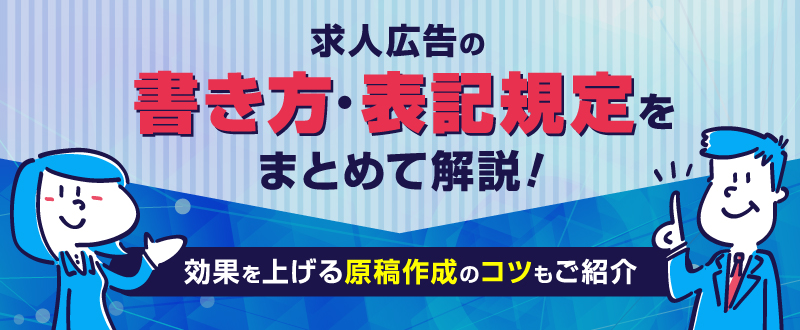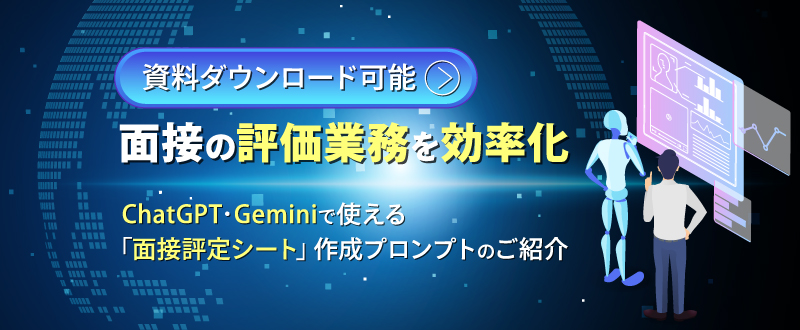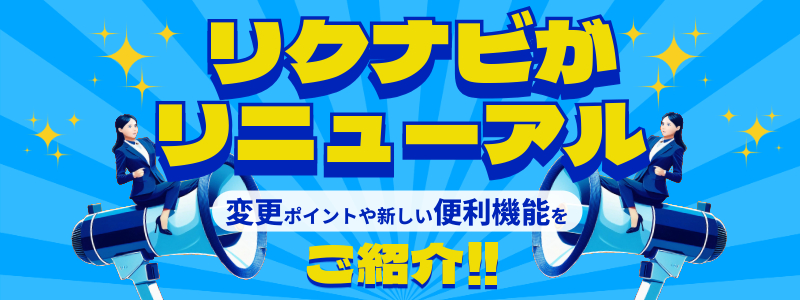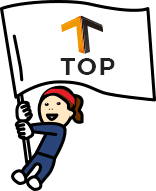トラコム社員がお届け!
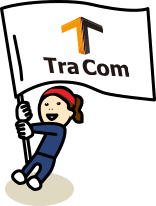
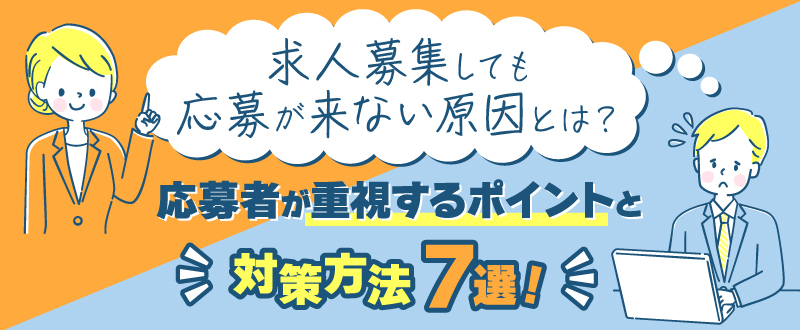
「せっかく求人を掲載したのに応募が来ない…」と悩んだことのある人事担当者様は多いのではないでしょうか。
本記事ではその原因を分析し、採用につながる対策方法をご紹介します。企業の採用ご担当者様がすぐに実践できる具体的な対策ばかりです。ぜひ参考にしていただき、効果のある求人募集を行いましょう。
こちらの記事もおすすめです
応募者が面接に来ない理由とは?面接率・採用率を高めるドタキャン防止対策13選
採用活動の全体像と求職者の行動の変化
「以前は応募があったのに最近は全然来なくなった…」「〇年前なら、同じ条件でも応募があったのに…」こうしたお悩みを抱えていませんか?
景気や社会情勢が日々変化するように、求人市場も時代に合わせて変化しています。ここではまず、その変化を2つの観点から見ていきましょう。
企業の採用活動の多様化
まず1点目は「採用活動の多様化」です。
以前は求人募集をするとなると、タウンワークやリクナビNEXTといった求人広告媒体への掲載が一般的でした。しかし、今は1つの方法に頼るのではなく、Indeedなどの求人サイト、X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNS、採用リスティング広告、スカウトメール、採用オウンドメディアなど、さまざまな手法を活用して採用活動を行う企業が増えています。
求職者の行動の変化
2点目は「求職者の行動の変化」です。
以前は“求職活動=就職・転職サイトを閲覧する”がセオリーでしたが、最近ではまず、口コミで企業を認知する ⇒ Googleでリターゲティングされ興味喚起 ⇒ 求人メディアで条件を確認する ⇒ 企業の採用ホームページ等を閲覧する、という流れが主流になっています。
サイトを閲覧して終わりではなく、上記のように複数の行動を経て就職先を比較検討する求職者が増えているのです。
求人募集しても応募が来ない8つの原因
人手不足を解決するためには、求人広告で確実に効果を出したいところです。しかしそのためには「募集をしたのになぜ反響がなかったのか?」その理由をしっかりと見極めることが不可欠。ここから、考えられる8つの原因をお伝えします。
①求人の情報量が十分でない
まず1つ目は「求職者の求める情報が足りていない」こと。
休日や勤務時間、待遇・福利厚生は詳細に書かれていますか?例えば、休日欄に<シフト制>とだけしか書かれていないと、求職者は不安に思います。月に〇日以上休める、季節ごとの連休の有無、有給休暇の消化率などもしっかり書くことは、求職者の安心感につながります。
また、仕事内容も重要です。営業職であれば1日何件ほどお客様を訪問するのか、ドライバーであれば1日に何キロ走行するのかなど、「自分がその会社で働く姿」をリアルにイメージできるような求人原稿が理想です。
②採用ターゲットに訴求できていない
2つ目は「採用したい人物像が明確でない」こと。
よくあるのは「働いてくれる人なら誰でもOK」という書き方になってしまっているパターンです。誰にでも当てはまる広く浅い内容の求人広告は、逆に誰の心も動かしません。特に、未経験者採用は他社との差別化が難しい案件です。経験不問とはいえ、コミュニケーション能力が問われる業務なのか、モクモク・コツコツ作業なのかなど、業務内容によって求められることは異なるはずです。
また教育担当を務める人の性格や年齢でも、採用したい人物像は変わってくると思います。「どんな人に来てほしいのか」をしっかり定めて、その人材に届く広告を作成しましょう。
③他社よりも条件が劣っている
3つ目は条件や待遇面。
競合他社よりも明らかに給与が低い、休日が少ない…それでは、人材は皆そちらに流れていってしまいます。
周辺の同職種・同業界の動向をしっかりとチェックし、条件面で劣っている部分があれば、改善に努めることも必要です。「ウチは中小企業だから…」と諦めずに、一度見直してみるといいかもしれません。
④適切な媒体選定ができていない
4つ目は「採用ターゲットに即した媒体を選んでいない」ことです。
極端な例で言うと、キャリア志向のユーザーの多い媒体に、アルバイト・パート採用の募集を出しても応募は集まりません。女性の志向に特化した媒体、地域の採用に強い媒体など、媒体によってユーザー層や特徴・強みが異なるため、採用したい人材に合わせた媒体選びが重要です。
自社に合った採用手法が知りたい方はこちら【資料無料ダウンロード】
採用手法が多様化したことで、「自社に合った採用手法がわからない!」とお悩みの人事・採用担当者は多いのではないでしょうか。
こちらの資料では、代表的な手法をご紹介し、ケース別の選び方のポイント、各手法の予算の使い方や成果の測り方についてまとめています。
⑤求人の発見性が低い
5つ目は「求人原稿を閲覧してもらえていない」こと。
例えばIndeed(インディード)は無料で掲載ができるということもあり、膨大な数の求人が掲載されています。特に営業職や事務職、接客・販売職などは求人掲載数が多く激戦区です。そのため、そもそも出稿した求人が採用ターゲットの目に触れてないため応募が集まらない…というケースも珍しくありません。
⑥選考フローが長い
6つ目は、「選考フローが長い」こと。
事前にある程度の情報を求人サイトに登録しておけば、クリック1つでエントリーできる媒体がほとんどです。そのため応募とは別に履歴書を送付する…といった“手間”がかかる求人は、求職者に敬遠されやすくなります。履歴書が必要な場合は、エントリー時ではなく面接時に持参してもらう方が応募のハードルはグッと下がります。
また、紙ではなくオンラインで履歴書を提出してもらうことも対策の1つです。最近ではスマートフォンで簡単に履歴書が作成できるため、求職者が手軽に求人に応募できるようになっています。詳しくは以下のサイトを参考にしてください。
参考:スマホで履歴書をメール送信する方法!注意点やPDF化の方法も解説|ワンポチ
そのフローがそのタイミングで本当に必要かどうか、今一度検討してみましょう。また、面接を2回以上設定している場合は、一次面接をリモートOKにしてみるなど、応募者が気軽に選考フローに参加できる工夫も大切です。
⑦口コミ対策ができていない
7つ目は「口コミ対策ができていない」こと。
冒頭で述べたように、気になる企業の口コミをネットで調べる求職者が増えています。口コミ対策はこの時代においては必須項目。いくら魅力的な求人原稿を掲載しても、悪い口コミがあるだけで台無しになってしまいます。「どうしようもない部分だから」と口コミを放置せずに、対策が必要です。
⑧振り返りをせず同じ内容・方法で掲載を続けている
そして最後は「反響の振り返りができていない」こと。
「条件は変わってないし…」と、原稿を作り直す手間を惜しんで“前回と同じまま”で求人広告を出し続けていませんか?求人は数字でしっかり結果が出る広告のため、採用成功に向けて「前回掲載時の反響はどうだったか」と振り返ることは非常に重要です。
反響が悪かった=たまたま運が悪かった、ではありません。媒体選びは適切だったか?広告サイズは十分だったか?などを再度チェックし、効果改善を図りましょう。例えば、検索性を高めるオプションを付けるだけで解決できる課題もあるかもしれません。
応募を増やすために知っておきたい求職者の重視するポイント
具体的な改善策を講じるために、今度は実際のユーザーアンケートの結果から、求職者の意識・動向を見ていきましょう。
注目したいデータは「仕事探しの絶対条件」についてです。正社員、アルバイト・パートなど雇用形態に関わらず、全体的に休日や勤務時間といった<労働条件>を重視する傾向があります。
雇用形態別に見てみると、正社員の場合は「就業形態」を条件にしている人が多く、これは即ち“正社員から正社員へ”という条件で仕事探しをしている人(93.5%)が多いということ。また合わせて「給与」に注目している人も多いようです。
一方アルバイト・パートでは、「勤務時間帯」と「勤務時間数」・「通勤(通いやすさ)」を重視している人が多いです。普段の生活と両立できるかどうか?に重きを置いて働きやすい職場を探している、ということを表していると言えます。
こうした雇用形態別の動向も、求人広告を作成する上でのヒントとなります。
参照)株式会社リクルート/求職者の動向・意識調査2023 基本報告書
求人に応募が来ないときの対策方法7選
それでは、ここからは求人に応募がないときに見直したい、採用に結び付ける対策方法を一つずつ見ていきましょう。
①採用ターゲットの見直し・明確化
「いい人材から応募がない」そんなお悩みがある場合は、まずは御社にとっての“いい人材”とはどんな人なのかを明確にしてみてください。
若い人がいい、未経験でもいい、それだけでは不十分です。採用ターゲットに「自分のことだ!」と気づいてもらうため、なるべく細かく伝えることを意識しましょう。人見知りでもいいから細かい数字などの作業を丁寧にキッチリしてくれる人がいい、などといったリアルな人物像をイメージできると効果大!または異業界・異職種のスキルが活かせる仕事であれば、具体的にその名前を出すのも効果的です。
例:老人ホームの入居営業 ⇒ 元介護士・ヘルパーの方は知識を活かせます など
②競合他社の調査・条件の見直し
自社を選んでもらうための工夫も必要です。周辺の競合他社を調査し、給与や休日、待遇・福利厚生を見直して改善できることは改善しましょう。出来ることは限られていると思いますが、条件面で優位に立てないからといって諦めることはありません。複数の媒体や施策などを活用して、広告の露出量を増やすことで応募母数の増加も期待できます。
また、ささいなことでも“自社のウリ”のアピールは効果的です。応募が集まる企業は、他社との違いを打ち出していることが多いです。アピールしたいポイントは採用ターゲットによって異なりますが、休憩室が広くてキレイ、社食が安くて美味しい、服装・髪型自由というのもポイントが高いです。
③関連キーワードの追加
ほとんどの求職者はキーワード検索で求人を探しているため、検索性の高いワードを原稿に盛り込むことも有効です。仕事に直接関係のあるキーワードはもちろん、関連するキーワードもしっかり入れていきましょう。
【参考記事】求人キーワードを原稿に記載することで採用率アップにつながる/人気の検索ワードを解説
④仕事内容の詳細の明記
仕事内容は、原稿の中でも求職者が細かく見る部分です。特に未経験者がターゲットの場合は、ユーザーが自分の働く姿を想像できるように詳細に書く方がいいでしょう。例えば、軽作業であればどれくらいの重さのモノを扱うのか、製造現場の仕事であればどういった機械を使用するのか、チーム作業なのか etc. 詳しく書けば書くほど、求職者の目線に寄り添った原稿になります。
⑤一覧に表示される項目の強化
ほとんどの媒体は、ユーザーがキーワードやカテゴリで検索すると関連性の高い原稿がずらっと表示されます。しかしながら、求職者はそれら一つひとつに目を通す時間はありません。表示画面を下にスクロールしながら、パッと目についた原稿だけ詳細に閲覧します。そこで大事になってくるのは、一覧表示画面でのアピール。媒体によって一覧画面の表示のされ方は異なりますが、例えば必ず表示される職種名欄に休日や残業に関する情報を併記するなど、「クリック率」を高めるために色々と工夫してみることをオススメします。
⑥求人媒体・採用手法の最適化・多様化
冒頭でもお伝えしましたが、採用手法は「求人広告を掲載する」以外にもたくさんあります。自社のHPに採用サイトを作成し、そこから応募できるようにするのはコストを低く抑える方法の一つです。またはIndeedや求人ボックスといった求人サイトに掲載することも、露出量の観点から効果が高いと言えます。無料でも利用できるサイト・媒体はローリスクではじめられるのも嬉しいポイントです。また新卒・中途に関わらず、採用トレンドとして「個別採用」への注目も高まっています。
こちらの記事では、新卒採用・中途採用における採用のトレンドや、多様化する採用手法とその選び方について解説しています。
・新卒採用・中途採用の方法を一挙に紹介!採用方法の選び方も解説
・新卒採用・中途採用のトレンドとは?多様化する採用手法を徹底解説
⑦求人広告代理店への相談
ここまで見てきたように、求人の市場動向を的確に押さえながら原稿を作成し、結果を出すのはなかなか一筋縄ではいかない時代になっています。自社で行えることにも限界がありますから、専門家に任せてみることも非常に有効です。求人広告代理店は、ただ広告を作成するだけではなく、周辺の競合他社の状況や相場、難易度の高い採用の成功例といったデータも持っており、適切な媒体選びから広告戦略まですべてを任せられるため、効果改善への一番の近道と言えるかもしれません。
求人広告代理店とは?必要性や依頼するメリット、サポート内容や発注の流れを解説
リクルート代理店トラコムの3つの強み
豊富な媒体・採用手法から最適なプランをご提案
弊社トラコムでは多数の求人メディアを取り扱っており、まずは貴社の課題や実現したい目標をお聞かせいただき、その中から最適な媒体をご紹介します。
リクルート求人媒体(タウンワーク、リクナビNEXT、はたらいく等)から、 求人サイトのIndeed、求人検索エンジン(求人ボックス、スタンバイ等)、web広告(Googleリスティング広告等)、SNSや採用オウンドメディアなど、豊富な媒体・採用手法のご提案が可能です。
コンサルティング・求人制作・運用までトータルサポート
採用活動は求人広告を出したら終わり、ではありません。どのような人材を採用していくべきか、どのようなタイミングで進めていくべきかなど、知見が求められる場面も多いでしょう。弊社ではコンサルティング的なサポートも実施しています。人材が足りなくなってから募集を始めるのではなく、将来を見据えて戦略立てて、長期的に採用活動を伴走することも得意です。
豊富な採用実績からなる知識とノウハウ
弊社では、採用業界歴20年以上のノウハウと豊富な実績にもとづき、専門的な知見やノウハウをご提供することが可能です。求人広告の効果的な出し方はもちろん、採用ホームぺージの改善や口コミ対策の方法など、求職者と接点を持つタイミングを包括的にアドバイスします。 また全国の主要都市に拠点を展開しているため、その地域に特化した情報も持っています。年間1万社を超える企業様の経営課題を解決してきたサポート力にご期待ください。
トラコムのサポート体制について詳しく知る
【資料ダウンロード可能】採用効果を最大化させるトラコムのサポート体制
求人募集での応募数改善・人材採用に関するご相談はトラコムまで
人手不足は経営に直結する重要な課題です。その一方で、採用手法は多様化しており「いい人材」の獲得が難しくなっていることも事実。ですが、良い結果を出す方法は必ずあります。大企業でなくても、採用に大きな予算をかけられなくても、採用が難しい立地・職種だとしても、採用成功の道は必ずあります。
応募がないことの悩みや、求人募集・採用活動においてお困りの方は、ぜひトラコムまでご相談ください。
関連する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る