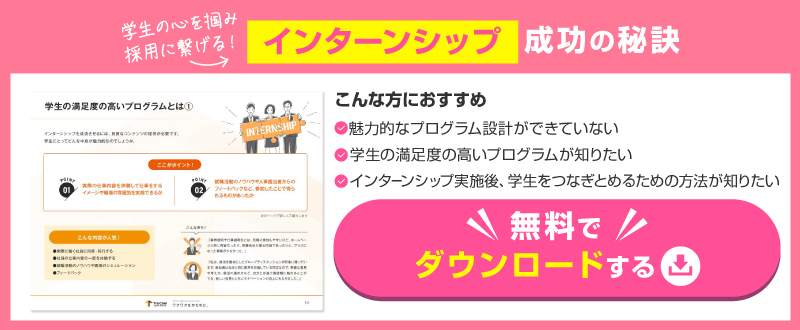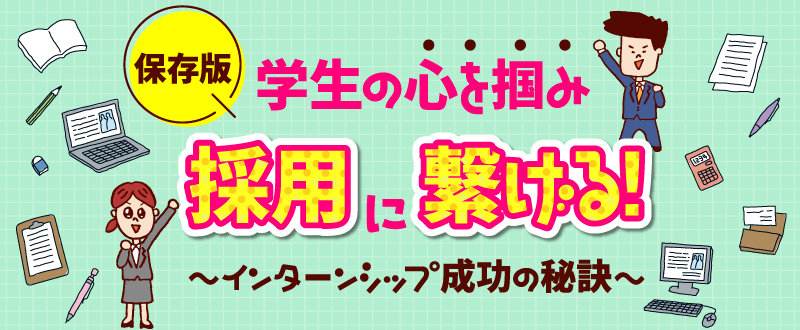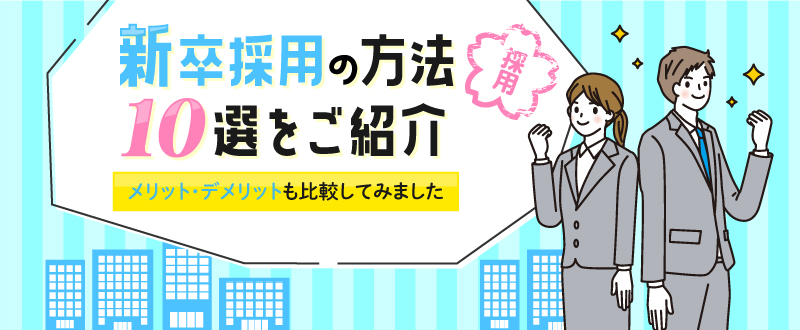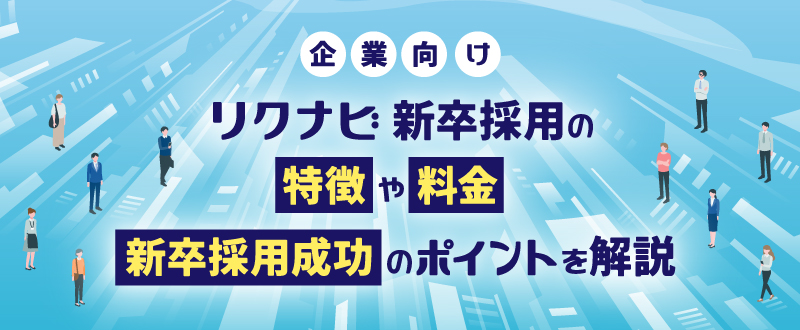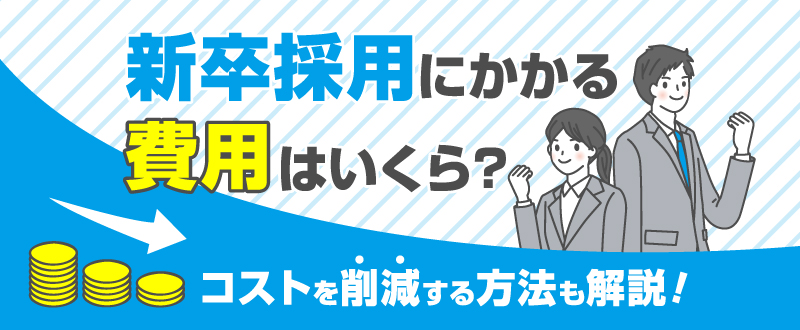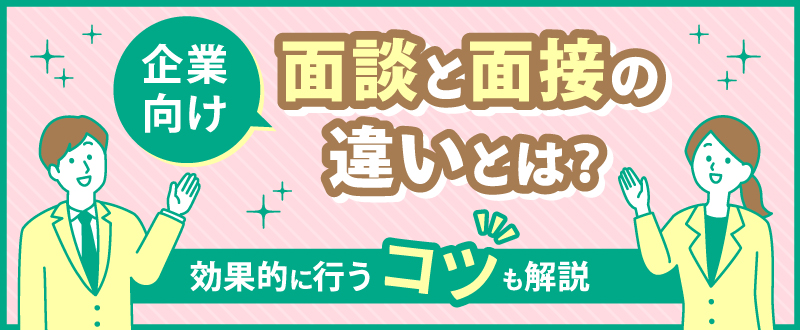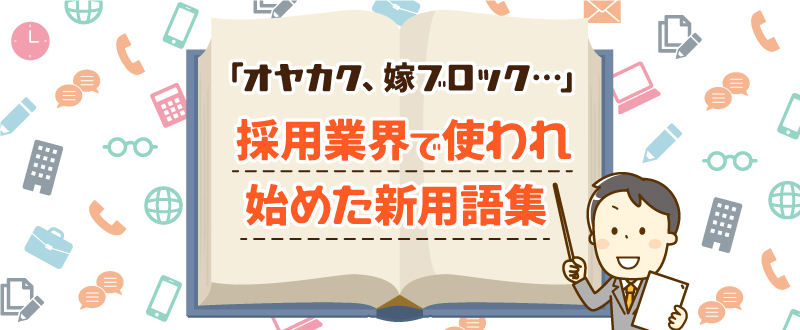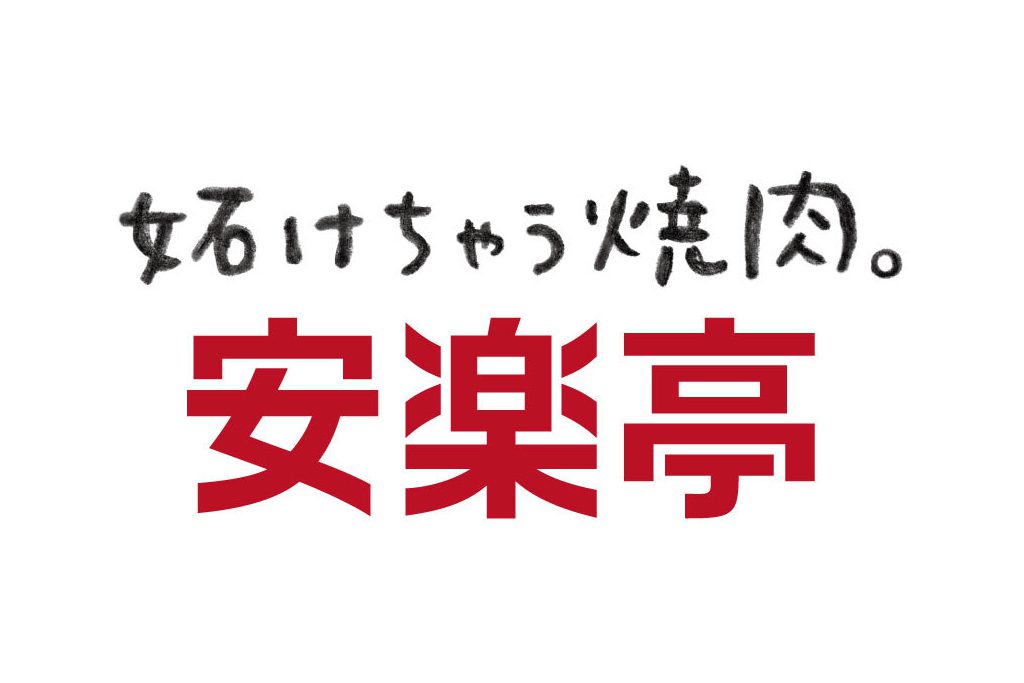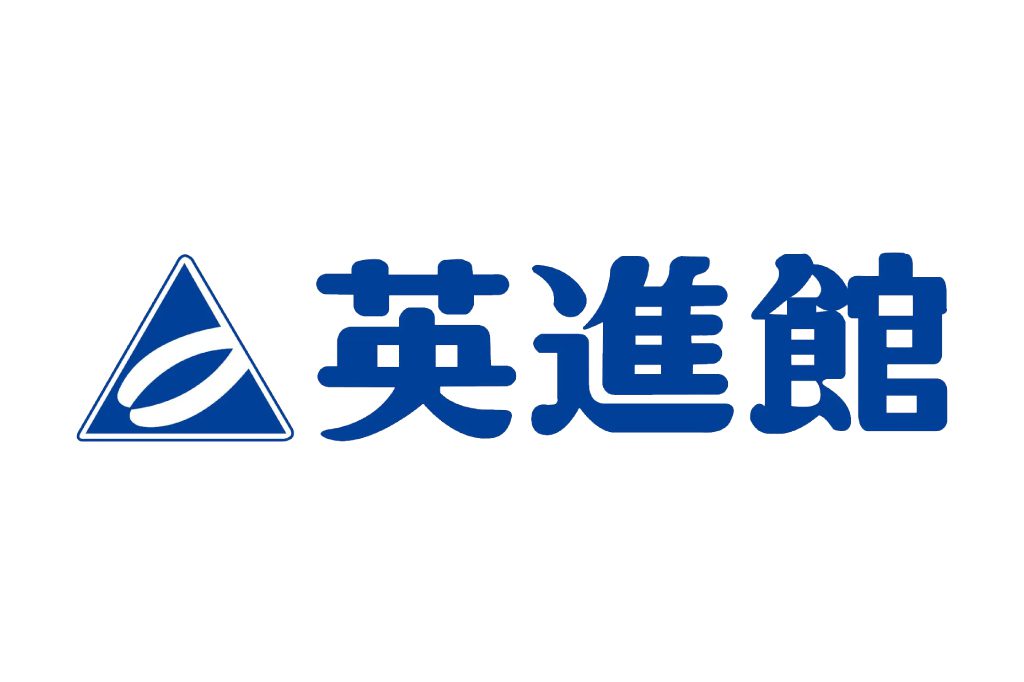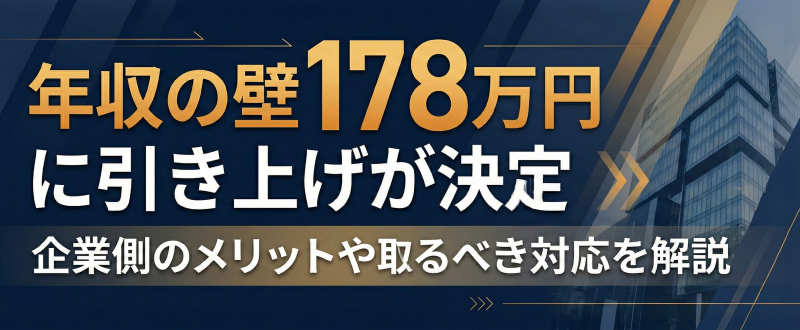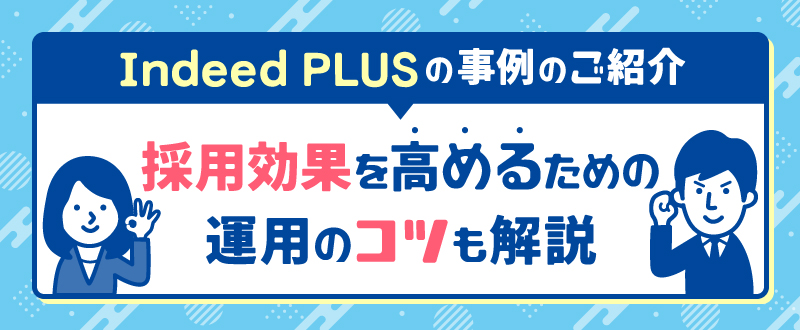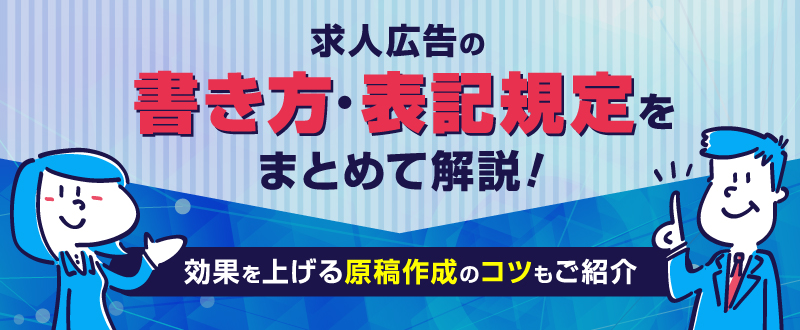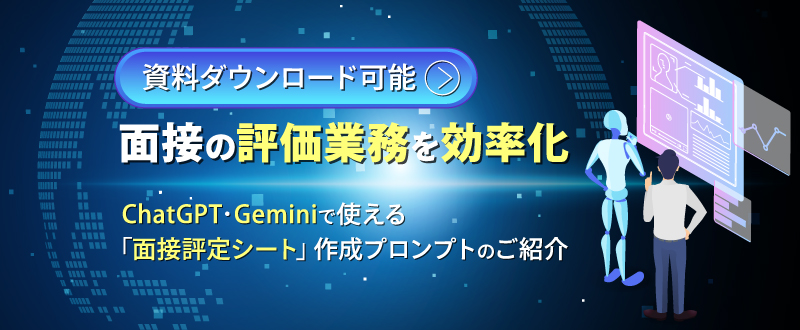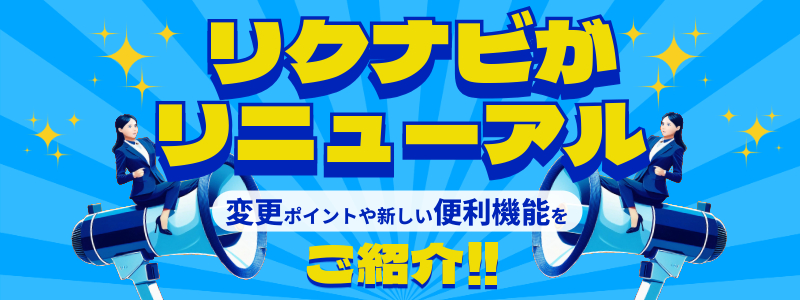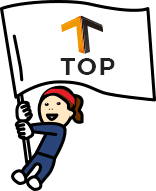トラコム社員がお届け!
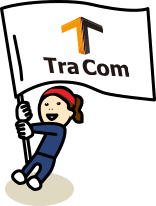
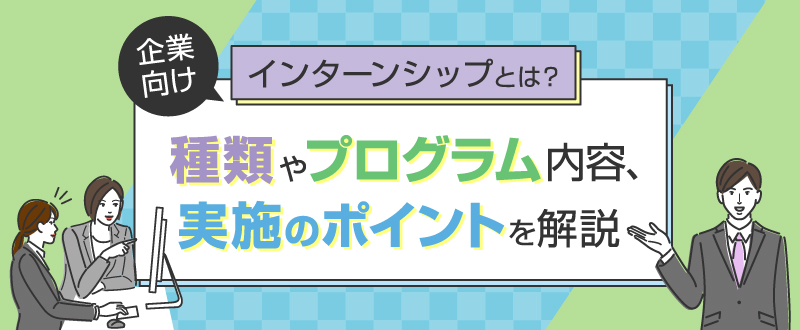
インターンシップは、新卒採用における学生への効果的なアプローチ手法として注目されています。
とはいえ、インターンシップを開催すれば必ず成果が出るとは限りません。進め方や内容を工夫しなければ、学生の満足度を高めることは難しく、期待した効果を得られないことがあります。インターンシップを開催する目的に合わせて、適切なプログラムを策定することが大切です。
ここでは、インターンシップの種類や具体的なプログラム例、効果を高めるポイントなどを紹介します。
インターンシップとは?
インターンシップとは、学生が興味のある企業や業界で実際に働いてみる体験プログラムのことです。学生は、就業体験を通して企業・業界・職種に対する理解を深め、業界研究や自己分析、志望企業選定の検討材料を集めるなどの目的で参加します。
インターンシップの実施時期
インターンシップの時期に決まりはなく、いつでも開催することが可能です。
リクナビのアンケート調査によれば、インターンの実施時期は多い順に8月(27.0%)、7月(24.3%)、6月(18.0%)、3月・9月(17.7%)となっています。
つまり、実施時期としては夏(7月~8月)と冬(3月)が多く、大学生の夏休みと春休みに合わせて開催する企業が多いようです。
インターンシップが注目される理由
多くの企業がインターンシップを導入・実践する背景として、少子高齢化による「採用売り手市場」が続いていることが挙げられます。そもそも母集団の形成自体が難しく、優秀な学生の確保がますます困難になっています。
人材獲得の競争が激化し、学生からの応募を「待つ」だけでなく、企業側から積極的に学生を獲得しにいく「攻め」の姿勢が求められる状況です。
例えば「ダイレクトリクルーティング」を導入して、企業側から学生に対して直接アプローチする企業が増えています。
そしてライバル企業よりもできるだけ早く学生にアプローチし、効果的に自社の存在をアピールできる手法として注目されているのが「インターンシップ」です。インターンシップを導入するメリットについて、詳しくは当ページの「インターンシップを導入する目的」をご参照ください。
インターンシップの市場動向
株式会社ディスコの調査によれば、22年卒のインターンシップ実施率は、前年の77.2%から13.9ポイント下がって、63.3%となりました。新型コロナウイルスの影響から開催を見送る企業が多かったようです。
一方で「Webインターンシップ」は増加が見られ、オンライン化が進んでいます。就職みらい研究所の「就職白書2022」によれば、学生のWebインターンシップへの参加率は21年卒の15.7%から、22年卒には48.4%と大幅に増加したことが分かります。
さらに、同調査によると「内定者の平均3割」がインターンシップ参加者です。このようなデータからも、採用手法の一つとしてインターンシップの効果が高いことが分かります。
また、株式会社SHiRO(ココシロ!インターン)の記事によれば、インターンシップには短期インターンと長期インターンがあり、短期のインターンシップに参加する学生が圧倒的に多く、長期のインターンシップに参加している学生が少ないことがわかります。
インターンシップを導入する目的
多くの企業がインターンシップを導入する背景には、どのような目的があるのでしょうか。インターンシップの代表的な目的を紹介します。
学生との早期接触
インターンシップを導入する大きな目的は、学生と早期接触を図ることです。
政府の定める採用スケジュールでは、企業情報などの広報活動解禁が「大学3年3月」、選考などの採用活動解禁が「大学3年6月」とルールが定められています。とはいえ、前述の通り人材の獲得競争が激化しているため、できるだけ早く学生と接触を開始し、自社の魅力をアピールすることが必要です。
インターンシップは基本的に、採用スケジュールとは関係なく開催できるため、学生と早期接触が可能になります。
採用活動が解禁される前から学生と接触を図り、競合他社に先がけて採用ターゲットの学生と関係性を構築できることがインターンシップのメリットです。
学生の早期戦力化
入社前に社会人としての基礎や、業務で必要になる最低限の知識を身につけてもらい、学生の「早期戦力化」を図る目的もあります。
インターンシップは学生が自社の業務を経験できる貴重な機会です。インターンシップで実際の業務を経験し、仕事内容はもちろん、企業や業種に関する知識を深めることで、入社後スムーズに社会人としてのスタートを切ってもらいやすくなります。
ミスマッチの防止
入社前に実際の業務や社風を体験してもらうことで、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
インターシップのセミナーや職場見学、業務体験などを通して、業務内容や社風に対する学生の理解を深めることができます。その結果、入社後に「思っていたような仕事ではなかった」「希望するスキルやキャリアを得られそうにない」というミスマッチが発生することを防ぎ、エンゲージメント向上や離職防止が期待できるのです。
インターンシップの種類とそれぞれの実施期間・対象学年
インターンシップは、期間や時期によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの実施期間や対象学年を確認しておきましょう。
期間別インターンシップ
インターンシップは、実施する期間の長さによって4つのタイプに分類できます。それぞれの実施期間と対象学年をまとめると、次の通りです。
| 実施期間 | 対象 | |
| ①オープン・カンパニー | 超短期(単日) | 全学年 |
| ②キャリア教育 | 学業に配慮した日程で短期的・簡易的なものが多い | 全学年 |
| ③インターンシップ汎用的能力・専門活用型 | ・汎用的能力 5日以上 ・専門活用型 2週間以上 無給・有給どちらもOK | 学部3・4年 修士1・2年、 博士課程 |
| ④インターンシップ高度専門型 | 2週間以上 (※給与発生) | 理系の博士課程 ※企業と国とで試行している最中 |
それぞれ、以下に詳しく解説していきます。
①オープン・カンパニー
企業が主催する、「就業体験なし」の説明会・就活イベントのことをオープン・カンバニーといいます。令和5年度の法改正前では「短期インターンシップ」「1dayインターンシップ」など数日程度で開催さていたインターンシップになります。
【具体的な実施内容】
- 企業説明会
- OB・OG訪問
- 座談会企画 など
(いずれもオンライン開催を含む)
②キャリア育成
業界・職種理解を深めてもらうためのプログラム・体験を行います。こちらも法改正前の「短期インターンシップ」「1dayインターンシップ」と同意義のインターンシップとなります。
【具体的な実施内容】
- 企業説明会
- OB・OG訪問
- 座談会企画
- 職業体験会・見学会
- ローププレイング企画
- チームに分かれて課題を発表するなどのグループワーク
オープン・カンバニーとキャリア育成のいずれも長期のインターンシップと比べると低コストで、社内リソースを大きく割かずに開催できることがメリットです。
短期間で多くの学生と接触できますが、学生との深い関係性を構築するには不向きです。「広く浅く」アプローチするために向いているといえます。
③④インターンシップ汎用的能力・専門活用型・高度専門型
5日以上・2週間以上といった長期間で開催するインターンシップは「長期インターンシップ」と呼ばれます。短期インターンシップと違って学生と長い期間にわたって交流があるため深い関係性を構築できる一方で、コストが大きい点がデメリットです。研修を担当する社員が大きくリソースを割くことになり、短期インターンシップよりも業務負担が大きくなります。
参考:【東大生が教える】長期インターンのメリットとデメリットについて!|U-inTern
通常業務に支障が出ないよう、十分な計画のもとで開催することが重要です。
時期別インターンシップ
開催する時期によっても違いがあり、「夏インターンシップ」「秋冬インターンシップ」と大別されます。それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。
※夏インターンシップ・秋冬インターンシップについても開催期間や実施内容によって上記の①~④のタイプに区分されます。
| メリット | デメリット | |
| 夏 | ・母集団を形成しやすい ・学生と早期に接点が持てる | ・本選考までのつなぎ止めが難しい ・競争率が高い |
| 秋冬 | ・選考まで進んでもらいやすい ・志望度の高い学生に注力できる | ・学業とスケジュールを合わせにくい ・幅広い学生とのマッチングは難しい |
それぞれ、詳しく解説します。
夏のインターンシップ
夏のインターンシップは、多くの学生が夏季休暇に入る8月をピークに開催されます。学生とスケジュールが合いやすく、活発に就職活動を行っている人が多いこともあり、幅広いターゲットと接点を持てることがメリットです。
ただし本選考まで期間が開くため、学生をフォローし、つなぎ止める工夫が求められます。また、多くの企業がインターンシップを開催するため、競争率が高いことも意識する必要があります。
秋冬のインターンシップ
秋冬のインターンシップは、9月~2月にかけて開催されるインターンシップです。本選考が近いため、志望度の高い学生に向けて、より選考に直結しやすいインターンシップを開催できます。
ただし学業との両立が難しい時期であり、スケジュールが合わないケースも多いことがデメリットです。またこの時期になると、すでに志望企業を絞り込んでいる学生が増えるため、幅広い学生とのマッチングは難しくなります。
インターンシップのプログラム内容
インターンシップでは具体的にどのようなプログラムを用意すればよいのでしょうか。代表的なプログラム例として、次の4つが挙げられます。
| インターンシップのプログラム例 | |
| セミナー | 企業の事業内容や業界の動向などについて説明会を実施する |
| 職場見学 | オフィスや工場で働く先輩社員の姿を実際に見学し、社風や働き方を見てもらう |
| グループワーク・ワークショップ | 一つのテーマを設定して業務を疑似体験するロールプレイングなどを行う |
| 業務体験 | 入社後に従事する業務の基礎的な部分や軽作業を体験してもらう |
1回のインターンシップで1つのプログラムのみを実施する場合もあれば、複数の種類を組み合わせて実施する場合もあります。それぞれの内容について、以下より詳しく見ていきましょう。
セミナー
セミナー形式のインターンシップでは、企業の事業内容や業界の動向などについて解説します。企業説明会の延長のようなイメージです。
セミナーといってもあまり堅苦しい雰囲気にはせず、学生が気軽に質問できる雰囲気で開催することが一般的です。準備物が少なく手軽に開催できるため、短期インターンシップでよく取り入れられます。
多くの学生に参加してもらえるため、早期に学生と接触して母集団を増やしたい場合におすすめの形式です。
職場見学
職場見学では、オフィスや工場で働く先輩社員の姿を実際に見学し、社風や働き方を体感します。採用担当者だけでなく現場で働く社員も見学会に同行し、その場で質問を受けながら社内を見て回る形式が一般的です。
職場見学では、学生の自社に対するイメージを具体化し、ミスマッチを軽減する効果が期待できます。入社に対する不安の解消や早期離職の防止にも役立つ形式です。
ただし開催するには社員のリソースを割く必要があり、また多くの学生を受け入れられないというデメリットもあります。そのため、志望度の高い学生に向けて、秋冬インターンシップで取り入れることが多いプログラムです。
グループワーク・ワークショップ
グループワーク・ワークショップでは、一つのテーマを設定して業務を疑似体験するロールプレイングなど行い、自社の業務理解を深めます。
例えば、「新商品のマーケティング施策を考える」というテーマをもとに、少人数グループを組んでディスカッションし、施策をまとめて先輩社員や経営陣にプレゼンテーションするといった内容です。
テーマや課題を通して企業や業界の理解が深まるだけでなく、社員からフィードバックや評価をもらえることで学生のモチベーションアップも期待できます。ただし、テーマ設定や人員確保などにしっかり時間をかける必要があり、リソースがかかる形式です。
業務体験
業務体験では、入社後に従事する業務の基礎的な部分や軽作業を体験します。実際に手を動かすことで、説明会だけでは分からない仕事の流れや雰囲気を体感でき、業務理解が深まることがメリットです。
業務の流れを理解してもらう必要があるため、一般的に1ヶ月~数ヶ月など中長期で実施されます。受け入れる部署のリソース確保が必要なので、人事担当部署と担当部署との綿密な事前調整が大切です。
このような特徴から、志望度の高い学生を対象に、早期内定や入社後の早期戦力化を目的に実施するとよいでしょう。
インターンシップを実施する際のポイント
インターンシップの目的を達成し、採用につなげるにはどのような点に注意すればいいのでしょうか。実施する際のポイントを解説します。
「没入感」と「達成感」を提供する
インターンシップでは、学生に「没入感」と「達成感」を提供するよう心がけましょう。
没入感とは、この会社で自分が働いている姿を想像できる感覚です。インターンシップを通して「どんな人」たちが「どんな職場・雰囲気」で働いているのかが伝われば、学生が自然と自分自身に置き換えて、働いている姿を想像できます。
「組織の一員として企業の力になれている」という達成感も、学生にとって重要です。自分の行った仕事が実際に企業の役に立っている、企業に新しいものを提供できているという感覚が持てると、ワクワク感と同時にやりがいとは何かを学生に感じてもらえるでしょう。
この2つの感覚を学生に持ってもらうと、入社動機の形成がしやすくなることが期待できます。
「没入感」の提供型プログラム内容例
学生に「没入感」を提供するためには、「自分だったら」と想像できるようなプログラムを企画しましょう。
- 朝会や締め会など、定例イベントに参加:「会社の雰囲気がわかる」「社会人とはなにかがわかる」
- 同行や職場見学:「仕事内容がわかる」「仕事上でのやりがいがわかる」
- 座談会:「会社の雰囲気がわかる」など
このように、会社のリアルを感じてもらうことができるプログラムにすることで、学生が自社で働いている姿を想像しやすくなります。
オンラインで行えるプログラムも多いため、これからインターンシップを始める企業でも採り入れやすいのもメリットです。
「達成感」の提供型プログラム内容例
こちらはいくつかの業界ごとに、プログラム内容例をご紹介します。
- 〈飲食業界〉特定のエリアにおいて顧客層のリサーチ&発表
- 〈IT業界〉仮想案件におけるケーススタディ(課題発見、ニーズ調査、ターゲティング等)
- 〈建築業界〉建物の設計とデザイン体験&発表
プログラムの中で発表等を行い、学生とコミュニケーションを取りながらきちんとフィードバックを行うことで、学生は「組織の役に立っている」という感覚が芽生え、達成感や安心感が生まれます。
学生へのフィードバックをする
学生はインターンシップを通して、「社会人の先輩から自分はどう見えるのか知りたい」と思っていることがあります。そのため、業務体験やグループワークを通して学生の強み・弱み、社会人として身につけるべき点などをフィードバックすることで、自社への志望度を高めやすくなります。
課題に対して取り組む姿勢や、意見の言い方、他人の話の聞き方はどうだったかなど、細かなフィードバックをすることがポイントです。「今後の就活はこう進めるとうまくいくと思うよ」といった具体的なアドバイスがあると学生から喜ばれ、信頼度アップが期待できます。
また、以下のサイトでは、就活生向けにインターンの種類や企業の見つけ方、エントリーから参加までの流れを解説しています。就活生の動向を把握するために、参考にしてみてください。
参考記事:就活のインターンシップを徹底解説!エントリー時期や企業の探し方を紹介
こちらの資料もおすすめ|学生の心を掴み採用に繋げる!インターンシップ成功の秘訣
インターンシップ実施における注意点
インターンシップを実施する際は、次の2点に注意してください。
報酬を支払わないと違法になる場合がある
就労体験といえども実際の業務に携わる場合には、インターン生は「労働者」とみなされ、最低賃金以上の報酬を支払わなければならないケースがあります。
労働者とみなされる基準となる要素は、以下の2つです。
- 企業とインターン生の間に、「指揮命令関係」があったかどうか
- インターン生の作業によって、企業が利益や効果を得たかどうか
(旧労働省行政通達:平成9年9月18日基発第636号)
具体的には「インターン生が作ったプレゼン資料を営業で使用する」「インターン生が営業活動に携わる」といったケースが考えられます。この場合「労働者」に該当する可能性があるため、報酬の支払わなければ違法になる恐れがあります。
インターンシップの募集を行う際は、報酬の書き方に注意が必要です。以下でご説明します。
- 報酬:1時間あたり0000円
- 報酬:日当0万0000円
※雇用関係ではないため「時給」「日給」の給与形態は使用不可
※但し労働の対価の報酬のため、 各都道府県の最低賃金を考慮した金額設定を強く推奨
※その他、雇用されているような文言(給与・残業など)は使用NG
誓約書を取り交わす
就労体験において学生が企業機密や個人情報に触れる可能性がある場合には、情報漏洩を防止するために誓約書を取り交わしましょう。
学生の情報漏洩によって自社や顧客に損害が出てしまうと、学生に賠償を求めるケースも考えられます。どのような場合に損害賠償を請求するのか、どのくらいの金額になるのか誓約書に明記し、口頭でもよく説明するようにしましょう。
また重要な情報に学生が触れないよう、社内体制を整備することも重要です。安心して学生を受け入れられるよう、まずは体制の見直しを実施しましょう。
インターンシップの開催にお困りの際はトラコムへご相談ください
インターンシップを開催する重要性は分かっていても、効果的なプログラム内容の企画は難しいものです。他社との差別化を図るためには、オリジナリティのある企画が求められますが、経験豊富な採用担当者でもインターンシップの内容には常に頭を悩ませているものです。
また、インターンシップを実施するには社内の受け入れ体制を整備する必要もあります。マンパワーが不足している企業だと「うちでは難しい」と諦めてしまっているケースも多いかもしれません。
そんな時は、ぜひトラコムにご相談ください。トラコムでは、お客様の企業体制やリソースを考慮し、最適なインターシッププランをご提案しています。相談は全国どこからでも無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、「具体的に自社に合ったコンテンツを考えてほしい」「人手が足りないので企画をまるっと任せたい」そのようなインターンシップのプログラム企画立案にお悩みの企業様には、弊社の新卒採用代行サポートもおすすめです。
ご興味をお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
初めての新卒採用&業務効率化におすすめ。トラコムの新卒採用サポートサービス
まとめ
学生との早期接触の重要性が高まる昨今では多くの企業がインターシップを実施しています。
一口にインターンシップといっても期間や時期には種類があり、自社の目的に見合ったプランを立てることが重要です。インターンシップでどのような学生と出会いたいのか、自社に対してどのような想いを抱いてほしいのかなどの「目標」を明確にし、最適なインターシップを計画しましょう。
インターンシップについての知識をさらに深めるために、以下の資料をご利用ください。最新の企業動向や効果の高いプログラム例、採用につなげるためのポイントなどを詳しく解説した資料です。ぜひダウンロードしてご活用ください。
インターンシップ・新卒採用に関連する記事

この記事を書いた人
K.OAMI
この人の記事一覧を見る
2006年に前身の会社で新卒入社。千葉支社で4年勤務。リーダーとして大阪支社で勤務。
マネージャーとなり、エリア組織・大手組織・京都営業所の管理を兼務をし、
2020年に東京本社勤務となる。
現在は、東京本社にて、エリアグループを担当している。
商品は、Indeed・Indeed PLUS・求人ボックスを中心に、中途社員・アルバイト新卒採用まで担当。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る