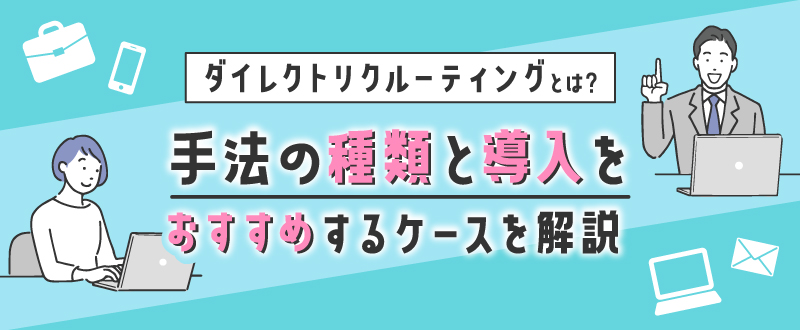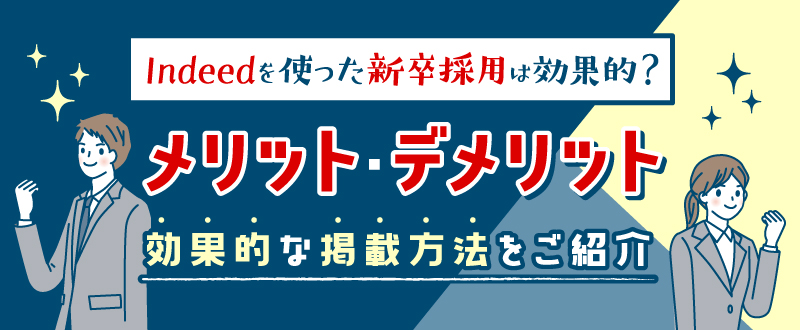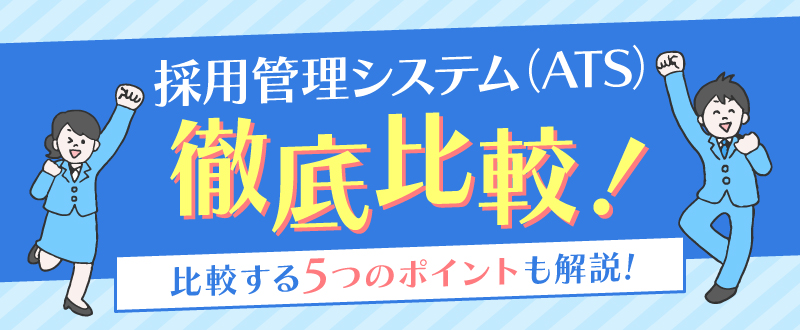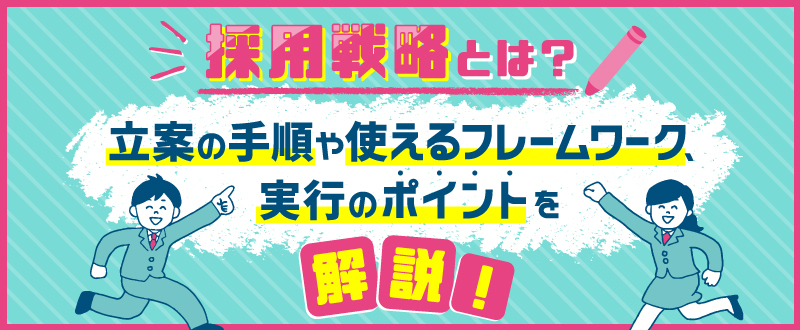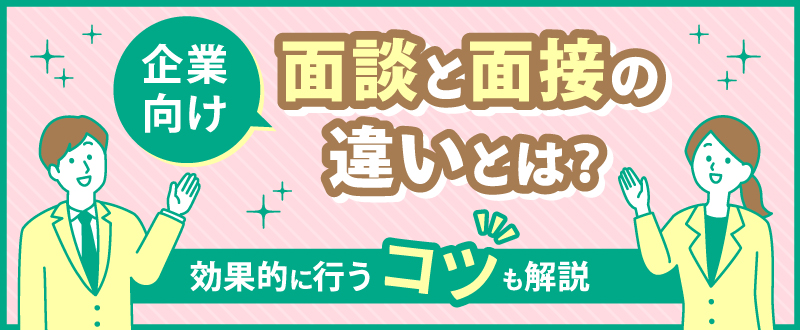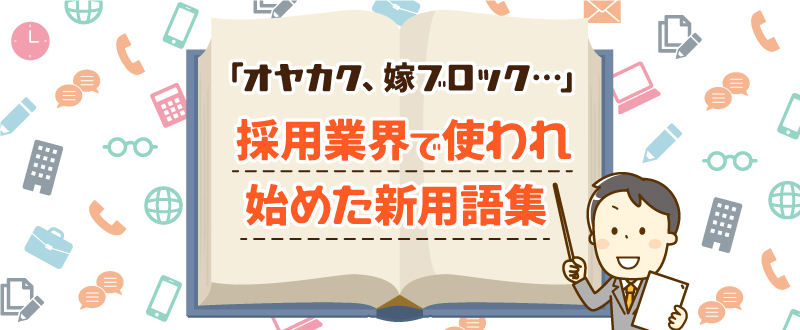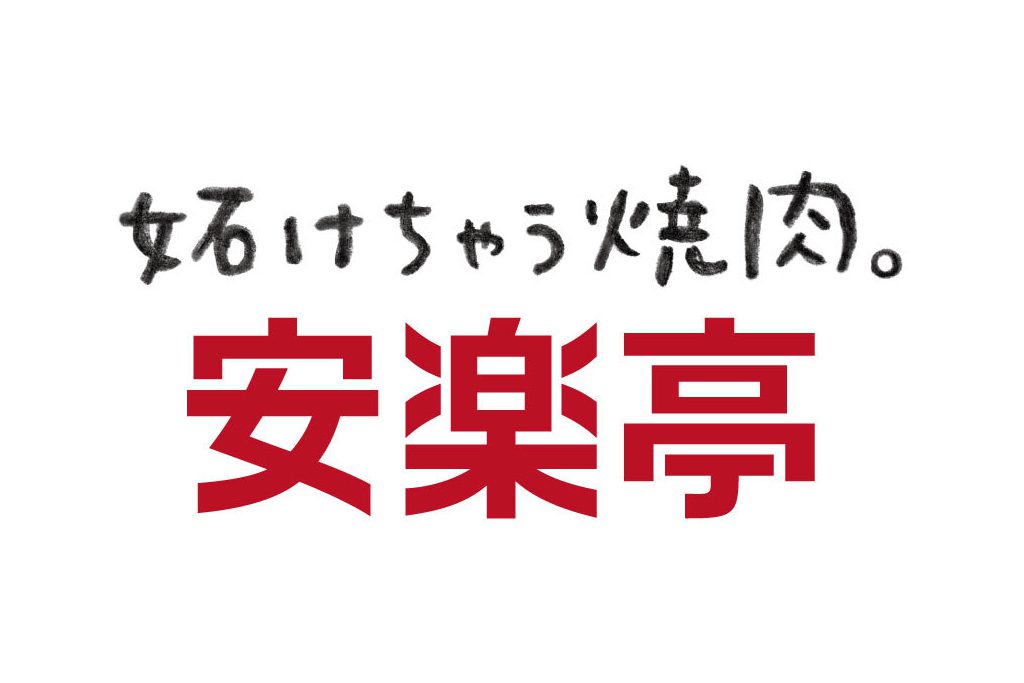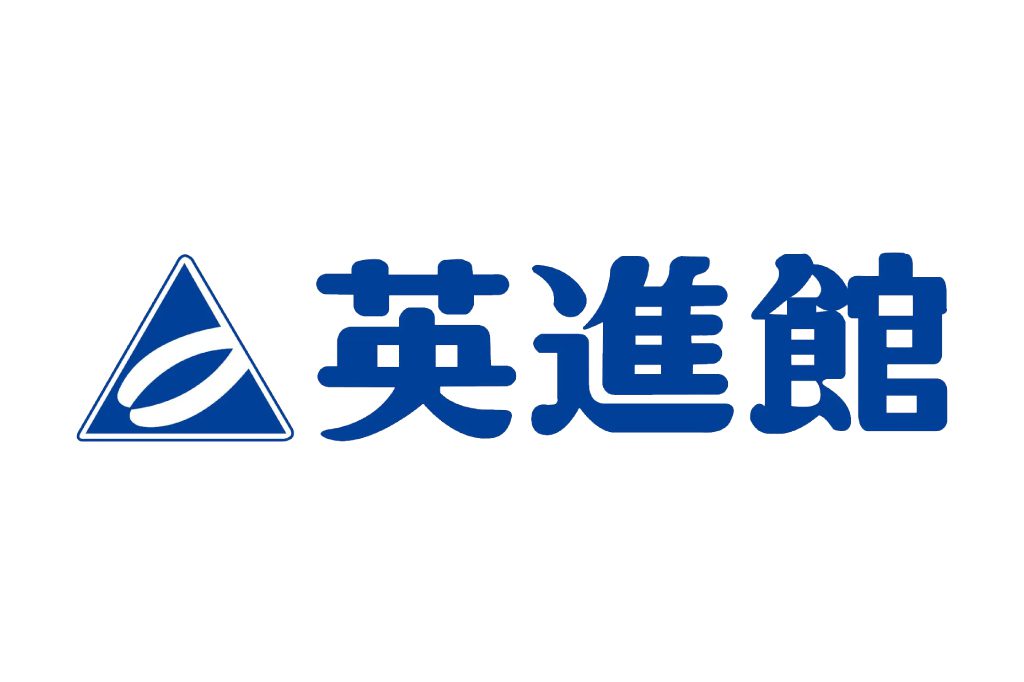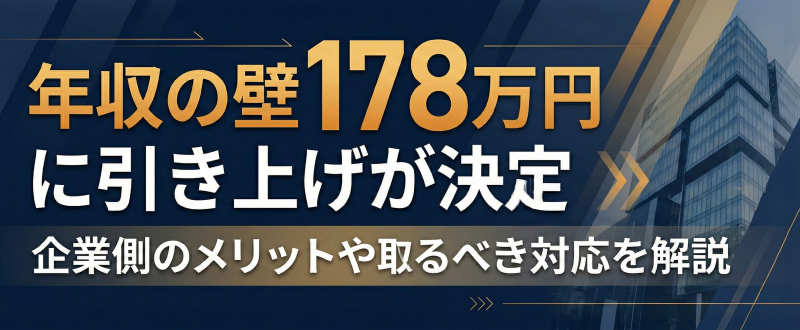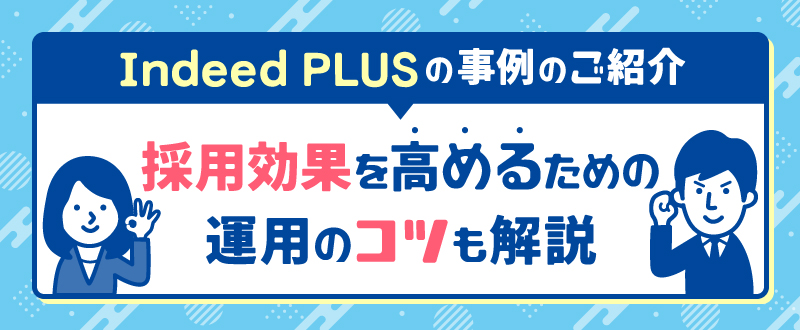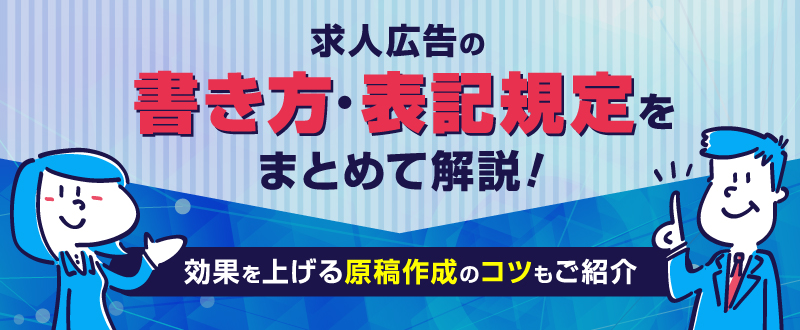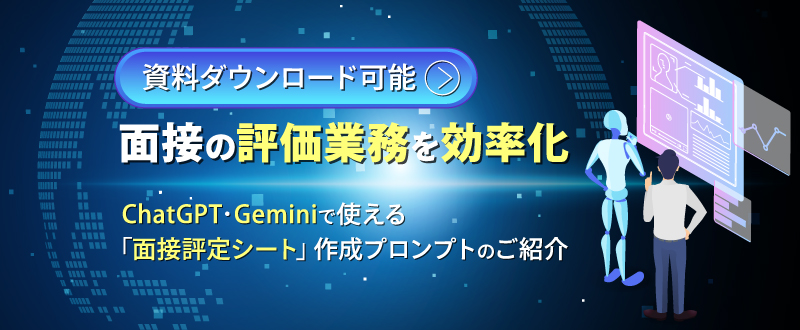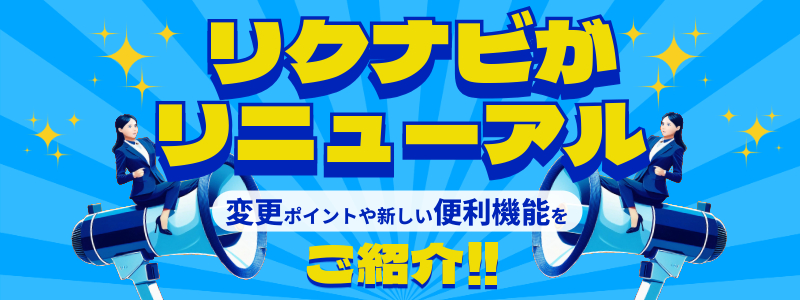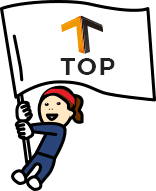トラコム社員がお届け!
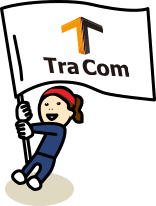
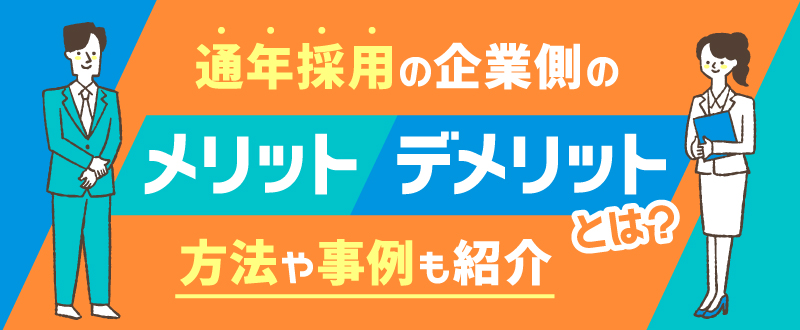
会社にマッチする人材を採用することは、企業の将来を左右する重要事項です。採用活動のなかでも大きなウエイトを占めるのが、3月に学校を卒業する学生を対象とした「一括採用」でしょう。しかし昨今では、新しい採用方法として「通年採用」が注目を集めています。
この記事では、通年採用とはどういったものかをお伝えしつつ、通年採用を実施するメリットやデメリット、具体的な導入事例などについて解説します。
通年採用とは
「通年採用」とは、採用スケジュールを限定せず、年間を通じて人材募集することです。
通年採用は「新卒一括採用」と対比して語られることがよくあります。日本では従来から、3月に卒業を迎える学生のサイクルに沿って採用活動を行う「新卒一括採用」が広く行われてきました。多くの企業では4月の新入社員の入社に合わせて、ある程度決まったスケジュールのなかで採用活動に取り組むのが一般的でした。
一方、選考や入社の時期を限定しない通年採用は、「スケジュールの制約がない採用方法」です。通年採用と一括採用では、スケジュール以外にも対象となる人材や目的などが異なるため、実際に導入するには新たな仕組みづくりが必要になってきます。
通年採用を導入している企業の動向
リクルートワークス研究所が2022年に実施した調査によると、2023年卒において「通年採用を実施または検討中」と回答した企業の割合は38.1%です。企業の規模別にみていくと、従業員300人未満の中小企業では46.8%と、特に割合が高くなっています。
企業が通年採用を実施する理由として最も多いのは、「必要な人員数を確保するため」で、87.2%でした。続いて「優秀な人材を確保するため」が61.1%、「多様な人材を確保するため」が50.3%となっています。この結果からは、従来の新卒一括採用だけでは企業側が求める人員の確保が人数・質ともに難しくなっていることがうかがえます。
通年採用が注目される背景
通年採用の注目度が高まっている背景には、2021年卒以降の採用選考について、経団連の定める「採用選考に関する指針」が廃止されたことがあります。
「採用選考に関する指針」とは、採用活動の解禁日など新卒一括採用スケジュールの指針を定めるものです。就職活動が学業の妨げにならないことを目的とするものでしたが、採用活動の早期化が進んだことなどから、廃止される流れになりました。
指針が廃止されたことで、企業は解禁日と関係なく新卒生の募集・選考をしやすくなり、通年採用を導入しやすくなりました。その結果、多くの企業が通年採用に注目し、導入が進んでいるのです。
通年採用の企業側のメリット
通年採用が注目されているといっても、「自社が導入してプラスになるのだろうか」と疑問に感じている採用担当者様も多いのではないでしょうか。通年採用には次のようなメリットがあります。
- 新卒一括採用では出会えない人材にリーチできる
- じっくり選考できる
- 人員確保がしやすくなる
以下、順番に解説します。
新卒一括採用では出会えない人材にリーチできる
通年採用では、新卒一括採用では出会えないような人材を採用できることがあります。
新卒一括採用は、あくまでも「3月に学校を卒業する学生」を対象にした採用方法です。毎年同じ時期に一定数の人材を確保できる効率的なやり方といえますが、学生の事情も個々に違ってきている昨今では、タイミングが合わないケースもあります。
例えば海外の大学の学生は、そもそも卒業時期が異なり、新卒一括採用のタイミングとマッチしません。日本の学生でも、秋に卒業するケースがあり、卒業から新卒一括採用の時期までにブランクが発生することがあります。
通年採用を導入することで、こういった新卒一括採用でタイミングが合わずにリーチしづらい人材を採用しやすくなります。
じっくり選考できる
通年採用では選考に時間をかけることができ、自社にマッチする人材をじっくり選べます。
新卒一括採用の場合、一度に多人数の学生を対象に採用活動をしなくてはならないため、学生1人に割けるリソースがどうしても限られてしまいます。「4月に入社」というゴールが決まっている以上、時間的な余裕もなくなりがちです。
一方で一人ひとりスケジュールが異なる通年採用であれば、採用時期にも制約がなく、じっくりと時間をかけて選考できます。その結果として質の高い選考がしやすくなり、自社とのマッチング度を高められるのがメリットです。
人員確保がしやすくなる
通年採用を導入することで、新卒一括採用だけに頼る場合よりも必要な人員数を確保しやすくなります。
必要な人員を確保できなくなる要因として代表的なのは、学生の「内定辞退」でしょう。新卒一括採用の場合、すでに大半の学生が就職活動を終えている時期に入ってしまうと、欠員を埋めることが難しくなってしまいます。その点、通年採用であれば常に採用の窓口を開けておけるため、内定辞退が発生した場合も新しい人材を確保しやすくなります。
通年採用は難しい?企業側のデメリット・注意点
通年採用は企業の人材採用に新たな可能性をもたらすものですが、以下のようなデメリットや注意点もあります。
- 採用担当者の負担が増える
- 研修・新人教育の手間が増える
順番に見ていきましょう。
採用担当者の負担が増える
通年採用で効率的に人材を確保するには、さまざまな採用方法を駆使する必要があります。その分、媒体選びや求人広告制作の手間が増えるのはもちろんのこと、適切に運用して成果を出すためのノウハウも求められます。
さらに常に窓口を開けておく以上、応募者との連絡や選考にも常に対応しなくてはなりません。結果的に、採用担当者の負担が増えてしまうことは避けられないでしょう。採用活動のリソースが足りなくなれば、新たに人員を配置したり外注したりしなくてはならず、コストもかかります。
研修・新人教育の手間が増える
入社時期が限定されない通年採用を取り入れると、新しい人材を雇用するたびに研修の手間とコストが発生します。入社時期が一定の新卒一括採用であれば、新入社員全員を対象にまとめて研修を行えますが、通年採用では個別に研修をする必要があります。
時期を問わず新人教育を行える体制を整えるために、社内の仕組みから変えなければならないこともあるでしょう。通年採用を導入すると、さまざまな面でより多くのリソースが必要になります。
通年採用の方法
通年採用では、新卒一括採用とは異なる方法を導入する必要があります。例えば、料金などの面で「長期的に使いやすい求人媒体」を選ぶなどの工夫が必要です。
通年採用に向いている採用方法の一例は以下の通りです。
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- 求人検索エンジン・求人サイトの利用
各方法について解説します。
ダイレクトリクルーティング
「ダイレクトリクルーティング」とは、企業側から求職者へ向けてアプローチする採用方法のことです。求人広告を出して応募を待つ採用方法が「守り」の採用だとすれば、ダイレクトリクルーティングは「攻め」の採用だといえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングにはさまざまなやり方がありますが、広く使われているのが「ダイレクトリクルーティングサイト」と呼ばれる人材データベースを活用する方法です。
ダイレクトリクルーティングサイトには、料金体系に「成功報酬制」や「月額制」を採用しているサービスが多く、長期的な利用に向いています。期間を限定しない通年採用にも適している方法だといえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ダイレクトリクルーティングとは?手法の種類と導入をおすすめするケースを解説
リファラル採用
リファラル採用とは、自社で働くスタッフに人材を紹介してもらう採用方法のことです。
「社風や仕事内容に合いそうな人がいればいつでも採用したい」と考える企業は多いものの、条件に当てはまる人材を見つけるのは簡単ではありません。その点リファラル採用では、企業の内部をよく知っているスタッフを介することで、マッチング度の高い人材にアプローチしやすいことが特徴です。
リファラル採用は導入にあたって外部の採用媒体やサービスを利用する必要がなく、長期的な運用に適しています。ただし成功させるためには、紹介の仕組みづくりと周知が必要です。
リファラル採用について詳しくは、こちらの記事で解説しています。
リファラル採用とは?メリット・デメリットや導入事例、成功のコツを紹介
求人検索エンジン・求人サイトの利用
「求人検索エンジン」とは、Web上に存在する求人情報を収集して掲載しているWebサイトのことです。代表的なサービスに「求人ボックス」や「スタンバイ」があります。
また、求人サイトとしては、代表的なサービスに「Indeed」があります。
無料で求人を掲載できる求人検索エンジンは長期的に利用しやすく、通年採用に向いているといえるでしょう。さらに訪問者数が多くユーザー層も幅広いため、新卒一括採用では出会えない人材と巡り会える可能性もあります。採用活動を活性化させるための有料プランもありますが、クリック課金制で余計なコストが発生しにくいのもメリットです。
たとえば、Indeedにはアルバイト・パートや中途採用向けのイメージがあるかもしれませんが、新卒採用にも活用できます。Indeedを使った新卒採用の方法は、以下の記事にてご紹介しております。あわせてご覧ください。
Indeedを使った新卒採用は効果的?メリット・デメリット、効果的な掲載方法をご紹介
通年採用を導入している企業の事例
通年採用は、すでにさまざまな業種の企業で導入され始めています。ここでは実際に通年採用を導入している3つの企業をご紹介します。
株式会社リクルート
株式会社リクルートの2024年卒の新卒採用では、「ビジネスグロース」や「プロダクトグロース」といった6つの募集コースがあり、全てのコースで通年でのエントリーを受け付けています。
応募者は選考の際に入社時期を相談することも可能で、個々の事情に対応する柔軟な採用活動を行っています。さらに30歳以下であれば、既卒者・就業経験者も応募できる点も見逃せません。
楽天グループ株式会社
楽天グループ株式会社では、エンジニア職の採用で随時入社可能な通年採用を実施しています。
対象となる職種は、エンジニアのほかプロダクトマネージャーやデータサイエンティストなど。入社時期を留学など個々の事情に合わせて決定するだけでなく、給与も能力・経験によって決まる仕組みで、楽天の巨大ビジネスを支えるシステムやサービスの開発・運用のために優秀な人材を求めていることがうかがえます。
ファーストリテイリンググループ
「ユニクロ」や「GU」で知られるファーストリテイリンググループでは、大学1年生や2年生も対象の通年採用を実施しています。不採用になった場合も年度をまたげば再度応募が可能で、チャンスが複数回あるのが特徴だといえるでしょう。
さらに人事面接を通過した応募者には「FRパスポート」を発行し、発行から3年以内であればいつでも最終面接を受けられる仕組みです。
参照:通年採用・FRパスポート | ファーストリテイリング 新卒採用
まとめ
年間を通して応募を受け付け、選考や入社の時期も問わない通年採用は、企業側にも学生側にも多くのメリットがあります。新卒一括採用と比較すると手間やコストがかかるものの、少子高齢化が叫ばれるなかでコンスタントに優秀な人材を確保していくには、企業側にも従来の方法にとらわれない柔軟な姿勢が求められるでしょう。
実際の採用市場に目を向けると、リクルートや楽天といった業界を牽引する企業はすでに通年採用を実施しています。大企業の事例ばかりを挙げましたが、ご紹介した調査結果によれば、むしろ中小企業の方が多く導入している傾向です。
通年採用を導入する際は、採用ターゲットや目的を明らかにしつつ、自社に合う採用方法を検討していきましょう。
通年採用をご検討の際はトラコムへご相談ください
通年採用を実施し、実際に人材を採用するには、従来の一括採用とは異なるアプローチが必要です。「通年採用を導入したいものの、何から取り組めばいいか分からない」「自社で取り組んでみたものの、うまくいかない」といったお悩みは、弊社トラコムにご相談ください。採用にまつわる全般的なコンサルティングを提供している弊社では、課題やご要望をお聞きしたうえで、あらゆる方向から採用活動をサポートいたします。まずは無料相談からご利用ください。
関連する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る