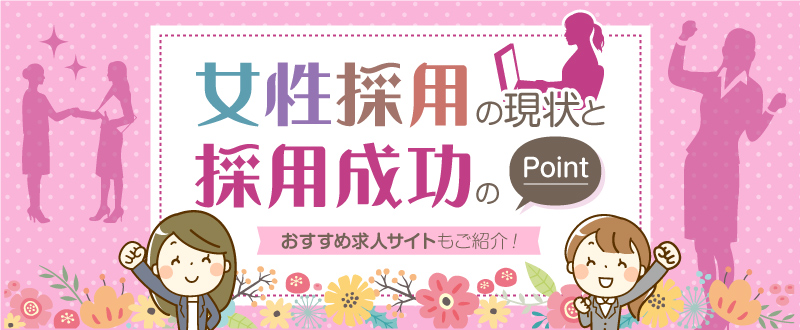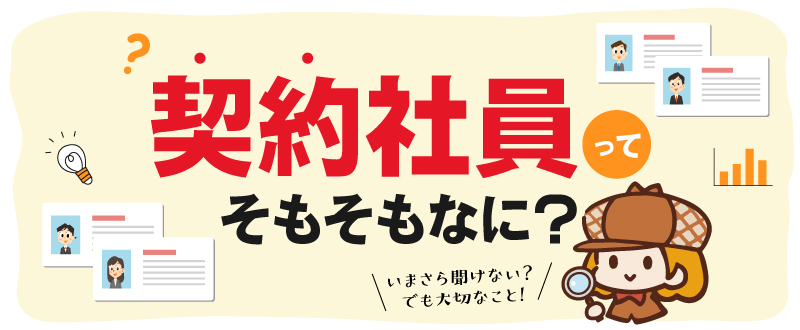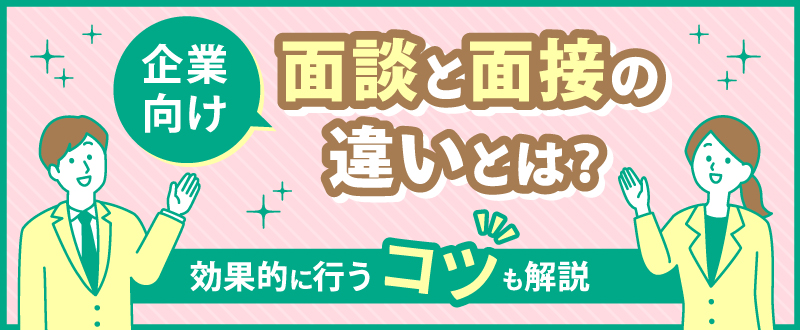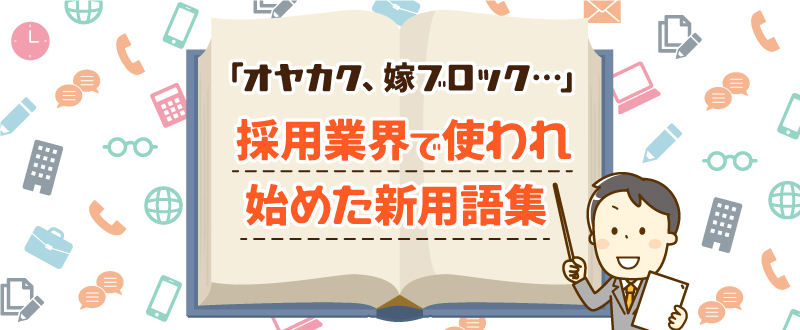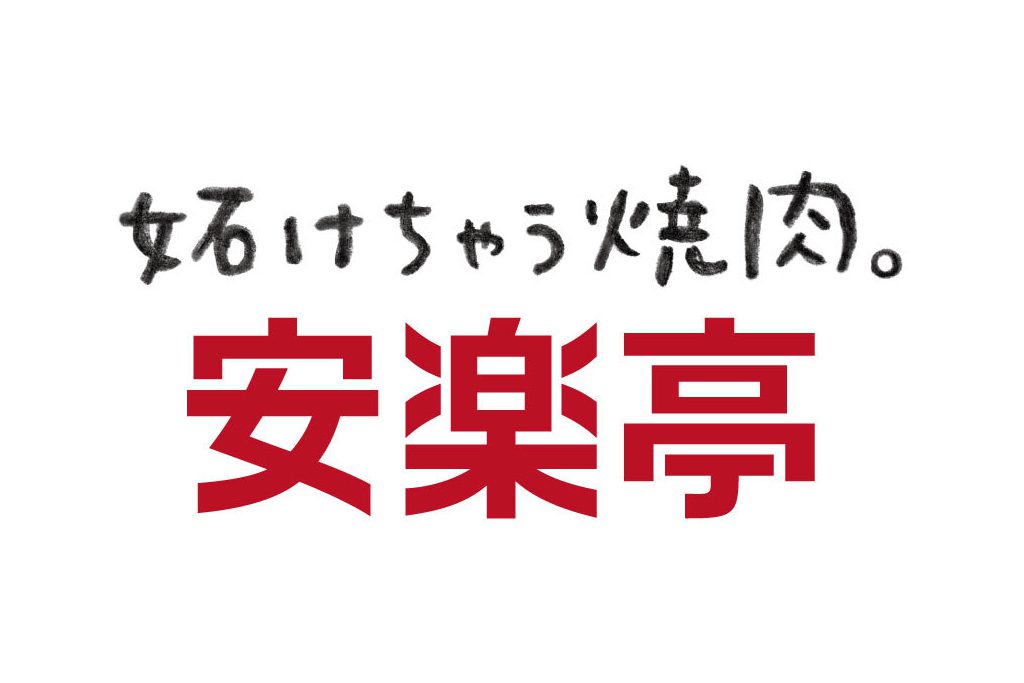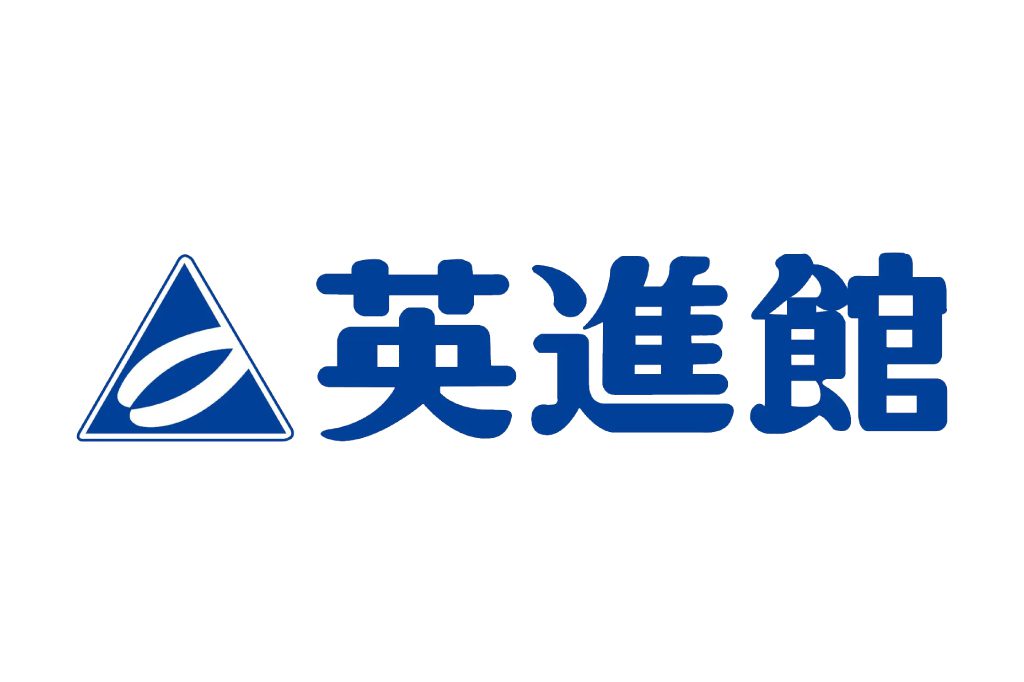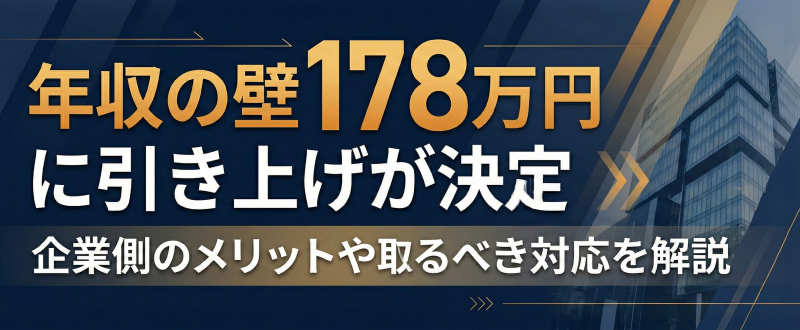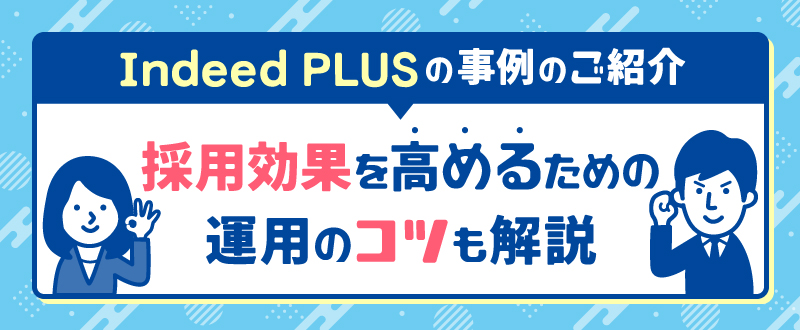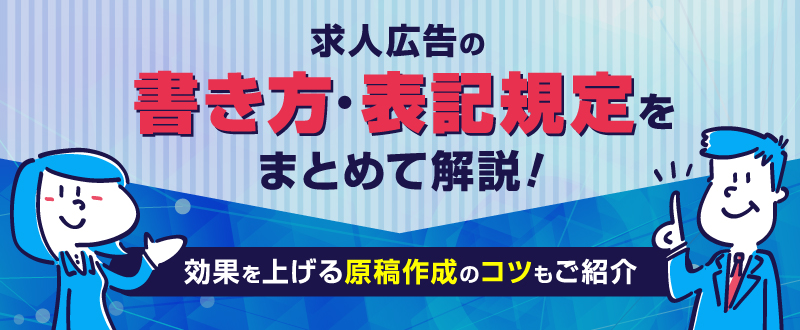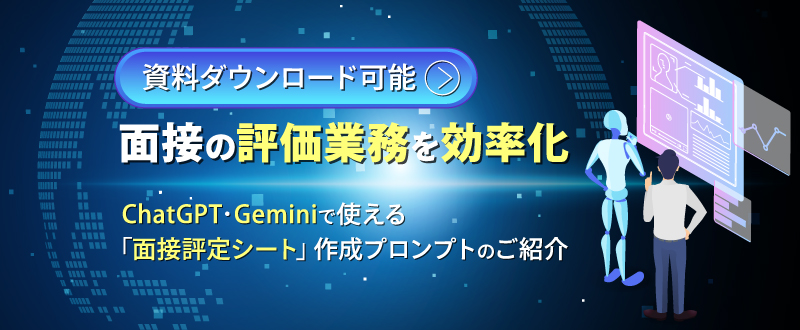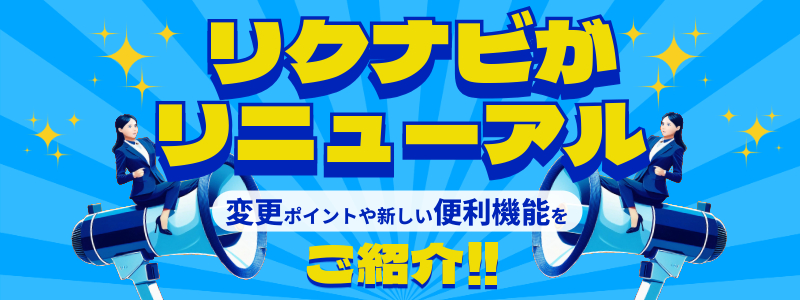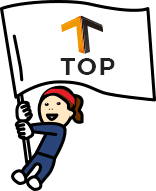トラコム社員がお届け!
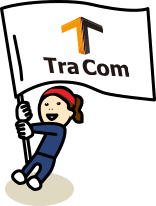
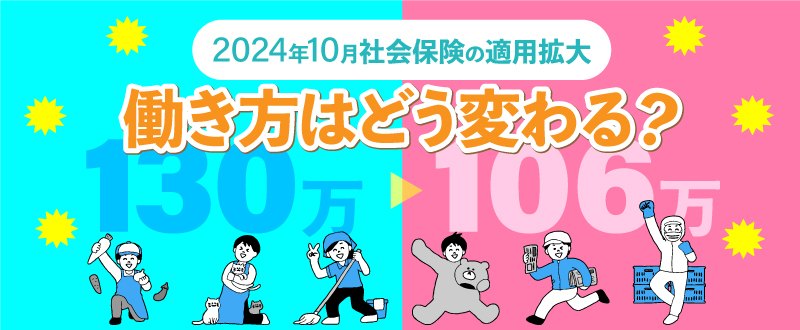
2022年10月~年金制度改正法により、中小企業に所属し働く、短時間パート労働者は社会保険加入が義務化されました。中小企業で働く短時間のパート労働者は、これまで社会保険の適用外でした。しかし、以降は適用の対象となる従業員が増加することが予想されています。「アルバイトやパートスタッフの働く時間を短縮する?もしくは延長させる?」「今後の契約・採用の方針は?」など、早めの準備をしておく必要があります。
本記事は、アルバイト・パートスタッフの労務環境を検討する人事担当者様向けに作成した内容です。今後の検討材料の1つになれば幸いです。
【お役立ち情報】アルバイト・パート採用の方法とは?
新たにアルバイト・パートスタッフを採用するためのポイントや、アルバイト・パートで働きたい人材がどのようなことを考えているのかをまとめています。無料で資料のダウンロードも可能です。あわせてご覧くださいませ。
2022年10月からの社会保険制度改正のポイント
2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大となりました。実は過去にも大手企業を対象に、短時間労働者に対する社会保険加入が義務化されました。(2016年実施/従業員人数501人以上の企業を対象に実施)当時もこれにより多くの短時間労働者の働き方が変わりました。
ここでは、2022年10月より適用が拡大する対象企業の範囲や、一連の社会保険制度の改正のポイントをまとめています。
社会保険加入の適用事業所が拡大される
2016年10月より、従業員500人以上の企業は、一定の要件を満たすアルバイト・パートなど短時間労働者を社会保険に加入させることが必要となりました。
それが2022年10月より、「従業員100人以上」の企業も同様の扱いとなり、2024年10月より「従業員51人以上」の企業も適用されます。より広範な企業において、アルバイト・パートなどの短時間労働者に対する社会保険加入手続きが必要となります。
「自社は該当するのか」「必要な手続きは何か」など、経営者、管理職、人事総務担当者様は準備が必要です。
企業規模・従業員数の計算方法
2022年10月より実施された社会保険の適用範囲拡大。これは、従業員の人数により社会保険の適用となる事業所かどうかが異なってきます。
そこで重要なのが従業員数の数え方です。ここでいう従業員数は社会保険の被保険者(加入可能性がある人)の数でカウントします。社会保険適用の対象にならないような短時間のアルバイト・パートなどはカウントされません。またいつのタイミングからカウントするかですが、「直近12ヶ月のうち、6か月で基準を上回ったタイミング」で、はじめて対象となります。適用対象となったあとで実際の従業員人数が対象人数を下回ったとしても、原則として引き続き適用は継続されます。
社会保険の適用拡大のスケジュール
前述した通り、以前からも短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は行われており、今回はその一環として行われるものです。
- 2016年10月から、従業員数500人超え規模(501人以上) ※既に開始
- 2022年10月から、従業員数100人超え規模(101人以上)
- 2024年10月から、従業員数 50人超え規模(51人以上)
こちらのように、対象となる事業者規模を区切りながら、社会保険の適用事業者が拡大されていくこととなります。
社会保険適用対象のパート・短時間労働者の要件
社会保険適用の対象となる方の要件は、下記の4つです。
- 1週間の所定労働時間が、20h以上~30h未満である
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 賃金の月額が8.8万円以上、年収が106万円以上である
- 学生ではない
これら全ての要件を満たした方が、短時間労働者でも社会保険の加入義務が発生します。ここからは、まず従来の要件をおさらいしたうえで、新たに社会保険適用となるのがどんな要件か、短時間労働者の4つの要件を見ていきます。
従来のパート・短時間労働者要件
まずは、今までの要件との違いを理解いただくため、改めて従来の要件をまとめてみました。
- 正規従業員/フルタイムで働く従業員であること
- 1週間の所定労働時間数と1か月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるアルバイト・パートなど
- 雇用期間が1年以上の方
こちらの要件に当てはまる方はそこまで多くなかったのではないかと思います。
新たなパート・短時間労働者の要件
そしてこちらが新たに適用となる方の要件です。2022年10月の社会保険適用範囲拡大で要件が緩和され、以下3つを満たす方が社会保険加入対象です。
- 週の労働時間が20h以上である
- 賃金が月に8.8万円(年収106万円相当)以上である
- 勤務期間の要件が「2ヶ月以上」に短縮
週の労働時間が20h以上
契約条件で決められている労働時間が20hを超える場合も、社会保険加入の対象となります。ただし、急遽発生した残業や休日出勤はこれらには含まれません。
また、ある月で20h以上働いたからすぐに社会保険に加入となるわけではありません。実労働時間が2ヶ月間連続で20hを超過し、次の月からも継続して20hを超えそうという場合には3か月目以降に社会保険に加入という形になります。
賃金が月額8.8万円・年収106万円
こちらも上記で紹介したように、契約で定められている所定の契約条件で判断され、基本給や手当などが計算の対象となります。残業代や賞与・ボーナスといった臨時の支給賃金分は含まれません。
臨時賃金の中には、残業代、賞与やボーナスに加えて、通勤手当や家族手当といった基本賃金に含まれない手当関連、結婚や出産に関わる手当などの一時的なものも該当します。
雇用期間2ヶ月以上
今までは、1年以上の雇用期間を経ていることが条件となっていました。しかし、この度の適用拡大では2ヶ月以上に変わります。雇用契約が2ヶ月以上とみなされるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 就業規則や雇用契約書などの書面で、契約更新がされるまたは更新される場合がある旨が記載されていること
- 同一事業所で、同様の雇用契約を結び雇用されている人に対し、契約更新等で1年以上の雇用実績があること
ただし、下記の場合には適用外となります。
契約期間が1年未満、かつ書類にも期間更新の旨の記載がなく、更新の前例がないケース
学生アルバイト・パートでない
最後の要件は、学生のアルバイト・パート以外であることです。休学中の方や夜間学部に通う方を除き、学生は適用対象外とされています。
社会保険の適用拡大による企業側への影響
社会保険適用が拡大となることにより、企業側にはどのような影響があり、またぞれぞれどの程度影響するのでしょうか?
シフトの調整が必要になる可能性がある
扶養内で働くことを希望し、社会保険への加入を希望しない人は、「月額8.8万円」、つまり「年収106万円」に収まるように働くこととなります。従来は「年収130万円」だったところから、働く時間を抑えることが必要となります。
短く働きたいというパートなど短時間労働者が多い場合は、その分の穴を埋めるよう、シフト調整が必要になるでしょう。
雇用計画の見直しが求められる
上記で記載した通り、短時間労働で働きたい人が続出しシフト調整する場合、既存の従業員だけでカバーしきれないようであれば、あらたな人員の補充が必要となります。
その際、単にパートなど短時間労働者を増やすというだけでなく、いっそ社会保険適用を前提とした「契約」「正社員」のようがよいのではないかと検討される方もいらっしゃるでしょう。雇用形態の見直しも必要になる可能性があります。
また、一方で、社会保険に加入しつつ、さらに手取りを増やすために労働時間を増やす労働者もいると考えられます。全体的な雇用計画を再検討する必要が出てくるでしょう。
「106万円の壁」超えで企業の社会保険料負担額が増加する
社会保険料は企業が半分を負担します。新たな社会保険加入者が増えると、それだけ企業負担も増えるといえます。
厚労省の試算によると、社会保険の適用が拡大されることによる社会保険料の企業負担は、1人あたり約24.5万円/年になるといわれています。さらに40〜65歳の人が新しく社会保険に加入すると、さらに約1.5万円増加するともいわれています。
社会保険の適用拡大による従業員側への影響
2022年10月よりスタートした社会保険適用範囲の拡大。企業側はもちろんですが従業員側にも大きな影響があったのではないでしょうか。ここからは、従業員側への影響はどのように変わったのかをまとめていきます。
パートなど短時間労働者が社会保険に加入しやすくなる
まずは、アルバイト・パートといった短時間労働者が、社会保険に加入しやすくなります。特にフリーターなどは、今まで社会保険に加入できないでいたケースも多くありました。加入希望の従業員が増える可能性があります。
扶養内「130万円の壁」が「106万円の壁」に変わる
また、2022年10月の社会保険適用範囲拡大により、扶養内の条件であった130万円が、106万円にまで引き下がりました。
すでに加入済のご家族がいるパートの方の場合、適用範囲拡大があっても扶養内で働くことを希望するパート・アルバイトさんが続出するケースが想定されます。
今まで130万円ギリギリまで働いていた方が例年と同じく130万円以内で働くと、保険料が差し引かれ働き損となってしまうこともあります。
扶養内で働くためにパート・短時間労働者が労働時間を絞る可能性がある
前述した通り、扶養内にカウントされる給与額の条件が106万円まで引き下がりました。しかし、なかには引き続き扶養内で働きたいと希望する従業員もいらっしゃいます。その場合、扶養内で働きたい方は年間の給与を106万円以内に収めるために、シフトを削る方向となります。
【2016年調査】パートの労働時間はどのように変化した?
2016年に同様の改正が行われた際には、社会保険加入を避け「働き渋り」が起こるのでは…と懸念されていました。労働時間はどのように変化したのか、独立行政法人労働政策研究調査機構による調査データがこちらです。
- 短縮派…32.7%
- 延長派…54.9%
という結果で、厚生年金の加入を選ぶ短時間労働者が増加しました。
理由として、手取りが下がることよりも将来の年金アップのメリットや、傷病手当などが受けられる健康保険の加入が魅力だったようです。
短縮派・延長派の意見は?調査結果 ※複数回答
- 短縮派「社会保険に加入しなかった理由」
- 1位…配偶者控除を受けられなくなるから 54.7%
2位…健康保険の扶養から外れるから 50.6%
3位…手取り収入が減少するから 49.4%
…7位に「会社側から言われたから 11.0%」というものもありました。
- 延長派「社会保険に加入した理由」
- 1位…もっと働いて収入を増やしたい(維持したい)から 44.9%
2位…将来の年金額を増やしたいから 44.3%
3位…会社側から言われたから 32.8%
※参考:「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」及び
「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」結果/独立行政法人労働政策研究機構:平成30年8月31日
【2023年調査】 短時間労働者の雇用状況 について
短時間労働者を雇用している企業へ、短時間労働者を雇用している理由・短時間労働者を活用するうえでの課題を調査した結果がこちらです。
- 短時間労働者を雇用している理由
- 1位…1日の忙しい時間帯に対応するため 38.3%
2位…女性や高齢者を活用するため 32.7%
3位…正社員(フルタイム)の採用、確保が困難だから 27.2%
4位…経験・知識・技能のある人を活用したいから 20.8%
5位…仕事内容が簡単だから 19.6%
- 短時間労働者を活用するうえでの課題
- 1位…労働力確保(人手不足) 39.8%
2位…最低賃金引上げへの対応 29.6%
3位…就業調整(による就労制限) 27%
4位…同一労働同一賃金ルールへの対応(賞与や諸手当の支給、定年再雇用者の待遇等) 21.3%
※参考:「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)
及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者 Web 調査)結果
社会保険の適用拡大に伴って企業側が検討しておくべき4つの対策
まずは現状の把握から始め、対象の方と話し、下記の流れで対応を行っていく必要があります。
社会保険料をシミュレーションする
まずは社会保険料がどの程度変わりそうかシミュレーションしておきましょう。既存アルバイト・パートなどの短時間労働者の人数を洗い出し、そのうち10月からどのくらいの人が社会保険の適用になるかならないを振り分けます。
短時間労働者が新しく社会保険に加入すると、1人当たり約24.5万円/年増加するといわれています。社会保険が適用になると企業が半分の負担を負うことになり、企業側のコストは増加することとなります。例えば、新たに10人が社会保険に加入すると、約245万円/年の負担がかかります。
適用対象となる労働者の意思確認を行う
対策のうち、なかでも重要なのは対象者が今後の働き方をどのように考えているのか、希望を聞くことです。今後どのように働きたいかを確認し、説明を行いましょう。
今回を機に、短時間労働者が今後どのように働くかを選択するかは、個人の事情により異なってくるでしょう。労働時間を調整するか、労働時間をそのままに社会保険の適用を受けるか。中にはこの機会に労働時間を増やし、フルタイムで働くことを希望する方もいるかもしれません。また、長く働きたいものの現在の職場ではシフトに入れないため、 ダブルワークを希望する方が出てくる可能性もあります。
ご家族がいらっしゃるスタッフの場合、家族との相談も必要となるため、すぐに答えが出るものではありません。早めの確認がおすすめです。
会社の人員・雇用計画を見直す
適用対象が精査できた後で、人員計画を見直しましょう。もし既存スタッフの多くが、「年収106万円に収まるように労働時間を調整したい」と希望した場合、その分稼働できる時間が少なくなります。
企業側は、足りないシフトを補うために新たな人材を雇用する必要があります。次に採用するスタッフはどのように働いてもらうかのシミュレーションをおこなったり、検討したりしなくてはいけません。
労働環境や雇用・労務管理体制を整理する
社会保険の適用になるように長く働きたい、扶養内で働けるように短時間で働きたいと希望は2極化する可能性があります。短時間を希望するパートや適用条件に当てはまらないよう管理しながらシフトを作っていく必要があります。現場のマメジメントを行う従業員にも共有や教育が必要です。
万が一適用対象にも関わらず未加入の従業員がいた場合、追加での支払いが必要となるなど後々の対応が求められます。一朝一夕に対策できることではないため、あらかじめ上記のような準備を進めておくことでスムーズに導入できるでしょう。
社会保険の適用拡大への対策はいつからするべき?
労働者にとっても、企業にとっても、すぐに対応を決められるものではありません。まだ先だと思わずに準備をしておくことが大切です。
過去では2022年10月から始まった社会保険の適用範囲拡大が、それぞれの短時間労働者の雇い入れや、短時間労働者の労働条件を再検討するタイミングとなったのではないでしょうか。
詳しくは厚生労働省の特設サイトでも紹介されていますので、ご確認ください。会社の社会保険労務士など、専門家にご相談いただくこともおすすめです。
また、シフトの見直しや新たな人材確保などの雇用に関しては、普段求人広告のやり取りをしている会社などにも相談することをおすすめします。
雇用計画の見直しに伴う人材募集ならトラコムにご相談ください
雇用計画の見直しに伴い、新たな人材を募集されたい場合はトラコムへご相談ください。募集したい要件に合わせたターゲット設定や、原稿コンセプト決めなどトータルでサポートいたします。
弊社がタウンワークをはじめとした求人メディアのなかから、最適なプランをご紹介いたします。
「掲載プランを相談したい」「料金が知りたい」など、気になることがございましたらお気軽にご相談くださいませ。
今回のテーマに関連したおすすめの記事

この記事を書いた人
A.KOJIMA
この人の記事一覧を見る
2005年前身の会社に新卒で入社
営業として京阪地区を担当。リーダー職を経て、2011年にステイセールス(内勤営業)に職種変更。
2度の出産・育休の後、現在京都営業所にてステイセールス(内勤営業)として社内サポートに従事。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る