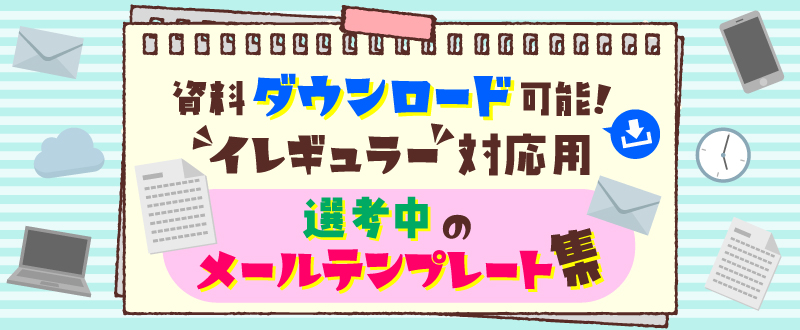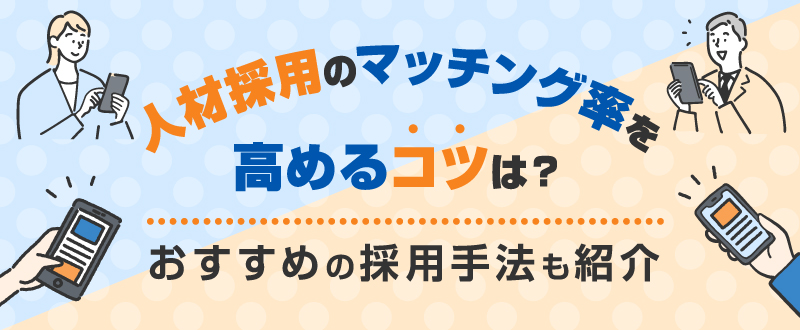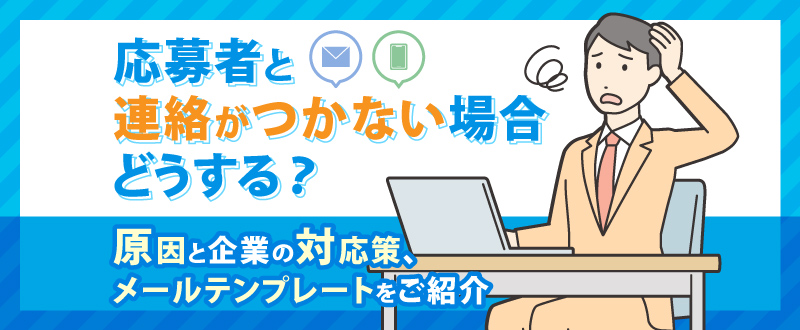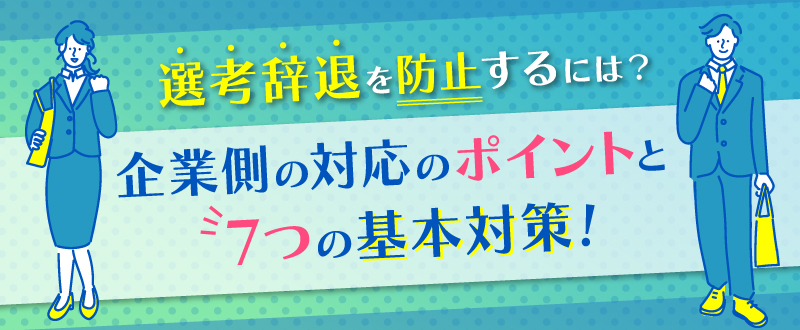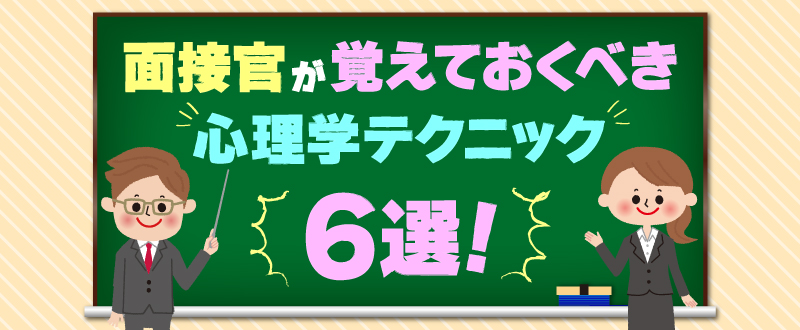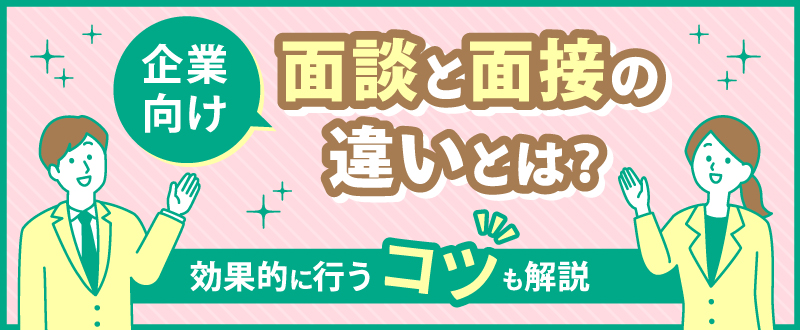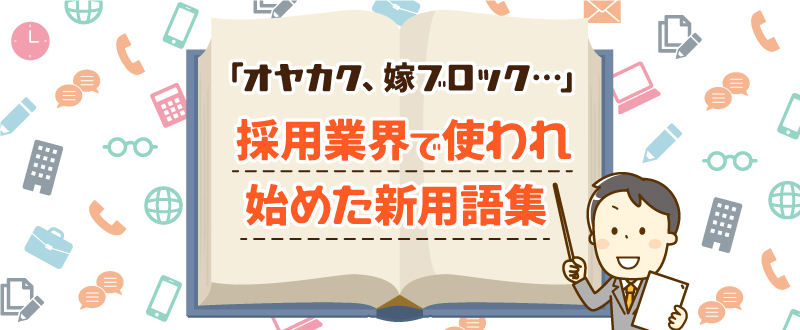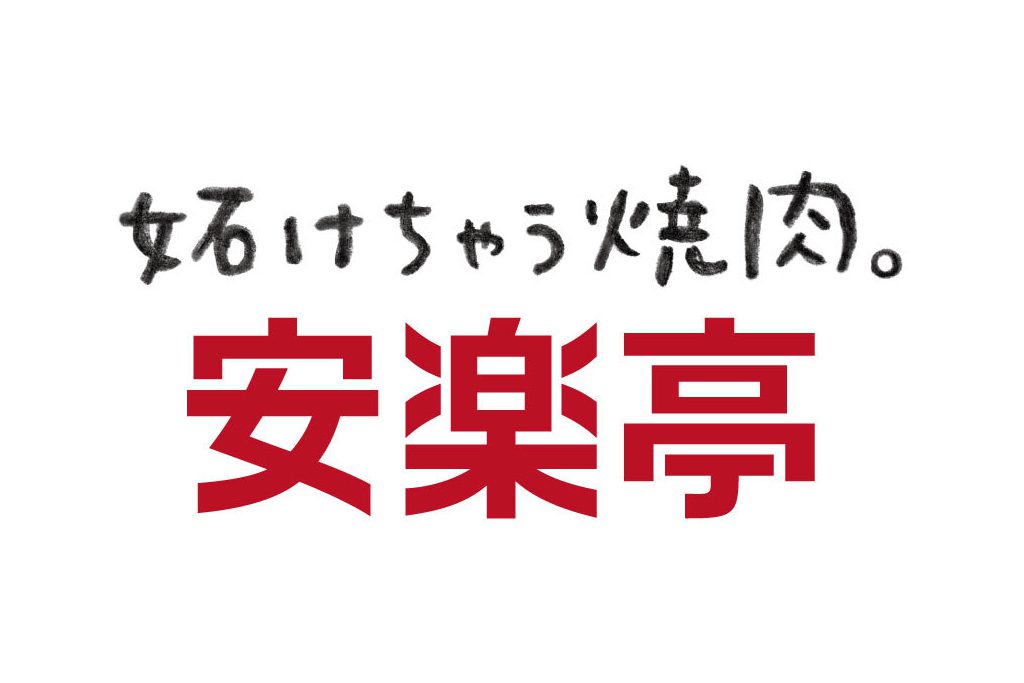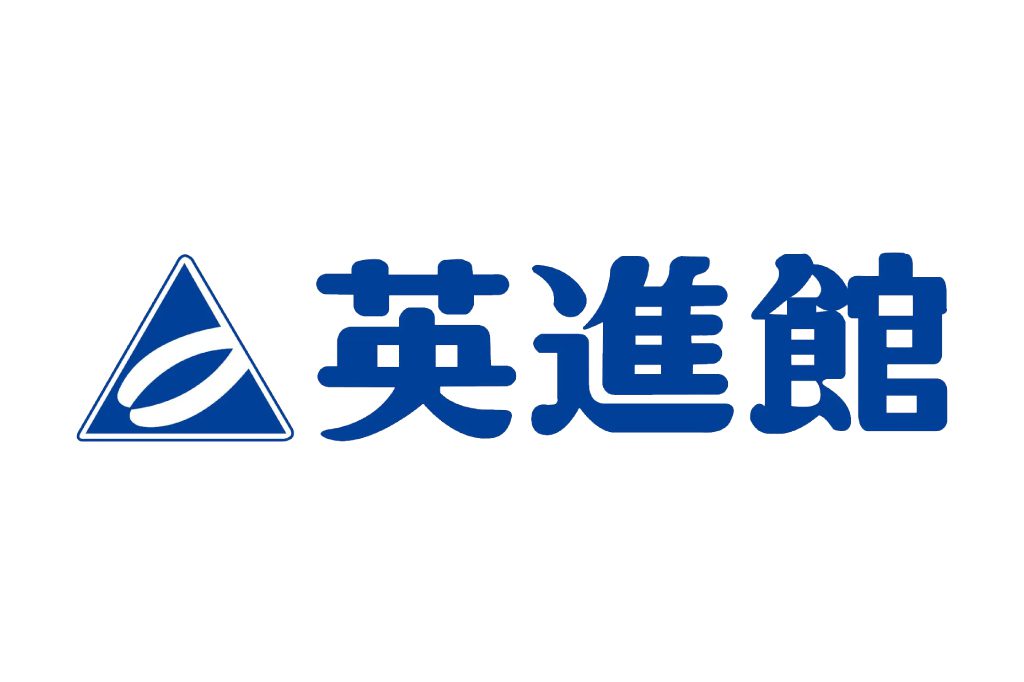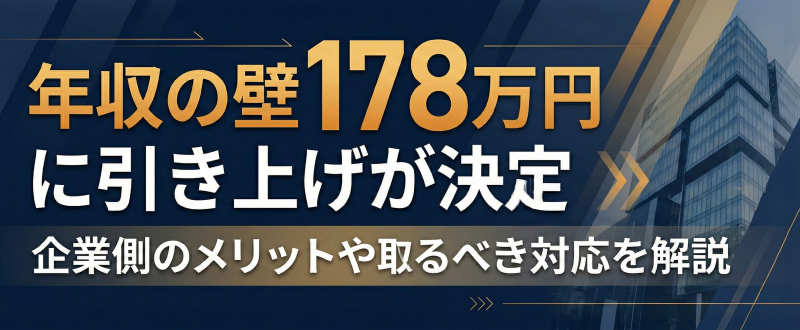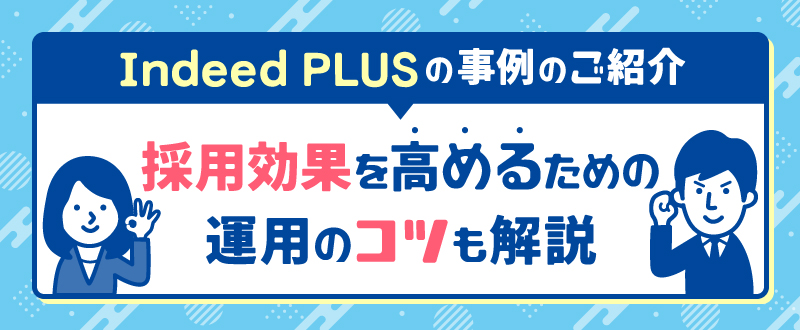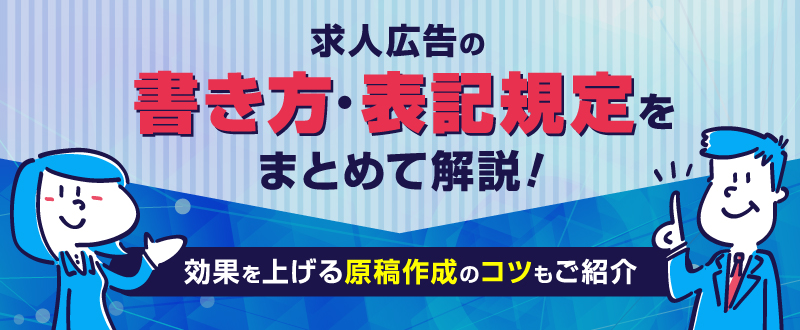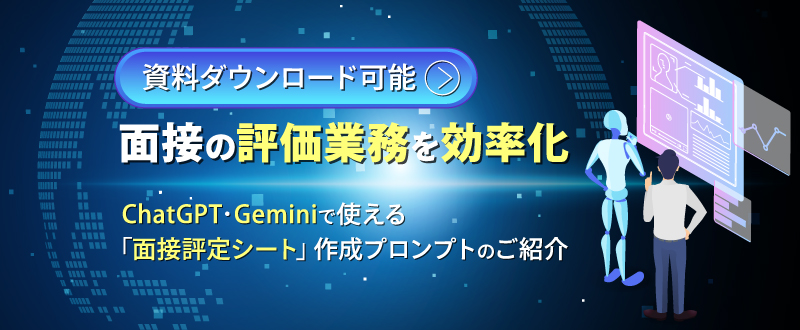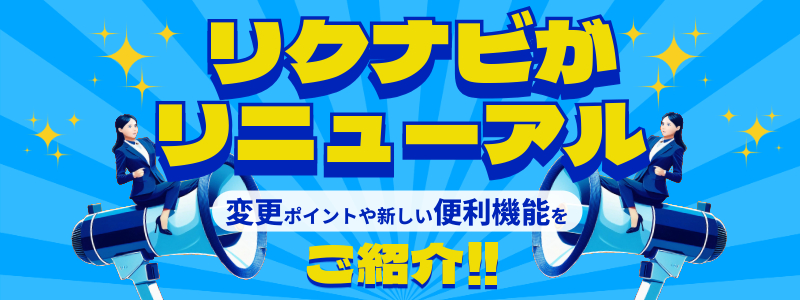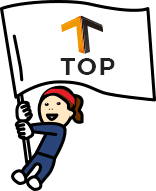メルマガ登録で最新情報をゲット!
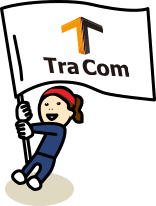
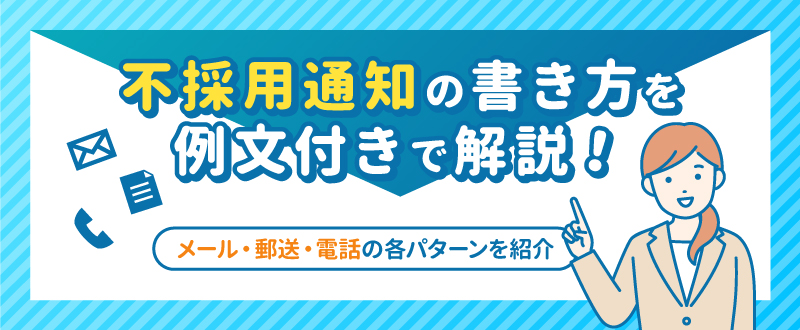
人事・採用担当者の頭を悩ます課題の一つに「不採用通知の送り方」があります。不採用通知の送り方を間違えると、企業イメージを損なう恐れもあるため、その内容や手段などを慎重に検討することが大切です。
本記事では不採用通知に書くべき内容を、「メール」「郵送」「電話」のパターン別に、例文と共に解説します。好印象を与えるコツや注意点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
不採用通知は必要?
不採用通知の送付は法的義務ではありません。とはいえ多くの企業が、書類選考、面接など各選考ステップで不採用になった候補者に対して、その旨の通知を行っています。
その理由は、不採用の応募者に対する対応が「企業イメージ」に影響するためです。不採用通知がないと、応募者から見れば「無視された」ように感じられ、それが悪評となって広がると次回以降の採用活動や企業活動そのものにも影響が出る可能性があります。
また不採用となった応募者も、自社の「顧客」になる可能性がある大切な存在です。自社の印象を損なわないよう、丁寧な対応をすることが大切です。さらに今回不採用となったとしても、別の機会に採用する可能性もあります。その道を閉ざさない配慮も必要です。
不採用通知に書くべきこと
不採用通知では、単に不採用になったことを知らせるだけでなく、応募者に感謝の気持ちを伝えたり、個人情報の取り扱いについて説明したりすることが大切です。
不採用通知に書くべきことを以下にまとめました。
応募してくれたことへの感謝
不採用通知では、自社に興味を持ってくれたことや、面接や書類選考などのプロセスに参加してくれたことに対する感謝の気持ちを添えて伝えましょう。
感謝の言葉は、不採用通知の冒頭に記載するのが一般的です。
例えば以下のような表現を冒頭に含めましょう。
- 貴重なお時間を割いて面接にお越しいただき、ありがとうございました。
- この度は弊社の求人にご応募くださり、誠にありがとうございます。
個人情報の取り扱いについての説明
応募者から提出された履歴書や職務経歴書、ポートフォリオなどの書類は、個人情報を含むものです。そのため不採用通知には、これらの書類をどのように扱うかを明記する必要があります。
郵送で同封して返送する場合は、それらの書類について「同封しておりますのでご査収頂けますと幸いです」などの記載をしましょう。
書類を破棄する場合は、「弊社にて責任を持って破棄いたします」などの記載をします。
不採用通知の3つの方法
不採用通知の主な方法として「メール・郵送・電話」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
不採用通知の方法ごとのポイントを詳しく見ていきましょう。
メールで通知する
メールでの不採用通知は、現在最も一般的な方法です。
メールでの通知のメリットは、郵送に比べて手間が少なく、すぐに届くことです。また、送信の記録も手元に残るため、管理しやすいという利点もあります。上司などにもメールが届くように設定しておけば、チェック体制ができ、送り忘れの防止もしやすくなります。
メールで不採用通知を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 件名は簡潔に分かりやすく「選考結果のご連絡+会社名」などにする
- 宛先のアドレス・宛名のミスがないよう慎重に送信する
- 応募者の今後の活躍を応援するような文面を入れる
郵送で通知する
郵送での不採用通知は、手間がかかるなどの理由から今ではあまり使われていない方法です。しかし郵送での通知には、メールにはないメリットもあります。
例えば、選考書類や作品集などを返送する場合に同封できることです。また、手書きのサインや社印などを入れることで、誠意や感謝の気持ちを伝えることができます。
郵送での不採用通知をする際には、以下の点に注意しましょう。
- 応募書類を同封し、その旨を記載する(破棄する場合はその旨を記載する)
- 「拝啓」で始めて「敬具」で締める
- 封筒に「不採用通知書在中」など結果が分かるような記載はしない
電話で通知する
電話での不採用通知は、誠意を伝えたいときやフィードバックを直接伝えたいときなどに活用できる方法です。
電話での通知のメリットは、声や口調などで感情や態度を伝えられることです。また応募者から質問や感想を聞けるなど、コミュニケーションが取りやすいという利点もあります。
ただし担当者の伝え方や相手の受け取り方次第ではトラブルにつながるリスクもあるため、電話による不採用通知は担当者と相手の信頼関係の土台がある程度できている場合に使うとよいでしょう。
また、電話による通知だけだと「証拠が残らない」というデメリットもあります。メールや郵送を併用するなどしてトラブル防止をすることも必要です。
電話での不採用通知をする際には、以下の点に注意しましょう。
- 事前に電話連絡可能な時間帯や連絡先番号を確認しておく
- できるだけ担当者が直接かける
- 応募者から質問や感想などがあれば丁寧に対応する
- メールや郵送でも不採用通知を送る場合はその旨を伝える
不採用通知の例文 無料テンプレート
不採用通知の具体的な例文を、「メール・郵送・電話」の3パターンに分けて紹介します。
メールについては「書類選考」と「面接」の両方を紹介しているので参考にしてください。
- メールによる不採用通知の例文【書類選考の場合】
- メールによる不採用通知の例文【面接の場合】
- 郵送による不採用通知の例文
- 電話による不採用通知のトーク例
また、下記ページでは選考フローにおけるイレギュラーな状況のメールテンプレートもダウンロードいただけますので、ぜひご利用ください。
【資料ダウンロード可能】イレギュラー対応用・選考中のメールテンプレート集
メールによる不採用通知の例文【書類選考の場合】
書類選考で不採用となった場合は、以下のようなメールで通知できます。
件名:【エントリー結果のご連絡】株式会社〇〇
本文:
〇〇様
この度は、株式会社〇〇の求人にエントリーいただき、ありがとうございました。
厳正なる審査の結果、誠に残念ではございますが、今回は書類選考で不採用とさせていただきました。
せっかくご応募いただいたにもかかわらず、誠に申し訳ございません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、お預かりしました応募書類につきましては、弊社にて責任を持って破棄いたします。
最後になりますが、貴重なお時間を割いてエントリーいただきましたことに改めて感謝申し上げます。今後も〇〇様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
株式会社〇〇
人事部 採用担当〇〇
メールによる不採用通知の例文【面接の場合】
面接後に不採用となった場合も、基本的な内容は書類選考の場合と同様ですが、冒頭の部分を少し調整しましょう。
冒頭では面接への参加に感謝し、面接内容に触れることで応募者への配慮を示します。例文は以下です。
件名:【選考結果のご連絡】株式会社〇〇
本文:
〇〇 様
この度は、弊社の採用面接にご応募頂きありがとうございました。
〇〇株式会社の採用担当 〇〇です。
さて、〇〇様の選考の結果についてですが、社内にて慎重に検討いたしました結果、誠に恐縮ながら今回はご希望に添いかねる結果となりました。せっかくご応募いただいたにもかかわらず、誠に申し訳ございません。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、お預かりしました応募書類につきましては、弊社にて責任を持って破棄いたします。
〇〇様の今後益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
株式会社〇〇
人事部 採用担当 〇〇
郵送による不採用通知の例文
郵送で不採用通知を送る場合は以下のような文章で通知できます。
書類選考・面接後いずれの場合も、基本的な内容は共通です。
書類を郵送せず破棄する場合は、メールの場合と同様に「弊社にて責任を持って破棄いたします」と記載します。
〇〇 〇〇様
選考結果のご連絡
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたびは弊社の採用面接にご応募いただき、ありがとうございました。
社内で慎重に選考を行った結果、誠に残念ながら貴殿の採用を見送らせていただくこととなりました。ご期待に沿えず申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
尚、ご提出いただいた応募書類一式は、同封しておりますのでご査収頂けますと幸いです。
末筆ではございますが、今後の貴殿のより一層のご活躍を心からお祈り申し上げます。
敬具
〇〇株式会社
住所~~~~~~
TEL~~~~~~
人事部
電話による不採用通知のトーク例
電話による不採用通知のトーク例は以下の通りです。
相手の受け答えに合わせて言い回しや流れを調整しつつ、完結・丁寧に伝えるようにしましょう。
〇〇様でしょうか?今、お電話よろしいでしょうか?
株式会社〇〇〇〇、人事部の〇〇でございます。
お世話になっております。
先日は弊社の面接にご参加頂き、誠にありがとうございました。
本日は選考の結果についてご連絡いたしました。
誠に残念ではございますが、今回はご希望に添いかねる結果となりました。
ご希望に添うことができず心苦しいのですが、ご理解いただければと思います。
履歴書等の選考書類はご返送いたしますので、追ってお送りさせていただきます。内容をご確認いただけますと幸いです。
今後の〇〇様のご活躍をお祈りしています。
好印象を与える不採用通知のコツ
不採用通知は、応募者にとっても企業にとってもデリケートなやりとりです。応募者に不快感を与えたり、企業のブランドイメージを損なったりしないよう、コツを押さえておく必要があります。
以下の3つのポイントを意識しましょう。
- メールの件名は具体的にする
- 簡潔な文章を意識する
- 感謝の気持ちが伝わるようにする
それぞれ以下に詳しく解説していきます。
メールの件名は具体的にする
不採用通知の件名は「具体的」にすることが重要です。
就職・転職活動をしている人には、企業や求人媒体などから多くのメールが届くことがあります。
メールの件名が抽象的だと、多くのメールに埋もれやすくなり、スパムメールと間違えられる可能性もあります。
メールの件名には、冒頭に「エントリー結果(選考結果)のご連絡」「会社名」などの記載をして、開いた方がよいメールであることが一目で分かるようにしましょう。
簡潔な文章を意識する
不採用通知のメールの本文は、簡潔にすることが望ましいです。
長い前置きや時候のあいさつなどは抜きにして、必要な情報を簡潔にまとめましょう。
文面が冗長で要点が分かりにくいと、応募者は読む気力を失ったり、誤解を招いたりする可能性があります。
不採用通知の本文では、一般的に以下の情報を簡潔にまとめるだけで十分です。
- 応募者の氏名
- 応募への感謝
- 選考結果(不採用であること)
- 選考書類の扱い
- 締めのあいさつ
- 署名(担当者名や部署名など)
ただし簡潔さを意識しつつも「冷たい印象」にならないよう注意することも大切です。
例えば「不採用といたします」ではなく「ご希望に添いかねる結果となりました」など、簡潔ながら印象の柔らかい表現を使うようにしましょう。
感謝の気持ちが伝わるようにする
不採用通知のメールでは、感謝の気持ちが伝わるような文面を心がけることも大切です。
応募者は企業に興味を持って応募してくれた人ですから、そのことへの感謝の気持ちを表現することで、応募者に敬意を示すことができます。
また感謝の言葉を添えることで、不採用通知のネガティブな印象を和らげる効果も期待できます。
例えば、以下のような文言を使って感謝の気持ちを表現できるでしょう。
- 貴重なお時間を割いてご応募いただきありがとうございました。
- ご応募いただいたことに深く感謝しております。
- 今回は残念な結果となりましたが、今後も当社へのご関心をお持ちいただければ幸いです。
不採用通知についての注意点
不採用通知で失敗しないための注意点として、以下の3つのポイントがあります。
- いつまでに連絡するかを必ず伝えておく
- エージェントには理由を伝える
- 宛先・宛名の間違いが起こらないようにする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
いつまでに連絡するかを必ず伝えておく
不採用通知を送らない場合でも、選考結果をいつまでに連絡するかは必ず伝えましょう。
上記でお伝えしたように、選考結果や不採用結果を伝えなくても法律上は問題ありません。業務負担を減らすために、通知をしないとしている企業もあるでしょう。
その場合、面接時に必ず「次の選考へ進む場合は、〇日までに連絡します」と、連絡の期限を伝えるべきです。応募者側も待つ期限が決まっていることで、他社の選考に挑めるなど動きやすくなります。
中には、面接の当日にフィードバックも含めて結果を伝えている企業もあります。特に新卒採用では、フィードバックを求める応募者が多い傾向です。
良かった点とより伸びると良い点を伝えてフォローすることで、「親身になってくれる会社だ」と好印象にもつながります。
エージェントには理由を伝える
エージェントを通した候補者の選考では、不採用になった理由をエージェントの担当者に伝えることが重要です。
不採用の理由を伝えなければ、エージェントの担当者は「なぜその人材ではダメなのか」が分からないため、次に紹介する人材を選びにくくなってしまいます。
理由を伝えることで、担当者は「どのような人材を紹介するべきか」についての新たな判断材料が得られ、次に紹介してもらう人材の精度をアップできます。
応募者には不採用の理由を伝える必要はありませんが、エージェントの担当者には必ず伝えるようにしましょう。
宛先・宛名の間違いが起こらないようにする
不採用通知は、個別に送ることが望ましいですが、一括で送る場合もあります。
その際は、宛先はもちろん「宛名」の間違いが発生しないよう注意しましょう。
宛名の間違いは相手に失礼なだけでなく、「社内のチェック体制が悪い」など自社の企業イメージの悪化や、悪い口コミにもつながりかねません。
特に間違えやすいのは「名前の漢字」です。漢字を変換する際などに間違いが発生しないよう、慎重に入力しましょう。変換ミスを避ける対策としては、名前を「手打ち」せず、応募者が送ってきた正しい表記をコピペするという方法があります。
また不採用通知を送る前に必ず「確認作業」を行うなど、基本的なことを怠らないようにしましょう。
参考記事:【例文あり】不採用通知メールの送り方や注意点を解説|ヒトクル
不採用通知と併せて考えたい「採用ミスマッチ」について
不採用通知を送る際に併せて考えたいのが、「採用ミスマッチが起きていないか」という点です。
「採用したいと思える人材に出会えず、何人もの方に不採用通知を送っている」といった場合は、以下の問題が考えられます。
- ミスマッチが起きている
- 有効応募が獲得できていない
人材採用を行う企業には、採用する人材に求めるスキルや経験、人柄などの「人材要件」があるはずです。また求職者側にも企業に求める職場環境や仕事のやりがいといったニーズがあります。その両方がマッチしているとマッチング率が高く、お互いが求める条件・ニーズにずれがある場合は「採用ミスマッチ」となります。
採用ミスマッチが多く発生すると、不採用通知を含めた応募者対応に時間を要することとなり、効率の良い採用活動からは遠ざかります。
自社にマッチする人材からの有効応募を獲得し、不採用通知にかかる工数を減らすためには、採用活動の見直しを図ることも重要です。
こちらの記事では、採用の「質」を高めるためのポイントや、マッチング率向上におすすめの採用手法をご紹介しています。
人材採用のマッチング率を高めるコツは?おすすめの採用手法も紹介
不採用通知についてよくある疑問
- 不採用の理由は書く?
- 不採用通知を送るタイミングは?
- 不採用の理由について聞かれたらどうする?
不採用の理由は書く?
不採用になった理由はあえて伝える必要はありません。
むしろ、下手に伝えてしまうことで悪い印象を与えてしまう場合があります。
よくある例が年齢制限についてです。
平成19年10月から雇用対策法により、年齢だけを理由に不採用にしてはならないと定められました。(※参照:募集・採用における年齢制限禁止について)
40代以下の方を採用できればとイメージしていたとしても、50代の方から応募があった場合に「年齢が合わないので」と断ることはできません。
トラブルになってしまう可能性もあるため、あくまでも結果のみを伝えた方がよいでしょう。
不採用通知を送るタイミングは?
選考や面接を行ってから、なるべく早めに連絡することがマナーとされています。
面接から3日程度、遅くとも1週間以内に通知を行うことが一般的です。
入社したばかりの求職者の方にお話を聞いたことがありますが、「面接後すぐに選考通過の通知をくれたことで、どんどん選考が進められてよかった」といった声も多く聞きました。
連絡が遅いと「自分は不採用になったのではないか」と不安を感じてしまいます。
またあまりに連絡が遅いと、選考通過や内定の通知を行っても 「他の候補者と迷っているのではないか」 と、ネガティブな印象を与えかねません。
良いと感じた応募者にはできるだけ早く連絡することがおすすめです。
不採用の理由について聞かれたらどうする?
メールの返信や電話などで不採用の理由について応募者から問い合わせを受けた場合、基本的には理由を伝えられないことを丁寧に伝えることが望ましいです。
前述の通り理由を伝えると、それが反論のきっかけとなり、大きなトラブルにもつながりかねません。
「大変恐縮ではございますが、不採用理由についてはお伝えができかねます」など、できるだけ悪い印象を与えないよう、口調にも注意しながら丁寧にお断りしましょう。
さまざまな人からの応募が想定される選考フローでは、他にも対応に困るようなケースがいくつか考えられます。
募集・選考フローにおけるさまざまな困りごとの対処方法について詳しくは、下記ページで解説しています。
面接ドタキャン、不採用理由の問合せ…人事の困った!を解決する方法
まとめ
不採用通知は、企業イメージを守り、自社が求める人材と出会うための重要なプロセスの一つです。
必要な情報を簡潔に伝えながらも、感謝や気遣いの伝わる文章を心がけ、応募者に対して悪い印象を与えないようにすることが大切です。
ご紹介したテンプレートを参考に、適切な文面になるよう十分に検討しておきましょう。
トラコムでは採用お役立ち情報をメールマガジンでお届けしています
弊社トラコムでは、「こういう時どう対処したら良いの?」といった人事の疑問やお悩みを解決するための情報をはじめ、今話題の採用トピックス、採用活動の進め方のポイントなど、人材ビジネス関連にかかわる皆様に役立つ情報をメールマガジンでも発信しています。
ご希望の方は、下記リンクのフォームよりお気軽にお申込みくださいませ。
採用にまつわるお悩み・ご相談はトラコムへ
トラコムでは採用全般のサポートが可能です。
「不採用通知の送り方が分からない」など採用フローについてのお悩みだけでなく、求人メディアの選び方など、人材採用にまつわるお悩み全般のご相談を受け付けています。
採用・不採用通知の「送付代行」など、採用業務の代行サービスのご依頼も可能です。
まずは無料相談からご利用ください。
応募者対応に関する記事
最新の採用事例やノウハウ、新着ブログ、セミナーなど
採用活動全般にプラスになる情報をお届けします。
ご登録いただく前にプライバシーポリシーをご一読ください
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る