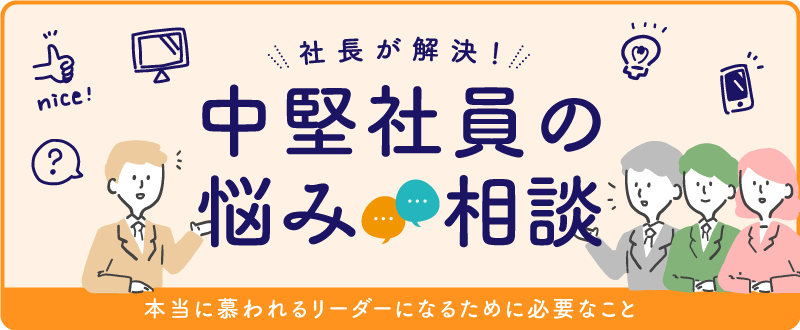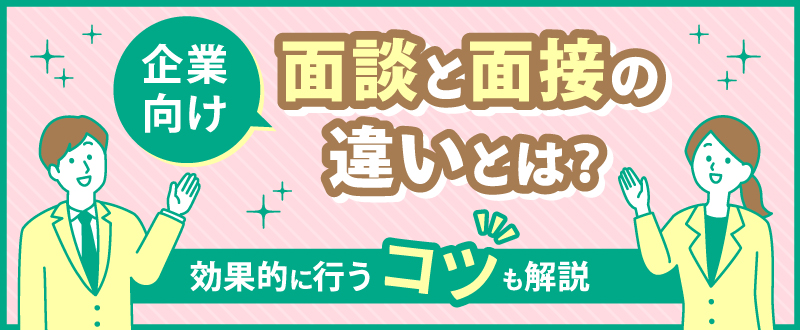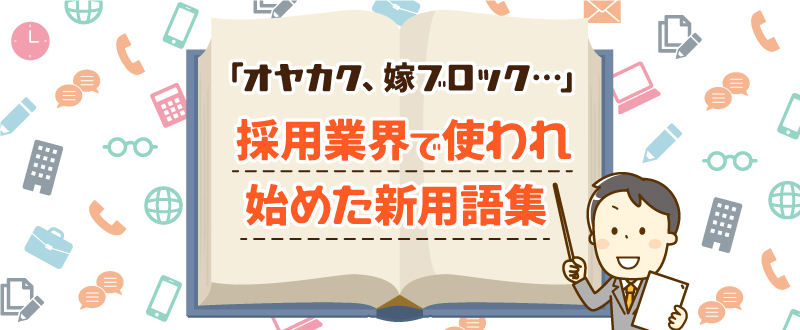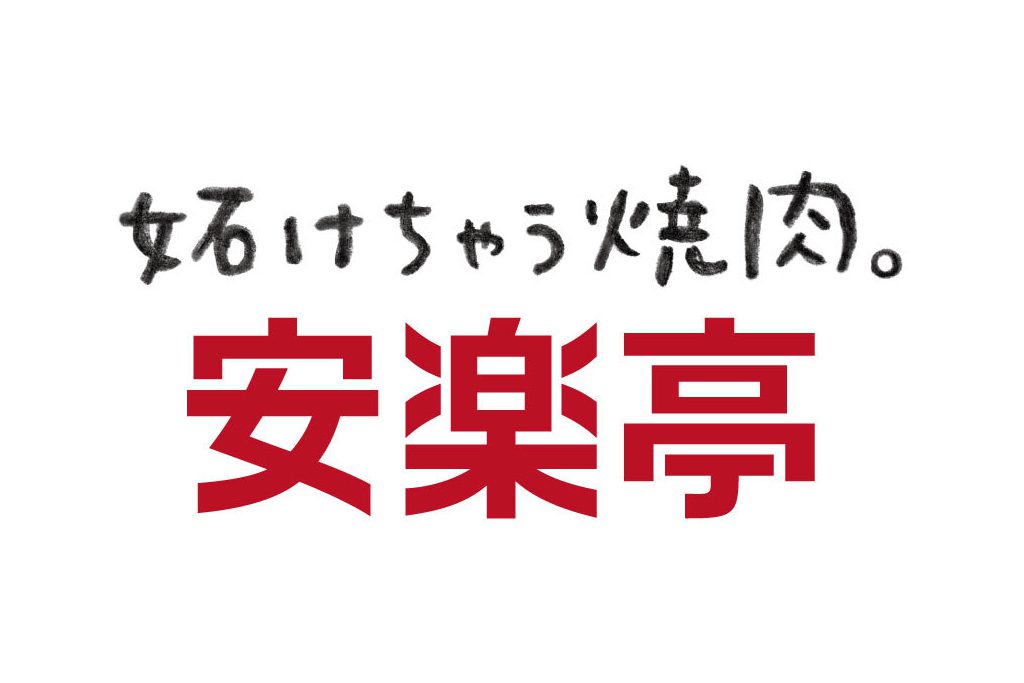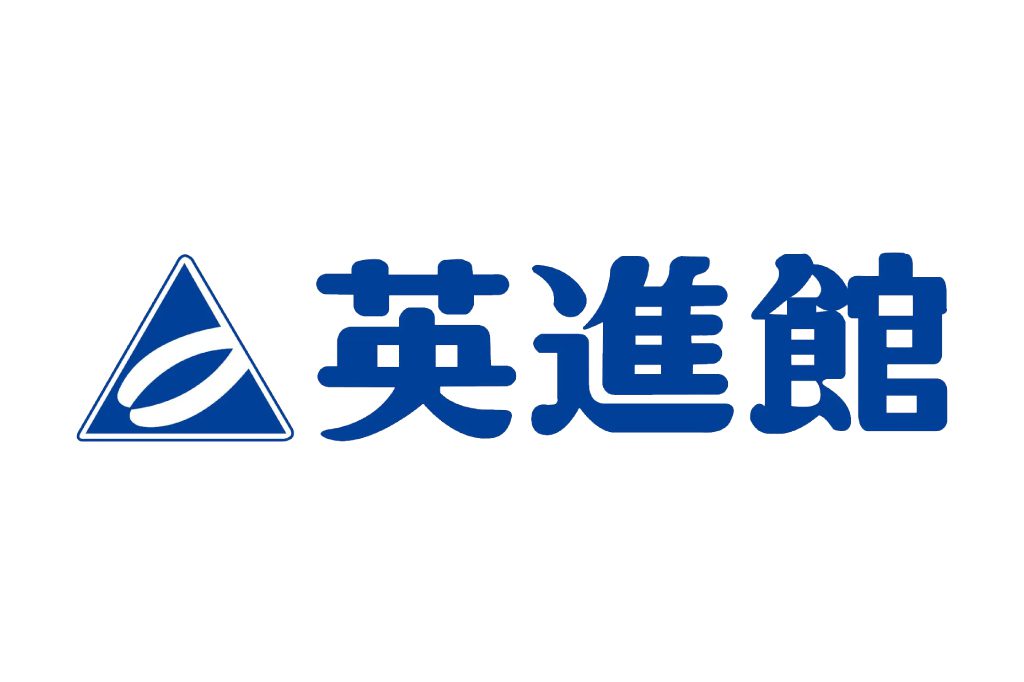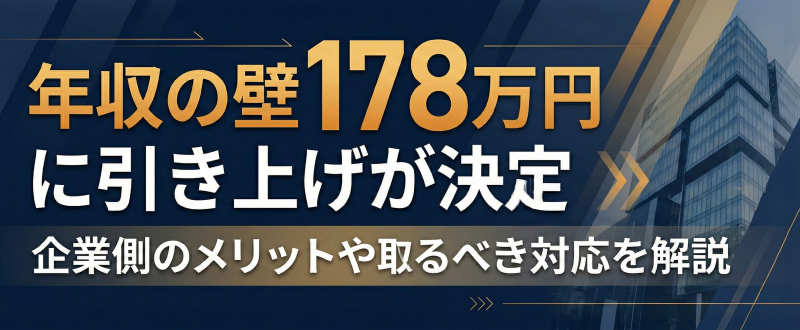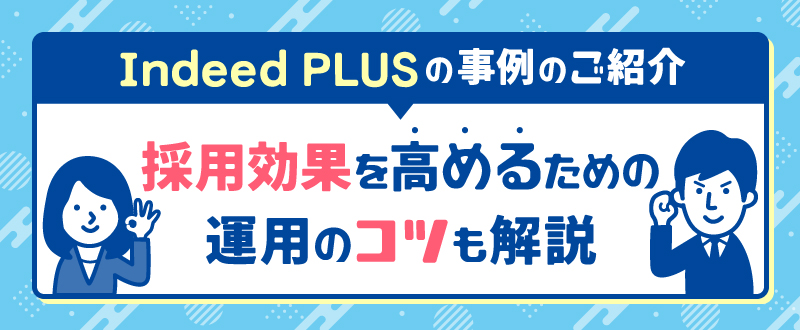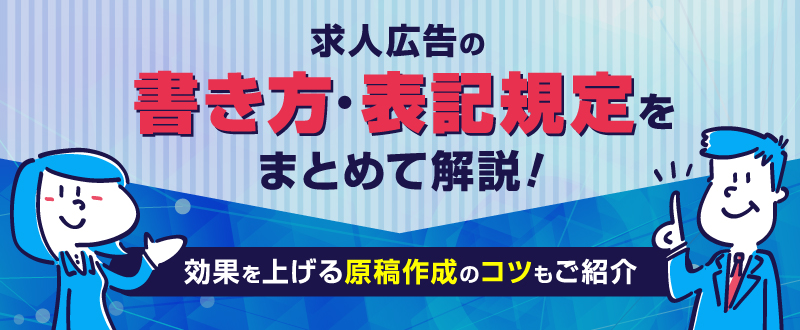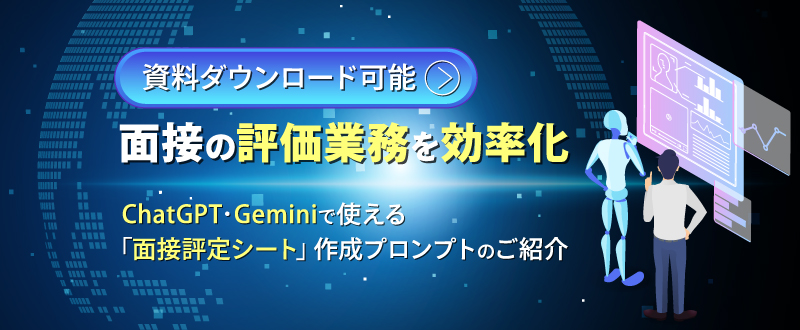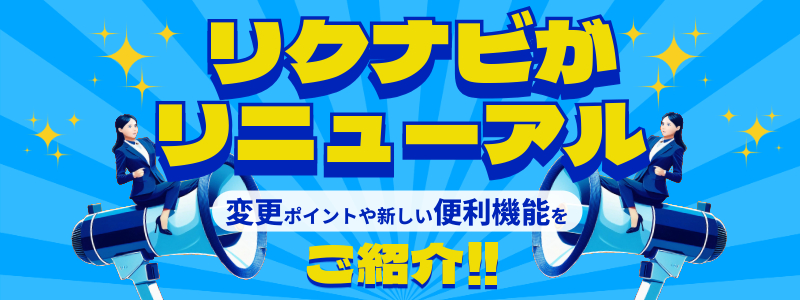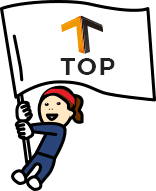トラコム社員がお届け!
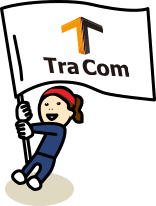

仕事の面白みを理解する前に、20代の若手が退職してしまった。ここから会社の主力として活躍してくれるはずというところで、中堅社員が退職してしまった。その結果人が育たず、組織に様々な課題がある。―人事担当者様や、経営者の方からこういったお悩みを聞く機会が多くあります。
組織成長の課題は、人の成長に大きく左右されます。言い換えれば、社員を離職させず育てることができれば、会社の成長にも良い影響を及ぼすことができるのです。弊社でも2020年4月より、新卒以上の社員向けに研修制度を導入致しました。弊社の取り組みを元に、研修制度の導入の流れやメリットをご紹介していきます。
アドバイザー:弊社中堅育成担当

- 【アドバイザー】
- トラコム株式会社
事業推進室 人事・採用・研修 シニアアカウントリーダー
笹原知明
2004年に中途入社し、千葉県内全域の中途採用領域を担当。2008年に求人全領域を担当する部門でマネージャーに就任し、関東全域のハイスペック人材の採用や新卒も扱うように。東京での部署立ち上げも経験。40歳を過ぎた頃から、自身の営業ノウハウを後輩へと伝えることに興味を持ち始める。リクルートキャリアが主催する採用ナレッジコンテストでの数度の優秀賞受賞をきっかけに、社内でもナレッジ共有を開始。それがきっかけとなり、2020年4月より中堅育成の担当に任命される。営業メンバーの相談役としても、社内で厚い信頼を獲得している。
研修の概要をご紹介!
弊社では、外部の研修会社に依頼するのではなく、弊社の求めるスキルに合わせて独自に研修コンテンツを作成し、実施しています。もともと入社1年以内の新人向けには行っていましたが、それ以上のメンバーには定期的におこなうものはありませんでした。
誰に対して行った?
業務の習熟度や求める業務に合わせて、研修内容を変えることが大切なため、年次や役職に合わせてグループ分けし研修を実施しました。弊社では、新人(入社2年目、3年目)、中堅(4年目~3名程度のメンバーを持つリーダー)、リーダー(複数名のメンバーを持つ役職者、社歴は5年目以上)に分け、研修を行っています。
何を伝えた?
それぞれの対象に合わせて、伝える内容を変えています。
新人(入社2年目、3年目)
入社2~3年目の新人には、業務の基本のやり方を教えています。1年目ではビジネスマナーやひと通りの知識を身につける研修を行っている場合が多いでしょう。しかし、実際に業務を行う中で、研修の内容を実践し、自身に合わせたやり方を確立できている人は少ない年次です。
弊社の場合は、営業スキルを教えています。営業の基本行動の中から、実際に私が試してみて良かったやり方だけを、実際に使ってみようと思えるように伝えています。たとえば、「お客様にあった提案を行うためにヒアリングが必要。なぜそれが必要なのか。」のように教えるイメージです。また、教えたことをどの程度実践できているかの共有も、研修に組み込んでいます。
中堅(4年目~3名程度のメンバーを持つリーダー) 、リーダー(複数名のメンバーを持つ役職者、社歴は5年目以上)
中堅やリーダー層の社員になると、基本の業務は一人で回せるようになっている年次です。この層へは基本の業務というより、メンバーを率いることを見越してよりハイレベルな仕事をするためのスタンス面を教えています。
ただ、年次や経験に合わせて理解できるレベルも変わってくるので、基本のテーマは同様に、伝える内容の深さを変えるようにしています。具体的には、「メンバーとの振り返りミーティングの仕方」「決めたことをやり切らせるにはどのように導いたらよいか」などをテーマにしています。
所要時間と頻度は?
1回のコンテンツは2h程度。各回にテーマを設けて、複数回の研修を1タームとしています。1タームの研修が終了した後に、求めるスキルが一定のレベルで身についている状態になるよう仕立てています。
組織の成長・離職率を下げることに研修が有効な理由
社員自身の成長の機会が増える
弊社が研修を導入したことで、組織の成長・定着率アップにも良い影響が出ていると思っています。
1点目として、社員自身の成長機会が増えます。現場に出て通常の業務を進めていると、目の前の業務をこなすことで精一杯になり、どうしても新しいことをインプットするのは後回しになってしまってしまいがちです。特に入社3年目~5年目くらいの中堅社員では、仕事がルーティーンワーク化していまい、より成長できる場所で働きたいと離職するケースも多いようです。
会社の用意する研修によってインプットの場が増えれば、業務にもすぐに反映でき、成長機会が増えることに繋がっていきます。
会社が求めるスキルまで社員を引き上げることができる
また、企業が人事評価する際、年次別に”この程度のレベルで、このスキルをもっていてほしい”など、社員へも求めるスキルとハードルがあるはずです。現場のマネジメントに任せているだけでは、求めるハードルにまでスキルを引き上げることは非常に難しいものです。
しかし、研修コンテンツ自体をそのレベルにあわせて作成することで、無理なくスキルを引き上げることが可能となります。
社員はキャリアの選択肢を増やすことができる
社員自身のスキルが上がり成長のスピードが上がると、社員自身もキャリアアップの選択肢を増やすことが出来ます。早い段階でマネジメントを経験したり、新しいキャリアの道を築くことができるかもしれません。
自分が求める働き方が叶えられる環境があれな、定着率の上昇にも繋がっていくのではないでしょうか。
自社で研修コンテンツを作るメリット
研修を実施する際、外部の研修を受けるのか、内製してコンテンツを作るのか、2パターンがあります。 内製した弊社の立場から、メリットとデメリットをまとめてました。
メンバーの状態を把握でき、育成がしやすく&されやすくなる
1点目は、育成がしやすくされやすくなることです。若手が退職する理由の一つに「上司と合わない」があります。これはマネジメント層と若手との間に、共通の言語がないためではないかと考えています。上司が数十年間をかけて築いてきたビジネススキルを、数年間の社会人経験しかない若手が、すべてを理解するのは難しいものです。
しかし、社内でコンテンツをつくることで、若手がどんな研修を受けどこまで理解しているのかを上司が把握することができます。実際に弊社でも、研修後にアンケートを実施。その所感を各メンバーの直属の上司へフィードバックしています。すると、その内容を踏まえて現場でも育成を行うことができます。これは、若手にとってみても、育成してもらいやすさに繋がります。
会社としての財産が増える
作成したコンテンツはすべてその会社のものになります。市況感や時代の変化に合わせて微調整は必要ですが、その後人員が増えてもそのコンテンツを使うことで研修を実施できます。同じような研修を外部に委託して導入すると、数十~数百万の予算がかかる場合があります。(受講人数にもよって予算が変わる場合が多いです)自社で作成すれば人件費以外は予算もかかりません。コスト面からもメリットが大きいです。
直属の上司とは別に相談役ができ、メンバーの拠り所が増える
相談できる人が同じチームのメンバーしかいなく、その人達との考え方が合わないことから退職につながるケースがあります。これは、横や斜めのつながりを増やすことで解消できると考えています。
弊社では研修を受けた社員を中心とした全社員に、業務や育成に関する相談を、研修担当である私になんでもしてくださいと伝えています。主に、社内の連絡ツールであるGoogle chatを使って相談をくれるメンバーが多いです。評価する立場でない相談役がいることで、自分ですべてを溜め込まずに悩みを解消しやすくなっているようです。
自社で研修コンテンツを作るデメリット
業務の経験がある人でないと講師を務められない
デメリットとしてまず挙げられるのは、社内にコンテンツを作成して講師ができる人がいるかどうかです。私は長年の営業経験により、営業の知識は持っていたこと、またマネジメントの経験もあったことから、現在講師を行えています。
教える内容に理解がないと、受講者を納得させることは難しいと思います。上手に話せるかどうかよりも、豊富な経験の方が重要だと考えます。社内で人選を行う場合は、そのような人物を選定することが良いでしょう。
スタート時の労力が大きい
研修を始める前のコンテンツづくりには、とても労力がかかります。1回分のコンテンツは、40~60スライドほどのボリューム。作成には20hくらいかかることもあります。
経験を元に、必要に応じて、さまざまな文献を読みながら内容を作っていくことが重要です。まったく0からのスタートの場合、作成の時間を鑑みながらスケジュールを立てていくことがオススメです。
研修コンテンツの作り方
メリット・デメリットについてもまとめてみましたが、弊社がしたように自社で研修コンテンツを作りたい場合、どのような流れで作成したら良いのかについてもまとめてみます。
上記でお話した仕立てだと、各回のテーマ出しが重要となります。弊社では元々育成に活用されていた、【年次別に求めるスキルを一覧化したシート】を活用しました。(何年目にどんなスキルが身についていてほしいかを、定義しているものです。)
そこから、教えるべきスキル・すでに身についているスキルを精査し、ときには複数のテーマを組み合わせながら、各回のコンテンツを作っています。
各回のテーマ決め
各テーマが決まったら、そのテーマの伝え方を考えます。いわば、研修コンテンツの構成です。私は、必要な理由→できたらどうなれるか→具体的な行動の順で伝えています。
たとえば、「メンバーの振り返りミーティングを行うことの重要性と、そのやり方」を教えるとします。まずは、どうして「振り返りを行うことが重要なのか」を伝えます。そのあとで、「振り返りが上手にできるようになったら、自分にとってどんな影響があるのか」をイメージさせます。そして最後に、「実際にどのようにやったら良いのか」を伝えていくイメージです。
この順序で伝えるかそうでないかで、腑に落ち感が全く異なります。研修後にアンケートを行い感想を聞いていますが、今のところ80回以上の研修を行い、マイナスな評価がついたのはたったの2回のみです。ほとんどの受講者が良い評価をしてくれています。
よりよい研修をするための工夫
初回は30分かけて自己紹介を実施
私は元々千葉支社で働いており、初めて顔を合わせるメンバーに教える機会も多くありました。すると、初回の研修はどうしても静かなスタートになります。講師がどんな人かわからない状態だと、受講するメンバーも前のめりに参加することは難しいです。
心理的な壁を取っ払うために、初回の研修では30分ほどかけて自己紹介をしていました。最初にこちらから自己開示を行うことで、メンバーたちも安心して参加してくれるようになっています。
1ヶ月後にフォロー研修も実施
研修がすべて終わったら、1ヶ月後にフォロー研修を組んでいます。このフォロー研修では、研修で伝えた内容をどのように活かして、どのような結果が出たのかを発表してもらう場としています。
改めて振り返りを行うことで、受講したメンバーにとっての成長の実感になることはもちろん、研修を行う私のモチベーションや成果を図ることにも繋がります。
諦めないことが重要!
中には、モチベーションが下がっており、後ろ向きな気持ちを抱えながら仕事に取り組んでいる社員に研修を行う場合があります。そんなときも、講師が諦めず前向きに、研修で伝えたいことを伝え続けることが重要です。”目の前にいる人を諦めない”ことは、講師を行う人物にとって、最も必要なスキルだと感じています。
定着率アップには研修の導入がおすすめ!
自社での研修コンテンツ作成は、初めは労力や時間がかかるものの、会社としての財産となります。採用した人がすぐに退職してしまうことは、結果的にコストや時間の大きな喪失にもなります。
定着を上げる施策にお困りの企業様は、取り組んでみてはいかがでしょうか。一度に全社員に対して行わずとも、まずは”若手だけ”など特に定着に課題のある層から導入することで改善につながるかもしれません。
トラコムに相談する
弊社では人材採用を通じて、企業の組織課題を解決するお手伝いをしています。採用や組織課題に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
関連する記事

この記事を書いた人
T.SASAHARA
この人の記事一覧を見る
もともとはSEだったが、地元千葉で働ける仕事を探していたところ、地域を元気にする求人広告の世界を知る。
2004年に中途入社し、千葉県の中途領域を担当。
2008年に求人全領域を担当する部門でマネージャーを務めた頃から関東全域のハイスペック人材の採用や新卒を扱うように。
その後は、東京での部署立ち上げなどを経験しながら、中途・新卒両方の領域の採用支援を続けてきた。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る