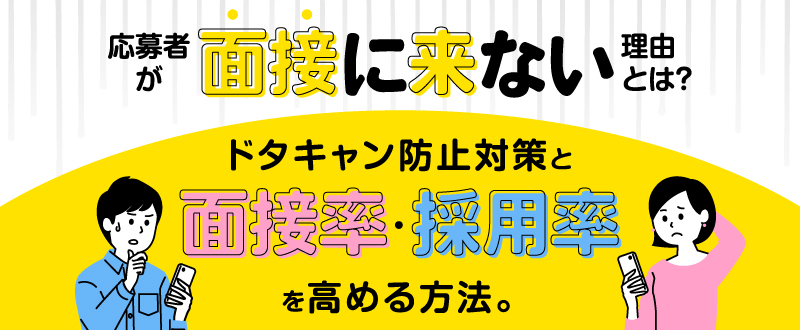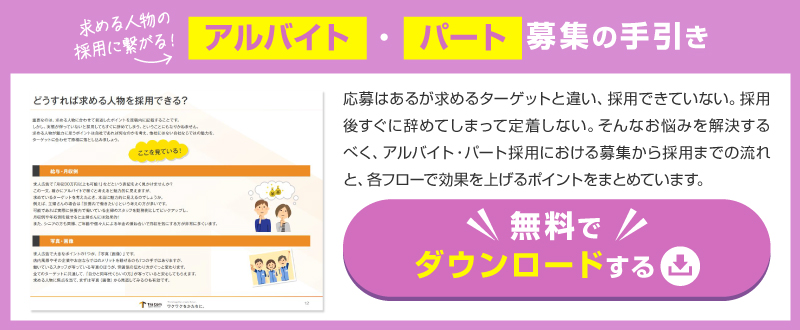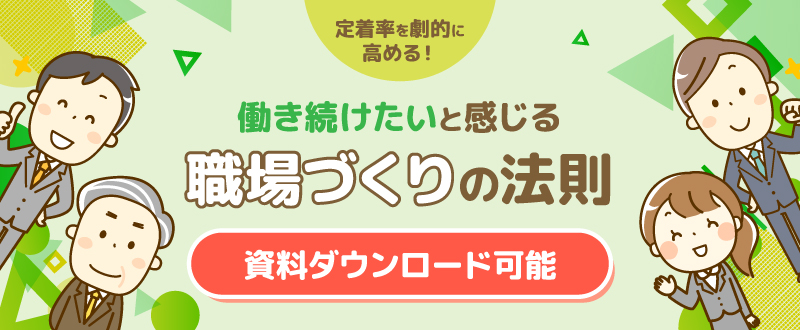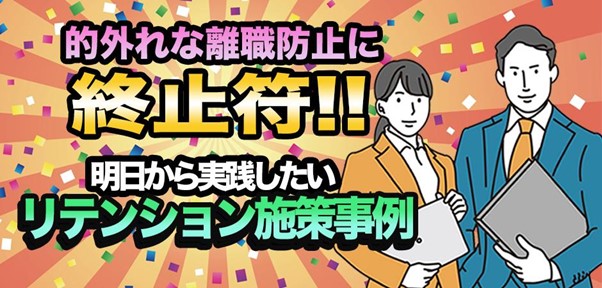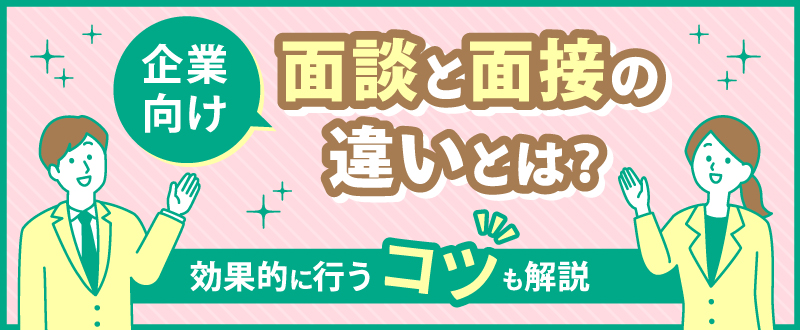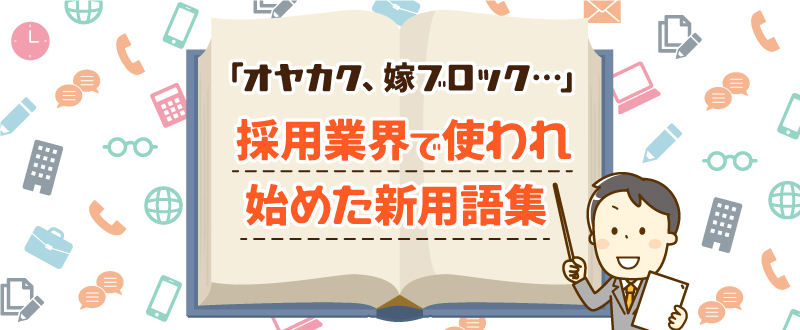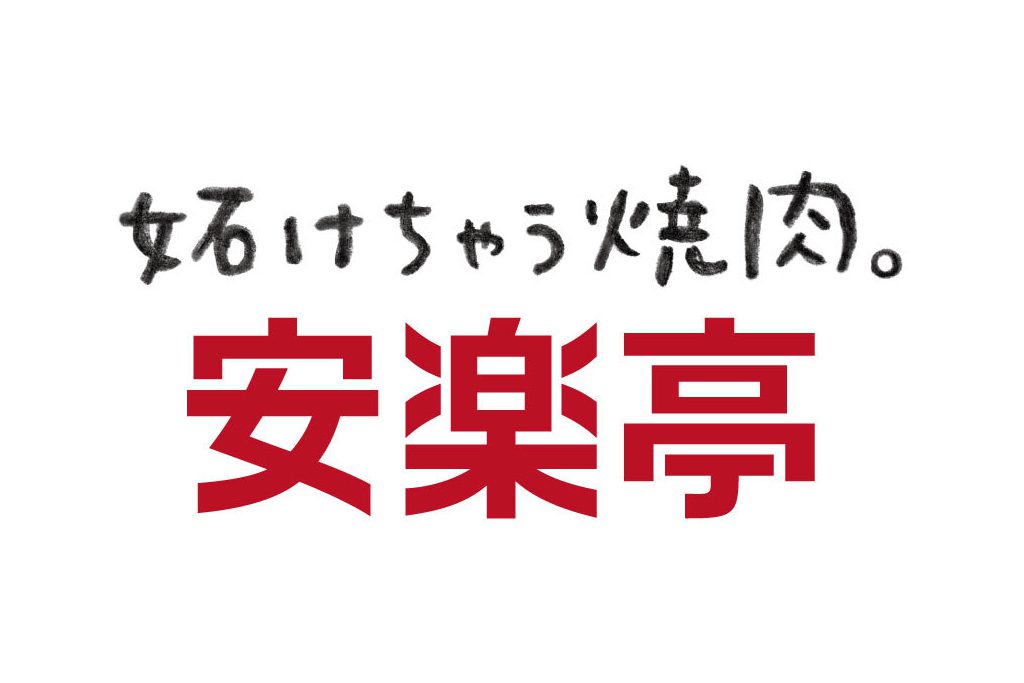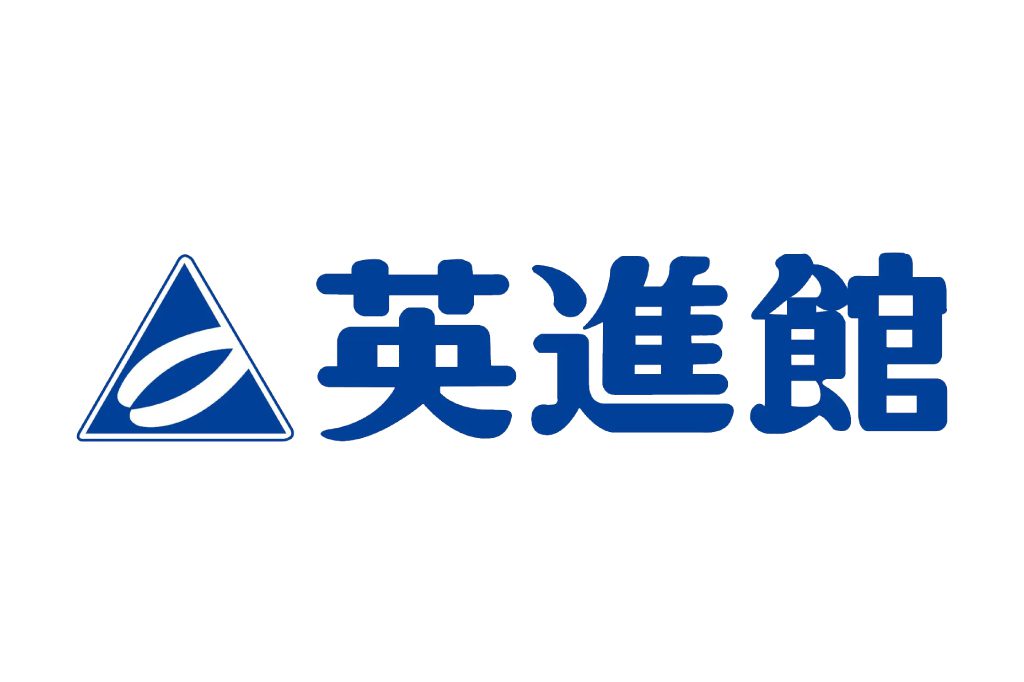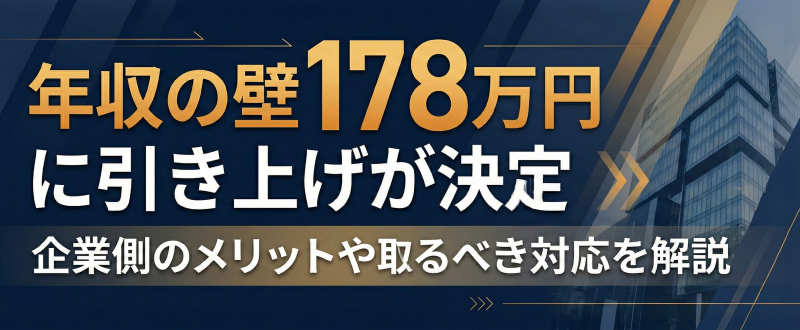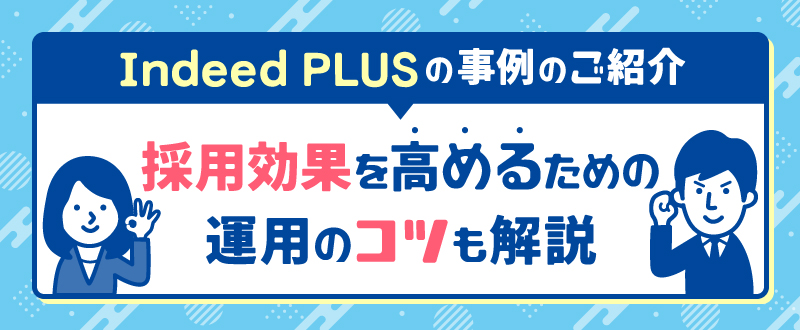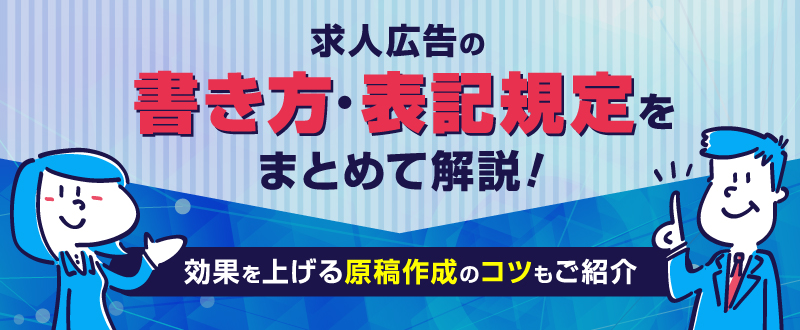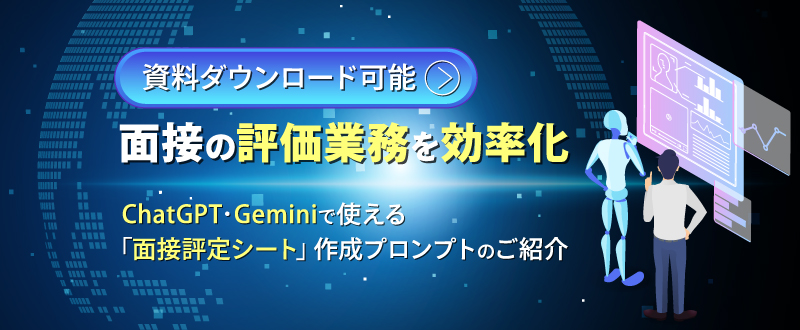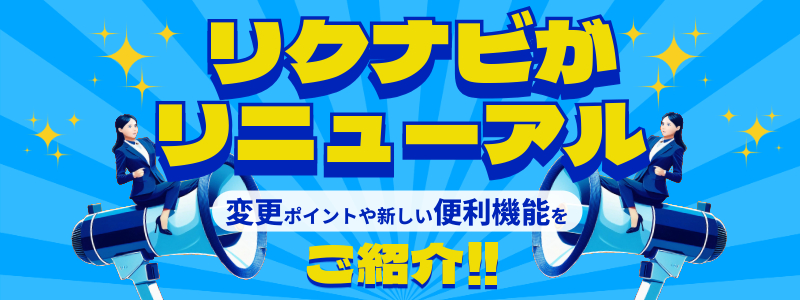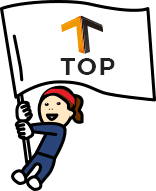トラコム社員がお届け!
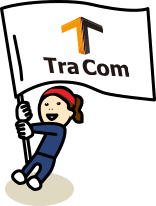
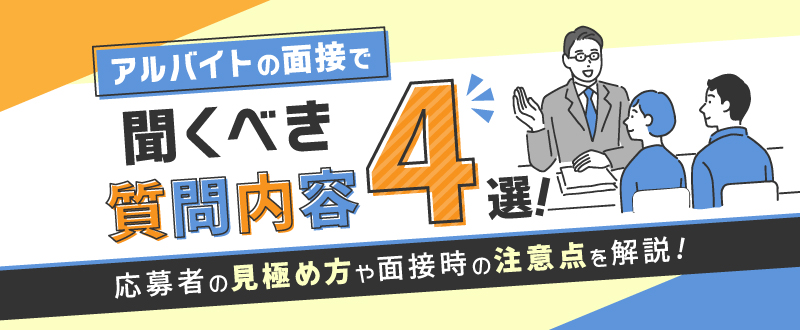
アルバイトの面接はどのようにされていますか?求職者側も企業側も社員採用とは別の観点で臨むため、アルバイトの面接をより良いものにするには、アルバイトで応募する求職者の志向状況を把握することが重要です。
「アルバイトの面接で何を聞いたら良いかわからない」「採用してもすぐに辞めてしまうアルバイトが多い」このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
応募者がアルバイト先を決めるうえで重視するポイントや、アルバイトの面接で聞くべき質問や注意点など、アルバイトの採用率・定着率アップにつながる面接のコツを解説します。
アルバイトの面接や採用に関連する記事はこちら
・アルバイト採用・募集の方法13選!ありがちな悩みと解決策も解説
・Z世代の特徴や採用方法・戦略を解説!Z世代採用に効果的なSNS媒体も紹介
・お客様に聞いてみた!採用率が上がる面接時の工夫ポイントとは?
・面接官が覚えておくべき、面接で使える心理学テクニック6選
企業がアルバイトの面接でチェックしたいポイント
まずは企業がアルバイトの面接でチェックしたいポイントについてです。面接では、以下の3つのポイントを意識しましょう。
仕事に意欲的であるか
アルバイト採用で応募者のスキルや経験、ポテンシャルを問うことは、社員採用に比べて少ない企業が多いかと思います。
アルバイト採用では、仕事内容にやりがいを持って取り組み、一定期間続けられるかを面接で見極めることが重要です。
給与や休みなどの条件重視の応募者は、仕事自体へのモチベーションが低く、入社後に「イメージと違った」と早期離職につながる可能性も大きいと言えます。
アルバイトの面接では、仕事への意欲や、やりがいに感じることを確認することが大切です。
人柄が職場の雰囲気と合っているか
アルバイトの面接では、応募者の『人柄』を知ることも大切なことの1つです。
なぜなら、人間関係が合わないことが要因で退職してしまう恐れもあるため、面接を通して応募者の人柄を知り、現在の他のスタッフとうまくやっていけるかを判断する必要があります。
「明るくハキハキとしている」、「自発的にコミュニケーションがとれる」など、面接では実際に応募者の人柄を知り、現在のスタッフとの相性を確認しましょう。
必要とするだけのシフトに入ることが可能か
アルバイトを雇用後、その人が活躍してくれることが最も大切です。
仕事への意欲があり人柄が良くても、全然シフトに入ってくれないアルバイトは、採用しても意味がありません。
シフトが埋まらないことで新たな人材を採用しなければならなくなると、採用コストや人件費はさらにかさみます。
面接を通して、勤務時間帯や出勤可能日数・土日の勤務が可能かなどを明確に擦り合わせておくことが必要です。
応募者がアルバイト先を決めるうえで重視するポイント
次に応募者がアルバイト先を決めるうえで重視するポイントをご紹介します。
応募者のことをしっかりと理解したうえで面接に進むことが重要です。
必要な給料をもらえるか
多くの人は、お金を稼ぐためにアルバイトをしています。
「欲しい物がある」「お小遣い程度を稼げたらよい」など、人によって稼ぎたい金額は違います。
アルバイトを決める際、「自分が稼ぎたい金額分、働くことは可能か」を応募者は重視しています。
応募者が希望する時給はいくらか、1ヶ月の目標給与分のシフトを聞き、それだけの出勤が可能かを面接の場では応募者に聞いておきましょう。
シフトの柔軟性はあるか
高校生・大学生などの学生だと学校、主婦・主夫だと子育てや家庭というように、多くの人は何かと両立しながらアルバイトをします。
そのため、学生だと「試験期間はシフトをずらしてほしい」、主婦だと「子どものお迎え時間まで働きたい」「土・日曜日は家にいたい」というように、希望の働き方があります。
応募者にとって、私生活や家庭と両立するために週のシフトの融通は効くか、柔軟性があるかは非常に重要なポイントです。
自分が望む経験は得られるか
アルバイトを趣味と同然に捉えたり、将来のキャリアにつながるスキル向上の場を探す機会と考える人もいます。
自社がアルバイトとして採用することが、本人の要望にあった経験につながるかどうかを明らかにして伝えると良いでしょう。
そうすることでお互いにとって納得感のある採用ができ、応募者の長期雇用につながります。
面接官がアルバイトの面接で聞くべき質問内容4選
せっかく応募者が集まって面接をしても、入社につながらなかったり、早期退職という結果となっては意味がありません。採用のミスマッチを防ぎ、選考をスムーズに進めるために、事前に聞くべき質問内容を用意しておきましょう。
以下では面接官がアルバイトの面接で聞くべき質問を4つご紹介します。
①「このバイトに応募した理由は何ですか?」
仕事自体への意欲を判断する質問です。
この質問に対して「給与」や「通勤しやすい」などの条件面をアピールする回答だと、仕事に対する個人の意思は弱いと言えるでしょう。
しかし、単純に給与やアクセスの良さが最上位の志望理由というだけで、業務に対する意欲も十分である場合もあります。 「なぜこのバイトを選んだのか」志望動機や長所、自己PRと整合性が取れているかを確認することが大切です。
最初の答えだけですぐに判断するのではなく、質問に対する深堀りを欠かさないようにしましょう。
②「月にいくら稼ぎたいなど、給料の希望はありますか?」
自社と応募者が望む条件に矛盾がないかを確かめる質問です。
お互いにとってもっとも重要な条件は、面接の場ですり合わせておく必要があります。
応募者は現場の要望にあった勤務ができるのか確認しておきましょう。
同時に、応募者が1ヶ月で稼ぎたい金額を確認しておくことも、シフトを調整する際の参考になります。
③「他に検討している会社はありますか?」
短期間で辞めてしまわないかを判断する質問です。
採用して研修や教育をしたスタッフが短期間で辞めてしまうことは会社にとって大きな痛手です。
売り手市場のため、より良い条件の現場を求めて簡単に辞めてしまう人が増えてきています。
他社と自社との条件はどうなのか、応募者自身は掛け持ちを希望しているのか、自社は短期間での勤務希望なのかなども確認すると良いでしょう。
その他にも、これまでにいつからどんなバイトで働いてきたかを聞いてみるのもおすすめです。
以前のバイトを辞めた原因を聞くことで、自社でも当てはまりうることかを判断することができます。
④「趣味はなんですか?」
現場や他のメンバーと、うまくやっていけるかを確認する質問です。
応募者の趣味嗜好がわかることで、既にいるスタッフの中で気や感じが合いそうな人は店にいないか事前に把握しやすくなります。
また、最初は同じ勤務時間に入れシフトを調整するなど、初めての現場に馴染んでもらうための取り組みをすることも可能です。
新人の業務フォローを充実させるためにもあると良い質問です。
面接官がアルバイトの面接で注意すること
面接官はアルバイトの面接を行う際に、以下のポイントを押さえて面接に臨みましょう。
NG質問に注意する
面接では聞いてはいけないNG質問に注意が必要です。普段は何気なく聞いてしまう質問の中にも、職業安定法に基づき指導や罰則の対象になってしまう場合があるかもしれません。
- 家族構成や両親についてなど、本人に関係のない質問:こういった内容も評価されているのかと誤解を与える可能性があります。
- 恋人や結婚の予定について:セクハラに捉えられてしまうこともあります。
上記の他にも、本籍地や出身地、自宅付近の情報や思想・信条などもNG質問に当たります。
面接は応募者の適性や能力を見るものであるので、選考と直接関係のない内容は就職差別につながる恐れがあるので十分注意が必要です。
NG質問については、こちらの記事で例文とともにまとめています。
応募者がリラックスして話せる空間を作る
企業と求職者が最大限お互いの魅力を伝えられるように、応募者の緊張を早くほぐし、話しやすい空間をつくることが重要です。
そこで、おすすめなのが「アイスブレイク」です。
面接はお互いに初対面で応募者の方は少なからず緊張しています。アイスブレイクでリラックスした空間を作りましょう。
アイスブレイク例
- 共通の話題:履歴書を確認し、趣味や経歴などから共通点をお話する
- 声の抑揚や表情:応募者の緊張をほぐすために、開始時から声のトーンや表情にも気を配る
企業側も面接されているという意識を持つ
面接官の印象=会社の印象です。
アルバイトの面接では、企業側も面接されているという意識を忘れず、清潔感やマナー、言葉遣いなどに注意し、丁寧な対応を心掛けましょう。
もし、不採用になったとしても応募者は企業によっての顧客・ファンになりうる可能性があります。面接や応募者対応で不誠実な対応をしてしまうと、企業ブランディングや口コミに影響を与えてしまう恐れがあるため、最後まで誠実な対応を心がけましょう。
面接来社率を高めるドタキャン防止対策
どれだけ面接に向けて準備ができていても、当日に応募者が来なければ意味がありません。
「面接日を設定したのに当日来ない」「応募者が来ず、連絡もつかない」といった面接のドタキャンを防ぐための工夫については、こちらの記事をご覧ください。
面接率・採用率を高めるドタキャン防止対策13選をご紹介しています。
応募者が面接に来ない理由とは?面接率・採用率を高めるドタキャン防止対策13選
アルバイト・パート募集の手引き|効果アップのポイント
アルバイト・パート採用における、募集から採用までの流れと、各フローで効果を上げるポイントを資料にまとめています。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
アルバイトの面接に関するお悩みはトラコムまでご相談ください
アルバイトの面接では、応募者の志向や重視するポイントをおさえ、企業側も対策することが必要です。
採用や入社後に長期で活躍してくれるかどうかは、面接の時点から始まっていると言っても過言ではありません。
面接を有意義なものにし、アルバイトの採用率・定着率を高めていきましょう。
弊社トラコムは、リクルート代理店、Indeedプラチナムパートナーとして、企業の人材支援を行っています。
求人広告掲載だけでなく、応募者対応のノウハウや採用ターゲットの設定など、採用に関して包括的にご提案が可能です。
採用・人材育成に関してお困りごとがございましたら、トラコムまでご相談ください。
関連する記事

この記事を書いた人
H.MORITA
この人の記事一覧を見る
2021年に新卒入社。東大阪エリアサービス配属。
工場、現場、ドライバー、介護 などを多く担当しました。
2024年にカスタマーサクセスグループへ配属。
エリアは問わず、様々な業界・職種のお手伝いをしております。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る