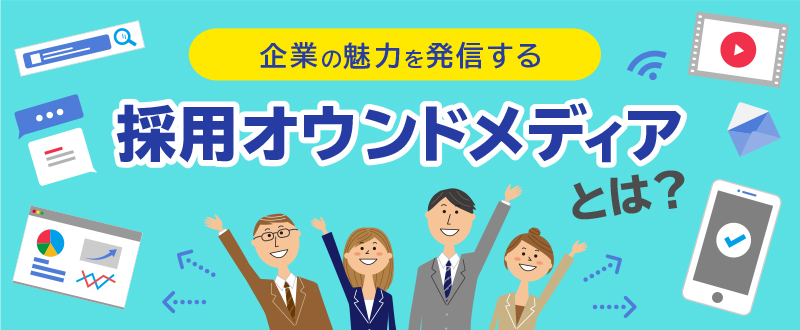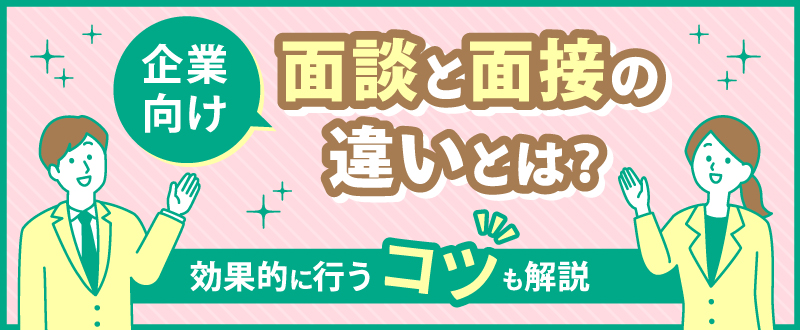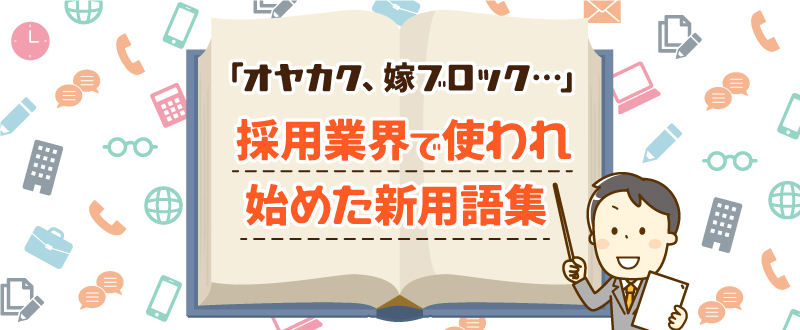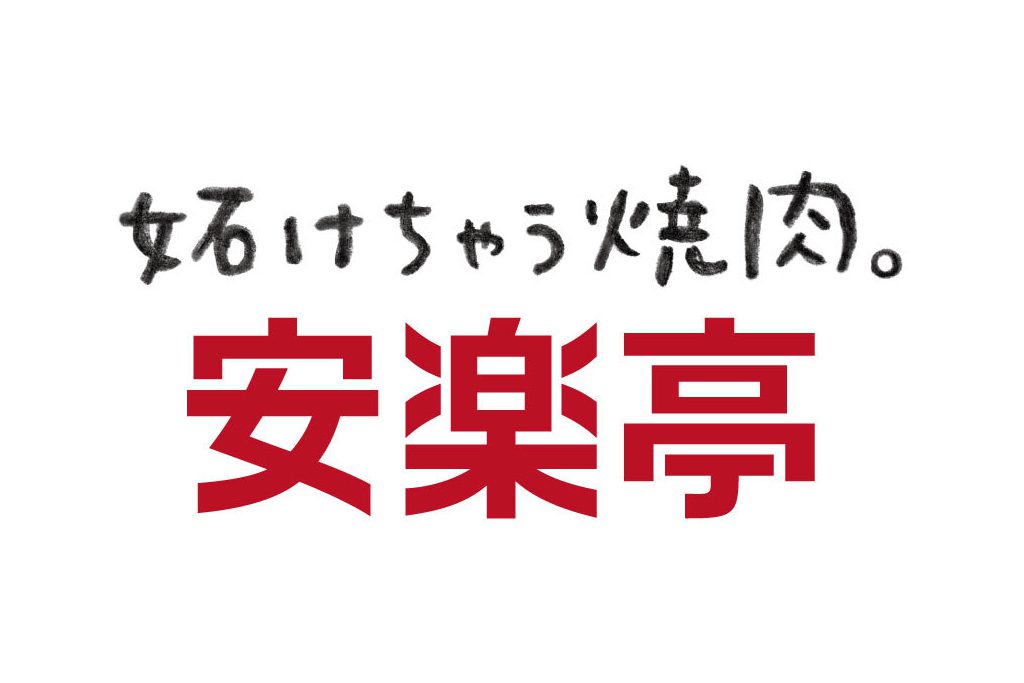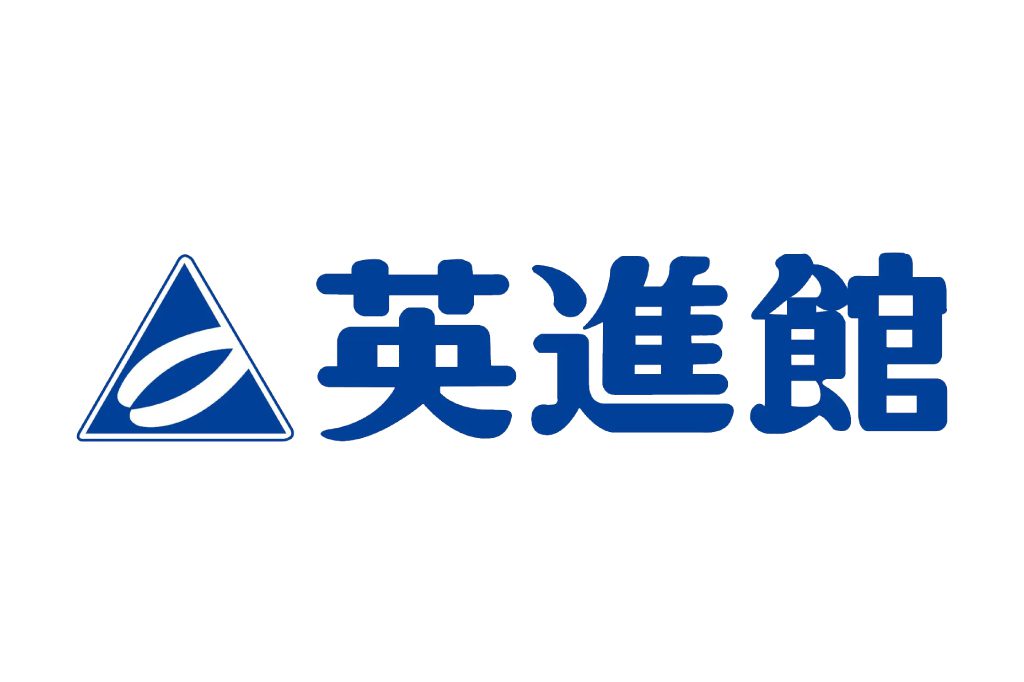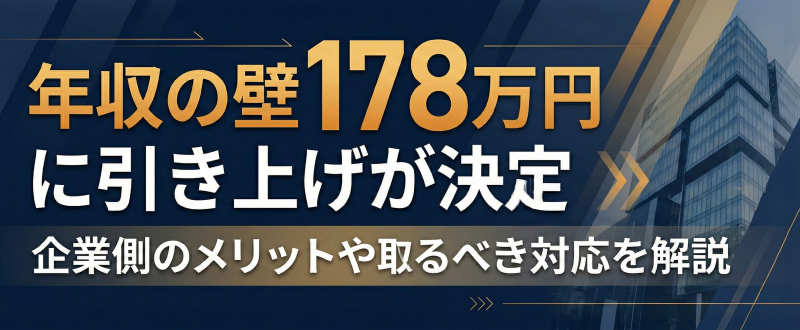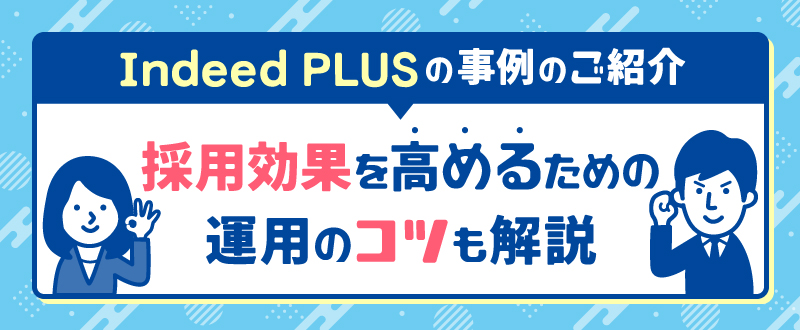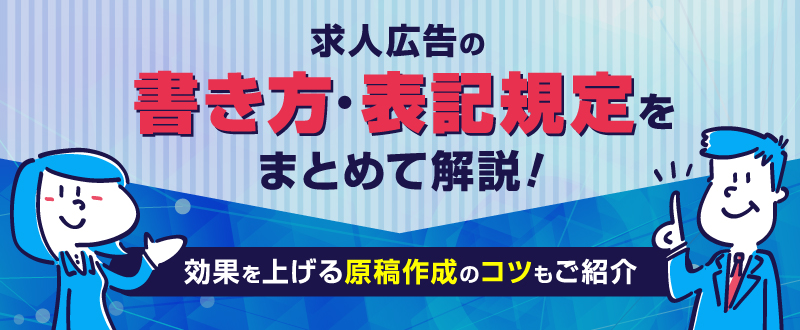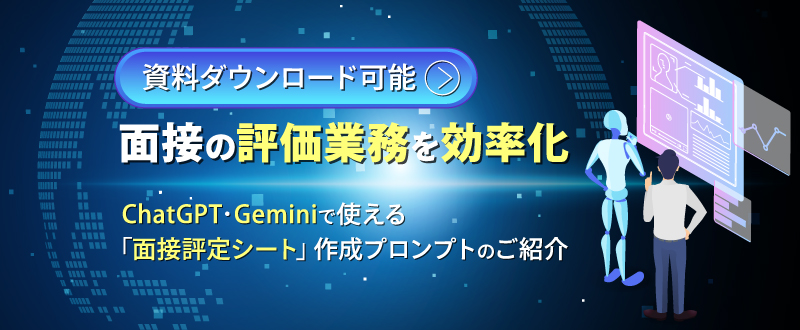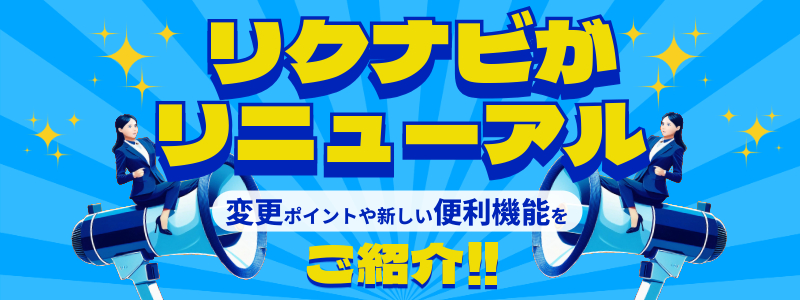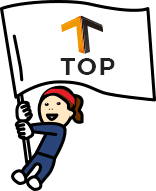トラコム社員がお届け!
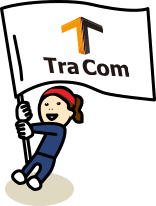

採用情報のオープン化が進む昨今、求職者はより“企業のリアルな情報を知りたい”という志向が強くなってきています。そんな中、新たな採用ツールのひとつとして注目を集めているのが「採用ピッチ資料」。
本記事では、企業の魅力だけでなく事業課題などもオープンに伝える「採用ピッチ資料」の内容やメリット、また採用ピッチ資料の作り方や活用事例などをご紹介します。 ぜひ参考になさってください。
採用ピッチ資料とは、オープンな会社説明資料
採用手法が多様化する中で、新たな採用ツールとして注目を集めている「採用ピッチ資料」。採用ピッチ資料とは一体どのような資料なのでしょうか?
簡単に言えば「企業を紹介する資料」「会社説明資料」です。「それなら説明会で伝えているし、企業情報はHPにも載せている!」そう思われるかもしれませんが、従来の説明会資料との大きな違いは“オープンに公開している”こと。つまり、採用ピッチ資料は、説明会で求職者にお伝えしてきた会社説明資料を、いつでも誰もが見られる・共有できる状態にしているのです。
良い部分だけでなく、課題もオープンに伝えましょう
また、主に企業の良い部分を公開してきたホームページの企業情報や説明会資料と違い、採用ピッチ資料は、企業の抱える“課題”なども包み隠さずオープンにするという特徴があります。
採用情報のオープン化が進む中で、求職者は、企業の魅力だけでなくよりリアルな情報を求めるようになってきました。採用ピッチ資料はそうした求職者の思考や時代の流れにマッチした“求職者が知りたいと思う会社情報をオープンにする役割”として注目を集め、さまざまな企業で導入が進められています。
採用ピッチ資料の4つのメリット
では、採用ピッチ資料を導入することでどのようなメリットが生まれるのでしょうか?ここでは、採用ピッチ資料導入による4つのメリットについて解説していきます。
採用ピッチ資料のメリット1|認知度アップによる応募数増
採用ピッチ資料を導入することにより、企業のリアルな情報が常時オープンに公開され、求職者への認知度アップを狙うことができます。
実際に採用ピッチ資料の公開を先駆けて行っている、人事労務ソフトを手掛ける株式会社smartHRでは、応募者が同社への転職を希望していることを友人に話したところ「会社情報をネットで公開しているあの会社ね!」と言われるほど認知度がアップしたそう。
企業の認知が広がり多くの求職者が企業情報を閲覧することで、結果的に応募数の増加も期待できるのです。
採用ピッチ資料のメリット2|面接の効率化と相互理解の促進
従来の面接・面談では、担当者による会社説明の時間を設けている企業は少なくありません。また、企業への理解度が不十分な状態で面接を迎えた場合、面接の中で相互理解の時間を十分に取れなかった結果、双方の理解が及ばないという状況に陥りがちです。
採用ピッチ資料を公開することで、求職者は事前に知りたい情報を十分に収集できるため、面接時間の短縮になります。また企業説明の時間を省略した分、相互理解を深めることに費やせるため、求職者にとっても企業にとっても面接を有意義に進めることができるのです。結果として、採用業務の効率化にもつながります。
求職者の志望度の高さや企業の理解度を判断できる
さらに、採用ピッチ資料を公開することは、面接の場で求職者の志望度の高さや企業への理解度を判断する手段のひとつにもなっています。
例えば、志望度が高い方の多くは、企業のことを熱心に調べ、その上で疑問に感じたことを質問したり理解しようと努力していませんか?もちろんそれがすべてではありませんが、採用ピッチ資料をいかに読み込み理解しているかは、応募者の志望度の高さや理解度の深さを知る基準のひとつにもなるのです。
採用ピッチ資料のメリット3|応募者のスクリーニング
採用ピッチ資料には、企業の良い面だけでなく、事業課題や組織課題、時には昇給実績や年収分布など、赤裸々な情報が開示されています。つまり、採用ピッチ資料を見た上で選考に進む応募者は、企業の表面的な部分や条件面だけでなく、本質的な特性や風土を理解し共感していることになります。
事前に企業への理解が十分深まっていることで、採用確度の高い母集団を形成することができ、面接や採用後のミスマッチも防げるのです。
本当に可能性のある方に選考の時間を割けるように
中には採用ピッチ資料を閲覧したことで、応募を踏みとどまったり辞退したりというケースも出てくるかもしれません。しかし、そうした辞退者はそもそも企業とマッチせず不採用の可能性が高い人材。または、採用したとしても定着しにくく、長続きしない傾向にあります。
面接前に応募者のスクリーニングをし、採用マッチング度の高い応募者を集めることで、本来時間を割くべき求職者とコミュニケーションが十分に取れ、採用の効率化・コスト削減にもつながるのです。
採用ピッチ資料のメリット4|社員の企業理解への共通化
採用ピッチ資料には、企業のあらゆる情報が掲載されています。そのため、求職者だけでなく、社員たちも同じ基準で企業理解を深めることができ、知識の標準化を図ることができます。
中でも、面接担当者などの採用に携わる社員の企業理解や知識量が揃うことで、同じ視点や共通の言語で企業を説明することができ、「面接官によって言っていることがバラバラ…」という説明のブレを防ぐことができるのです。
採用ピッチ資料の作成手順
こうしたメリットを踏まえ、実際に採用ピッチ資料を作成してみましょう。
採用ピッチ資料作成手順1|誰が作るのかを検討し選定する
企業のあらゆる情報を提供するには、様々な職種やポジションの社内メンバーから情報を集める必要があります。
人事・営業・エンジニアなど、幅広い職種の中から、役員・管理職・現場社員まで偏りなくメンバーを選定することで、企業の情報をよりリアルに伝えることができるのです。企業規模によってメンバーの人数は異なりますが、およそ10名前後のメンバーで作成するのが妥当でしょう。
採用ピッチ資料作成手順2|企業の魅力と課題を抽出する
先述の通り採用ピッチ資料には、企業の魅力だけでなく課題や欠点なども掲載されています。
そのため、まずは企業の魅力と課題の洗い出しが必要。さまざまな角度から自社の魅力と課題を洗い出し、その中で採用ピッチ資料に掲載すべき内容を検討していきましょう。その際、良いことばかりにならないように客観的な視点で見つめることをおすすめします。
採用ピッチ資料作成手順3|採用コンセプトに沿った内容の検討
魅力と課題の抽出ができたら、いよいよ実際にどんな内容で作成していくかを検討していきます。
採用ピッチ資料で公開している主な内容は以下の通りです。
- 【内容の一例】
- ・企業紹介(会社概要、実績を踏まえた事業内容、沿革、将来的な展開など)
・組織図や社風(経営者・メンバー紹介、組織構成、ミッション・ビジョン・バリュー、文化や風土など)
・求人概要(募集ポジション、仕事内容、求人要件、選考フローなど)
・その他(年収テーブル、離職率、福利厚生など)
手順2で洗い出した魅力や課題を踏まえて、上記のような内容を集約していきます。
その際に重要なのが、“採用コンセプト”に沿った内容にすること。コンセプトに沿って公開する内容を精査したり、言い回しや文言を検討したりすることで、一貫性のある内容になり求職者にとって企業のカラーが伝わりやすい資料ができあがります。
採用ピッチ資料を通して、求職者に採用コンセプトが伝わるような内容を目指しましょう。
採用ピッチ資料作成手順4|定期的なアップデート
企業の状況は、日々変化していくものです。採用ピッチ資料は、そうした変化に合わせて定期的にアップデートすることが大切です。
せっかく企業のリアルな情報を公開しても、古い情報が掲載されていてはイメージダウンになりかねません。組織構成が変わったり、事業が成長・変化した際には公開内容を見直しましょう。
採用ピッチ資料を作成する際の注意点
採用ピッチ資料は、企業の情報を公開するための資料ですが、単に企業情報を説明するだけでは意味がありません。
採用ピッチ資料の役割・目的は、あくまでも“求職者が知りたい情報”を提供すること。「本当にこの内容は求職者が求めていることだろうか?」を考え、企業が伝えたいことばかりに偏らないよう注意しましょう。
例えば、企業の魅力や特性を伝えたいあまり、社長の想いや理念ばかりを語りがちになっていませんか?もちろんそうした内容は、企業の特性を伝える手段としては有効ですが、本当に求職者が求めている情報と言えるでしょうか。
客観的な視点を得るために、入社したばかりの新人社員や、自社以外の企業を知っている中途入社の社員に意見を聞くこともおすすめです。採用ピッチ資料を作成する際には、「これは求職者が知りたい内容?」「求職者が知りたいことって何?」とひとつひとつ立ち止まりながら検討を重ねて、全体をデザインすることが大切です。
採用ピッチ資料の活用方法
採用ピッチ資料を効果的に活用するには、いくつかの運用方法を検討することが大切です。
自社の採用手法や採用課題に合わせた運用方法を選択することで、採用ピッチ資料の効果を最大限に発揮することができますよ。ここでは、4つの例を挙げて活用法を解説します。
採用ピッチ資料の活用方法1|WEB上での公開
最もオープンな運用方法として挙げられるのが、WEB上での公開です。WEB上に公開することで、誰もがいつでも閲覧することができるため自社ブランディングに活かすことができます。
中でもSNS上での発信力が強い企業の場合、採用ピッチ資料がSNS上で拡散され話題になることも。そうした話題性から企業の認知度アップを狙うこともできるのです。
採用ピッチ資料の活用方法2|面接前に候補者へ送付
面接の日時などの案内と合わせて、応募者に採用ピッチ資料を送付するという手法も有効な運用方法のひとつです。
面接前に「会社紹介資料」として候補者に送付することで、企業への理解度が高まり面接での企業説明を省略することができます。その分、採用ピッチ資料の内容に基づいた質疑応答に時間を費やすなど、面接を有意義に進めることができますよ。
企業への志望度を高めることができるため、面接の実施率を上げ、当日キャンセルの可能性を下げることにもつながります。
採用ピッチ資料の活用方法3|スカウトメールに貼付
企業側からアプローチできる採用手法として、スカウトメールを活用している企業も多いはず。
多くのスカウトメールは通数が限られており、より採用ターゲットを絞って送信していくため、1通でも多く応募に結びつけたいものです。ですが、文字数の制限などから、最低限の情報しか伝えることができず、企業の特性や魅力まで伝えるのは難しいのが現状です。
そこで、スカウトメールに採用ピッチ資料のURLを記載することで、企業の情報を詳細に伝えることができ、有効な求職者からの応募を促進することができるのです。
採用ピッチ資料の活用方法4|リファラル採用への活用
リファラル採用とは、社員が友人や知り合いに自社を紹介して選考へとつなげる手法です。
そもそも、社員自身が自社に魅力を感じていないと、友人を紹介するという行動を起こさないため、従業員満足度が高いことが前提になります。社員たちに魅力を再認識してもらうこと、そして紹介された側に企業を理解してもらうこと、どちらにとっても採用ピッチ資料が役立ちます。
採用ピッチ資料を活用することで、紹介する側も企業情報を説明しやすくなり、紹介された側の企業理解を深めるのにも効果的なのです。
採用ピッチ資料の事例
ここからは、実際に資料を公開し、認知度アップや応募者数増に成功している企業の導入事例をご紹介します。
採用ピッチ資料事例1|株式会社SmartHR
他社に先駆けて採用ピッチ資料を導入した「株式会社SmartHR」。同社の資料は、求職者が知りたい情報をしっかりと網羅している上、企業の抱える課題についても公開し、企業の透明性やオープンな風土が伝わる内容であることが大きな特徴です。
資料公開後は、公開前と比べて応募数が5.3倍に増加。資料の閲覧数も40万回を超え、「マッチしそうな応募者が増え、ミスマッチな応募者が減った」など、企業ブランディングや採用の効率化に成功しています。
株式会社SmartHRの採用ピッチ資料はこちら
採用ピッチ資料事例2|株式会社ミラティブ
ミラティブ社の資料は、『採用候補者様への手紙』という求職者に寄り添ったタイトルが話題となり注目を集めました。
また、事業内容だけでなく同社が大切にしている価値観や姿勢を伝えているほか、経営陣や社員の顔写真、経歴も公開。企業の風土や入社後のイメージをリアルに感じることのできる内容に仕上がっています。
株式会社ミラティブの採用ピッチ資料はこちら
採用オウンドメディアとの併用が効果的
採用ピッチ資料は、求職者に企業のありのままの情報を伝え、応募意欲を引き出すのに有効な手段ですが、「応募したい」という意欲の高い求職者にとっては、さらに企業を深く知るツールが求められます。
そこで有効なのが「採用オウンドメディア」です。採用オウンドメディアは、採用ピッチ資料と同じく、企業のリアルな情報を公開する自社サイトです。例えば、社員のインタビュー記事やイベント報告、事業にまつわる豆知識など幅広い内容を公開でき、より企業の風土や魅力を伝えるのに効果的なツールと言えます。
また、それぞれのツールで発信した情報を、もう一方のツールに活かすことも可能。両社を併用することで、採用力強化への高い効果が期待できます。
採用オウンドメディアについては、こちらの記事も詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
まとめ
今回は、今注目を集めている『採用ピッチ資料』についてご紹介しました。
採用ピッチ資料は、企業の魅力だけでなく事業課題や給与テーブル、働くメンバーなど“求職者が本当に知りたい内容”を公開することで、求職者の応募意欲を惹きつけるだけでなく、面接時間の短縮や候補者スクリーニングなど、効率の良い選考にもつながります。
資料として一度作成してしまえば、求職者向けとしてだけでなく、社内への共通認識やリファラル採用の促進など、さまざまな方法で活用できるのも魅力のひとつ。
また、採用ピッチ資料を通して応募意欲の高まった候補者に対してより深い情報を提供するには、採用オウンドメディアとの併用がオススメです。それぞれの特徴やメリットを最大限に活かすことで、着実な採用強化につながりますよ。
トラコムでは採用ピッチ資料作成をお手伝いしています
トラコム株式会社 テクタス事業部では、求人広告の経験を活かして、求職者観点の採用ピッチ資料の作成をお手伝いしています。
企業の魅力を客観的な視点から分析し、ターゲット設定からコンテンツ企画・作成・運用サポートまでご要望に応じて幅広くご対応致します。お客様の抱えていらっしゃる課題や状況に応じて、企画から改善まで柔軟に支援させていただきます。
「うちの会社には語れるような魅力がない」とおっしゃる人事担当者様もいらっしゃいますが、どのような企業にも必ずアピールポイントがあります。「採用ピッチ資料に興味はあるけど、何から始めたらいいか分からない」そのようなご相談もお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
関連する記事

この記事を書いた人
K.YUASA
この人の記事一覧を見る
2004年中途入社。トラコムで初の産休・育休取得。
リクルート求人営業を10年以上経験し、派遣会社・介護などを担当。
2019年~、テクタス事業部の立ち上げメンバー。
ディレクターとしてホームページ、オウンドメディア制作・運用、採用代行などに携わる。
自らインタビュアーを年間200件しつつ、様々な企業様の記事をディレクション。
WEBライティング能力検定1級を取得し、自分のスキルを常に磨く。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る