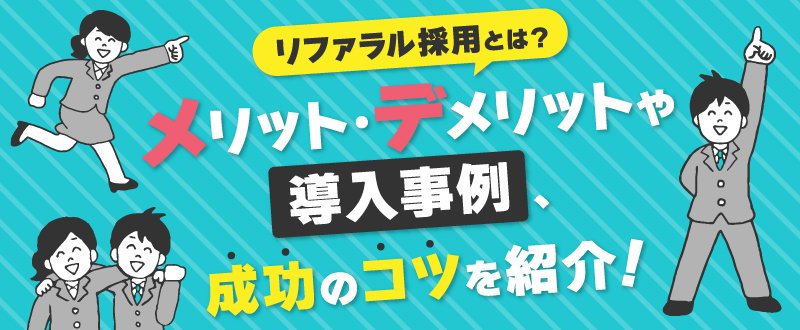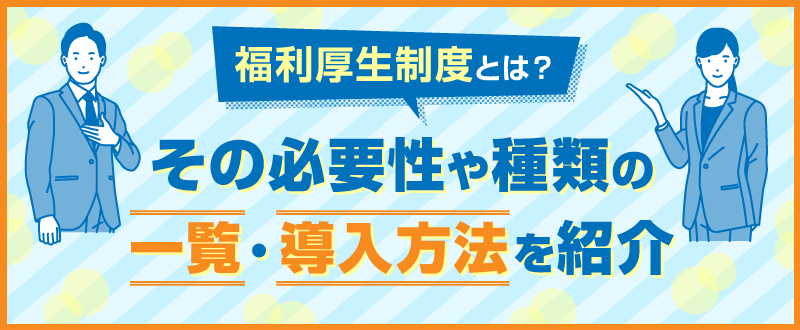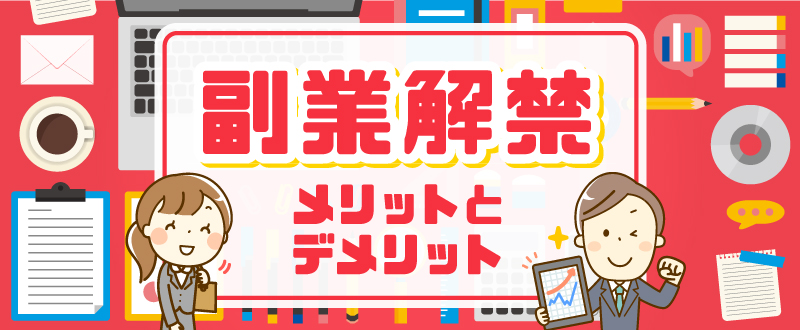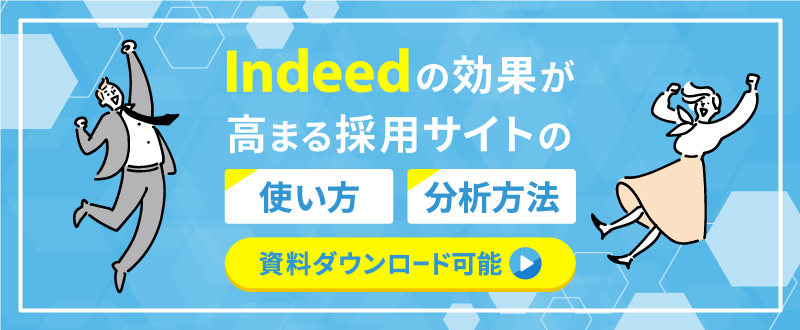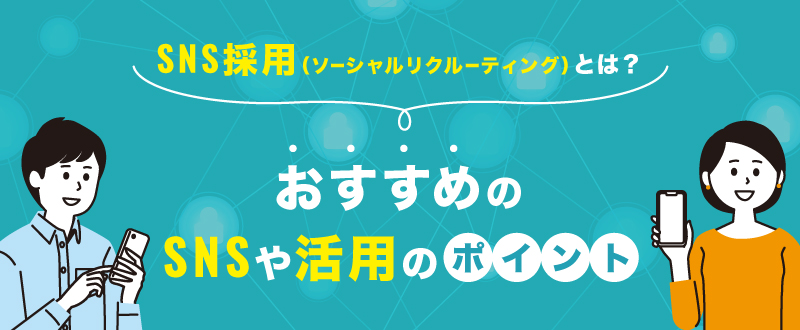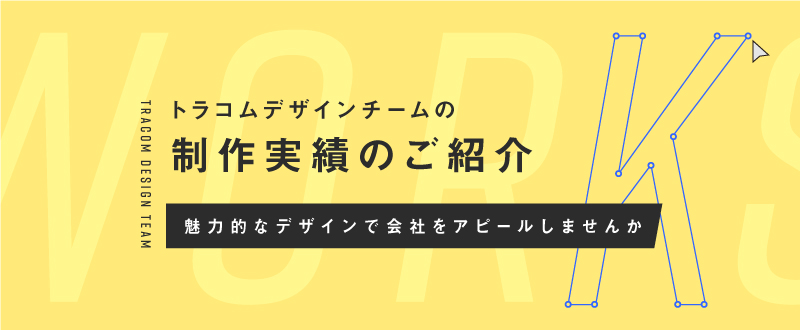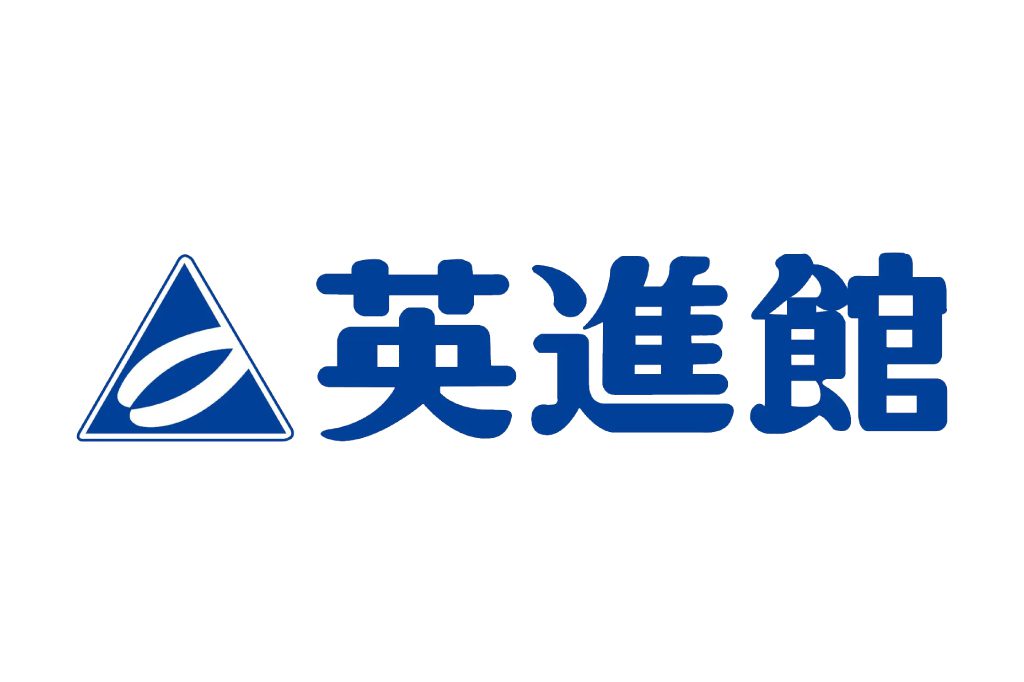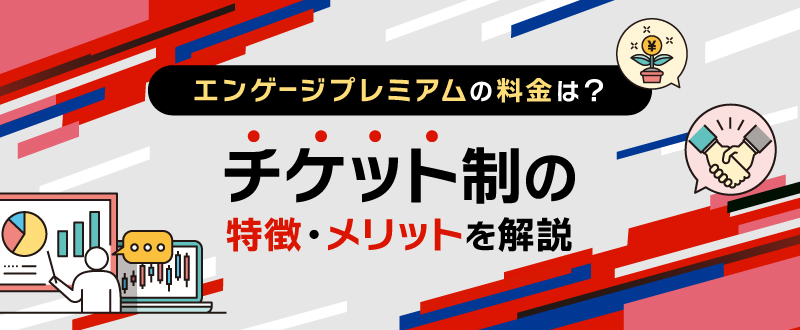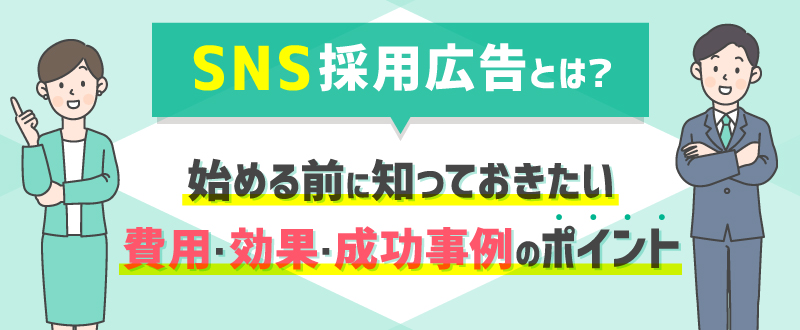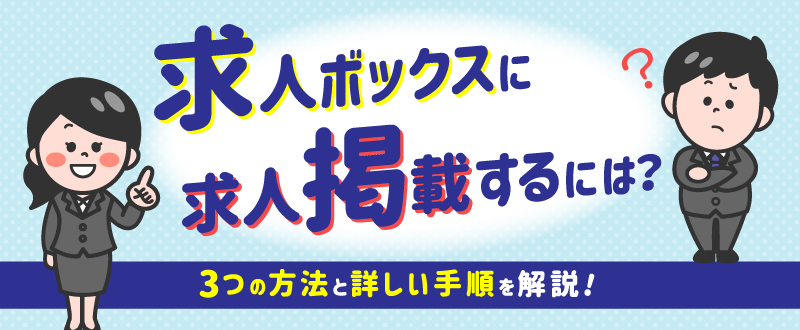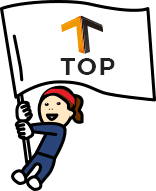メルマガ登録で最新情報をゲット!
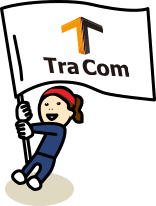
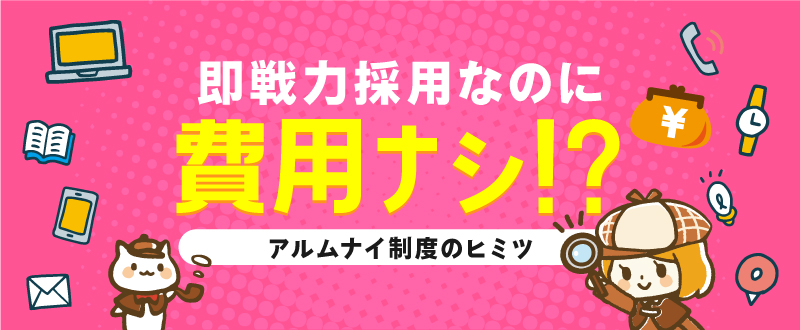
「お金をかけずに、即戦力を獲得(採用)できる!」そんなうまい話があれば、どんなものか知りたいと思いませんか?ここでは、最近注目されている「アルムナイ制度」という人事戦略をご紹介します。
アルムナイ制度のメリット・デメリットや導入手順・採用成功事例についても解説しているので、アルムナイ制度に興味をお持ちの企業様はぜひ参考にしてください。
「アルムナイ」とは?
アルムナイとは、本来大学の卒業生(OB・OG)や同窓生を意味し、企業においては離職者や退職者のことを指します。
また、アルムナイ同士がSNS(ソーシャル・ネットワーク)で繋がったり、パーティーなどの交流会を開いて作られたコミュニティのことをアルムナイネットワークと言います。
そこでは、ビジネスの話や情報共有を行うことが多く、企業はそこに注目するようになりました。
「アルムナイ制度」とは?
近年、注目されている「アルムナイ制度」とは、一度、離職・退職した元社員を、再度、自社の社員として再雇用する制度のことです。
もともとは海外など、外資系企業で取り入れられてきたアルムナイ制度ですが、最近では日本でも注目され、離職・退職者との関係を継続しようとする企業が増えてきました。
なぜ注目された?
アルムナイ制度が注目された背景には、「転職」が一般的なものとなりつつあるからだと言えます。
終身雇用が崩壊し、転職へのマイナスイメージがなくなりました。
転職が一般化したことにより、フリーランスや在宅など、労働者の働き方が多様化。特に近年では、若くて優秀な人材を雇用し続けることが難しくなってきました。そのため、一度会社を離れたものの、自社のことを理解してくれている即戦力を確保できる「アルムナイ制度」が注目されるようになりました。
「アルムナイ制度」のメリット・デメリット
アルムナイ採用を取り入れることで、企業にとってはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
メリット①採用や研修などのコスト削減
アルムナイ制度を使うことで、元社員も企業側もお互いをよく知った上で入社を迎えるので、入社後のミスマッチが少なくなります。また、元社員から直接相談されたり、現職の社員からの紹介により再度入社するので、求人媒体や紹介会社を通さず採用に繋がり、採用コストを大幅に削減することが可能になります。
入社後は、会社の方針や仕事内容・業務などをある程度理解した上で入社するので、今までの経験を活かすことができます。 オリエンテーションやOJTなどの育成、研修、教育に関わるコストも削減できる点は企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。
メリット②企業のブランディング力の向上
一度、別の組織に移った社員を再雇用することで、経験や知識など、新しい情報を通じ社内に良い影響を与えてくれる可能性がありエンゲージメントの向上も期待できます。
また、近年はSNSによる情報の拡散が採用活動にも大きな影響を与えています。 自社のアルムナイ制度について積極的に発信することで、社内外に「退職してももう一度戻りたい会社」「退職者と良い関係を築いている企業」という印象が広まり、企業のイメージアップにも繋がるでしょう。
メリット③資産が増える
仮に再雇用ができなかったとしても、退職してからも良好な関係を築けていれば、その所属している企業が取引先になる場合もあります。 会社の取り組みや商品などを知っているからこそ、それを伝えてもらうことでビジネスチャンスが広がり、営業面であれば取引先の拡大が見込めます。
また、採用面でいえば、元社員の友人を紹介(リファラル採用)で雇用する可能性も出てきます。 まだまだ普及していないアルムナイ制度だからこそ、今から仕組みづくりをしておくことで、良い影響を及ぼしてくれるだろうと考えられます。
デメリット①既存社員への配慮が必要
アルムナイ採用は、一度退職した元社員を再雇用する制度のため、アルムナイ(元社員)の過去の実績や立ち位置・スキルによっては、給与や待遇面など好条件で採用することもあるでしょう。そのため、長く勤めている社員にとっては、「ずっと会社に貢献しているのに評価されない」「一度辞めた人よりも条件が悪い」など不満を感じることもあるかもしれません。
アルムナイ採用を導入する際は、そうした不公平感が生まれないような評価制度を設けるなど、既存社員への配慮も必要です。
デメリット②社員の退職を後押しする可能性がある
アルムナイ制度は、社員のキャリア形成にも役立つ一方で、「辞めてもまた戻ってこられる」と捉えられて退職のハードルを下げてしまう可能性もあります。 そうしたリスクを避けるためにも、アルムナイ制度の意義や制度を利用できる条件などをきちんと周知しておくことが大切です。
「アルムナイ制度」を自社で取り入れるための準備
新しい制度を取り入れる時には、その分反対意見も出てくるので、取り入れるための準備が必要になります。
準備①アルムナイ制度を周知させる
在職中の時からアルムナイ制度があると周知させる必要があります。
例えば、元社員との交流する機会を作ったり、退職後の活躍を社内報で盛り込むことで、「退職後も自分のことを想って、大事にしてくれる会社」であると安心感を与えることに繋がります。
また、退職時に関しては、転職支援を行ったりと気持ちよく社外へ送り出してあげる環境づくりが効果的です。また退職後も気軽につながることができるよう、SNSなどを活用しネットワークを整えておきましょう。
準備②受け入れ体制を構築させる
一度は会社を離れてからの再雇用になるので、良く思わなかったり不安を感じる社員も少なくないでしょう。
そのため、受け入れる企業側の社員と定期的に話す時間を設けたり、再雇用をするとなった途中段階で、社員と話をさせるなどし、コミュニケーションを取る機会を設けることが必要です。
準備③復職可能となる条件を明確にする
何か理由があって離職や退職をしているので、そこの理由をクリアにする必要があります。
例えば、家庭ができた女性にフルタイムではなく、時短勤務を提示してあげたり、外で得た経験や能力を評価した上で何かのミッションを与えてポジションをつけるなど、お互いが納得し、満足のいく雇用にしなければなりません。
そのため企業は、自社のことを考えながらも離職・退職者側のことをまずは考えてあげることが大事になります。
実際にアルムナイ制度を導入している企業の成功事例
アクセンチュア株式会社様

外資系企業の中には、積極的に「アルムナイ制度」を取り入れている企業が多くあります。その中でもアクセンチュア株式会社様は、「アクセンチュア・アルムナイ・ネットワークサイト」という、約15万人以上のアルムナイが登録している巨大規模の専用サイトを保有しています。
多くのメンバーとコミュニケーションをとれるだけではなく、再就職をするための支援や年間100回以上のイベント交流などを通じ、情報やアイデアの共有や新しいビジネスを創り出しています。
株式会社スープストックトーキョー様
「アルムナイ制度」を導入している企業は、外資系企業だけではありません。 株式会社スープストックトーキョーでは、退職(卒業)後も企業とのつながりを持ち続けられるよう、バーチャル社員証を発行。バーチャル社員証を保有している元社員は、社員割引の適用や社内イベントの参加などが対象となります。
いわゆる出戻りという意味でのアルムナイ採用とは一線を画し、アルムナイ(卒業生)とのつながりを大切に考えるスープストックトーキョーならではの制度で、企業ブランディングの強化にも繋がっています。
アルムナイ制度についてお悩みの企業様はトラコムにご相談ください
トラコムは人事・採用のプロとして3万5000社以上*の企業様のサポートを行って参りました(*2024年8月時点)。昨今では採用手法が多様化しており、さらに求職者の仕事探しの動きも時代に合わせて変化しています。人材採用を成功させるためには求人メディアでの掲載だけでなく、求職者の動き・転職活動の動きに合わせた採用手法を取り入れることが重要です。トラコムでは、アルムナイ制度のほか、リファラル採用、SNS採用、Web広告運用(リスティング広告)など多方面からのサポートを行っています。まずは気軽に採用に関するお悩みをご相談ください。
まとめ
近年、働き方が多様化したことで、注目を集めている「アルムナイ制度」。社内の仕組みを整えることで、お金をかけず即戦力の獲得が可能になります。
また、それだけでなく、企業の良いイメージが社内外に広がっていくことで企業のブランディング効果にも繋がります。今後、アルムナイ制度を取り入れる企業は、更に増えていくのではないでしょうか。 アルムナイ制度の導入に興味をお持ちの企業様はぜひ一度トラコムへお問い合わせください。
関連する記事

この記事を書いた人
N.SHIRAHORI
この人の記事一覧を見る
2017年に大阪支社に新卒入社し3年在籍、主に物流企業様中心に担当。
2020年に千葉支社に異動、ユニットリーダーに就任
関東エリアに展開する派遣企業様や物流企業様中心に担当。
2022年に東京本社に異動、リーダーに就任。
全国に展開している大手企業様の直接雇用の組織に所属。
2025年4月より京都営業所へ異動。
企業の魅力を発見することが好きで
原稿改善やターゲット設計が得意です。
応募率の改善もですが、採用までの取組みも力を入れています!
・R表彰(クラスTOP/通期MVP/グランドスラム)
・トラコム表彰(上期・下期優秀賞/通期MVP22年23年連続表彰)
・Tracom Way Advance などもろもろいただきました!
最新の採用事例やノウハウ、新着ブログ、セミナーなど
採用活動全般にプラスになる情報をお届けします。
ご登録いただく前にプライバシーポリシーをご一読ください
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る