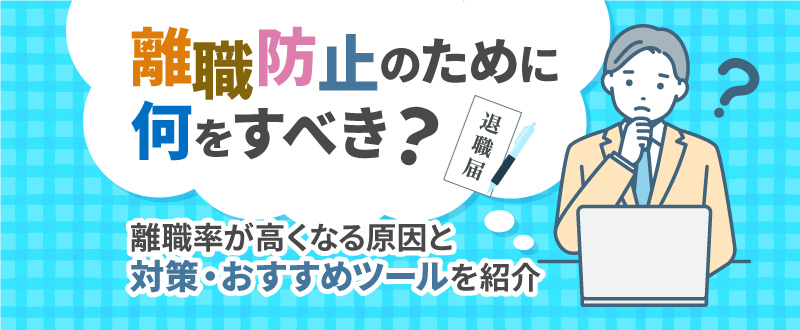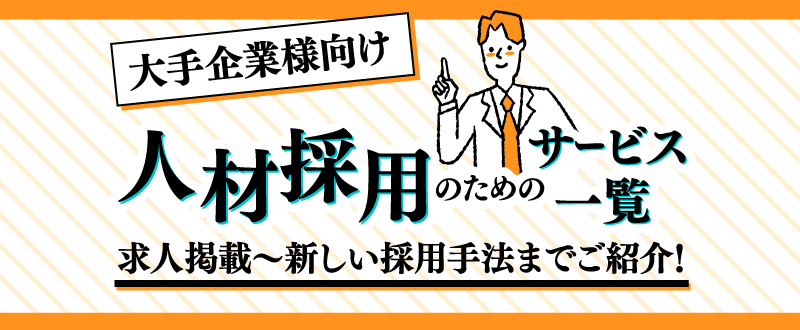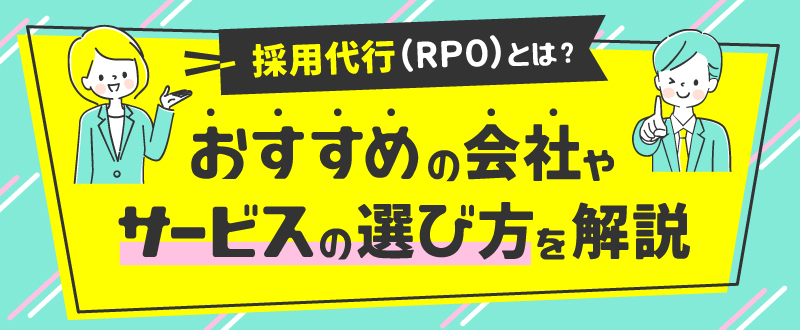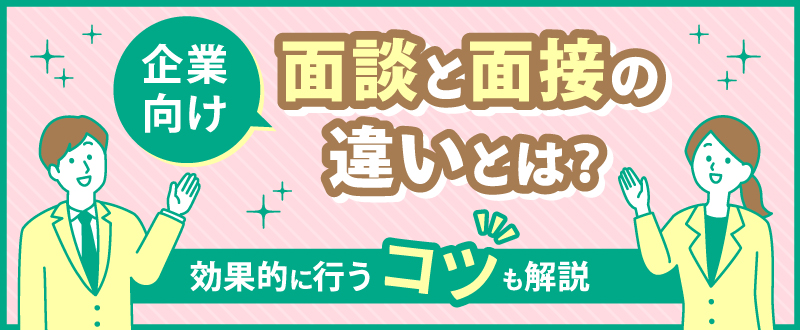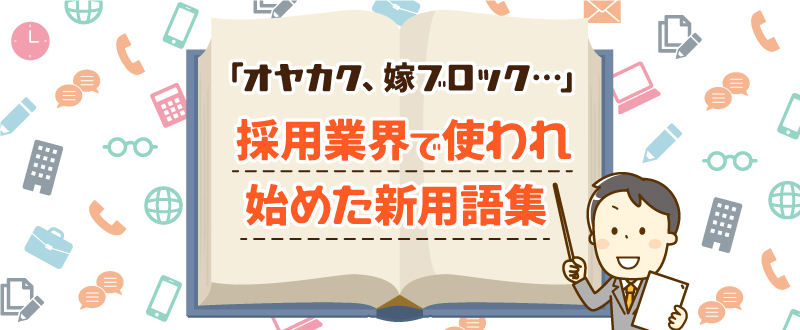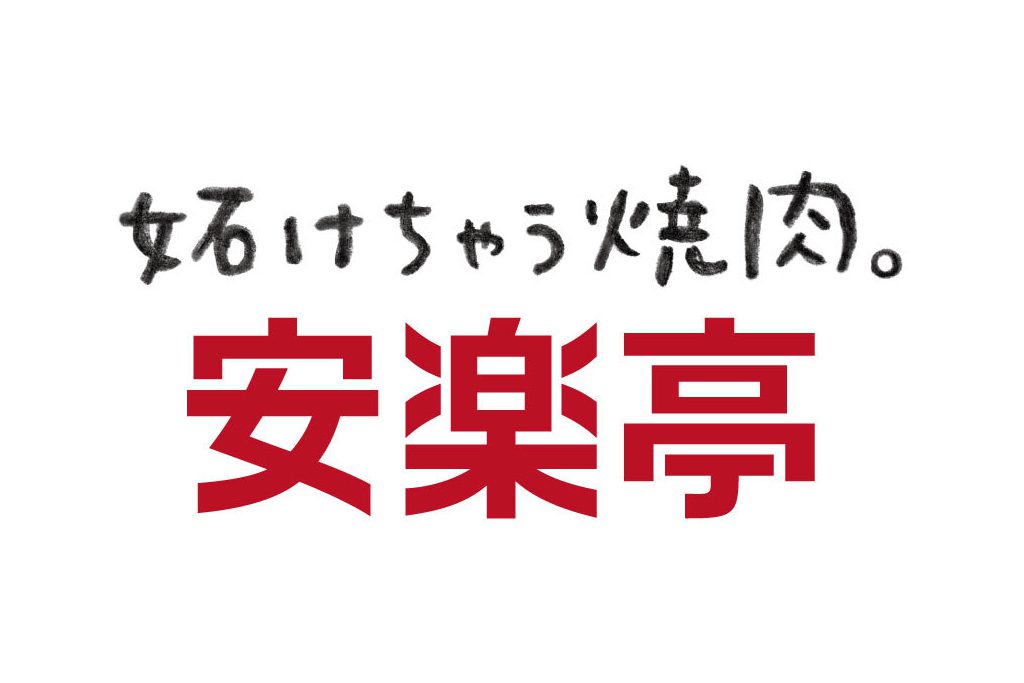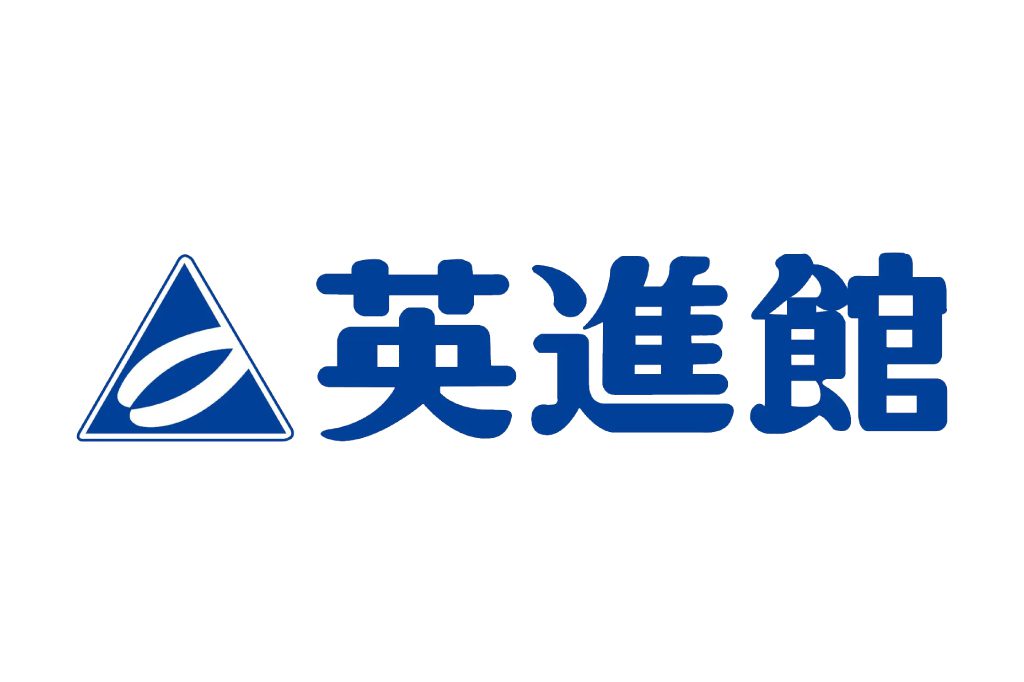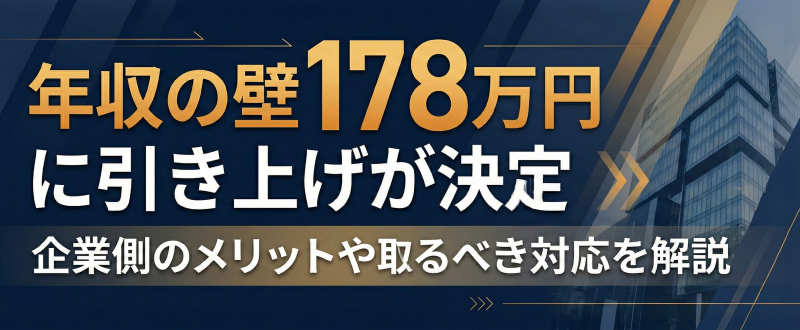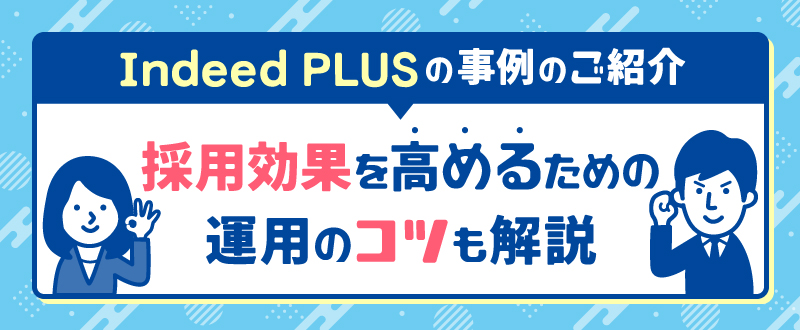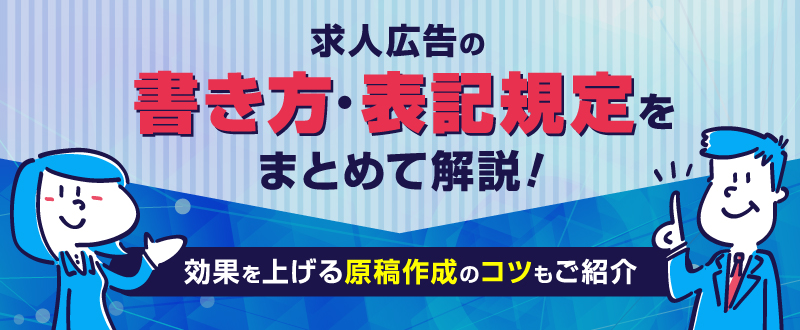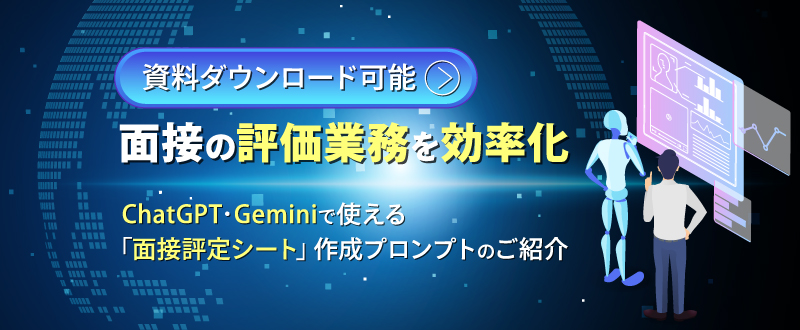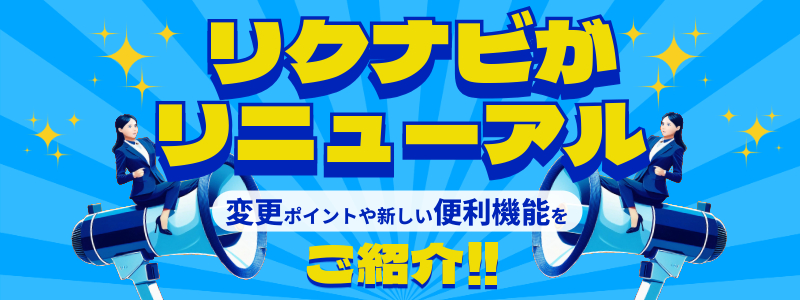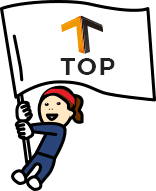トラコム社員がお届け!
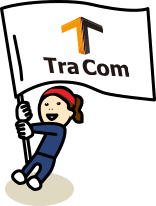
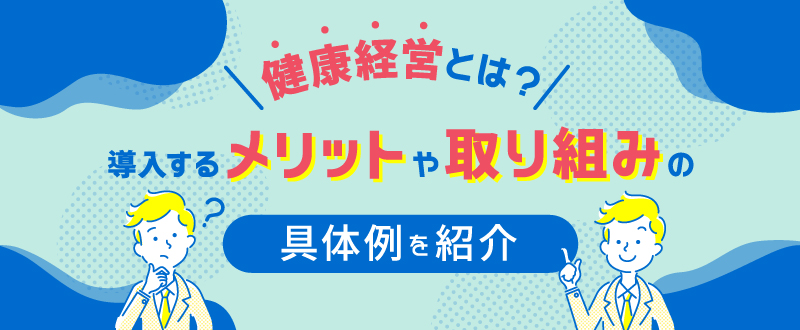
「生産性がなかなか上がらない」「自社に合う人材が採用できない」など、企業の経営にはさまざまな課題がつきまといます。「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も定着した今、「健康経営」というキーワードが気になっている経営者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、健康経営とはそもそもどういったものなのかを解説しつつ、健康経営に取り組むメリットや実際の具体例をご紹介します。
健康経営とは
健康経営とは、経済産業省の公式Webサイトの中で「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と紹介されています。堅苦しく思えますが、シンプルに表現すれば次の2点に要約できます。
- 従業員の健康を保つことは、企業を健康的に成長させるために不可欠
- 企業は「経営的な視点」から従業員の健康づくりに取り組む必要がある
健康経営の根本にあるのは、「従業員の健康を増進することが生産性向上や会社の利益にもつながる」という考え方です。
企業の継続や成長には、その中で働く人材が欠かせません。もしも従業員の健康状態が悪ければ作業効率が低下するだけでなく、休職や退職の引き金になってしまうでしょう。
健康経営の実践は、従業員の健康維持だけでなく、経営面でも大きなメリットをもたらします。株式会社クリエイティブバンクが行った調査では、健康経営に取り組んでいる企業の76.1%が「健康経営は事業成長に好影響」と回答しており、 今や企業にとって健康経営は単なる福利厚生ではなく、成長戦略の一環として正しく理解し、取り組むべき課題といえます。
出典:デジタル化の窓口「健康経営」は事業成長に好影響 76% ― 働く人の“健康意識”と企業の取り組み調査
健康経営を導入するメリット
健康経営の取り組みを導入することには、さまざまなメリットがあります。まずは、どのようなメリットがあるのかをチェックしておきましょう。
生産性の向上
健康経営の取り組みによって従業員の体と心の健康が向上すれば、仕事のパフォーマンスがアップし、生産性が向上します。一人ひとりの生産性が上がれば、ひいては企業の業績アップにもつながることは、いうまでもありません。
反対に従業員が心身の健康を損なってしまうと、ミスが増えたり作業効率が落ちたりなど、仕事に悪影響が出てしまいます。心身に不調を抱えたままで働き続ければ、ケガなどの労災も発生しかねません。さらに体調不良による休職や退職が続けば、いずれは現場が立ちゆかなくなってしまうでしょう。
企業を成長させるには、リスクをできる限り減らしていくことが求められます。生産性が向上することで、労災や人材の流出といったさまざまなリスク回避に効果的なうえ、金銭的な損失の防止にもつながります。
企業・ブランドのイメージアップ
健康経営に取り組んでいることを対外的にアピールすることで、自社のイメージアップになります。
長時間労働やハラスメントが大きな社会問題となっている昨今において、体調を崩す従業員が続出するような企業はイメージダウンが避けられません。従業員が健康的に生き生きと働いている会社とそうでない会社とでは、どちらがよいイメージを持たれるかは一目瞭然でしょう。
後述する「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」などの認定を受けられれば、さらなる印象アップが期待できます。
企業・ブランドのイメージアップは、顧客からの印象アップによる売上の向上だけでなく、人材確保がしやすくなったり、融資が受けやすくなったり、株価が上昇したりなど、さまざまなメリットにつながります。
健康経営にまつわる政府の認定制度
健康経営に取り組む際に知っておきたいのが、政府による認定制度です。公的に認定されることで「健康経営の取り組みに積極的な企業」と評価され、社会的な評価が高まることが期待できます。健康経営の認定制度とはどのようなものかを解説します。
健康経営優良法人認定
「健康経営優良法人」は経済産業省が実施する制度です。認定を受けると専用のロゴマークを求人広告や名刺などに使用できるようになり、対外的なアピールができます。認定には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2部門があり、どちらに分類されるかは従業員の人数などによって決まりますが、業種によって要件が異なるため、事前に確認しておきましょう。
さらに、認定された企業や法人の中で上位ランクに入ると、大規模法人部門では「ホワイト500」、中小規模法人部門では「ブライト500」という名称が付き、特別なロゴを使用できます。
認定を受けるのにまず必要なのは、「認定要件」で定められた取り組みの実施です。認定要件は毎年改定され、経済産業省の公式Webサイトで公開されています。
申請の流れは「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」で異なります。それぞれの申請方法と、満たすべき要件について詳しくは、以下の公式ページをご参照ください。
健康経営銘柄
経済産業省の管轄するもう一つの認定制度として「健康経営銘柄」があります。こちらは健康経営優良法人認定とは異なり、「東京証券取引所の上場会社」向けの認定制度です。
認定を受けるにはまず、毎年8月から10月頃に行われる「健康経営度調査」に回答し、その総合評価の順位が上位20%以内であることが求められます(健康経営銘柄2022の場合)。ただし要件は変更になる場合があるため、毎年確認が必要です。
「健康経営銘柄」の認定要件や申請方法についての詳細は、以下の公式ページをご参照ください。
代表的な健康経営の取り組み内容
では具体的に、健康経営の実現のためにどのような取り組みを行えばよいのでしょうか。多くの企業が取り入れている代表的な取り組みの例は、以下の通りです。
・運動習慣の推進
・健康にまつわる研修・アドバイスの実施
・禁煙の推奨
・ストレスチェック・健康診断
・職場環境・働き方の整備
各項目について詳しく解説します。
運動習慣の推進
運動習慣の推進とは、従業員に運動する習慣を持ってもらうための取り組みを指します。具体的な例は次の通りです。
- 業務開始前のラジオ体操の実施
- 運動器具・トレーニングルームの設置
- 歩数計測アプリの導入
例えば、毎日時間を決めてラジオ体操などの軽い運動を実施することも取り組みの一環となります。このほか、社内に運動器具やトレーニングルームなどを設置し、従業員が自主的に運動できる環境を提供するという方法もあります。
また、歩数計測アプリなどを使って、運動した時間や量に応じてポイントを付与するなどの特典を用意することも有効です。
このように、例えば運動会のような一時的なイベントとしてではなく、運動が「習慣」になるような取り組みをすることが重要です。
健康にまつわる研修・アドバイスの実施
健康促進のためのセミナーや研修を実施し、意識を改善する取り組みです。例えば以下のような方法があります。
- メンタルヘルス研修の実施
- 健康診断の結果に応じたアドバイスの実施
- 健康相談窓口の設置
健康経営を実現するには、企業が機会や場を提供するだけでなく、従業員にも理解を促したうえで積極的に取り組んでもらわなくてはなりません。研修や面談・アドバイスの機会を設けて、全員に健康経営に向けた意識を持ってもらいましょう。
また、健康に関する不安を感じたときに、気軽に相談できる環境づくりも大切です。相談窓口に関しては、24時間対応の外部サービスを利用するという手もあります。
禁煙の推奨
禁煙を推奨し、禁煙プログラムをサポートする取り組みを実施している企業もあります。具体例は次の通りです。
- 喫煙室の廃止・禁煙化
- 禁煙外来の受診費用補助
たばこを吸っている本人だけでなく、副流煙による「周囲への影響」も考慮する必要があります。その対策としては、禁煙の取り組みが有効です。喫煙室の廃止や、社用車の禁煙化など、できる部分から取り組みましょう。
喫煙者向けの取り組みとしては、本人の禁煙をサポートするための禁煙外来や、オンライン禁煙プログラムの受診費用を補助をするといった方法もあります。
ストレスチェック・健康診断
健康経営には、従業員の健康状態を「把握する」ことも大切です。その手段として、以下のような取り組みを実施できます。
- ストレスチェックの実施
- 健康診断の実施・費用補助
従業員の健康診断は企業の義務ですが、法定項目以外の検査にかかる料金や人間ドックの費用を会社が負担すれば、病気の早期発見や予防につながるでしょう。また、アンケート形式のストレスチェックは、各自が自分自身の健康状態を意識するセルフケアにもなります。
診断やチェックの結果に応じて早期に対応することで、体の不調やメンタル状態の悪化による離職を防ぐことにもつながります。
職場環境・働き方の整備
職場環境や働き方の改善を図り、健康を害するような働き方が発生しないようにすることも、健康経営に欠かせない取り組みです。具体的な例は次の通りです。
- 雑談の推奨
- 有給休暇を取りすい体制の整備
- ノー残業デーの実施
ピリピリとした雰囲気の職場では、過度な緊張によるストレスを感じる人が少なくありません。従業員同士の適度な雑談は人間関係を良好にし、気分転換にもなるため、快適な職場環境づくりに役立ちます。
また、有給休暇も健康経営につながる大切な要素です。企業には一定の日数を取得させることが義務づけられていますが、義務の日数はあくまでも「最低限」と考え、できるだけ多く取得できるように工夫しましょう。従業員が有給休暇を取りやすくするには、気兼ねなく取得できる体制づくりも必要です。例えば上司が率先して取得したり、1日単位ではなく1時間単位での取得を可能にしたりするなどの方法があります。
ノー残業デーを導入する場合は、形だけの制度にならないようにすることが重要です。別の日にしわ寄せがいくようでは、導入する意味が薄くなってしまうでしょう。
健康経営の取り組み事例
健康経営を実現すべく、多くの企業がさまざまな施策を取り入れています。実際の取り組み事例を3つご紹介します。
サントリーグループ
サントリーグループでは社員の相談窓口となる看護職を配置し、産業医やメンタル専門医、臨床心理士らが連携することで従業員が健康に働ける体制を整備。定期健診のほかに健康面談を実施することで、より個人に合ったサポートを提供しています。
職場環境を整えるだけでなく、「健康セミナー」や「生活習慣の指導」などを通じて健康への関心を高める取り組みをしています。
メンタルヘルス面のサポートも手厚く、本人による「セルフケア」にプラスして個別相談などを行う「ラインケア」も導入。心の不調の予防と早期発見、さらに休職者のスムーズな復帰に力を入れています。
参照元:サントリーグループの健康経営 サントリーグループのサステナビリティ|サントリー
ローソングループ
ローソングループは、「新入社員」「管理職」「女性」といった階層別にきめ細やかな健康支援を実施しているのが特徴です。相談会の実施や相談窓口の設置といった環境整備のほか、研修やeラーニングによってリテラシー向上を進めるなど、働き方や世代に応じた支援を行っています。
また、アプリを活用したウォーキングイベントやラジオ体操の動画配信などでも運動習慣の改善を図り、一定の成果を達成しています。
メンタルヘルス面では、ストレスチェックやストレス対抗力を付けるためのセルフケア推進、管理職向けラインケア研修といった多角的な取り組みを実施。具体的な実績が公表されているため、これから健康経営に取り組む際の参考になるでしょう。
花王グループ
花王グループが掲げる健康経営の目標は、「健康リテラシーの高い社員を増やす」です。健康保険組合と人事部門の連携によって、健康づくりを推進する基盤を固めつつ、健康診断や生活習慣のデータを集計。そのデータを「花王健康白書」にまとめて、現状の分析と課題の洗い出しを行い、健康経営に役立てています。
さらにヘルスケア商品を取り扱うブランドらしく、製品開発に関わる研究で得られた成果を従業員と家族の健康づくりにも役立てている点が特徴的です。内臓脂肪をためにくいランチの提供や、活動量計の配布、自社製品のプレゼントなど、多角的な取り組みが行われています。
健康経営の始め方・導入ステップ
健康経営の取り組みには、大きく分けて以下の4ステップがあります。
- 担当者の決定
- 自社の課題の洗い出し
- 施策の実施
- 社外への通知
まずは企業のトップが従業員に対して健康経営の取り組みを行うことを従業員に告知し、そのうえで実際の職務を担当する「担当者を決定」します。その後、担当者が中心となって現状の把握やプランニングを行い、「施策を実行」していきましょう。
取り組みのスタートを切った後は「社外へ通知」することも重要です。取り組みをプレスリリースや公式Webサイトへの掲載といった形で発信し、営業や採用活動に役立てましょう。健康経営優良法人などの認定を受けたら、そのロゴをさまざまな場所に掲示することで、より強くアピールできます。
健康経営の注意点・デメリット
健康経営は企業にとってプラスになるものですが、デメリットがないわけではありません。注意点とデメリットについて解説します。
取り組みがストレス・負担になる場合がある
まず注意しておきたいのが、健康経営の取り組みや制度そのものが負担となり、従業員のストレス増加や労働時間の増加、業務の妨げとなってしまう可能性があることです。
特に禁煙に関する施策などは、対象者の理解を得られなければ不満につながりかねません。実施する理由やメリットを説明する、セミナーを開催するなどして、従業員にも健康に対する意識を持ってもらい、理解を得る工夫が必要です。
効果検証・数値化が難しい
健康に関する取り組みは数値化が難しく、効果を測定しづらいという側面があります。例えば施策を実施後に売り上げが向上したとしても、それが健康経営によるものかどうかを正しく判別するのは困難です。
休職者の割合や有給休暇の取得数など数値化できる部分もありますが、業務上の事情なども絡んでくるため、効果を証明できるとは限りません。短いスパンでの結果を見て一喜一憂するのではなく、取り組みを継続しつつ長期的な視点で取り組むことが重要です。
健康経営導入のご相談ならトラコムへ
健康経営の導入方法についてお悩みの際は、トラコムへご相談ください。
トラコムでは人事や労務に関するさまざまなご相談を受け付けています。健康経営の導入方法だけでなく、効率的な人材確保の方法や、離職率の改善など、人事・労務にまつわる幅広いテーマに対応可能です。
健康経営について「何から取り組めばよいか分からない」などのお悩みがありましたら、お気軽にお申しつけください。
まとめ
従業員の健康は、組織の成長や発展につながる重要なものです。「ブラック企業」という言葉が根付いた昨今では、心身の健康を損なうような働き方は、もはや時代遅れといわざるを得ないでしょう。健康経営の理念や施策を導入して、従業員の健康を向上させ、業務にも役立てましょう。
健康経営にまつわるお悩みは、リクルート代理店・Indeedプラチナムパートナー認定企業のトラコムにご相談ください。コンサルティングサービスを通じて、理想の職場づくりの実現をお手伝い致します。
関連する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る