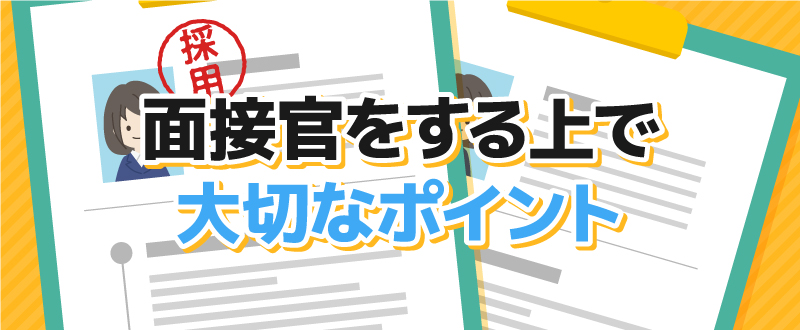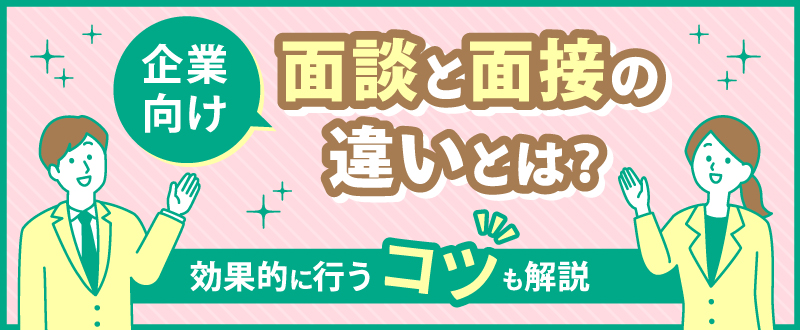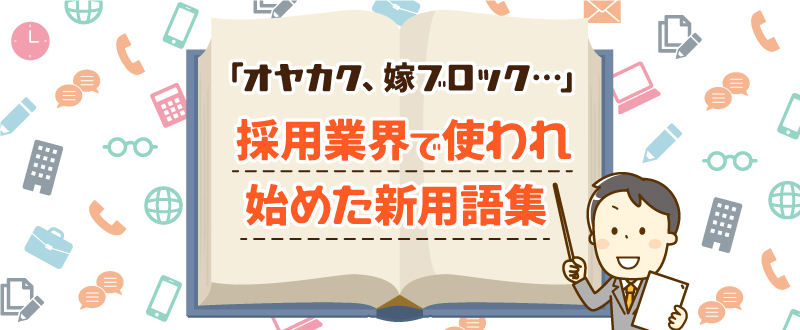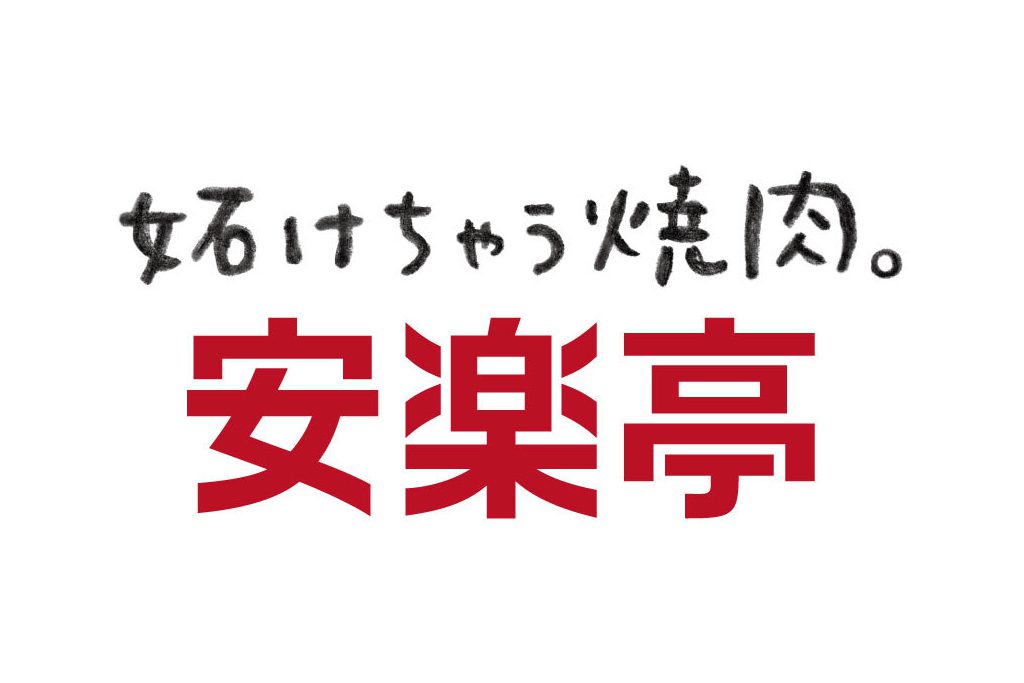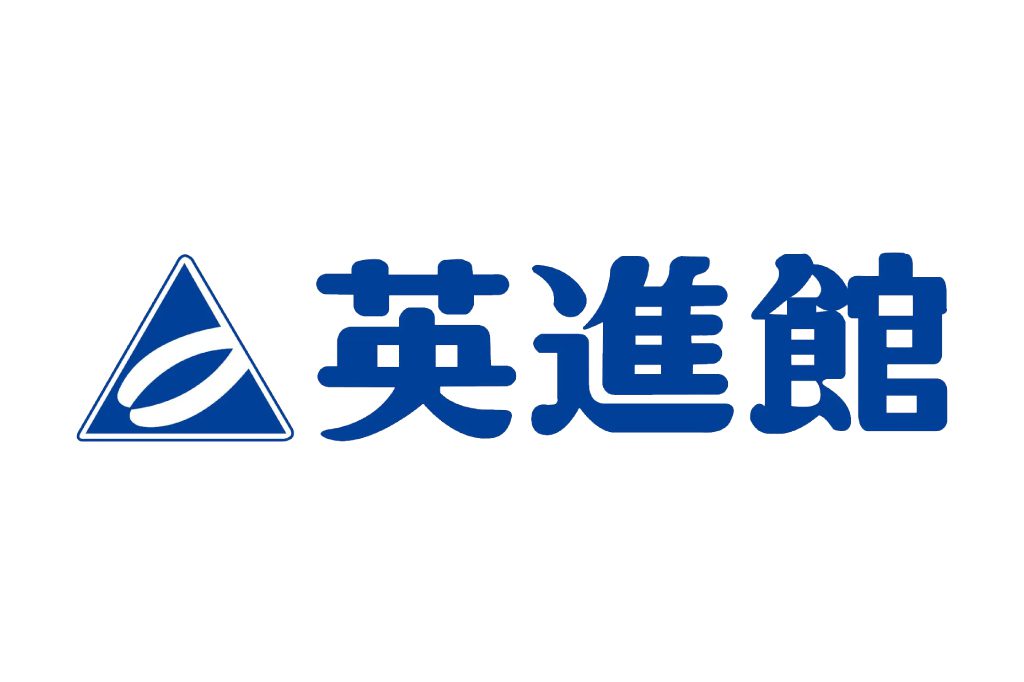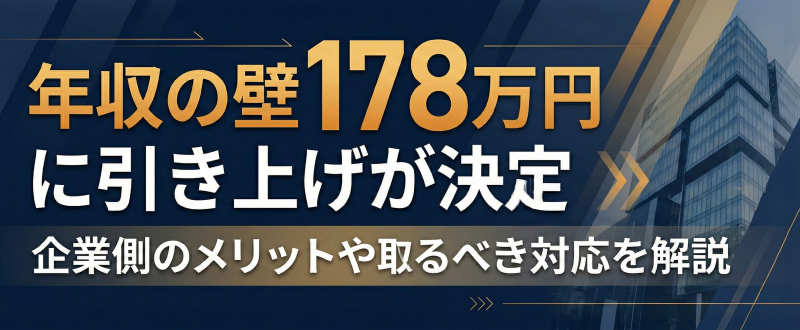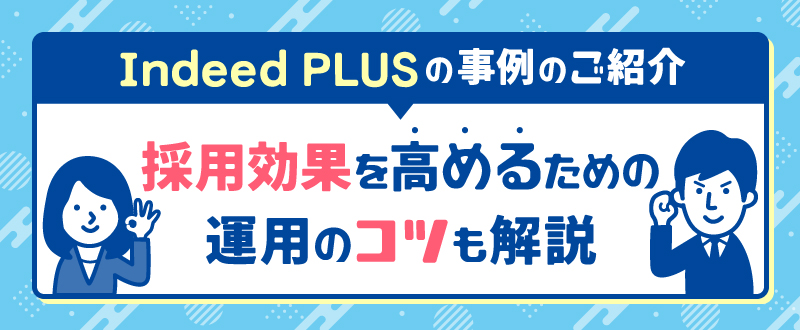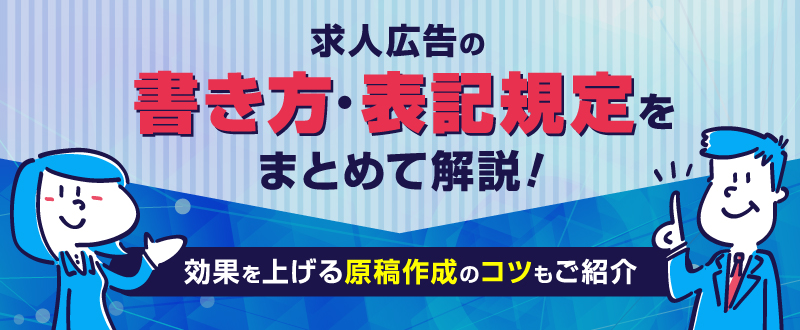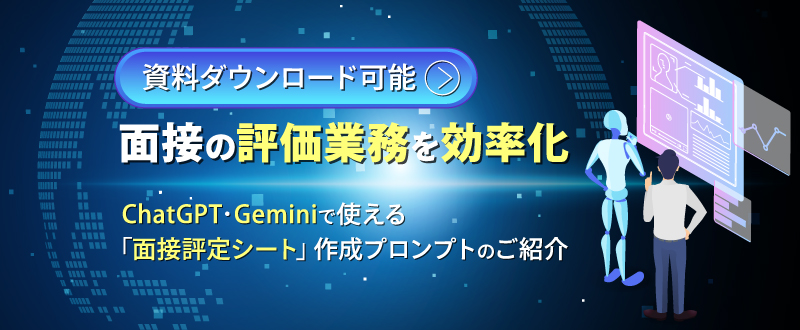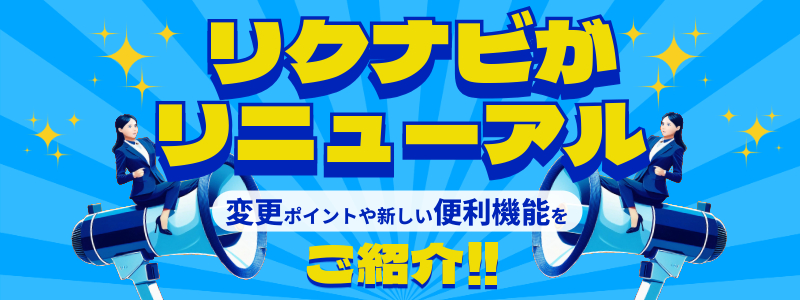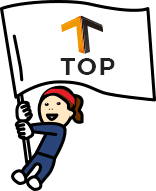トラコム社員がお届け!
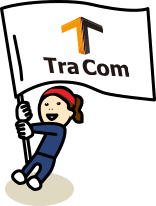
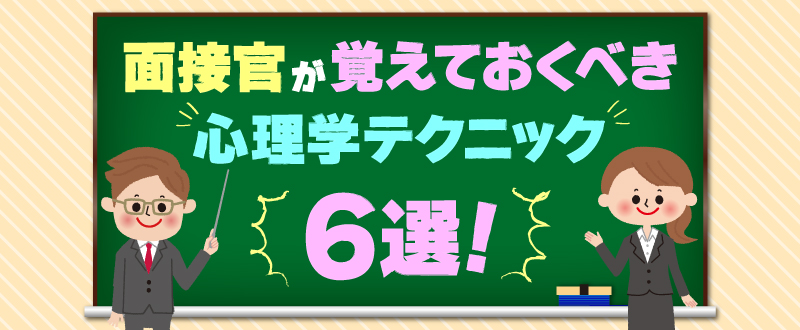
採用の市場が変わり、多くの求職者が複数の会社の選考を並行して受けることが当たり前になってきています。「この方いいな。入社してほしいな。」と思っても、面接の中で自社の志望度を高めることは難しいですよね。
そこで、面接の中で使える心理学をご紹介。面接で応募者に良い印象を与える、プラスアルファのテクニックとして覚えておいて損はないはずです。取り入れられるところから、ぜひ試してみてください。
応募者は会社選考を複数並行して受ける時代
現在の採用市場は、有効求人倍率があがり『求職者1人あたりに、1社以上の仕事がある』という状況です。求人募集を出しても、応募者は並行していくつかの企業の選考を受けています。なかには面接にも来てもらえないというケースも多いでしょう。
せっかく面接にまできてくれた応募者は、次の選考に進んでもらいたいですよね。面接の中で会社のことを理解できなかったり、魅力的に感じられなかった場合には選考に進んでもらえない可能性も高まります。面接の中で会社のことを印象付けたり、会社をよりよく感じてもらえるようにする工夫も大切です。
そこで、面接で使える心理学をいくつかご紹介いたします。
大前提:会社の魅力をきちんと整理することが大切
いくら心理学のテクニックを使ったからといって、「この会社で働きたい」と思わせる魅力がないことには、いくら頑張っても求職者の心を動かすことはできません。募集をかける前には求める人物像を決めると思いますが、改めてその方々にとって当社で働くことのメリットはなにか、他社とは違ってどのような魅力があるのかを整理し、面接の中でしっかりと伝えることが大切です。
また、 応募者の心理や行動を分析し、その人柄や特徴がわかったうえで選考をすすめることは、採用担当者だけではなく応募者のメリットにもなり、入社後のミスマッチも減らすことがにつながります。
求人募集から採用のプロに任せたい方はこちら
求人募集から採用のプロに任せたい方は、弊社トラコムまでお気軽にご相談・お問い合わせください。貴社の求める人物像にあわせて魅力を整理し、訴求する原稿を作成いたします。担当より一営業日以内にご連絡を差し上げます。
面接で使える心理学テクニック6選
1.メラビアンの法則
メラビアンの法則は、人と人とのコミュニケーションにおいて、言語コミュニ―ケーションと非言語コミュニケーションが与える影響の違いを研究したものです。
アメリカの心理学者であるアルバート・メラビアンは、コミュニケーションの要素が人に与える影響度として、表情や見た目、ボディランゲージなどの視覚情報が55%、声の大きさや声色、話すスピードなどの聴覚情報は38%、会話そのものの情報などの言語情報は7%だと示しています。
この研究結果からいえることは、伝えたいことに対して言葉・態度・話し方などがバラバラだと、聞き手は視覚情報>聴覚情報>言語情報の順に優先されるということです。
面接ではどう活用する?
面接中に応募者の話を聞く場面は多くありますよね。自分はきちんと相槌を打っているつもりでも、不愛想だったり背もたれに寄りかかっていたりすると、応募者は「あまり手ごたえがないな」「あまりいい印象を持たれていないのかもしれないな」と感じてしまうことにもつながってしまいます。最悪の場合、応募者は委縮し、本来は選考を通過できるポテンシャルがあるのに、面接の対応ひとつで可能性のある方を逃してしまうことにもなりかねません。
話している言葉の内容と、態度、話し方の3つが、バラバラになっていないかは常に意識しながらコミュニケーションを行っていきましょう。
2.ミラーリング効果
ミラーリング効果は、自分と同じ行動やしぐさをする人に好意を持つ心理効果のことを指します。同じペースで話せたり、自分と同じ感情で話せるなと思う人に好意を抱いた経験を、皆さんもお持ちではないでしょうか。まさに息が合うなと感じますよね。
これから長い時間を働く会社選びにおいて、どんな人と働くことになるのかを重要視する求職者は多いでしょう。面接においても、いいなと思った候補者にはミラーリング効果を使うことで、「自分と同じ雰囲気の人がいる会社ならやっていけるかもしれない」と感じてもらえ、選考意欲向上の後押しになるかもしれません。
面接ではどう活用する?
動作や姿勢、表情、話すペース、声のトーン、声の大きさを合わせたりしてみましょう。また、履歴書などからわかる求職者の興味関心と共通点があった場合には「〇〇さんは水泳をやられているんですね。私も学生時代やっていたんです。」のように伝えてあげることも効果的です。あくまでもさりげなく自然に行うことがポイントです。
3.バックトラッキング
バックトラッキングは、相手の言ったことを返すことで、日本語ではオウム返しともいわれます。
バックトラッキングを行うことで、受け取り手は自分の意見を肯定的に受け入れてもらえる感覚を感じられたり、会話の中での違和感や抵抗感をなくすことができ、心を開いてもらいやすくなります。面接以外にも、既存社員との面談にも使えます。
面接ではどう活用する?
候補者:「学生時代、学園祭実行委員長を行った経験から、人とのコミュニケーションを大切にしながら仕事を行っていきたいと思っています。」
面接官:「学園祭の実行委員長の経験の中で、人とのコミュニケーションの大切さを感じられたんですね。具体的に、〇〇さんはどのようなときにそう感じたんですか?」
というように、相手が話した言葉を繰り返しながら相槌を行っていきましょう。このときに注意したいのが、相手が言った言葉を言い換えないことです。例えば「コミュニケーション」を「意思疎通」と言い換えた場合、「自分の言いたいことと少し違うんだけどな」といった小さな違和感が生まれてしまうことにもなりかねません。
4.ネームコーリング
ネームコーリングは、会話の中で「あなたは」「君は」などの三人称ではなく、「〇〇さん」と名前を挙げて呼ぶことで、相手はより好感を持ちやすくなるという心理効果です。
名前を呼ばれる側は自分の名前を呼ばれることで、安心感や肯定感を感じやすくなります。
面接ではどう活用する?
面接においても、「〇〇さん、今日はよろしくお願いします」「まずは、〇〇さんが当社を志望してくださった理由を教えてください」というように、会話の中で名前を呼ぶように心がけましょう。適度なタイミングで行うことがポイントです。
5.リフレーミング
リフレーミングは、物事についてある枠組みで捉えていたことを、違った枠組みで捉えなおすことを指します。
例えば、優柔不断というとネガティブな印象を持つ方が多いかと思います。ですが、別の枠組みで見ると人の意見を柔軟に取り入れられると、ポジティブにも捉えられる傾向があります。
このように、変えられない事実も、違った見方をすればポジティブな形で捉えることができるのです。
ただし、リフレーミングの際に事実を湾曲させたり、現実逃避したりしないように注意が必要です。
面接ではどう活用する?
面接の中で、候補者から質問を受ける場面がありますよね。一見ネガティブなことを質問された際にも、リフレーミングを使って回答してみてはいかがでしょうか。
(例)
・離職率が高い→チャレンジ精神を持った人が多いため
・かわっている人が多い→個性があり、独創的な考えをする人が多い
・忙しい仕事→早く経験を積める環境がある
こちらはあくまでも一例です。御社にあわせて回答を考えてみてください。
6.両面提示
両面提示は人を説得する際に、物事の良い面(メリット)と悪い面(デメリット)の両方をあえて提示することです。初対面やまだ関係性がない人を説得する際には、メリットのみを伝える片面提示よりも両面提示がより効果的です。
また、両面提示するときにはデメリットを伝えた後でメリットを伝えることが大切です。例えば、「当社は朝8時からの勤務なので朝は早めです。しかし16時には退勤できて残業もほとんどないので夜の時間を有意義に使えますよ。」というイメージです。後からメリットを伝えることで、デメリットの印象を薄めることができます。
面接ではどう活用する?
面接に来る候補者は、就職先を選ぶ際の軸を複数持っている場合が多いです。まずは、どのような観点で次の職場や仕事を探しているのかをヒアリングしましょう。その後、就職先を選ぶ際の軸や条件について御社の現状を他社と比べ、他社より劣っている点や候補者がネガティブに感じている点については、両面提示を使い有効的に伝えていくと良いでしょう。
まとめ
面接で使える心理学テクニックをいくつかご紹介しました。面接官が応募者を評価するように、面接官も応募者に「この会社に入るべきかどうか」と評価されています。
応募者に少しでも良い印象を与え、この会社に入りたいと思ってもらうことができれば、その中からさらに良い人材に入社を決めていただくことができます。
ぜひ心理学テクニックを取り入れながら、面接を行ってみてはいかがでしょうか。
採用お役立ち情報をメールマガジンで発信中
人事や採用担当など、人材ビジネス関連にかかわる皆様に役立つ情報をメールマガジンでも発信中!登録は無料です。お気軽に登録くださいませ。
面接に関する記事

この記事を書いた人
トラコム編集部
この人の記事一覧を見る
採用支援・求人業界歴16年目。Indeedプラチナムパートナー・求人ボックスダブルスターパートナー・Google Partner として、全国6拠点(東京・千葉・名古屋・京都・大阪・福岡)から、35,000社以上の企業様の採用をサポートしてきました。
トラコム編集部が運営しているブログサイト『トラログ』では、求人媒体のご紹介だけでなく
・採用要件の整理
・応募数を増やすための工夫
・入社後に長く活躍してもらうための仕組みづくり
といった、採用にまつわる “お困りごと” に役立つコンテンツを配信しています。
その他にも、SNS運用・Google広告・採用サイト制作など、「どうやって自社の魅力を伝えるか?」といった採用広報やブランディングに関する情報もお届けしています。
<トラコム株式会社の運用実績>
■Indeed運用実績:2,100社以上
■Google広告運用実績:100アカウント以上
■SNS運用実績:40社以上
これまでに積み重ねてきた経験とノウハウをもとに、トラログでは「明日から試したくなるヒント」や「採用に役立つ考え方」をできるだけわかりやすくお届けしています。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る