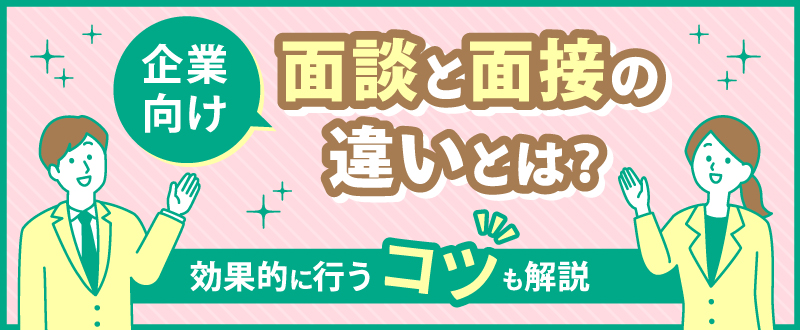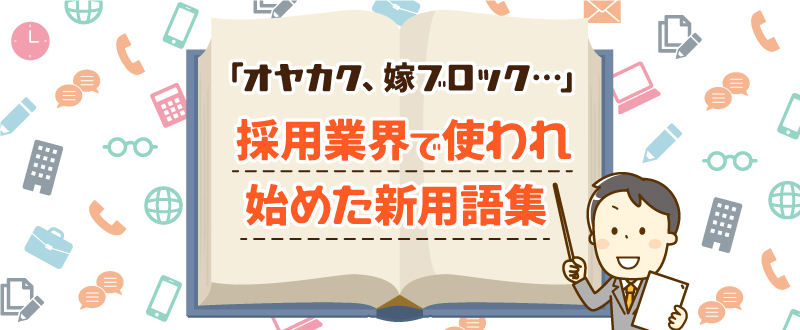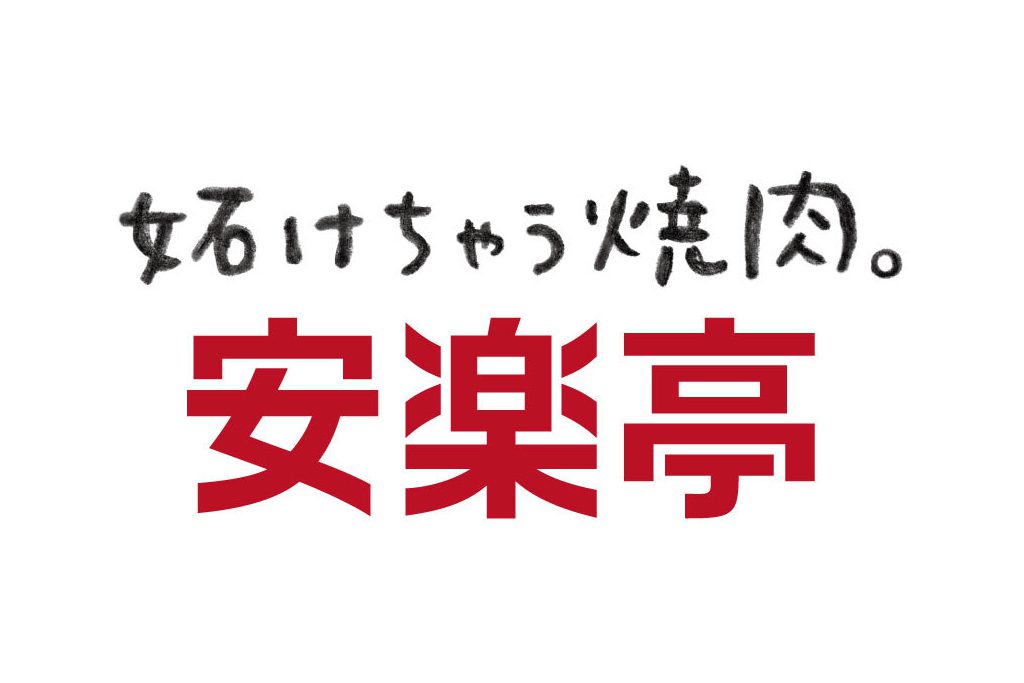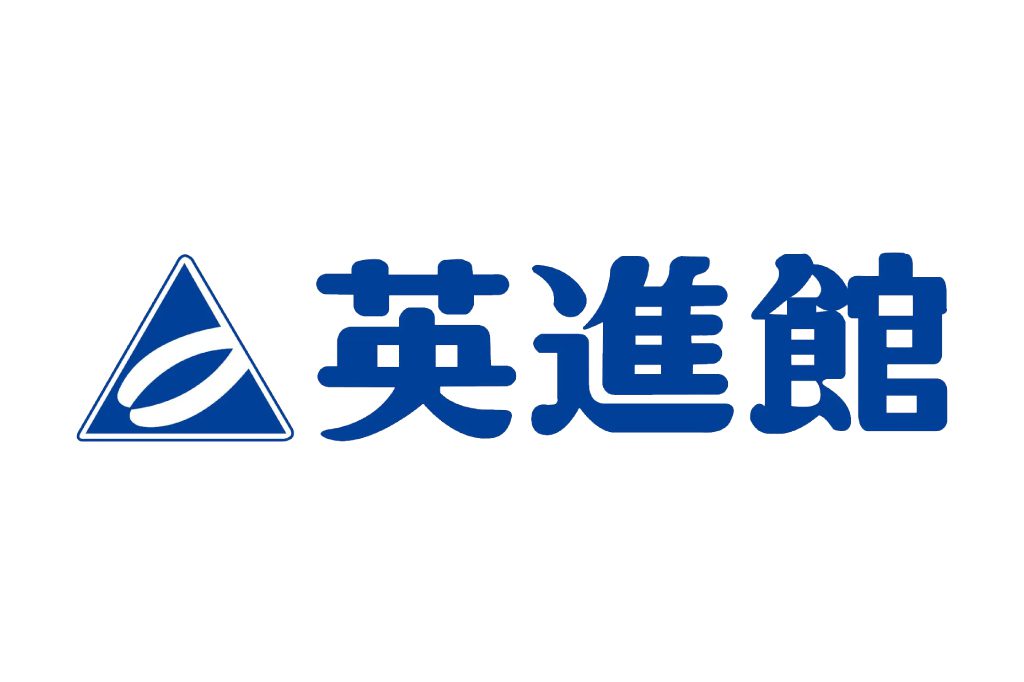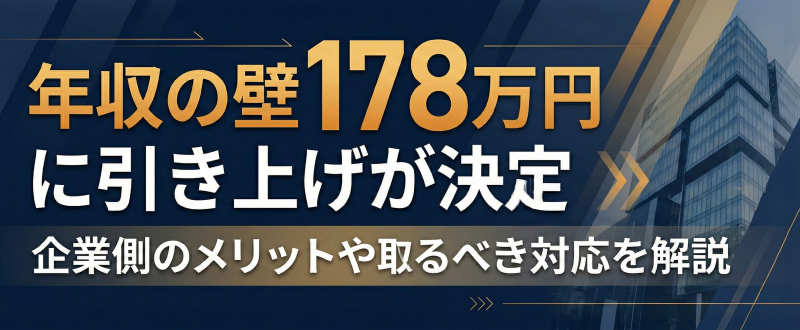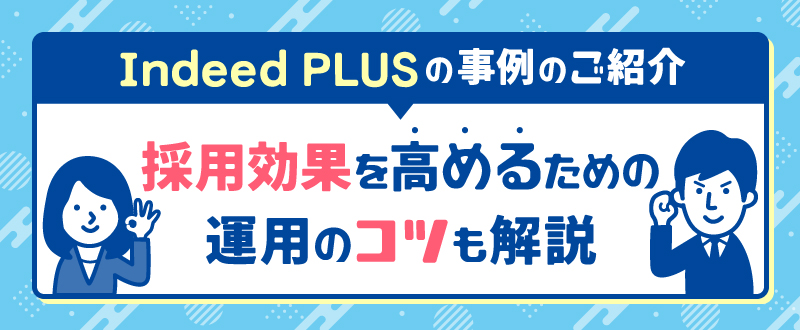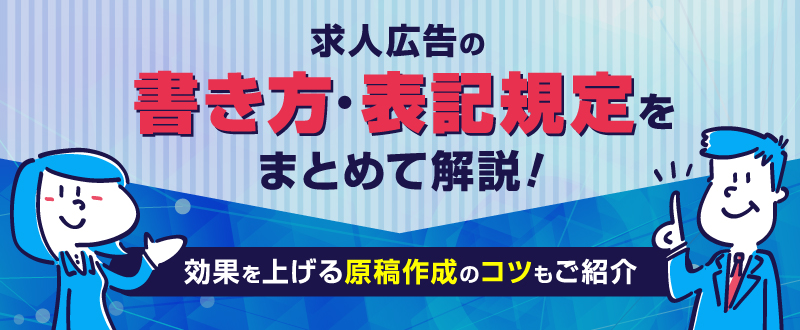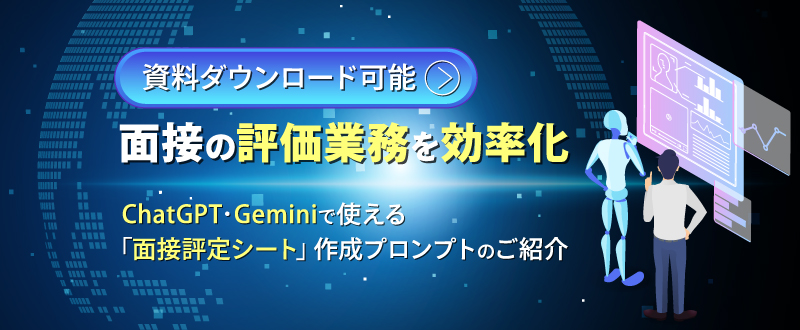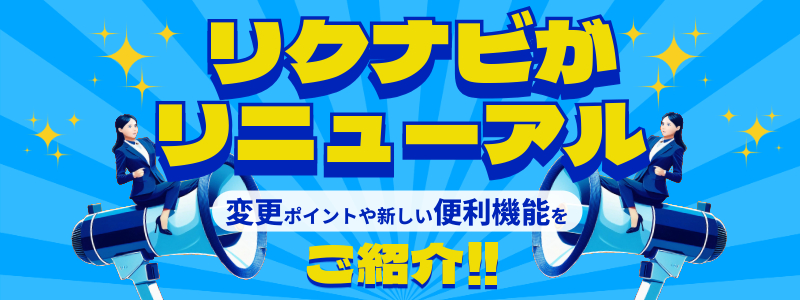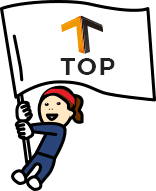トラコム社員がお届け!
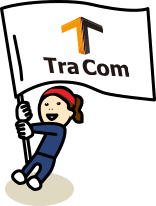

福岡県(または九州)には、意外と大手通販会社の本社が多く存在しています。
CMでおなじみの健康食品や、化粧品など誰もが知っている商品を生み出した企業の本社が、実は九州にあることを知っている人は少ないと思います。それぞれの企業に必要不可欠になっている機能が「コールセンター」です。購買実績のあるお客様などに注文を取りに行く「アウトバウンド」のタイプのコールセンターが主流です。
どちらかというと「不人気」とされるアウトバウンドのコールセンタースタッフを必要とする企業が、どのようにして採用成功に結びつけていけるか、解決策を探っていきます。
福岡県内にコールセンターはどれだけあるのか。
福岡市を含む福岡県内のコールセンター数は34拠点(平成24年時点 福岡県調べ)で、全国でも上位となっています。
さらに雇用機会を増やすため誘致を行っていることや、通販大手、通信大手などの数百ブース単位の大型投資の影響もあり、拡大が続いています。
福岡県の人口・年齢層は?
福岡県の男女別人口総数(2014年)
男性人口→240万3000人
女性人口→268万8000人 ※20万人以上も女性の方が多い!
年齢層の分布をみると、10代までは男性比率の方が高いのですが、20代以降は女性の方が比率が高いんです。特に人口の分布は20~40代までが多く、女性の方が福岡県内には多く在住しているということがわかっています。働き盛りの年齢層が多いのは、企業が採用を行う上ではとても良い環境だと言えます。
コールセンターも、労働人口の性別を見ると女性の方が多い職種です。福岡県でコールセンターが多いのは、20~40代の働き盛りの人を採用するにはぴったりの場所!という理由も1つあると言えます。理由としては、男性は比較的大学進学や就職を機に転出する場合が多く、女性は地元で進学・就職することが多いと言われています。しかも、九州で最大の都市なので他の県から移り住む人も多いのです。
テレアポ(アウトバウンド)で働くイメージ
良いイメージ
- 「会話や敬語など上手く話せるようになる」「時給が良い」
- 「時間の融通が利く」「Wワークしやすい」
- 「好きな洋服・髪型で働ける」
- 「インセンティブが出るので給与が上がる」
悪いイメージ
- 「相手先に怒られる」
- 「ノルマをこなすのがつらい」
- 「ノルマによって給与が変動する」
- 「案内する商品を覚えるのが大変」
コールセンターで働きたい人が気にする点
1)時給
高時給のイメージがある仕事ですし、やはり1日何件も知らない人に自分から電話をするというのは、精神的に気を遣う仕事なので大変なことに変わりありません。
その分の対価として、時給がある程度高いかどうか気にされる方が多いです。
2)時間の融通が利くか
高時給で短時間が可能というイメージがあるようです。
比較的週2・3日~勤務可能で1日3・4h~勤務という融通の利くところが多いため、主婦層やWワークの方々には人気です。
3)研修の充実度
商品など案内する必要があるので、それを覚えなければなりません。
未経験でもできるように、マニュアルがあるか・研修期間が十分設けられているかなど気にする人も多いです。
4)ノルマ/インセンティブ(給与)
稼ぎたいという人には気になる情報です。
給与が毎月一定ではなく、頑張った分だけもらえるのがモチベーションに繋がることも。ノルマの件数も、毎月こなせそうかどうかで判断します。
5)立地・職場環境
中心部など便利な地域にあることが多く、ターミナル駅近辺で帰りにどこか寄って帰れるかなど、プライベートとの導線でも重視されることが多いです。
あとは社内禁煙か、休憩室があるか、会社の入っているビルがキレイか…などもあります。
定着率の良い企業ではどのような特徴があるのか?
トークマニュアルを完備させている
マニュアルがあるだけで、新人でも話すことがある程度決まっていれば案内
しやすい。
簡単に始められるというイメージから応募してくる人も増える。
ベテランのスタッフさんが教育に携わっている
長年いるスタッフの方に教育を任せれば、定着やアルバイト同士ならではの話ができ、新人も精神的に救われる。
研修期間をある程度長く設けている
いきなり知らない人に電話をするため、まずしっかり学ぶ時間がほしいと思う人が多い。それを解消して仕事をスタートできるかで長く勤められるか変わってくる。
時給が良い
安定した収入を得られる、短時間で高収入を得られる。
インセンティブが良い
給与が頑張った分上がる、頑張り甲斐がある。
職場環境が良い(人間関係や設備)
スタッフ間の交流がある。悩みを分かち合える。通勤が便利。
困ったときに質問できる環境が完備されている
わからないことをすぐに解消できる環境か。
今回の担当
福岡営業所の多田が担当しました。

この記事を書いた人
C.TADA
この人の記事一覧を見る
2011年に新卒で大阪支社へ入社。東大阪エリア2年、大手チェーン系のお客様を1年半担当。
2014年福岡営業所立ち上げ時の拠点長を務める。現地採用と顧客開拓を行い、立ち上げ2年で黒字化。
2018年マネージャーへ昇格、2019年より千葉支社へ。
2023年よりカスタマーサクセスにて、約5000社を超える全国のお客様へ、
システムを活用しながらお客様の課題解決にスピーディーに対応できる仕組み作りに力を入れている。
トラログはこんな記事を
書いています
-
採用ノウハウ

年間1万社以上の取引と採用実績から採用課題の解決につながる、現場のリアルな事例やお役立ち情報を発信しております。
記事一覧を見る -
求人媒体のノウハウ

いつもご利用されている求人採用を見直してみませんか?悩み、ぜひ教えてください!御社の魅力を一緒に考えさせてください!
記事一覧を見る -
集客・販促ノウハウ

今注目されているGoogleマップやSNS(インスタ等)を活用した集客、インバウンド対策、オウンドメディア企画・運用など最新の集客トレンドやノウハウを発信していきます。
記事一覧を見る -
セミナー情報

媒体活用の採用支援や人材育成に関わるセミナーから研修や集客方法をご紹介するワークショップまで、さまざまな自社開催のセミナー情報をお届けします。
記事一覧を見る